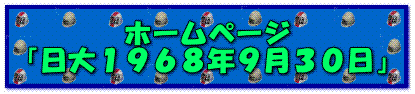大ウソつきの首相をいつまで放っておくのか
2013年9月のIOC総会で福島の汚染水が「アンダーコントロール」と平気で大ウソをついた。福島ではいまだに汚染水を制御できずに苦しんでいる。
積極的平和を提唱した提唱者ヨハン・ガルトゥング博士の言葉を盗用し、戦争に積極的に加担するすることに「平和主義」という全く反対の言葉を当て自身の政策の本質をごまかした。
安倍首相の言葉はすべてこのごまかしの言葉で満ちている。
かつて「リーマン・ショック並みの経済危機」あるいは「東日本大震災級の大災害」が起らない限り、2017年4月の消費税増税実施に踏み切ることを明言していたが、先日のサミットでの安倍首相冒頭発言では唐突に「リーマンショック」を連発し、今が「リーマンショック前夜」であるかのような印象を与え、2017年4月の消費税増税を延期を決めた。サミットでの各国首脳からは「リーマンショック」の連発に失笑を買った。未だに失敗した「アベノミックス」とか一度も命中したことのない「三本の矢」を振りかざし「経済が緩やかに成長している」などと言って、消費税をあげられなかったことへの自らの責任をうやむやにしている。しかも次に消費税をあげる時期は安倍が自民党総裁の任期が終わったあとであり、結局は安倍首相自身では消費税は上げないということだ。安倍首相は今まで偉そうなことを言ってきているが、消費税増税から単に逃げたということだ。
こんな首相にいつまで政治をやらせておくのか?
かつて自民党が政権を奪われた時、自民党の石破氏は「自民党に驕りがあった」と言っていた。今はその時以上に驕っていないか?政権党にしがみつくことしか考えない公明党と共に。
安倍首相の政策
安倍首相のやっている政策は一部の輸出大企業と投機家しか喜ばないアベノミクスと戦争法を言いかえた安保法、言葉を変えていうならば富国強兵政策だ。これは明治時代の政策。それが結局昭和初期の軍部の暴走につながった。彼が目指しているのはまさに昭和初期から戦前の時代だ。「一億総動員」ならぬ「一億総活躍」なんて言う言葉まで使いだした。本当に彼は戦前、戦中の彼のじいさん(岸信介氏)が活躍した時代が懐かしくて、恋しくてたまらないんだろう。彼は私より若いのに発想は全く戦中・戦前派だ。
富国強兵といえば近くの中国や北朝鮮でも同じことをやってる。安倍首相は中国や北朝鮮は大っ嫌いなのだろうが、実はやっていいることはそっくりなのだ。中国も北朝鮮も、そして日本もトップは2代目3代目の出来の悪いボンボン。せめて日本くらい何とかならないか。
ところでアベノミクスの3本の矢は錆ついてしまったのか新しい3本の矢がまた出てくるらしい。
戦争法案 強行採決
戦争法案(安全保障関連法案)が自民党と公明党その他自民補完政党により強行採決された。世間では理解がまだ深まっていないとかいう人が多いが、私はむしろ理解が深まって反対する人が増えたため与党が慌てて強行採決せざるを得なくなったのだと思っている。憲法に違反している法律をいくら時間をかけて説明しても合憲にはなり得ない。安倍首相は、オリンピックの招致の時に福島の汚染水を”under control”と言ったように、違憲を合憲と言い、戦争をする事を「積極的的平和主義」と言い、派遣法を派遣労働者の「正社員化の道を開くもの」と言ったり、すべて「黒を白」といっているにすぎない。戦後最悪の内閣である。
2013年7月の参議員選挙
2013年7月の参議員選挙の投票時間が終った直後、NHKのアナウンサーが叫んだ。にこやかな顔で「ねじれが解消されました」と。それが喜ばしいことだったかのように。そして今。安倍政権は一向に景気が回復しない経済政策アベノミクスを掲げ、また次々と悪法を成立させ、憲法をも無視した戦争法案をも強行採決した。暴走が止まらない。NHKは自民党の放送局か?
2009年の政権交代時に自民党の石破氏は自民党に驕りがあったとしきりに反省をしていた。今はその時以上に驕りがあるが一向に反省の言葉は出てこない。
それにしても民主党の最後の首相であった野田氏は2012年12月の衆議院選挙では野田氏は自民党の政権復帰のためのお膳立てばかりしていた。あれは自民党の隠れ党員だったのではないかと思う。
闘うことを忘れた日本人
2009年1月4日の朝日新聞の「耕論」という欄に仲代達矢氏が「日本人は全学連時代以降闘うことを忘れてしまった」と書いていた。
「全学連」の表現が適切かどうかは疑問だが、主旨は極めて適切といえる。
「教育」の場が、「受験」のテクニックを教える場と化し、「大学」に行けばそれで終わり、という「教育」からは「社会」の問題を考える人間は生まれてこない。
従順に「お上のいうことに従え」という「教育」からは「変化」に対応できる人間は育たない。
一つしか回答のない問題の答えをどれだけ覚えているかを競う「教育」の中からは、世の中が「多様」であることが理解できないし、「新しい問題」に対応できる人間も育たない。
「社会」が分からないから「闘う」相手も分からなくなっている。
だから相手が「誰でもいい」と無茶苦茶な自暴自棄的な行動が生まれる。
仲代達矢氏は、
「何か問題があれば全員で闘う」ことの必要性を説いている。
「悪しき権力に向かって闘う事」を説いている。
これが「民主主義」なんだ、と思う。
企業の「談合」に思う
2006年の正月だったと思う。
大学の同窓の仲間3人と新年を祝った。
その際に、当時、あちこちで発覚した談合事件の話題があり、私以外の仲間は一様に「談合は必要悪」と認めている。
日大闘争の時には、一度はデモに参加したことのある仲間である。
私は「我々の世代がそんなものをなくしていくべきではなかったのでは?」と言ったが、所詮少数派。
企業の中にトップリ浸かると結局そうなってしまうのか、と私は、嘆かわしく思った。
私も企業の中にいたが、「偉く」ならなかったおかげで、今でも全共闘で闘った時の気持ちだけは残っている。体はなかなかついて行けないが・・・。
企業の中にいると、その企業の中のことしか考えられなくなる。
社会に対する影響、人々の生活に対する影響が見えなくなる。
企業内労働組合も同じことだ。企業内の組合員のことしか考えない。
いや考えているのならまだいいが、往々にして企業内組合は、経営者の
ご機嫌を伺う組織に成り下がっている。
それが今の「派遣」の問題につながっている。
社会に対する責任を考えない経営者が増えたということだろう。
私はそう思う。
「敗北を抱きしめて」を読んで
以前、図書館で「敗北を抱きしめて(上・下)」(ジョン・ダワー著 岩波書店)を借りて読んだ。なかなか良い本だと思った。
増補版が出て、もう一度読みたいと思い今度は買った。
写真や図が豊富になったこともあり、また前に読んだときの記憶が薄れたこともあり、とても新鮮に感じた。
著者がアメリカ人でありながら、GHQの占領政策にはかなり批判的な書き方をしてる。
戦後の状況を極めて詳細に記述しており、GHQの初期の政策から朝鮮戦争に向けた大きな政策変更が、日本の保守政治家の利害と一致し、戦争責任の追及もうやむやになったことがよく記されている。
最高責任者の責任を問わなかったことは、これをアメリカが利用しようと意図したことであり、昔は軍隊に、戦後はアメリカに利用されることになった。
ちなみに中国で人体実験などを行い、細菌の研究していた731部隊についても、その成果を利用するためにアメリカは罪を問わなかった。
この成果は朝鮮戦争やベトナム戦争で使われた。
極東軍事裁判(東京裁判)では結局、最高責任者の罪は問わないように、アメリカも日本の戦犯もまた反動政治家も最大限の努力をした。
731部隊や岸信介のようなアメリカの役に立ちそうな者の罪を問わずに済ませた。
明らかに「勝者の裁判」であった。
アメリカのご都合主義だったのだ。
本来、日本人が戦争犯罪人を裁くべきだったのだろう。
それが成されなかったことが、良くも悪くも今日の日本を作っている。
アメリカはいつでもろくでなしを支援する
アフガニスタンのオサマ・ビン・ラディンやイラクのフセインは、アメリカが手を焼いた(ている)人物であるが、結局、彼らはアメリカが育てた人物である。
オサマ・ビン・ラディンは、アフガニスタンでのソ連侵攻に対抗するため、フセインは、イラン・イラク戦争時にイラクに対抗するため、アメリカが育てた。
いつもアメリカは、ろくでもない人間を支援する。
中国では蒋介石。韓国では李承晩や朴正煕。ベトナムのゴ・ディン・ジエム。
日本に至っては、保守政党の歴代首相。
具体的には、岸信介や佐藤栄作というところか。
軍隊で平和が守れるのか?
憲法改正論者は「軍隊がないと国の安全が守れない」とよく言う。
では、軍隊で平和が守れるか?
60余年前の日本の軍隊はどうであったか?
大日本帝国陸海軍はむしろ日本を滅ぼした。
アメリカを見るとベトナムにしろイラクにしろ軍事力で何か解決したか?
答えは誰にでも分かることである。
軍隊は、戦争をすることが仕事である。平和が続けば仕事がなくなる。
多くの場合、軍隊は「仕事」を作り出す。職場を求めて。
軍隊があれば、戦争はなくならない。
仮に軍隊が必要だったとしよう。
この軍隊は、強いほうがいいのか、弱いほうがいいのか?
それは強いほうがいいに決まっている。
世界一強くなければ意味はないだろう。
アメリカより強い軍隊が作れるのか?
アメリカより弱くていいのなら、アメリカとは戦えないということだ。
だからいつでもアメリカの属国になっていればいいのか?
軍隊を強くするには、実戦が欠かせない。
平和な世の中で、実戦の場をどのように見つけるのか?
やはり「仕事」を作り出すししかないではないか。
軍隊があれば、戦争はなくならないのである。
軍隊のある平和なんてあり得ない。
政権交代の必要性
アメリカは、史上最悪の部類に属するブッシュ政権からオバマ政権に移る。
アメリカは、時々大きな間違いを起こすが、これを修正しようとする民意が働くことが救いだ。
”Change”(変革)を求めて民意が動いた。
我々も1968年には「変革」を求めた。
日本も今の閉塞感を打開するには「変革」しかない。
利権屋集団の自民党保守政治が続く限り、日本に明日はない。
首相に「麻生」いいか「小沢」がいいか?
なんて聞いているばかばかしい質問がよく新聞に出ているがくだらない。
今必要なのは「政権交代」である。
「政権」が年中交代すると「不安定」だなんていう人があるが、これは大間違いだ。
年中交代する可能性があるということが、政権に緊張感が生まれ、愚かな政治が
出来なくなるので、むしろ「安定」になるのだ。
「小沢」がいいから民主党を選ぶのではなく、政権交代が必要だから、現在の
野党を選ぶのである。次の与党に一番近いのが民主党どろということである。
民主党が決していい訳ではなく、自民党より多少ましかもしれないというだけである。
また、このような緊張した政治状況では、いつも与党にくっついて甘い汁を吸おうと
する、公明党のような政党の正体があらわになるのである。
「不安定」は「安定」、「安定」は「不安定」につながる。
全共闘「運動」?
2008.11.23東大駒場際の「今語られる、東大、学生、全共闘」という企画があり参加してみた。
第一部の立花隆氏の話は1時間もの長い間やっていたが何ということはなかった。
第二部のディスカッションでは、ゲストに元東大全共闘の最首悟氏、片桐氏、明大全共闘の米田隆介氏が、主催者や現役東大生からの質問に答える形式で進められた。
当然のことであるが、現役東大生は当時のことを知らないので、仕方がないが、私にとっては最初の質問からして違和感を持った。
「どうして全共闘運動に参加したか?」
私は、この全共闘「運動」なる言葉に非常に違和感を感じる。
「学生運動」という言葉があるので「全共闘運動」なんていう言葉が出てきたのかもしれないが、全共闘に参加したものにとっては、全共闘「運動」に参加した、という認識はない。全共闘の「闘争」であって「運動」なんていうものではないと思っている。
大学の不正、不当なこと、矛盾に対し、「それはおかしいんじゃない?」と感じ、それを声にして出す。同じような仲間が、一緒に声を上げ、共闘してその不正や矛盾を追及する。これが「全共闘」だ。
はじめから「運動」があって参加するものではない。
全共闘は、はじめは「問題」ありき、というところから出発する。
「学生運動」は、はじめに「組織=セクト」ありき、である。
似ているようで、基本的に違う。
ただ、日大や東大の全共闘の闘いが始まってから、それを真似て、できた全共闘に参加した人にとっては、全共闘「運動」に参加、といっても違和感がないのかもしれない。
全共闘は基本的には個人の自主的な参加である。
今日参加しても、明日は参加しないこともある。組織に縛られないのである。
それ故、全共闘という闘い方にも限界があるのだ。
全共闘は、「問題」が解決されれば、それで消滅。
新たな「問題」がおきれば別の全共闘が出来て当たり前だ。
また、闘えない状態になっても残念ながらそれも消滅だ。
よく、学者や評論家、あるいは元警察官僚の佐々淳行などが、全共闘は後世に
何も残していない、とか総括がされていない、・・・等々の批判をしている。
私はこう思っている。
全共闘は個々人の自主的な参加で成り立っていた。
個々人の参加の動機だって十人十色、一万人いれば一万通りの答えが返ってくる。
従って一つの総括などありえない。一万人いれば一万通りの総括があるのだと思う。
すでに総括してすっきりしている者、まだ総括しきれずに、悶々としている者、いろいろいるだろう。それが全共闘なのだと思う。
また、後世に何も残さなかったか?
全共闘とは、先にも書いたように、不正、不当なこと、矛盾に対し、「それはおかしいんじゃない?」と声を上げること、これが全共闘の基本だ。
全共闘の闘争以後、このような声はいろいろなところで出ているではないか。
決して特殊なものではない。もう普遍化しているではないか。
上記の討論会については、最首氏の話が一番分かり易く、共感が持てた。
ところで、現役東大生が作成したという資料集。気になったところがいくつかあった。
年表に、ちょうど40年前の前日すなわち1968年11月22日の出来事が記されていない。
意図的ではないことを希望したいが、日大・東大闘争勝利全国学生総決起集会が載っていないのだ。
また、日大全共闘の秋田さんの名前が、わざわざ明大(めいだい)と仮名が振ってある。
徳川慶喜(よしのぶ)を(ケイキ)と呼ぶことがあるが、振り仮名を振るときは、「よしのぶ」だろう。
日大全共闘も明治大学(明大)の学友にはお世話になったが、議長は「メイダイ」ではなかったはず。「あけひろ」さんが正解だろう。
日本に「二大政党制」はふさわしいか?
自由民主党(自民党)の政権が長く続いている。
そして長期政権であるが故の不祥事も相次いでいる。
昨年の参議院議員選挙で民主党が大勝してから、そろそろ民主党に政権交代かと期待も寄せたくなる。
政権交代は必要なことだ。
ただ私は、この自民党と民主党の二大政党制を支持していない。
何故か。
民主党といっても、中身は、旧/元自民党ばかりではないか。
日本は、残念ながらいまだに民主主義が浸透していない。
それは、権力者に従順な国民を作る教育が徹底しているからだろう。
小泉政権時の政策は支持しているわけではないのに、「小泉劇場選挙」では、国民の多くが自民党に入れてしまった。国民の愚かさを象徴する選挙だった。
このように民主主義は浸透していない日本で、二大政党制というのはどのようになるのか。
日本は、談合社会ともいえる。企業でも、役所でも「談合」が日常茶飯事で行われている。
日本で二大政党制が行われて、自民党と(元自民党がいる)民主党だけの政治になったら、どのようなことがおきるか、誰もが想像できることだ。
日本の政治には絶対に3つ以上の政党が必要だ。「談合政治」を防ぐためにも3つは最低必要だ。
3つに限定することも必要はないが、第3に政党の力がもっと強くならなければいけない。
某宗教政党のように政権党に迎合して政権党の利益を享受するような政党は、この第3の政党の資格はない。
「改訂新版・叛逆のバリケード」裏話
1968年に日大全共闘が自主出版した「叛逆のバリケード」(その後三一書房が出版)の「改訂新版・叛逆のバリケード」(三一書房)がそろそろ(2008年9月?)出るという。
「改訂新版・叛逆のバリケード」については、昨年(2007年)末頃から話があって、私にも2月中旬くらいに文理学部(当時)の先輩から「今、あの闘争を振り返って、闘争とは自分にとって何であったかをとらえなおす、という観点で、また930同窓会結成の経緯を含め手記を書いてみないか」との誘いがあった。
私も大学を卒業してからずっと自分としての「総括」をしたいと思いながら、何もせずに
40年経過してしまったこともあり、これを機会に何かまとめたいと思った。
私は「何故闘争に参加したのか」を自分なりに検証したかった。
これは、闘争に参加した人それぞれみな違う、百人いれば百通り、1万人いれば1万通りの答えがあるものだ。
高校に入学したときから書き始めた日記を読み返し、自分の思いを書き綴った。
原稿用紙に100枚程度になってしまった。
文理学部の先輩は、とりあえず三一書房に提示してみるといったが、結局、三一書房からは、原稿用紙15~20枚にしろと、ついては、相談したいと言ってきた。
文理学部の先輩と共に4月3日に新宿で三一書房の関係者と会った。
私は、100枚を簡単に15~20枚にできないと断ったが、三一書房側で、案を考えるとのことで、そのときは別れた。
ついで三一書房の提案は、私の書いた原稿は無視して、インタビュー記事にしたい、といってきたので、それでは私の思いは伝わらない、と断った。
次の三一書房の提案は、何とか30枚くらいに出来ないか、と私の原稿で残そうと考えているところを選択して連絡してきた。
私の原稿も小項目に分けて記述していても途中の経緯で単純になくなってしまうとつじつまが合わなくなるところがあるのでそれを補ったり、自分が言いたかったことを最低限残して原稿を仕上げたが、原稿用紙36枚になった。
三一書房は36枚でも結局許容枚数をオーバしたと判断したのか、文理学部の先輩から、2000字削減した原稿を提示してきたが、私の限界は36枚に凝縮していたので、それ以上の削減は、私の思いを正確に伝えられないと判断し、掲載はお断りした。5月末のことである。
文理の先輩にはご苦労をおかけしてしまったが、なんとも後味の悪い結末だった。
従って、私が「改訂新版・叛逆のバリケード」(三一書房)を買うことはないし、人に勧めることもない。
私のボツになった原稿は、本ホームページの「日大闘争私史」、「管理人の独り言」に掲載している。
エルネスト・チェ・ゲバラ
 alt="guevara">
alt="guevara">
映画「チェ 28歳の革命」を見た。
主演のペニチオ・デル・トロがなかなか似ていて良かった。
この映画は、キューバ革命50周年に向けて制作された2部作のうちの
キューバ革命を成功に導いたときのものである。
最初に「アメリカがもっとも恐れた男、世界が最も愛した男」とナレーションがあるのがいい。
そして、途中に女性記者の「革命家にとって重要なことは?」に答えて「バカらしいと思うかもしれないが、真の革命家は偉大なる愛によってこそ導かれる。
人間への愛、正義への愛、真実への愛。愛のない真の革命家を想像することは、不可能だ。」と。
ゲバラの人間性をよく表している。
1968年の我々が闘っている時には、既にアメリカに支援されたボリビア政府軍によってゲバラは殺されていた。
でも彼は、我々にとってもカッコイイ”英雄”であった。
1968年当時、私が模写した絵が残っていた。
ノーベル賞と学歴
2008年のノーベル賞には日本人が4人も受賞した。
物理学賞では、南部陽一郎氏、小林誠一氏、益川敏英氏。
化学賞では、下村脩氏。
今までの受賞者の多くは、旧帝国大学出身者。
2000年の白川英樹氏(化学賞)が東工大で唯一の例外かもしれない。
今年は、物理学賞には、やはり東大や名古屋大学の旧帝大出身者のほか
下村さんが長崎医科大学附属薬学専門部卒という世間ではむしろマイナーな
大学出身者が受賞した。
非常に喜ばしいことだ。
「自分は(旧長崎医大という)小さな地方の大学の出身だが、それでもノーベル賞を取ることはできる」という言葉にも感動した。
要は大学の名前ではなく、その人のやる気なんだろう。
そのことを改めて教えてくれた、下村氏は素晴らしい。
ところで、話は全く変わるが、ノーベル平和賞の佐藤栄作氏は一体どうして受賞したのか全く分からない。
最近の新聞には、佐藤栄作氏が、中国と戦争になった場合には「米国が直ちに、核による報復を行うことを期待している」といったことが明らかになった。
佐藤栄作という人は、「平和」など全く頭になかった人だ。
日大の大衆団交を否定したのも彼だ。ろくな人間ではない。
ノーベル平和賞とは、きっといかにアメリカ(圏)に忠実だったかを
評価する賞なのではないかと思う。
再び「大学」「教育」について思うこと
フィンランド 豊かさのメソッド」を読んで
「フィンランド 豊かさのメソッド」(堀内 都喜子著 集英社)を読んだ。
フィンランドは、2006年と2007年に学力調査世界一位になったという。
授業数は、日本より少ないということだ。
一体どうしてだろうか?
次のことが挙げられていた。
・質の高い教師
・偏差値編成や能力別クラスがない
・同じクラスでの特殊教育
・学生のカウンセリングとサポート
・少人数制
・進学希望が強い
・平等な義務教育
・社会における教育の重要性が高い
・教師という職業の社会的地位が高い
・安定した政治
・経済格差が少ない
・地域差があまりない
私立学校もないそうだ。
大学への進学は、高校卒業試験の結果以外に、これから専攻したい分野の専門知識も問われるそうだ。
従って、高校を出たばかりで何を勉強してよいか分からない場合は、アルバイトなどをしながら考えて進むべき分野が決まってから進学するということもあるそうだ。
日本のようにただ「大学受験」が最終目的の教育、何でも大学に行って「学士」をとることだけが目的の学生たちとおのずから差が出てくるであろう。
最近、日本では「大学全入時代が迫る中、「学士」の質保証を求める声が
強まっている」なんていうニュースもある。
日本の「教育」そのものが地に落ちている証拠だろう。
受験戦争という意識がなく、リラックスした雰囲気で勉強が出来る環境になっているとのこと。
日本も本当の「教育」を考える必要があると思う。
「大学」「教育」について思うこと(2)
(「さらば『受験の国』高校生ニュージーランド留学記」を読んで)
新聞の書評を見て興味を持った。
読んでみて、作り話ではないかと思うほど、日本では考えられない「教育」、ほんとうの「教育」が行われていることに感心した。
「日本という国はどこかおかしくなっている」からはじまって、日本の教育の姿を、「学校は教育機関というよりロボット工場のように見えた。
それはヒエラルキーに忠実で、疑問を持たない生徒を作っていた。・・・」と。
また「すべての授業が、良いといわれる大学の入学試験に合格することに集約されていた」と書いている。
そして、著者の選択は、高校の交換留学制度のよって、ニュージーランドの交換留学生になった。著書はその体験記というべきもので、元々は、両親に宛てた報告の原稿(英文)を編集したものだとのこと。
日本の「教育」は、著書にもあるように「いい学校に行く」あるいは「大卒」という肩書きをもらうことがすべてのような「教育」が行われている。
その学校で何をするのか、などほとんど問題にされない。
今の日本の大学は、入学しさえすれば、よっぽどのことがない限り、卒業できるのだ。
そのような「教育」に比べて、ニュージーランドで行われている「教育」は、何とすごいことか。
国際的な視野から行われている「教育」といえるのではないか。まさに「国際人」を作る「教育」である。日本の「大学」という狭い世界のことだけ考えた「教育」とは、全く次元が違うように思われる。それも高校のときにそのような「教育」が行われている。
これでは、世界で日本人が太刀打ちできないのは明らかだ。
大分県の教育委員会の出来事は、恐らく氷山の一角であろう。
「教育委員会」というのは本当の「教育」など考えていない。
文部省も物事を考えられる人間を育てたがらない。権力者の、あるいは支配者の言うことを聞く人間(著者の言う「ヒエラルキーに忠実」)が文部省の理想だろう。
それには、教育に携わる人間も、文部省に文句を言わない従順な「教育者」を望んでいる。
それに従って人事を行っているのが教育委員会なんだろう。
「大学」「教育」について思うこと(1)
高校時代、私の成績は悲惨であった。ただ、出来はよくなかったが、唯一物理の授業は楽しかった。物理の先生は、最初の授業で「文部省がうるさいので、皆さんには指定の教科書を買ってもらうが使わない。」と自ら作成したプリントを配った。それ以降プリントから小冊子になった。
実験器具も大手S製作所のものでは物理現象をきちんと説明できないと、これも自作の器具を使って実験していた。
この先生の熱意が私にも伝わって楽しいと感じさせたのである。この先生は現在八五歳とのことだが、最近、中高一貫校になることに対して「エリート校には反対」「高校は学問の面白さを知るところ」と述べられていた。
現在の「教育」は、すべてが「受験」が中心となっている。「いい学校に入るため」である。
「いい学校」に入って何をするかの議論はない。すべての人が「いい学校」には入れるわけがない。
でも「いい学校」には入れなかった人でも、今ではとにかく入学金と授業料を払えば、レジャーランド化した大学に入れ「大卒」の肩書きは何とかもらえる時代になった。
本人が「いい学校」に入りたいと思わなくても、周りや学校自体がそういう「教育」になってしまっているので学校が面白いはずがない。この「教育」は「学問」とは無縁だ。学校は本来「学問」をするところだ。
「学問」の楽しさを教える場でなくてはいけないのである。
小さいときからテストで人より一点でも多く点を取って「いい学校」を目指す「教育」が行われているが、これで本当に社会に役立つ人間が出来るのであろうか。「いい学校」を目指すのもすべて「自己の利益」のためであろう。本来は、「こういう学問をしたいからこういう学校に入りたい」「こういう仕事をしたいからこういう学校に入りたい」でなければならないはずだ。
私の高校時代の日記に、こんなことが書かれていた。
授業終了後の清掃時に、清掃もしないで帰ってしまう人間が多かった。進学校であったので、受験に直接役に立たないことは逃れようという精神の人間が多かったのだ。
そんなことで「いい大学」に入って、高級官僚や大企業の幹部になったって、自己の利益しか追求しない人間になるだけだと思うと。
今、世間で問題になる、官僚の問題、企業の問題は結局は日本の「教育」の問題ではないかと思う。
私の父は、常日頃「学校の名前で飯を食うな」と言っていた。「いい学校」を出たからといって、それだけで驕るなということであり、また「いい学校」を出なかったからといって悲観するなということである。要は中身だと。これが「教育」ではないのか。
「がん」が見つかったときのこと
私は、30代になって結婚後まもなく「がん」が見つかった。
最初は、左の耳のそばに何かしこりがあるのに自分で気が付いた。
当時、私の勤めているところは、子会社の敷地でその中に子会社の診療所があった。
その診療所の医者に相談すると、その医者は「そんなもの、放っておけばいいんだよ」その一言だった。
それでも気になったので、今度は週に1度くらい来る本社の女医さんに相談してみた。
すると「私は専門ではないので、他の事業場の先生を紹介します」とのこと。一番近い事業場の診療所長宛ての紹介状を書いてくれたのですぐに行ってみた。
診療所長の外科医は「ここでも簡単な手術は出来るけど近くの病院を紹介するよ」と紹介状を書いてくれた。
近くの病院にいくと、外来での手術になった。耳下腺腫瘍である。
手術後、病院の医者から「病理検査の結果、悪性の疑いがあるので入院してもう一度手術を行う」とのこと。
入院して手術をし退院したが、今度は「念のため」放射線治療を行うという。
その病院には放射線治療の設備がないので姉妹病院で放射線治療を受けることになった。
放射線治療というのは、体に相当負担がかかるようで、夜中失禁しそうになって目が覚めたことがある。
放射線治療の後もその病院で術後の経過を見てもらっていたが、耳鼻科での診療の際、インターンであったのか、私が「ここにしこりがあるでしょ?」と聞いても、その医者は分からないという。この医者は大丈夫なんだろうかと不安になった。
そんなある日、会社の工場移転のため、家を引っ越すことになり、これを機会に引越し先の公立のがん専門の病院を紹介してもらうことにした。
そして紹介してもらった公立病院で最初に見てもらった医者の一言「手術の仕方が間違っています。また、この種の治療には、放射線は効きません」だった。
そして「再手術が必要です。そのとき下顎の骨も切除する必要があるので、セラミックを準備します」
一体、今までの治療はなんだったのか?
15時間の手術の後、ICUに何日入っていたのか、自分の記憶はない。
その後、入れたセラミックは、感染症のため抜いてしまった。
ハイテク製品は、体が受け付けないということか。
その後、おかげさまで25年生きている。
その公立病院の担当していただいた医長は、優れた医者として有名だったようだが、私が入院中に、若い医者にこんなことを行っていたことを記憶している。
「患者は、いろいろ分からないことを言うが、これをきちんと聞かなくてはいけない。
その中に真実が隠れていることがある」と。言った言葉通りではないが、そんな主旨だった。
私の手術は、患部の筋肉を切除してしまうので他の部分から移植することになっていたが、その医者は、その手術前に何時間もかけて写生をしていた。他の患者でもそうだという。
移植のときの縫い目は細かく丁寧だった。
私の一つの病気で、何人もの医者に出会った。
ピンからキリまであった。
また技術は優れていても、医学が分かっていない医者もいた。
最後は良い医者に出会ったため、「がん」にかかっても25年生きている。
患者にも医者を見る目が必要だと感じた。
中公新書 「安田講堂 1968-1969」(島 泰三著)
この本が出版されてすぐに買って読んだ。
書評を書く能力はないが、感想を若干記しておく。
「日大全共闘」についての記述も多く、また好意的に書いていただいており一応は、満足できる内容だったが、いくつか「おや?」思うところがあった「ひとつの『仮定』」としているが、「日大では右翼・体育会と全共闘が合流したとする」という記述がある。日大闘争を本当に理解しているのかな?
という疑問が湧いてくる。大学当局の私兵としての「右翼・体育会」「合流」できるのであれば、そもそも闘争など起きなかった。
もうひとつ。「大和魂」なんていう言葉が最後のほうに出てきた。
私は、「大和魂」とか[武士道」だとかいう言葉が大嫌いである。
数年前、日大芸術学部の在校生が「取材」と称して、「日大闘争」についてインタビューを受けたことがある。(「取材」の真偽はわからないが。)
そのときに、「当時『武士道』ということを考えましたか?」なんていう質問を受け、私にとってあまりにも唐突な質問であったので、一瞬答えに窮し少し経ってから「そんなこと考えたことないよ」で終わってしまった。
「日大闘争」は、譬えていえば、「百姓一揆」であり、決して「武士」道ではないのである。「武士」などという「支配階級」の闘いではないのである。
私は、「大和魂」や「武士道」は偏狭的ナショナリズムを鼓舞する言葉だと感じており、ともに嫌いな言葉である。
全共闘ベクトル論
「全共闘ベクトル論」などと大仰な書き出しであるが、そんな大層なことを言うわけではない。
何かいい言葉が見つからないので、そんな書き方をした。
何が言いたいのかというと、巷では、全共闘世代に対する、全共闘世代以外の人からの言いたい放題の罵詈雑言。言わせておけばいいのだが、全共闘世代の立場から言っておきたいこともある。
そこで、以下の話になる。
そもそも、全共闘世代とは何か。
全共闘世代とは、全共闘で闘った人たちが属する世代ということであって、「全共闘世代の人」=「全共闘で闘った人」ではない。そこを取り違えて話をしている人がなんと多いことか。
全共闘で闘った人は、同世代の必ずしも多数派ではない。
私はむしろ少数派であると考えている。
多数派でなければ、真理はないのか。それも違う。
歴史をつくるのは、むしろマイノリティからではないのか?
「団塊の世代」=「全共闘世代」これは、大体当たっているかもしれない。世代はニアリーイコールということ。
ただ、ここでも、上で述べたことと同じであるが、「団塊の世代の人」=「全共闘で闘った人」ではない。
私が思うには、「団塊の世代」とか「全共闘世代」とか呼ばれる、私たちの世代の特徴のひとつには、「多様性」があげられるのではないかと思っている。
巷では、「群れる」とか「集団でしか行動できない」とかいわれているが、決して皆がみなそういうわけではないと思っている。
私たちの世代の中には、いろいろな奴がいる。これは、確証があるわけではないが、私たちの世代以前の世代よりは、考えられないほど、多様だったのではないかと思う。
音楽では、ビートルズやグループサウンズ、フォーク。
服装にしろ、髪形にしろ、私たちの世代から新しい物が出てきているし、同じ世代でも、それを好む者、好まない者も当然いた。
今では、誰でも「ビートルズが好き」と言う人が多いが、ビートルズが日本に来た頃は、ビートルズが好きな人間は日本では、少数派であった。
先日、テレビを見ていたが、RCサクセションの仲井戸麗市氏(1年歳下?愛称:チャボ CHABO)も「同級生で、ビートルズが好きだといっていたのは、2~3人だった」と言うような話をしていた。
要は、私たちの世代は「多様化の始まり」なのだと思っている。
全共闘、とりわけ日大全共闘は、決して多数派ではなかったのだけれど、何故、あんなに(当時を知らない人にはわからないかもしれないが)大きなうねりを作り上げることができたのか。
当時の日大生のひとりひとりは、皆、考え方も趣味も、また政治志向も違っていた。それこそ多様化していた。
その人それぞれの、考え方、そしてそれへの思いの強さをひとつもベクトルであらわせるとすると、このベクトルは皆バラバラ。そして、時と場合によっては、その方向も、強さも変化する。
世間で言われている「団塊の世代」や「全共闘世代」評では、画一的な方向を向いたベクトルだととらえているけれども、それは全く違う。
それが、1968年、1969年に、皆のベクトル合成値が極大になったのだと考えている。
日大の場合には、それは1968年9月30日に最大の極大値に達したのではないかと思っている。
ある意味では、皆のベクトルが、ある方向に「共振」or「共鳴」
(ニュアンスは違うかもしれないが)したのかもしれない。
それにもうひとつ。
「全共闘」といっても、全国の大学の全共闘が同じ「全共闘」だったのかといえば、それも”No”である。
多くの大学の「全共闘」がセクトの共闘に近いものがあったが、日大の場合は、ノンセクトが主導であり、むしろ右翼的な連中から、左翼まで幅広く共闘していた。セクトはむしろ脇役であったのではないだろうか。
1970年以降は、日大に限らず、「団塊の世代」のそれぞれの人のベクトルもまたバラバラ。ひとつにまとまる事はなくなったように思う。
2007年以降、また、まとまりそうな雰囲気もあるが、あまり期待は出来ないであろう。
「ニホン」?「ニッポン」?
私は、「ニッポン」という響きが大嫌いである。
「大日本帝国」を連想するからである。
「日本大学」は"Nihon Uviversity"であって、"Nippon University"ではない。
「ニッポンダイガク」ではないのである。
日大を、「ポン大」と呼ぶ人がいるが、間違いである。
「日本大学全学共闘会議」も「ニホンダイガクゼンガクキョウトウカイギ」であって「ニッポンダイガク・・・」ではない。
「日本大学」が良かったのは、「ニッポン」ではなく「ニホン」であったことぐらいか・・・・?
蛇足だが、卒業して、就職した会社は、日本**株式会社で、「ニッポン」であった。