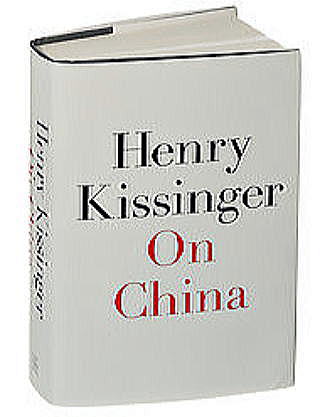中国は巨大な帝国を何度も経験した国で、今や再び大国家を形成しつつある。「一帯一路」の政策はかっての栄光・成功体験の延長上にある。微視的な個人の観察は、3千年にもおよび、人間臭く、掘り下げが深い。巨視的、微視的の歴史史観をしばらく主として宮崎市定の著作で追うことになる。
宮崎市定『大唐帝国 - 中国の中世』
高島俊男『しくじった皇帝たち』
宮崎市定『隋の煬帝』
Henry Kissinger「On China」
宮崎市定『大唐帝国 - 中国の中世』初版は1988年 中公文庫
中国TVドラマ「隋唐演義」では、煬帝の側近宇文化成が、李淵の勢力を殺ぐため、反隋勢力への反撃する役を与え、その勢力を消耗させるという一石二鳥の策を進言する。李淵の次男世民がこの際、隋に反旗を翻すことを父親に説得する。李淵は唐の高祖、世民は太宗で、大きく時代の転換期を迎える。別の李氏に李密という男があり、それより先に、反隋勢力に加わっている。TVドラマは唐王朝の始まる所で終わっているが、この時代の転換を見ようと『大唐帝国』を手にしたら、副題にあるように中国中世史(2世紀~10世紀)本であった。隋唐の記述は、4分の3過ぎたあたりから出てくる。
三国時代から始まるが、三国志お馴染みの人物が活躍する上、歴史家としての知見が示されるので面白い。五胡十六国時代、南北朝と続くが、多くの国の興亡、そこに登場する名君、暴君、暗君、英雄、官僚・・・走馬灯のように描かれる。歴史は人間が作るのであるから、人を描かないと歴史にならない。もちろん、風土、人種、民族、制度、文化などの大きな枠組みを考えるのも歴史学で、本書は両方を満たす優れた歴史書だと思った。
先に放映された中国TVドラマ「武則天」は主役の美女が大いに楽しませてくれたが、歴史的には、則天武后は、一種の暴君で、大量の処刑を行い、唐王朝建国時代の人脈を一掃してしまい、結果的に唐朝後半の繁栄に寄与したことが分かる。
文化史的な記述は殆どない代わりに、制度的、財政的面の記述は充実しており、塩の専売のことなどは特に面白かった。日本についての随所に触れてあって嬉しかった。諸国の盛衰が、人物名と共に次々現れて、年寄りには覚えきれないので、『総合世界史図表』を座右において楽しんだ。

煬帝が父文帝を殺して帝位を乗っ取ったという説の真偽の論考から始まり、この説が、後世が付加した俗説であるということを示しています。
このことは、宮崎市定の本にも出てきますが、幾つかの文献を示してやや詳しく書いてある点、この本の良いところです。
その他は、楊玄感、李密が丁寧に描けていた。
高島俊男の本は昔、『本が好き、悪口言うのはもっと好き』など、専門知識を小出しにして、読者を楽しませる作風の作品を楽しんだ時期があったのを思い出した。この本も同じ作風であった。
なお、TVドラマ「隋唐演義」では、俗説に従って作られています。
歴史として、隋の煬帝そのものを知るには、下記宮崎市定の本が優れています。
『しくじった皇帝たち』の後半は明の建文帝についての記述であるが、これは幸田露伴の「運命」の批判的論考のようなので、露伴ファンの私としては、まず、露伴の作品を読んでから、高島俊男の読むことにします。
2020・12・4

宮崎市定『隋の煬帝』中公文庫(初版は1987年)
「隋の煬帝といえば、誰しもすぐ連想することは、中国史上に稀にみる淫乱暴虐な君主で、大昔の殷の紂王を再生させたような天子というイメージであろう。・・・」で始まるが、まず、そのような暴君、暗君が、掃いて捨てる程いたというこの時代が再現される。
細やかな事実を積み重ねながら、時々、歴史家としての総括、感想が入るのも面白い。南北朝末期の混乱した時代の中で、北方の防衛に当たった軍閥、特に武川鎮が新しい時代を作る。隋という国が立ち上がり、また、滅びて行くかを描く歴史書なのであるが、個人の人物像、人間関係を生き生きと写しているのが特徴である。
煬帝の出来事として、私の頭にあるのは、大運河建設、高句麗征伐の失敗、科挙の開始があるが、前の二つについてはそのスケールの大きさが描かれているが、科挙については本書では触れていない。(同じ著者の『科挙』でははっきりと、煬帝の時始まったことを否定している)
面白く、歴史本が好きになります。
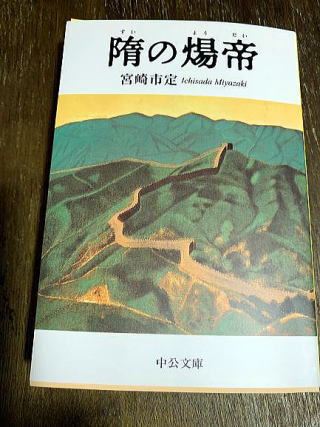
新型コロナ禍で巣籠り生活を続けている中で、テレビが大きな役割を果たしている。最近、我が家では、最近、「武則天」(舞台はAD7,8世紀)を見たのがきっかけ、中国歴史ドラマを楽しむようになった。現在、「隋唐演義」(AD7世紀)、「瓔珞(エイラク)~紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃~」(AD18世紀)、「コウラン伝 始皇帝の母」(BC3世紀)を見ている。
2千年も年代差のある作品(エイラクとコウラン伝)を、しかも、主役俳優が同じ作品を平行して見ると、時々混乱することもあるが、絢爛豪華な王宮、後宮に渦巻く嫉妬と嫌がらせ、権謀術数の政治、戦闘シーン、・・・ひとたび見だすと、目を離すことが出来ない緊張感。セットや衣装の豪華さはNHK大河ドラマ以上の巨額な資金が投じられていると思われる。
娯楽作品であるが、一応史実を踏まえているので、その時の時代背景や、勢力関係などを知りたく、年表や通史を紐解く楽しみが加わってきて、TVにより色々イメージが頭に入ってくると、中国の歴史に親しさが増してくる。秦の時代では文書は木簡なのだが、それがどんな形で使われているかもも分かるし、清朝の後宮の部屋がどんなものだったか、酒を呑むにどんな杯を使っているかなど・・・細部も面白いし、政治の意思決定のプロセスも垣間見ることもでる。ハラハラ、ドキドキさせる大人の電気紙芝居の感もあるが、文献で確かめたいという意欲を起こさせた。
巨視的な通史と細部の伝記的文献とを読み継ぐことになりそう。
(つづく)
2020・11・23

Henry Kissingerの「On China」530頁(邦訳は岩波書店から『キッシンジャー回顧録「中国」』として上下2巻)の面白いところは、このアメリカ有数の知識人、外交家が、中国というものを丸ごと鳥瞰していようという意欲の元に書かれていること、毛沢東、周恩来、江沢民など中国の要人と実際に言葉を交わし、折衝に当たっての実録であることである。特に後者は余人をもって代えがたい。そしてアメリカの立場もよく分かる。
中国の台頭がにわかに意識に上るようになったが、中国は世界史上、大国であった時の方が多く、さらには辺境民族との抗争が歴史のダイナミズムを作ってきた国だから、巨視的に捉えなければならない。いろんな中国論があろうが、本書も優れたものの一つと思う。
ー-------
この本は、処分して今手元にはない。
中国に関する洋書は、当然のことながら、人名、地名がアルファベットと表示なので、日本人には頭に入りにくい。巻末に人名対照表が付いていても煩わしいものである。
日本人には中国人の名はは漢字でないと困るし、落ち着かない。
2022・8・19 追記