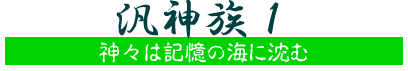|
号羅の城がある、エスンの街は開基以来の活気で賑わっていた。
今日あるという号羅の人間に向けた告知を見ようと、物見だかい旅人たちが街に集まったのだ。
汎神族があらかじめ人間に対してなんらかの告知をする前例は以前にもあった。そしてその多くは人間を驚かす内容だった。
もっとも時代の近い告知は「ラブドエリスのリ・ラヴァーが各地に八千体撒かれる」というものだった。
そのことはしかしほとんどの人間にとって意味を持たない言葉だった。リ・ラヴァーの存在自体が刑罰であることをどうして人が理解できよう。人から見たとき珍奇に思える不思議さも含めて汎神族の言葉は人に影響を与えた。
内陸の湖、モス湖に面したエスンは、かつてのグリュースト閥の街、栄別のあとにできた古い街だった。針葉樹の森がうっそうと茂る、緑の豊かな土地ではあるが、黒い葉を持つ木々は人にやすらぎを与えてはくれなかった。
本来の人口は少ないが、内陸の通商の要として、常に多数の外国人が居住していた。各国の情報が集中し、拡散していく、大陸の神経節にあたる街だった。
「リ・ラヴァーって見たかい? あんた」
広場に集まった行商人らしい男が、地元の老人に聞いた。
「いや、見てねえ。今度はなんの発表だろうね。この間のリ・ラヴアーは八千人も造ったっていうけど、全然見てねぇ。えらいべっぴんだっていうじゃないか。今度は八万人くらい造ってくれないかね」
「まったくだね。このあいだ行った国じゃ、王子どもがリ・ラヴァーを嫁にしようとして大変だったぜ。神様も罪なことをするね」
「あんた、食わせていけるんかね?」
「うーん、いきなり八万人も年頃のぺっぴんが出てきたら、えらい騒ぎだろうね。年頃の娘たちが鬼っこになっちまわあ」
「おっ、見なされ。号羅様の告知が立てられるぞ」
号羅が好んで使う蜘蛛型の従属生物が、広場の一段高くなった土留に立看板を刺した。
「おっ? なになに。なんだこりゃ。求人状だぞ」行商人が言った。
「求人状?」
「えーっと、号羅様の城から荷物を運び出すのに人間を大勢雇いたいってさ」
「号羅様は引っ越しでもするのかな?」
「さあね。褒美はなにかくれるのかね」
「別に書いてない。でもきっとなにか良いものに違いないだうさ。あんたいくかね」
「号羅様はわしらの神様じゃからね。行くにきまっているさ」
行商人は立看板を刺した蜘蛛型の従属生物に聞いた。
「あんたさんさぁ、これぁ、なにを運ぶんだい? あんたたちだけじゃできんのかい?」
「樽を城から運び出す。その数はあまりにも多い。人間の助力が必要である」
器用な発音で蜘蛛は答えた。
「樽? 樽って樽かい」
理解しがたいことを聞いた人間の顔で男は尋ねた。
「酒樽のような大きさだと思えば良い。それを城の外の広場に並べるのだ。それはたやすい仕事だ」
「ははあ、そうかい。なんでって聞いても教えてくれんのだろうね」
「知る必要はない」
気門からスースーッと音をたてながら従属生物は言った。
「えーっ。でもさ、号羅様の告知があるっていうから、こんなに人が集まったんだ。それが樽を運ぶのを手伝えだけじゃあな」
回りに集まった大勢の人々のあいだから、一斉に同意の声があがった。
「まったくだ。俺たちはこの街の者じゃないんだぞ」
蜘蛛型は表情のない眼で人間たちをぐるっ、と見渡したあと大声で言った。
「聞け、人間ども。号羅様は亜ドシュケ閥・雅流様と問答を試みるおつもりである。神々の直問答が見られる機会など、貴様らには金輪際ないと思え。樽の運搬はそのための神聖なる用意である」
人間のあいだからどよめきが起こった。
「雅流さま……?」
「雅流様と言ったぞ」
若い神の名前が人間のあいだにじわじわと広がっていった。
「雅流様! 雅流様か。レンスファの地の」
老人がうれしそうに笑った。自分の知る神の名を異国で聞いた人間の誇らしさを持って、号羅の地元の老人が笑った。
「知ってるのかい」と、行商人。
「なんだ、あんた知らないのかい。たいしたことないね」
「失礼しちゃうね。知ってるよ。あんたが知ってるのに驚いたんじゃないか。旅もしないあんたがどうして知ってるんだ?」
「いま、雅流様を知らない奴はいないんじゃないか? 偉大な美しい神様だって」
蜘蛛型はそんな人間たちの騒ぎを無視して叫んだ。
「すぐに城に向かえ。樽の数は膨大である。すべては号羅様にとってかけがえのないものである。命をかけて扱え。人間ども。号羅様に報ぜよ」
「蜘蛛様。問答ってのはいつあるんだ?」
誰かが聞いた。
「明日か、明後日か。いつかはわからぬが、期待を裏切らぬ近日だ。雅流様の御心ひとつ」
号羅の城が立つその地は、かつて汎神族の神殿があったとされているアカベツの丘だった。汎神族が自らの宗教を持ち、神を持っていた時代の伝説の地だった。
すでに遺跡は風化していた。赤茶けた土の山が点在していることが、かつてそこに鋼鉄の建築物があったであろうことを示していた。
日が落ちようとしていた。
城の前の巨大な空き地には、緑色をした不思議な素材の樽が、競馬場ほどの広さを占めて並んでいた。ワイン樽ほどの大きさのそれは、見かけ以上に重い。しかし集まった数万人にも及ぶ人間たちによって、城の地下から短い時間で搬出されて並べられた。
城の回りにはグリュースト閥の博士が数柱と、護国法兵士が五柱立ち、法円を組んでいた。そのなかには由美歌の姿もあった。
さらに外側には、丘が湖に没するのではないかと疑いたくなるほどの数え切れない人間たちが集まっていた。
月が天空に光り、星がまたたき始めていた。だが号羅、雅流の姿はいまだになかった。
城に向かってすさまじい量の視線が集中していた。まるでそこに降り立つ者を焼きつくそうとしているかのようだった。
「おいおい、こんなふざけたところに雅流が来るもんかよ」
観客にまぎれて丘に近づいたラブドエリスがギュリレーネに言った。
「…………」
ギュリレーネもそれは同感だった。
雅流の性格をよく知っているギュリレーネにとって、このお祭り騒ぎは嫌悪すべきものだった。
「でもよ、レンスファの村で贄の儀式をやるときはこんな感じだったな」
「贄の儀には神の尊厳と、畏敬の念があったわ。それがこれはなに? 相撲でも見るようじゃない。号羅様の気が知れないわ」
そのとき丘の遥か左端から花火のようなものが空に上がった。
人々はどよめき、光を目で追った。赤い火の玉は、ちょうど丘の中央の上空で破裂して七色の火の粉を散らした。
壮麗な眺めの正体は知れなかったが、なにかの始まりを告げているに違いなかった。
かすかに響く高い音が、空を右から左へ、北から南へと縦横無尽に駆け抜けた。人間の間からどよめきが漏れた。
「なんだ?」
ラブドエリスがいぶかしげに聞いた。ギュリレーネにもその意味はわからなかった。
火の玉に応えるように、城の右の空高くから丸い玉が落下してきた。
夕焼けの逆光に浮かび上がったそれは、不思議にゆっくりと落ちてきたが、杉の大木の頂上ほどの高さで破裂した。
中からは細い光の紐が四方八方に飛び散った。
「おおっ」
人間の口から低い歓声が漏れた。
「花火大会かよ」
ラブドエリスは呆れてささやいた。
「おい、ギュリレーネ。いったい……」
ギュリレーネを振り向いたラブドエリスは、ぎょっとして言葉を止めた。
ギュリレーネが耳を押さえてうずくまっていた。人間の姿が透けていた。本来の銀色の毛並みがかすかに見て取れた。
「お、おい。どうした。大丈夫か」
ラブドエリスはマントを広げてギュリレーネを隠した。回りの熱狂した人間たちはまったく気がついていない。
「……聞こえなかったの? すごい高速言語よ。こんなに圧縮されたものは初めて……ううっ……!」
再びどこからか火の玉が射ち出された。
汎神族は身じろぎしながら、それに耐えていた。
号羅たちの姿は見えないものの、華麗な光のショーに人間たちは熱狂した。
「号羅様。戯れがすぎましょう」
アリウスが言った。
「興味深い実験体。アリウス君。私は人間を愛する。いつでも我が元に来るが良い」
号羅は気さくな笑顔を形作って笑った。
「隷ラディオのように。宗旨にこだわらず、私は迎え入れるだろう」
アリウスが応えて言った。
「私はゾンビロウを愛せません」
彼らはすでに城の尖塔のうえで対峰していた。空中に浮かぶようにして、遥か眼下の人間たちを見下ろしていた。
位相遷移により、ラブドエリスたちのいる現実の空間から二相ずれた異界にいた。
示し合わせたわけではない。彼らは同じ手段を選びこの地に至り、そこで会ったのだ。
号羅は一柱で。雅流はアリウス、アピアをともなって。
「機械学は人間むきだと思うがね」
号羅は回りに透けて見える人間をオーバーなジェスチャーで指さしながら言った。
彼の柱は存外に若い神だった。
雅流とさして違うことはないだろう。汎神族としては修行中の扱いを受けても当然の年齢に見えた。
その容姿は豪紗。
赤みがかった金髪にきついカールがかかり足元まで垂れていた。肌の色は健康なピンク。汎神族にしてはがっしりした骨格で、極めてスタイルよく見えたが、けっして筋肉質でも痩せすぎでもない。
スタイルを自負しているのか、自分の美しさを誇示するためか、服装は軽微なものに止められていた。ほとんど裸体と言ってもよい、わずかな布切れで身体を隠していた。
しかし輝く眼は、膨大な記憶を継ぐ神にふさわしい深く鋭い紫に光っていた。
絵画のように美しい深紅の唇がゆっくり開いた。
「この場は人間にとって、神の偉大さを知るところであり、我々のいずれがより良き回答を提示したとしても、汎神族への尊敬はいや増すことだろう。我が汎神族にとっては、忌まわしき記憶溢れへのひとつの回答が用意された場として、多くの記憶に残る場となろう」
「前置きは良い。私も貴公の実験には多いに興味がある。話しを聞こうではないか」
雅流がゆっくりとまぶたを開き言った。
「善哉、善哉」
ほがらかに号羅は笑った。
「貴公と貴公の祖先。私に記憶を与えし者たち。すべての汎神族の願いである記憶溢れ克服は、いま二つの回答の可能性が用意された。すなわち貴公の成しえた実験。事象発生確率による記憶溢れ以前の身体召還と、時間循環による状態固定。超絶の業績である」
「二つとは?」アリウスが聞いた。
「私が言おう」
雅流が号羅をさえぎるように言った。
「私はグリュースト閥への尊敬を禁じえない。大いなる過去に、記憶抽出の技を実現していたとは。まさに偉大なり」
それは聖火香によるアリウスへの記憶潜行の最大の発見だった。
「さすがに雅流殿。事情を知ることは光栄である。では言葉遊びはもうやめよう」
「応」
「私は請う。貴公との共同研究を」
「否」
雅流は一言のもとに否定して言葉を続けた。
「私も言おう、号羅殿。貴殿の研究を私は欲する」
アリウスは、ぎょっとして雅流の言葉を聞いた。なんと率直な物言いか。
「勿論、否である」
号羅もやはり毅然として答えた。
「雅流殿。我々の研究成果は絵そら言ではない。具体的な結果をすでに出している。これを推し進めることは、汎神族全体にとっての利益となるであろうに、貴公はそれを妨害しようと言うのか? 御自身の研究にしがみつき、我が種全体の利益は顧みないおつもりか。それはあまりに狭量である」
「……なんと」
一方的な言葉に驚いたアリウスは、雅流を仰ぎ見た。
「汎神族としての義務を果たさんと欲すれば、貴公は私に研究を公開すべきである。それにより記憶溢れ克服の栄光は貴公のものとして記憶されることだろう」
黙って聞いていた雅流は、ゆっくりと口元に笑みを形作った。
「号羅殿。貴殿は考え違いをされているようだ」
「ほお?」
「聞くが良い。未曾有の知恵を持つ者よ。私は貴殿の研究のすべてを欲しているわけではないのだよ。なに、ほんの暇つぶしに見てみたいだけのこと。貴殿が見せたくないというのなら、それはけっこう。私の研究には貴殿の成果は必ずしも必須ではないのだから」
雅流は余裕の微笑みを浮かべて言った。
「貴殿とてそうであろう? 号羅殿」
「…………」
号羅は挑むように雅流をにらんで言った。
「では言おう。私は自分の研究をお渡しするつもりはないが、どうしても貴殿の研究がほしい。どうしたらよいものだろう?」
雅流は再び目を閉じた。
「欲深い者は焦りを持ち失敗をする。貴重な実験にやり直しはきかない。貴殿が研究の真の意味を捕らえずにそれを玩ぶよりは、私がその完成をめざしたほうが有意義であり、安全というものだ。そう考えるだけの器量はないのかね?
私は貴殿を尊敬しているのだよ。どうか私を失望させないでほしい」
「よくわかった。もし貴重な実験成果が失われたとしても、それは貴公の責任である。私は最大限の努力を惜しまなかったことを記憶せよ」
「笑止」
雅流が言い放ったそのとき。号羅は第五階梯の法呪文を発した。
最高位の法呪は、城とそのまわりのあらゆるものを発光させて揺さぶった。物体を髄から奮い立たせる不可思議な力があたりに満ちた。
「知識とはいかなるものかをご覧にいれよう。さすれば己の無力を知り、我が実験に参加することを希望されるに違いない」
号羅は法呪文を唱えつつ言った。
広場に並んだ数え切れない樽が反応を始めた。ひとつひとつがゆっくりと揺れ始めた。中に詰められたなにかが活性化し、甘酸っぱい芳香がたちこめた。
樽がゆっくりと地面を離れた。回りを取り囲む人間たちの驚きの声に応えるかのように、くるくると回転しながら、ゆっくりと空中に浮いた。
雅流はその様を楽しむかのように、妨害もせずに見つめていた。
やがて樽は空中で、ピラミッド状に積み重なあっていった。下から上に三角形に成長していく樽の山は、見る見る高さを上げていった。
小山ほどの大きさにも成長した樽のピラミッドは、一塊のまま重々しく動き始めた。
それは城をかすめるように上昇を続けて、位相遷移をした号羅に近づいた。
号羅は眼下に展開する光景を満足そうに見つめていた。まもなく樽の頂上は彼の足元に達した。
「これがなにか理解できるだろうか?」
号羅が聞いた。その目は汎神族にふさわしい威厳と傲慢さに輝いていた。
「雅流殿。これこそが知識だ。無限の力だ。私の研究の集大成であり、汎神族を救う唯一の完璧なる技術だ」
うわぁん、と空気が鳴っているようだった。
「先人の貴い犠牲と献身が我々を救う。そして未来の子らを生かすのだ」
城の回りを不快な振動が満たしていた。アリウスとアピアは耳を押さえて身をよじった。船酔いに似た、こみ上げる吐き気に懸命に耐えた。
不吉な振動は樽に発していた。
樽という樽から不自然な音が漏れ出ていた。それはあたかも法呪文を低速で唱えているような、生理的嫌悪感をもよおす振動だった。
「……それはいったいなにか?」
雅流が確認するように聞いた。
「貴公は知っているはずだ。我がグリュースト閥の老神の記憶を継いだアリウス君がそれを知っているのだから。のお、アリウス君」
アリウスは知っていた。記憶潜行により得られた不吉な知識。その樽は「病の館」で行われていた実験の結果であることを。
号羅は言葉を続けた。
「これが真に汎神族を助命する技術の証明である。選択的記憶抽出による……」
「やめよ!」
突然、声が響きわたった。空気が言葉を持ったような圧倒的な命令だ。
「忌まわしい言葉を続けてはならぬ」
空を揺るがせて声が鳴り響いた。音のひとつずつに法呪の力を持つ強制力で、いずこかの神が言い放った。
あまりの力に空は雷を吐き出し電光を走らせた。雲一つない夜空に、青白い電気の光が突き刺さった。
「……貴公は何者か?」
己の言葉をさえぎられた号羅は、腹立ちを隠しもせずに怒鳴り返した。
「号羅よ。貴様の実験は閥への申請を越えた不当なものである。ただちにこの場を納め、城に入れ。追って沙汰する」
「なんだ。グリュースト閥の御老体か」
号羅は相手が知れるや、鼻で笑って緊張を解いた。
声はグリュースト閥総本山に住まう、閥の最高宮司たちのものだった。六人の古い血を持つ神たちが、法呪による意識結合を行い、あたかもひとつの意志であるかのように、閥にかかわる最高決定を行っていた。
意識結合され、一柱のように振る舞う仮人格が俗に御老体と呼ばれていた。
その最高意志が号羅に命令を出したのだ。
「貴公の不遜な態度はなにごとか!」
ふたたび雷が空を裂いた。
「雅流殿。頓着せずともよい」
「号羅!」
「過去の記憶を元にしか考えることも感じることもできない彼らには、我々の実験の偉大さを理解できようはずもない」
「ならぬ。ならぬ! それ以上の妄言は許さん。貴様は我が閥の実験を盗み、曲解している。貴様のやろうとしていることは汎神族の尊厳を踏みにじることだ」
「わはははは。聞いたか、聞いたか?
雅流殿。これを笑わずにおられようか」
号羅は樽の上で腹を抱えて笑った。
「御老体たちは勘違いをされているようだ」
「なに? なにをたわけておるか」
「御老体。発言を許していただけるか」
雅流が両手を高くかざして言った。
「亜ドシュケ閥・雅流殿。なにか」
鳴り響く声だけの神が言った。
「光栄でございます。私は一度記憶溢れを起こした身でございます。その意味ですでに死に体。ゆえに自分の実験を進めることこそ第一義と考えます」
「うむ」
「号羅殿の樽の中身は汎神族から機械的に吸い出した記憶。知塩ですね」
不意討ちのように雅流は言った。
雅流の言葉はラブドエリスたちのいる通常の世界にも漏れだした。
白い火の粉となって広場を埋め尽くした人々の上に降り注いだ。
「……知塩」「知塩?」「知塩だ」
「知塩ってなんだ」
「知塩だ」
白い火の粉となった雅流の言葉は、麻薬のように人の身体に染み込み、包含した意味を伝えた。
神の秘密が言葉よりも確実な方法で人の脳髄に達していった。
「神様から作るらしい」
「機械だ。神様を機械にかけるんだ」
「神様から機械が吸い出すらしい」
「記憶らしい」
「神様から記憶を抜くらしい」
さざなみのように驚きが広がっていった。
「……おお、おおっ! おお! 雅流殿! なぜだ。なぜそのようなことを知る? なぜ人間ごときに知らせる」
無様なほどうろたえた声の神がうなった。
「人間どもに知らせてなんとするのだ。我がグリュースト閥をおとしめることが願いか」
怒りと悲しみに翻弄されつつ、声の神は雷で言葉を紡いだ。
雅流はそれらの一切を無視して人間たちに向かい声を放った。
「畏れるな。人間よ」
よく通る肉声で、広場に集まった人間たちに言った。
「雅流である」
人々の間から明るい驚きの声が上がった。不安な状況下で自分の知る者に出会ったような理屈抜きの歓声だ。
「私はここにいる。雅流はここにいる」
広場に不思議な安堵感が流れた。世に広がる偉大な雅流の噂話しが脳裏によみがえった。親に対する子供の信頼にも似た、理屈のない安心感が人々の心に沸き起こった。
「雅流様!」
アリウスが警告を出した。同時にアピアの喉を使って、雷撃の法呪を放った。
「ううっーーむ」
号羅がうなり声をあげた。
雷撃は急迫してきた号羅の前面に炸裂した。
雅流が人間に呼びかける、わずかな隙をついて肉薄していたのだ。
「こしゃくなり」
しかし号羅は接近を止めることなく、樽の上に立つ姿のまま、襲いかかってきた。
「見よ! 雅流殿。これが我が実験の成果である。我が祖先の成しえた実験の累積である」
号羅が大きく口を開いた。眼が狂気の科学者の歓喜に満ちた。
「ガ、ガッ、ギイィィィーーー…………」
それは聞いたこともない法呪文の奔流だった。
火でも水でも質量でもない、単一の機能を持つ法呪文ではない。複雑怪奇な攻撃法呪だ。
金属を研究する神の法呪、農業をなりわいとする神の法呪、経済の法呪、毒の法呪、水の法呪、そして戦争の法呪。
ありとあらゆる分野の攻撃法呪が、一撃となって炸裂した。
「…………ジ…………」
雅流とアリウスは知りうる最高の防御法呪で第一撃を避けた。反射された奔流は月までも届きそうなすさまじさで夜空に消えた。
声の神も今は言葉を失っていた。どこかで号羅の超絶の技に目を奪われていた。
それはまさに汎神族の歴史に記憶されるべき技だった。
けっして有り得ぬ、多分野の神の記憶の保持が、現実に行われているのだ。一柱の神が物理的に、時間的に成しえない様々な学問の求道。そしてその成果の記憶と駆使が、いま号羅の手により成しえられているのだ。
それはまさに無限の記憶力の実現にほかならなかった。
可能性は語られながら、実現を不可能とされていた神々にとってさえ空想の法呪。
無限の知識の活性化と利用。
間違いなく号羅の意志の元に、気の遠くなるような膨大な記憶が活用されていた。
「見たまえ。雅流殿。このすばらしい知識を、記憶の海を」
号羅は歓喜に震えながら叫んだ。
「我が実験の成功を。そして聞け。我がグリュースト閥の御老体よ。我々は鉄士別の昔から機械学による記憶の抽出を実現しながら、己の記憶を失う恐怖のために、これをタブーとしてきた。しかしいま、抽出したそれを知塩として自在に活用する術を得たのだ」
いま、この場で行われている戦いを遠視していたすべての汎神族が号羅の言葉に息を飲んだ。
「我が実験の成功を見よ。そして讃えよ。汎神族はこの瞬間から記憶溢れの恐怖におののくことのない繁栄が約束されたのだ」
わずかな時。世界は静寂に包まれた。
汎神族と人間の意識に、その意味が染み込むためのわずかな時間が流れた。
「……号羅」
最初に声を上げたのは、意外にもグリュースト閥の御老体だった。
「我は讃える。号羅博士」
偉大な言葉を合図に、ゆっくりと感動の輪が広がっていった。
「……すばらしい」
「優秀である。救いである」
「すげぇ、神様だ。ありがたや、ありがたや」
「号羅様ーーーー!」
賞賛の絶叫が、汎神族と人間のあいだから同時に沸き起こった。地鳴りのような喚声が津波のように広がり鳴り響いた。
「号羅・号羅・号羅・号羅」
彼をほめ讃え、あがめる声が草原の野火のように大地を覆い吹き上げた。
「号羅博士。我が閥の誇り。すべての神が讃えるべき偉業になり」
御老体が宣言するかのように言い放った。
歓喜の声は一層高く響きわたった。
号羅は満足そうに、きわめて満足そうに天を降り仰いだ。
「御老体に感謝する。我が実験の真価に迅速なる理解を持って応えられる洞察の深さに感動を禁じえない」
「………………」
その騒ぎのなか、アリウスはアピアとともに雅流の背後に隠れ、密かに法呪文を紡いでいた。小さく抑えたアピアの高速言語は、すでに二十万文字を越えていた。
雅流は号羅の実験をうれしそうに笑いながら見ていた。
「まったくすばらしい。貴殿の成果を讃える言葉を私は持たない」
ぱちぱちと、人間流に拍手をしながら雅流は笑いかけた。
「私のつまらぬ研究など、貴殿の偉業に比ぶれば、クンフほどの価値もない。なぜ私の実験を望むのか」
|