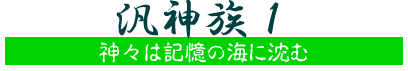|
隷ラディオを始めとした部隊の失敗は、グリュースト閥中央に衝撃を与えた。護国法兵士までが帯同して、なおかつラブドエリスたちにしてやられるなど、想像も及ばないことだった。
グリュースト閥は他閥への影響を鑑みて、この件の一切を号羅に預けることとした。
グリュースト閥は、号羅の進言により雅流の野望を了解し、正義を持ってこれを妨げようとした。その動機は公正であり、神の名にふさわしい行いだった。それゆえに護国法兵士の出動は、宗派間調停委員会に申請して認可もされた。
しかし他の閥は、特に雅流の属する亜ドシュケ閥は、これをグリュースト閥がラブドエリスとギュリレーネの攻撃を受けたことへの私怨であると批難した。この件についてはラブドエリスがすでに罰を受けているとして、疑問を呈した。すなわち八千体ものリ・ラヴァーを造られるという、万死にも勝る罰を受けていると。
グリュースト閥中央にとっても、これ以上の積極的介入は、閥自体の不利益につながると判断された。
しかし号羅にとって、それはあながち不利な状況ではなかった。むしろ歓迎すべき状態であると考えていた。
「ひいーっ。ひいぃっーー」
号羅の城に隷ラディオが転がり込んできた。巨大なカケスを知性化した従属生物の脚にぶらさがり、ほうほうの体で逃げ帰ってきた。
首だけの姿は無様であるが、眼は凶悪に血走り、決死の光を宿していた。
「号羅様、号羅様。どこにおいでですか。おおっ、卑劣な奴めらにしてやられました。号羅様、無知で恐怖を学ぼうとしない、あのけだもの達は畏れ多くもこの地を目指しております。号羅様、ご用意をなさいませ」
床に転がった隷ラディオは火を吹くような激烈さで呪祖の言葉を吐いた。
しかしどこからも返答はなかった。
号羅の城はいつも通り、暗く湿って生命に溢れていた。しかし号羅の気配が感じられなかった。従属生物は汎神族の気配に敏感である。そこに神の息吹は感じられなかった。
「……号羅様? どちらにおいでです。号羅様! 城を捨てられたのか? 号羅様」
隷ラディオの叫びが広い通路にこだました。 号羅はある意味で雅流に近い神だった。汎神族には珍しく、積極的に己の実験を押し進めていた。己の実験の可能性を信じ、祖先からの記憶を最大限に活用することを良しとした。
彼も雅流らと同じに、汎神族の記憶溢れの解消をテーマに持ち、長く研究を続けていた。
彼は機械学による方法論を用いていた。すなわち鉄士別の「病の館」に端を発する法呪と機械学の融合を目指した研究だった。
彼は雅流になんの恨みもなかった。雅流や聖火香の研究に嫉妬するものでもなかった。むしろ尊敬さえしていた。ただ、自らの研究の優位性を信じ、成功にみじんの疑いも持っていなかった。
ゆえに機械学による研究のあり方、実現の姿を汎神族各閥に誇示する絶好の機会であると考えたのだ。
彼はこれから起こるであろう、雅流との接触を最適な研究発表の機会ととらえていた。そのためラブドエリス達への恨みに燃え、倒すことを考える隷ラディオはうっとうしい存在になりつつあった。
「……隷ラディオ」
遠呼声で号羅は呼びかけた。
「号羅様! 号羅様ですか? どこにおられるのですか。お姿をお見せくださいませ」
隷ラディオは主人を見つけた犬のように狂喜した。首だけの姿で床をごろごろところげ回り、号羅の姿を探した。
「私はそこにはいない。忠実なる隷ラディオよ。このたびの失敗はおまえの責任ではない」
「ああっ、ああ。真理に近い御柱よ」
「しかし、おまえはできうるかぎりの挽回をし、正当な実力を示す機会を望んでいるに違いない」
「お、おおっ。それは、もちろんでございます。外道の手段を好むラブドエリスごときに本来遅れをとることなど、万に一つも有り得るはずがないのです」
「よい。私は雅流殿と語り合う場を設けたい。ラブドエリス、ギュリレーネらをもてなすことはおまえに任せよう」
「光栄の至り! 至福のご命令!」
「ただし、言っておく」
「はっ」
「戦うな」
「……なんと、いま、なんとおっしゃいましたか」
「これは命令である。けっして戦ってはならぬ。私が雅流殿と会議するあいだ、妨げとならぬように、茶の席でも設けるがよい」
「この……この私にラブドエリスと茶をしろと?」
「彼はなかなか愉快な人間だ。おまえも学ぶところがあろう」
「号羅様! お戯れにもほどがございます」
「戯れではない。命令であると言ったはずだ。偽りではない証拠に、おまえに身体をやろう」
神の言葉とともに、壁の隙間に巣喰っていた蟻たちがいっせいに隷ラディオの首の下に集まりだした。
「お、ほおっ、こ、これは号羅様……」
「おまえには、より汎神族に近い身体をやろう。私はこれで死後に億にもちぎられることになるかもしれぬな」
そう言って、号羅はさもおかしそうに笑った。
「…………尋常ではない…………」
隷ラディオは処置を受けながら、漠然と考えた。汎神族の考え方ではないと思われた。
「しかし良しとしよう。我が名が汎神族の記憶に留まるならば」
「号羅様、あなた様はいまいずこにおられるのですか? この身体ができ次第、あなた様の元に駆け参じたく思います。どうか、私に尽力の機会をお与えください」
隷ラディオは号羅の精神状態を疑い、そばにいることを希望した。雅流のように記憶溢れを起こしつつあるのではないかと。
「心配には及ばぬ。いまここにおまえがいたとして、助けにはならぬ。おまえはラブドエリスに対して本分を全うせよ」
「……御意」
隷ラディオの新しい身体は、時間をかけて少しずつ形になっていった。
ラブドエリスが意識を取り戻したとき、そこは雲の上だった。聖火香の造る不思議な泡に包まれて、はるか空高く舞い上がっていた。
泡の表面からは、始終水蒸気のような白い煙が風に飛ばされていた。まったく音は聞こえないが、外はすさまじい風が吹き荒れているらしい。
はるか彼方の空が紫色に染まっていた。ラブドエリスは初めて見る、高い空の上からの朝焼けだった。
ギュリレーネは傷こそ癒えているものの、まだ意識を取り戻していなかった。
「聖火香様。雅流たちはいったいどこに」
「いまどこにいるかは知らない。転送の法呪を発動したのはアリウスだから。ただしどこに向かうかはわかる」
「どこに?」
「グリュースト閥。号羅の城だ」
「まさか。なぜ、いきなりそんな無謀なことを。護国法兵士が集っているかもしれないのに」
「ならば、なおのこと、そこに行くだろう。雅流の実験はひとつの成功をみたが、いまは行き詰まりに陥っているはずだ。すなわちアリウスの実験、知塩による我が種の記憶保存のあり方についてだ。これは号羅が得意とする分野だ」
「機械学でですか?」
「私も雅流も機械学を否定するものではない。雅流は号羅の研究を利用しようとしているに違いない」
「しかし号羅様が研究を公開するでしょうか」
聖火香はアリウスの記憶潜行を思い出していた。記憶を吸い出す、あの技法は汎神族に衝撃と嫌悪を感じさせることだろう。
「自ら公開することはあるまい。それでも雅流は知ろうとするだろう。彼は自分の不安定なことを知っている。強引な手段も厭わない」
ラブドエリスは複雑な想いでそれを聞いていた。どんどん過激になっていく雅流。
「さらに、おそらく雅流は号羅、グリュースト閥、そしてすべての汎神族に、己の実験の成果を見せつけるつもりだ」
にやり、と笑いながら聖火香は言った。
「おまえの影響を多分に受けているからな」
「ええっ?」
ラブドエリスはなんのことかわからずに聖火香を仰ぎ見た。
聖火香は手にした長い杖によりかかるようにして、ラブドエリスに笑いかけた。
「雅流を知る汎神族のあいだでは、おまえはよく知られているのだぞ。奇妙な人間。雅流の教育係として」
「教育係?」
「雅流のような古い血の一族は、その記憶量に甘んじて傲慢になることが多い。知るべきことは知っていると考えるのだ」
朝日が近づいてきた。聖火香の美しい姿が赤紫の光に照らし出されて、きらきらと輝いた。
「かつての雅流がそうだった。修行僧とは名ばかりの自堕落な生活を送っていた。しかしラブドエリス、おまえに逢ってから彼は変わった」
「俺はなにかしましたか」
「その傍若無人さが良かった」
「ぶっ」ラブドエリスは変な声を出した。
「非常に良い刺激となったようだ。前向きな性格に変わった。積極的に事に当たることを学んだ。人間がペットと精神的に依存関係にあることが見受けられるが、汎神族と人間の関係はさらに密接だ。影響を受けるのは双方向のことだ」
人間が神に影響を与えることがあるなど、考えもしなかった。
「ただし、それが高じて今回の騒動になったのだがな」
「俺が……雅流を破滅に導いたのではないでしょうか」
ラブドエリスは悩み続けていた言葉を口にした。
「気にする事はない。雅流は記憶溢れを起こしたではないか。なんでもありだ」
拍子抜けするほど、さばけた聖火香だった。
「いまの雅流は不安定な存在だ。いつ消え失せても不思議はない」
「聖火香様の実験は成功したのではないのですか。雅流は姿を結びましたが」
「しょせん不安定な事象発生確率だ。マロウン・隷ラディオの姿を揺れ動く、あの装置を見たであろう? まだ完成には至っていない」
ラブドエリスは聖火香の言葉に息を飲んだ。
「では、雅流は姿を止められずに、消えてしまうこともありうると?」
「事象発生確率がペドロ値を切れば、彼は消える。いまの彼は実態をまとう幽霊のようなものだ」
聖火香はラブドエリスの肩の玉石を指さして言った。
「彼の時間循環の実験はほぼ完成の域に達した。だが私の実験は完全ではない。彼の状態は安定にはほど遠い」
「なんと」
そのとき聖火香の杖が、小さく澄んだ音で鳴った。
「ほら、見つけた。雅流だ。かわいい奴。わかりやすい男だ」
聖火香は杖の表面に浮き出た、なにかの模様を読みとりながら言った。
「あの山脈のむこうにいる。あそこにはなんの街がある?」
「海が見えるから……あれは、アウツール山脈だ。シベツの街だと思う」
「シベツ? シベツ! あはははっ」
聖火香が爆笑した。
「どうされたのです?」
驚いてラブドエリスは聞いた。
「雅流は明日にも号羅に挑むつもりだぞ」
さもおかしそうに聖火香は言った。
「シベツの街になにがあるのですか?」
「リ・ラヴァーどもの生まれ故郷だ。昔は鉄士別と呼ばれていた。アリウスの記憶潜行で知ったのだが、あそこはもともと「病の館」があった街だ。その技術の流れで、リ・ラヴァーが造られた」
「それが号羅様に勝負を挑むことと、なんの関係があるのですか?」
「まあ、気にするな。準備は雅流にまかせて、我々は号羅の城があるエスンに向かうぞ」
気にするなと言われても、それは無理だ。少し気分を害したラブドエリスはいじわるな質問をしてみた。
「聖火香様。雅流とは恋仲か?」
聖火香は大きく目を見開いた。
「……雅流と? ふむ。私はかまわないが」
「はあ?」
「私は雅流の母親ほどの歳なのだが」
「なんと。それはまた。ええっ?」
|