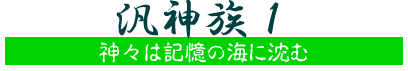|
聖火香の城が崩壊を始めていた。
物理的構造はそのままに、聖火香の法呪で維持されていた様々な仕組みが動きを止めた。抑圧されていたクンフどもが溢れ出した。華麗な絵画が枯れ始めた。
多くの実験装置が、熱の供給を絶たれて固まり、または溶け出した。どこにこれほどの数がいたのかと疑いたくなるような、ネズミ級の低級従属生物たちが城から脱出を始めた。
それらは窓という窓から溢れ出し、城を支える大地の下に逃げ散っていった。隷ラディオたちの脇を、恐れることもなく走り抜けていく。
「なに? いったいどうなったの? 由美歌様は失敗なされたっていうの?」
隷ラディオは信じられない気持ちで、城の崩壊を見上げた。
「あっ、護国法兵士様たちが」
人間の兵士が声を上げた。彼らを援護していた護国法兵士たちが傘のような飛翔機を広げて、空中に舞い上がった。
あっけに取られる隷ラディオたちを一顧だにせず、見る見る高度を上げていく。
「……し、城が。城が!」
兵士と従属生物たちは一斉に悲鳴を上げた。城を乗せた一かけらの大地が、プリンの山から滑り落ち始めた。大地と大地を繋いでいた不可思議な力が消失していた。
巨大な構造物が彼らの頭上に落下を開始した。
「ぎゃああああ」
残された者たちは我先に逃げ出した。武器も法呪具もなにもかもをうち捨てて。
「号羅様、号羅様!」
従属生物どもは口々にその名を呼んだ。
しかし呼びかけに応える力は届かず、圧倒的な質量が彼らの多くを飲み込んでいった。
ラブドエリスは闇の中で意識を取り戻した。どれほど時間がたったのかわからない。鎧はずたずたに裂けていたが、傷はすでになかった。
彼の腕の中に傷ついたギュリレーネがいた。まさぐるように胸に手を当て心臓の鼓動を探った。
「……生きてやがる」
ほっ、と安堵のため息をついた。
彼らの上には驚くほどの量の土砂がのしかかっていた。だが致命的な衝撃はマシューの羽が受け止めてくれていた。
羽はいまだ、きらきらと美しい光を放っていた。
ラブドエリスは苦労して土砂を除くと、闇の中で立ち上がった。
ポケットから着火石を取り出して、自分のマントの端に火をともした。
「おいおい。よく生きていたな、こりゃ」
階段はくの字に曲がり、天井の一部は床にまで落下していた。城の構造材である巨木が壁を突き破って、階段に刺さっていた。
「アリウスはうまくやったらしいな」
彼の後ろに雅流たちの姿はなかった。転送は成功したのだろう。
ラブドエリスはギュリレーネを床に横たえると、階段を降りた。人間の正当な欲求として、由美歌の身を案じたのだ。たとえ自らに害する神であっても神は神だ。
由美歌が座り込んでいたあたりはすっかり土砂に埋もれていた。ラブドエリスは手近な材木に火を移すと、床に落ちていた槍を取り上げた。ゆっくりと切っ先を土砂に刺してみる。
幾度めかのとき、先端に柔らかい手ごたえを感じた。槍を投げ捨てると、ラブドエリスは両手で土砂をかき分けた。
「……うっ……おう」
たくましいうめき声をあげて、巨体がゆっくりと動きだした。
「なんだ、あんたかよ」
ラブドエリスは舌打ちをした。身を起こしたのは臼砲でも受けなければ死にそうにないイシマ将軍だった。
「まあ、生きていておめでとうさんってところか」
「……おお、これは。ラ、ラブドエリス殿」
「元気そうじゃないか。おい、手伝えよ。由美歌様を探すんだ」
「はっ、由美歌様を、ですか?」
「あたりまえだろう。それとも兵隊たちを先に掘り出すか?」
「ああ、いや。それは。そうですな」
人間として当然の反応だった。
二人は由美歌が埋まっているだろう処を力まかせに掘りまくった。ほどなく彼女は見つかった。天井から落ちた梁の下敷きになっている白銀の鎧が現れた。
二人は犬のように、夢中になって土砂を取り除いた。由美歌にとって梁の下敷きになったことが幸いした。梁が覆いとなって土砂で窒息することなくすんだのだ。
だが梁の直撃を受けて、左足が潰れていた。
イシマ将軍は由美歌の横にひざまずくと、招気の法呪文を器用に唱えた。
一流の戦士としてのたしなみである。
由美歌は汎神族らしい敏感さで法呪に反応した。
「…………キイ…………」
高い声が真紅の唇から漏れた。意識を取り戻した。
「由美歌様。ご無事でなによりでございます」
イシマ将軍が子供のようにうれしそうに言った。由美歌はゆっくりと薄い緑の瞳を開けた。
「うっ、やばいぜ。兜がへこんじまってる」
ラブドエリスは躊躇せずに由美歌に触れると、顎紐をはずして無惨に潰れた輝く兜を頭からはずした。長い白銀の髪が溢れるように流れ出た。幸い頭部に損傷はなかった。イシマ将軍は人間が神に触れる光景に驚いた。いともたやすくそれを行うラブドエリスに改めて自分とは違うものを感じた。
ゆっくりと目を開いた由美歌は、自分を見下ろすふたりの人間に視線を合わせた。
「おまえたちは……無事か。幸いなり」
人に豊かな愛情を持つ護国法兵士の優しさでつぶやいた。
「………………」
しかしつぎの瞬間、肩を震わせて静かに泣き出した。それを足の痛みと考えたイシマ将軍は、あわてて痛み止めの薬草を取りだした。
「なにを泣かれる。由美歌様」
ラブドエリスは直接に聞いた。
「私はリ・ラヴァーに侮辱された。言葉で、面と向かって、クンフのように罵倒された。これほどの屈辱を受けた汎神族がかつてあろうか? 私は知らない……」
おそらく神の涙を見た人間は数えるほどしかいない。由美歌は幼い少女のようにぼろぼろと涙をこぼし、声を上げて泣いた。
「いずれの御柱も持たない記憶でございます」
ラブドエリスが言った。
「汚らわしいリ・ラヴァーごときにやり込められた。それを論破できなかった」
「神なら誰しも言葉を失ったことでしょう」
「……忌まわしい記憶を得たのだ。決して子孫に伝えることのできぬ屈辱の記憶を。……私はもう子を成せぬ」
由美歌の両手がラブドエリスの裂けた鎧をつかんだ。
すがりついた。
人間の少女と同じ声で、由美歌はわんわんと泣き出した。
さすがにラブドエリスも肩を抱くことまではできなかった。由美歌の号泣に静かに寄り添うだけが精いっぱいの優しさだった。
身も世もない姿で泣き崩れながら、それでも由美歌は美しかった。
「…………醜態を晒した。恥いる」
やがて涙を止めた由美歌は、まだ嗚咽に震える声で詫びの言葉をささやいた。いまになって気がついたのか、素肌をさらしたラブドエリスの胸元から長い指を戻した。
「どうか、人に語らないでほしい」
「由美歌様。神の涙に触れるこの奇跡を何者が信じましょう。私は子孫に記憶を伝えられぬことが悔いでなりませぬ」
ラブドエリスは言葉を選んで答えた。意味のある音でそれを聞くことで、由美歌は安堵のため息を漏らした。
「由美歌様。教えていただけますか?」
ラブドエリスは暗闇の中で居ずまいを正した。
「助けてくれた礼をしなければならないでしょう。私に答えることのできるものならば」
「恐れ入ります。雅流はなぜ……雅流様はこれほどグリュースト閥の神々に責めたてられるのでございましょうか? ましてやあなた様方、護国法兵士ともあろう御柱が、なぜグリュースト閥と共に動かれるのでしょう。それほどグリュースト閥の動機には理があるのでございましょうか」
「ラブドエリス。あなたは雅流様の実験体でしたね」
「いかにもそのとおりでございます」
「あなたは雅流様の実験をどのように理解しているのでしょう」
「はっ、それは。時間循環を用いた、記憶溢れ制覇のためのものであると。そして聖火香様の事象発生確率の制御と併せて実験を完成される意向であったと理解しております」
由美歌は真摯な眼差しで、ラブドエリスを見つめた。
「優しく賢い人間の勇者よ。私はおまえが好きだ。おまえは汎神族を引きつける魂を持つ」
「……はっ」
意外なことを言われて、ラブドエリスは純情な少年のように赤面した。
「私たち護国法兵士は、かつてはグリュースト閥の母国である安芸津の国兵でした。グリュースト閥との関係は深いと言えます。しかし今はその立場を離れて、調停委員会の直属です。グリュースト閥の私怨で動くことはありえません」
「号羅様の意志ではないと?」
「号羅博士はグリュースト閥の偉大な指導者の一人。しかしそれだけの意志で私たちは動きません。私たちが動くのは、あくまで汎神族にとっての大儀のため」
「雅流は神々に仇なすことをなされているといわれるのか?」
「その可能性が極めて高いと考えられます」
ラブドエリスは想像もしなかった言葉に動揺した。
「いま多くの国に住む人間のあいだで、雅流様を讃える噂が流れています」
「おお。私はそれを知っております」
イシマ将軍が言った。
「部下の兵士たちが口々に語っておりました」
「一柱の神の噂が広い範囲において語られることは稀です。なぜなら神の実体のない地で語られる噂には、実証が伴わないからです」
「はい」ラブドエリスが肯いた。
「あなたがいない処で、あなたの噂が語られるとき、それが根も葉もない暴言でない保証がありましょうか? それに対して自らが反論できずに、我が種の記憶に止められたならば、あなたは屈辱を甘んじて受ける以外に手だてはありません」
「……子孫の神が、いわれのない非難を浴びるかもしれないと?」
「聡い人間よ。そのとおりです。己の記憶にない悪逆非道を、自分以外の神々が共通の記憶として持つならば、世の神々はなにを信じましょう? 汎神族は自らの記憶を最大の拠り所とするものです」
ラブドエリスとイシマ将軍は神々の世界にわずかでも触れた気がした。ふたりは神妙な面もちで顔を見合わせた。
たしかに人間にはない感覚である。
「私たちがリ・ラヴァーを忌み嫌い、死後においてさえ、身体を分かつことが刑罰として成り立つのは、同じ想いによるものです」
由美歌は真理を告げる者の口調で言った。
「ゆえに汎神族の噂は、多くの国々で語られることが少ないのです。私たちは慎重に行動することが必要です」
人間ならば、噂の中身はどうであれ、有名になりたいと願うことこそ自然な姿であると考えていた。まるで正反対の考えが汎神族の間にあることは、神に近しいと自負していたラブドエリスでさえ想像もできないことだった。
「しかるに、いま人間の世に広がっている雅流様の噂は何事でしょう。地の果てから果てまでも多くの国々でその噂は語られています」
由美歌は静かに言った。
「イシマ将軍。なんのことだ? 俺は知らない」と、ラブドエリス。
「雅流様が神のなかの神である、というような内容です。もっとも徳が高く、知識も力も秀でている、美しく偉大な神であると。北から南まで、ロスグラードに流れてくる雑多な国々の兵士たちが共通の内容で語っておりました」
「そのとおりです。雅流様の数々の偉業を否定するものではありませんが、この状況は異常です」
ラブドエリスは次に続く言葉を恐れながら聞いた。
「雅流様による情報操作が行われています」
由美歌は確信を込めて言った。
ラブドエリスはその意味が十分に理解できなかった。
「しかし、いったいなぜ。どのようにしてそのようなことを。雅流様はいつも城におられた」
「おそらくリ・ラヴァーを利用したのでしょう。リ・ラヴァーはあなたを罰するために造られた者どもです。我が種による創造物ではありますが、ラブドエリス、あなたの属性を基としています。あなたのことを知り尽くした雅流様にとって、リ・ラヴァーの存在はあなた自身がいたるところにいることとかわりないものと考えられます」
「……私を利用しようとしたものだと?」
「リ・ラヴァーは、造られて間もない不安定な状態です。あなたのように自身の意志が強固ではありません。外界からの刺激にたやすく反応致します。雅流様にとってリ・ラヴァーに暗示を施し、意のままに言葉を紡がせることなど、児戯にも等しいことでしょう」
「しかし、いったいなんのために? そのことが護国法兵士出動の理由になるのですか」
ラブドエリスは納得がいかなかった。
由美歌は傷が痛むのか、苦しそうな息を吐き出して、壁にもたれかかった。しゃらん、と歪んでさえ美しい装身具が音を立てた。
「……噂の流布はひとつの段階にすぎません。雅流様の実験、聖火香様の実験。雅流様を賛美する噂による人間の記憶への干渉。すでに意図は明きらかです。わかりませんか?」
「恐れながら測りかねます」
神の洞察力を求められても、それはかなわない。
「私たちの認識は共通しております。雅流様は汎神族始まって以来の試みをなそうとしておれらます。そのことは大変意味深いことであり、だれしも実験の成り行きを知りたい欲求にかられるものではあります。しかし同時に決して許されない外法でもあります」
ラブドエリスは身を乗り出して聞いた。
「雅流の真の実験とは?」
「雅流様の真の意図は、すさまじくも、汎神族の神となることです」
女神の言葉は暗い階段を、さらに深い闇に落とした。
言葉自体に強い力が宿るこの世において、由美歌の言い様は混迷を深める力があった。
「……神の神? ……」
イシマ将軍が間の抜けた声をあげた。
ラブドエリスも言葉にしなかっただけで、同じ意味を想像した。それは人間の想像力の及ばぬ姿だった。汎神族にとっての神の有りようがいかなるものか、その意味するところさえ不可思議だった。
「わかりませぬ。由美歌様。記憶溢れの克服が雅流の目的だったのではないのですか?
神の神……などという、らちもないことを、いつから雅流は企てていたのですか」
「概念自体は我が種の中に古くからあります。我が種の神になる。つまりすべての個体を大きくしのぐ知識を有する者になること。溢れることのない記憶力を持つ者。その者こそ我が種の神として認知されることでしょう」
「無限の記憶力を持つ神……」
ラブドエリスは漠然とこの定義を想像した。
「そのとおりです。溢れぬ記憶。記憶溢れのない状態。それは記憶溢れの研究と、常に表裏一体なのです」
「それは神にとって正しいことではないのですか?」ラブドエリスが聞いた。
「理想と考える者もいます。悪であると考える者もあります」
「しかし由美歌様。護国法兵士が出られるということは、悪である証拠なのではありませんか」
「ああ……」
由美歌が不思議な声をもらした。神の声に近い速い声だった。
「迎えが来ました。ラブドエリス、イシマ。またお会いできることを祈ります」
由美歌の身体が法呪による光に包まれた。
「えっ、由美歌様? まだお聞きしたいことがございます! 由美歌様」
ラブドエリスが食い下がった。
「城の外部に残った我が同胞が、私を見つけてくれたのです。いずれ語り合うことを約束しましょう。愛しい人間、ラブドエリスよ。心から忠告します。雅流様とは袂を別ち、その行為に荷担することのないように。どうか、我が種の倫理に係わることのないように……」
護国法兵士たちの超絶の技を、ラブドエリスたちは目の当たりにした。城の外部から発動された転送の法呪が、由美歌を連れ去っていった。由美歌の位置の固定、正確な質量の把握。塵すら異物と認識して由美歌のみを選択し転送する技量。護国法兵士たちの力にはすさまじいものがあった。
「由美歌様!」
去っていく神に、ラブドエリスは抗議の声をあげた。しかし呼び声はむなしく闇に消えていった。
「……行ってしまわれた」
イシマ将軍が惚けたように言った。
「くそっ! くそ、くそぉ!」
ラブドエリスはこみ上げてきた怒りに身を震わせて壁を殴りつけた。
「ド畜生!」
「いったいどうさなれた。ラブドエリス殿」
驚いてイシマ将軍が聞いた。
「なんでもねーよ。あんたにゃ関係ない」
「ラブドエリス殿」
「……いや、悪かった。気にしないでくれ。雅流のくそったれが俺をだましていたことが許せないんだ」
「く、くそっ……たれ?」
イシマ将軍は神をくそったれ呼ばわりすることに目を白黒させた。
「いいじゃねえか。神の神になる? 最高だぜ。すげえ実験だ。雅流は大っ嫌いだが、その夢は最高だ。乗ってやろうじゃねーか。はっきり言えよ。雅流の奴。だいたい聖火香様も知っていたんなら教えてくれたっていいようなものだぜ。いったいどこに隠れてんだ」
「水臭くてわるかった」
ぼそっ、と神の声が彼らの後ろで響いた。
「げっ」
ラブドエリスはおそるおそる振り向いた。
「正直に言いましょう。あなたの言うとおり、私は位相遷移で隠れていた」
そこにはいつのまにか姿を現した、聖火香が立っていた。傷ついたギュリレーネを抱いていた。アリウスの記憶潜行に入ったときの姿のまま、美しく汚れない姿で、がれきの上に立っていた。
「げげげっ。せ、聖火香様」
変な声を上げてラブドエリスはひざまずいた。イシマ将軍はいち早く平伏していた。彼は聖火香の城に攻め入った立場をよく理解していた。言葉もなく額を地面にこすりつけた。
「…………」
幼いころからこの地に住む彼だが、聖火香の姿を見るのは初めてのことだった。
「ラブドエリス。私が雅流の計画を知ったのは、そう遠い昔のことではない。正確に言うなら、雅流がこの可能性に気づいたこと自体、ラブドエリス、おまえに逢ってからのことだ」
「私に?」
「おまえは忘れているかもしれないが、こう言ったそうだ。ーー俺が冒険をするのは、どこかの誰かの昔話しに出たいからさーーと」
「……はあ」
ラブドエリスはぜんぜん覚えがなかった。
「我が種と人間の考え方の大きな違いを知っているか? 我が種は新たに得た知識を他柱に積極的に語ることはしない。なぜならそれは黙っていても子孫に伝えられるものであり、血の財産となりうるからだ」
「ごもっとも」ラブドエリスはうなずいた。
「人間は他者に対して伝えようとする。伝えること自体が己の価値を高めるからだ。汎神族の情報伝達は強固であるが、縦の線にすぎぬ。人間のそれは弱く、たやすく変形を伴うが、面による大きな広がりを持つ」
「そのことが雅流の計画とどのように関わるのですか」
「どこかの誰かの話しに出るということは、逆に言うと、既に誰しも知っているということになる。あらゆる地で伝説として語り継がれ物語に記される。誰の記憶にもある状態が、人間にとっての不死であると言ったのはおまえだ」
「…………」
「その状態を創り、それを形にとどめることができれば、我が種の神となる可能性が生まれる。雅流はそう考えた」
「それを形にとどめる?」
ラブドエリスはまだ理解できずにいた。
「見たいか?」
聖火香がじらすように笑った。
「当然!」
「ならば来い。ラブドエリス。死すことになろうと、知識のために悔いを残すな」
「応!」
聖火香は瞬間で法呪を発動させて、ラブドエリスとギュリレーネを連れ去った。彼らの身体の形に空気が渦を巻いた。
気がついたとき、イシマ将軍はぱちぱちと木が燃える静かな闇のなかに、ひとり取り残されていた。
|