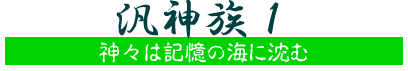|
「良いのか? 本当に良いのか?」
イシマ将軍が隠すことなく苦悶の叫びをあげた。
それは兵士という兵士のすべてが胸のうちで繰り返している言葉だ。
「第五射、用意ーー!」
臼砲隊長のドリオーレ大佐が震える野太い声を響かせた。
彼らロスグラード自治軍は、サギマンの執事長ローリーセバスチャンに率いられて聖火香の城に攻撃を仕掛けていた。
総勢二百人ばかりの軍勢はけっして多いものではなかったが、肉と火の戦いを想定していない汎神族の城を攻めるには十分な数だった。
「第五射、うてーっ」
ずらりと並んだ十門の臼砲が一斉に火を吹いた。漬物石のような楕円形の重合金が轟音をあげて城を支える岩盤に炸裂した。飛び散る土くれが、蟲系クンフのような化け物に姿を変えて彼らの頭上に落ちてきた。
「おおおっ」
兵士たちはそのたびごとにどよめいた。しかしそれは彼らに危害を加えようという積極的な意志を持っているわけではなかった。
亡霊のようにゆらゆらと彼らのあいだを歩き回るだけで、すぐにどこかへ姿を消していった。
ときどき兵士を喰おうとするものがいたが、それらは兵士に近づく前に雷に打たれて燃え上がった。
また稲光が空気を裂いた。
「おおっ。隷ラディオ様」
イシマ将軍は雷を放ち、兵を守った恐竜を振り返った。いや正しくは首に礼をした。
「がっ、ぐるるるるっ。がっ! し、将軍」
「はっ」
隷ラディオの首がうめくように声を発した。それはまさにあの戦闘生物のなれのはてだった。
不思議なヒスイ色に輝く、透き通った槍の先に、およそ無造作に刺された恐竜の生首。それが今の隷ラディオの姿だった。
しかし隷ラディオの首は強烈な生命力を周囲に放っていた。なにを持って呼吸しているのか、鼻からは白い水蒸気を絶え間なく吹き出し、真っ赤に充血した両眼は少しも留まることなく周囲をにらみつけた。
「恐れるな。神の御加護は我々にある。ゆえに見よ。聖火香様の結界はもろくも破れ、我が勇敢なる統兵たちはーー、神の命を実行する兵士たちは、たやすくここに至ったのだ。なにを恐れよう。神の世界にも正しき道と誤てる道がある。正義の道理を我々に代行せよと、号羅様はおっしゃった。神ならぬ身にありて、これに勝る栄誉があろうか」
「ああっ、ああ。隷ラディオ様。我々に神の御加護を。神の栄光を」
ローリーセバスチャンは戦いの場に似つかわしくない神礼祭用のローブをまとっていた。裾でしきりに涙を拭いながら、隷ラディオの首にひれ伏した。
イシマ将軍は、その光景を苦々しい思いで見下していた。
彼の容貌は一言で言うなら東洋鬼。
見事な赤毛の頭髪は、びっしりと短くカールして首まで伸び、頬から顎までを包む茶色い髭は堅く四方に突き出ていた。海の日に焼けた褐色の肌はなめし皮のように強靭であり、ナイフごときでは傷すらつかないのではないかと疑わせるほどだった。
彼は三十二歳。前任のトチシハン将軍のあとを継ぎ、わずか二十九歳の若さで将軍の座に上り詰めた秀才肌の軍人だった。
ロスグラード自体が商業、流通をもって存在している街ゆえに、ここでは頭の切れる人材には多くのチャンスが開けていた。
彼は四才のとき、秤屋をしていた両親とともにロスグラードに住み着いた。
物心ついた時から、聖火香の存在を感じながら育ってきた。隷ラディオという恐竜の従者がいることも知っていた。
しかし、いま彼らがしていることは、ロスグラードの繁栄と共に、長い年月彼らの神だった聖火香の城を破壊しようというものだった。隷ラディオはサギマンに対してそのことを幾度となく訴えていたらしい。だがサギマンはどうしても信じようとはしなかった。そこで隷ラディオはハワイ家の執事長という要職にあるローリーセバスチャンに的を変えた。
隷ラディオがいつからグリュースト閥に宗旨変えしたのかはわからない。
ローリーセバスチャンの前にグリュースト閥の神である号羅が実体を持って現れたという。
サギマンと違い聖火香が人間に多大な害を加えていた時代を知り、ラブドエリスが城に直訴した時代を知る彼はたやすく号羅に従った。それは無理のないことだった。
商売で家を開けがちなサギマンに変わって、会計を預かっていたローリーセバスチャンの元で、ロスグラード自治軍の編成と強化が急がれた。
目的は一途に今日の日のためにあった。すなわち汎神族の秩序を乱し、人間に仇なす聖火香の討伐を号羅の先兵となって果たすこと。
「将軍。だめです。法呪結岩が築かれつつあるようです」
ドリオーレ大佐がまわりの号音に負けない大声で叫んだ。見ると、すくいかけのプリンのような岩盤の回りを、ぼんやりと透き通った三角形の岩が取り巻きつつあった。
「ィイイイィィィィン…………」
前触れもなく、耳をつんざく高速法呪文が彼らの後ろから発せられた。
「うわっ、わわ」
兵士たちはたまらずに地面にうずくまった。
さきほど城の結界を破った護国法兵士の三柱が、真っ白な鎧を打ち鳴らしながら法呪文を放った。神々の法呪は物理的な力をもつように法呪結岩を侵食し始めた。
「カリキヤ、カリキヤャ!」
隷ラディオが槍の上で歓喜の声を上げた。槍を支える蜘蛛のような姿の神の従属生物が、じっとしていろと芯棒を叩いた。
「行け! 勇者どもよ。正義は我がもの。恐れるな。号羅様の御心に報じよ」
隷ラディオはうわずった声で人間たちを激励した。
兵士たちは人間らしい切り替えの早さで、状況に慣れつつあった。
自分たちを真におびやかすモンスターが現れるわけではない。悪意ある罠が襲いかかるでもない。鍛え抜かれた自らの肉体を頼みとする彼らに、心地よい手ごたえを与えてくれる。そんな城攻めだったのだ。海賊どもと戦うよりも容易とすら感じていた。
ここが神の城だということを除けば、だ。
彼らの後ろには隷ラディオをはじめとする神の従属生物が二体いた。そればかりか人間にとっては伝説の世界に等しい戦う汎神族。護国法兵士が三柱も応援に駆けつけていた。
どう考えても、分は彼らにあった。
ギュリレーネは、記憶潜行に入った聖火香たちを、彼女にできる最大の防御法呪「貝氷」でくくった。
その姿は、半透明に輝く淡いピンクの巻貝状だった。奇妙な姿勢のまま、聖火香、アリウス、アピアの一柱と二人が閉じ込められていた。
時間固定がされているように、ぴくりともしない。生きていることは見ただけではわからなかった。
「まったく、なにもよ。こんな通路の途中でおっぱじめなくてもいいだろうによ」
ラブドエリスはぶつぶつ言いながら、どこからか人間なら六人は座れるようなソファを引っ張ってきた。
「どっせえ!」
家具を積み上げて、彼らを隠すバリケードを築いた。
「畜生め。記憶潜行ってな、どれくらいかかるんだ?」ラブドエリスが聞いた。
「長ければ一ヵ月にも及ぶというわ」
「短くて?」
「一・二ビョウ」
「気休めにもならないな。自力で解決しろってことか」
「私たちはまだ聖火香様に雅流様をお渡ししていないわ。義務を果たさなければならない」
ギュリレーネが確認するようにつぶやいた。
「さて、くそったれなロスグラードの奴らに、窓から残飯でも投げつけるか? アイディアはあるかい」
「戦うのはあなたの仕事でしょう?」
「人間が二百人、従属生物どもに、よりによっての護国法兵士だ。はっきり言って逃げるよりも討ち死にするほうが簡単だな」
「へらず口は笑えるユーモアで言いなさい」
「……おい。なんだ、そりゃ」
ラブドエリスがギュリレーネの胸を指さした。薄い皮のマントを通して赤い光が漏れだしていた。
「…………」
ギュリレーネ自身がひどく驚いていた。
「……雅流様……」
それは肌身はなさず、大事に守り続けてきた雅流の首球だった。小さく収縮した球が甦ったように、光を放ち出していた。
真紅の光とともに、神の甘い香りが立ちこめた。
神の気配に反応するように、城が精気を取り戻し始めた。主人を迎えた犬のように、急速に生命の活気が戻りつつあった。
「おお、クンフでも湧いてきそうな空気だぜ」
かつての聖火香の城を彷彿とさせる生命の力がみなぎりだした。その力に反応するように、タペストリーから現れた隷ラディオの姿をした実験体が、ふたたび姿を変化させ始めた。みるみるうちに体が細かくはがれ出した。白いひとつひとつが爬虫類系クンフに姿を変えて空中を舞いだした。
「なんなんだ? こいつ。変身ばっかりしやがるぜ」
またたく間に、息苦しいほどのクンフに囲まれてしまった。
「聖火香様の実験体よ。きっとなにか深い意味があるに違いないわ」
「聖火香様の実験って。ああっと、じ、事象発生確率の操作だっけ?」
「あら、おりこうさんだこと」
「じゃあ、こいつはそいつの操作器なんじゃないのか?」
ラブドエリスが思いつきで言った。
「…………」
ギュリレーネはまじまじと彼の顔を見た。 それは考えもしなかった。
聖火香がモンスターレベルの事象発生確率の操作に成功してから長い時間がたつ。より完成の粋に達していてなんの不思議があろう。ましてや、その方法は誰も見たことがないのだ。ラブドエリスが独り言のようにつぶやいた。
「俺たちが隷ラディオにビビッてたときに、釜の中から奴の姿をした恐竜が現れた。タペストリーのマロウンを見たときに彼女が実体化した。そしてクンフを考えたときに、この有り様だ」
「私たちが考えたり、望んだりしたから、この実験器がそれらを発生させているというの?」
「俺に聞くな。おい、めったなことは考えるなよ。当たってたら大変だ」
「……雅流様がいてくれたら」
ギュリレーネの口から、本音がこぼれだした。耐えていた思いが言葉になった。
「おい。やめろったら」
ラブドエリスが言葉をさえぎるように手をかざした。
そのときクンフどもの動きがめまぐるしく変化した。色がみだれ飛びて入り交じった。
「……雅流様の首球が……!」
ギュリレーネが自分の胸を押さえた。球が呼応するかのように激しく光り出した。
雅流の姿が、霧の中の立木のように固まりだした。それは彼らの知る雅流の姿だった。
漆黒の髪が流れ落ちるタールのように床に届いた。ゆったりとしたローブがさらさらと波うち広がっていった。
「雅流様……」
それはギュリレーネの知る雅流だった。あくまで気高く、汎神族の神々しさと優しさと美しさを体現した偉大な姿だった。
「……雅流? これがか」
ラブドエリスがそう考えたとたん、微妙にイメージが変化した。
尊大で威圧的であり、容赦のない眼差しは他者に条件抜きの服従を期待している。その美は破滅的な冷たさをしたたらせていた。
「驚いたぜ……追跡してやがる」
ラブドエリスがつぶやいた。
「私たちの記憶を読んでいるの? この……実験体は。私たちの記憶にあるものを実体として固定しているの?」
ギュリレーネが信じられずに言った。
聖火香の実験は事象発生確率の操作。つまり、なにかがそこにある、または起こる確率を極限まで操作しようというものだ。
目の前で起きていることは、雅流がいまここに居る確率がペドロ値を越えて操作されているということである。
そればかりかギュリレーネとラブドエリスが持つそれぞれのイメージの雅流が姿を変えながら現出した。
「間違いないな。こいつ俺達の記憶を探りやがったぜ。すごいものを造ったな聖火香様は」
ラブドエリスが驚きを隠さずにうなった。
「あっ、首球が……!」
ギュリレーネが獣の仕草で前足を振った。首球が己の意志で、彼女の胸元から飛び出した。球は吸い込まれるように雅流の姿の中に消えた。
「なっ! なにをする気だ。雅流」
ラブドエリスは危険な気配を感じてギュリレーネの前に回り込んだ。目の前で起きようとしていることは、ただの法呪ではない。聖火香の実験の成果たる実験器に、なにかを仕掛けようとしている。
ひときわ激しく実験器が光った。
首球が完全に吸い込まれた。
実験器の形作る雅流の姿が微妙に変化した。
「雅流様。雅流様……」
ギュリレーネが床に座りこみ、額を床につけた。ラブドエリスはそうしたい衝動を懸命に堪えた。
彼らの知る、雅流の姿が形作られていった。
イシマ将軍は、自ら突撃隊を率いて、プリン型の山の頂上に登りつめた。その数三十人。
彼らには護国法兵士が一柱同行した。まばゆいばかりの白の鎧を身にまとった小柄な神。小柄といっても人間として体格の良いイシマ将軍よりも大きいのだが。
女神は少女と言って良い姿形をしていた。護国法兵士は才能の集団である。正しい資質を持つ神が若くして任に就くと言う。
残りの護国法兵士と隷ラディオたち従属生物は山の下に残り、呪弾を放ちながらクンフを撃ち落としていた。残りの人間の兵士達は、彼らを守るために陣型を組んでいた。
隷ラディオ達はイシマ将軍が突破口を開くのを待ち進入するつもりでいた。
「将軍、障害となるものは見あたりません。城の一番乗りをこのメッソーにお言いつけください」
南方系の若い雇兵が言った。戦うことを知らないモンスターやクンフを倒して、すっかり気が大きくなっているのだ。彼を初めとして、経験の浅い者ほど血気に走っていた。
「いや、私に」
「私に」
イシマ将軍は、そんな若者たちを苦々しい思いで睨みつけながら、この場に留まるように命令をだした。
イシマ将軍はあくまで護国法兵士ーー由美歌(ゆみか)と名乗るーーを前面におしたてて、慎重に進む計画でいた。
人間の肉眼ではなんの変哲もない岩山の頂上であるが、ここは神の城である。人智を越えたなにかがあってなんの不思議があろう。
護国法兵士・由美歌は人間のあらゆる舞踏よりもさらに美しい舞を踊りながら、少しづつ前進していった。
「イシマ将軍」
由美歌(ゆみか)が高く可憐な声で言った。
「はっ」
「私の右前方、八メンツルに兵を一人進めなさい」
「はっ、そこになにか?」
「わ、私が! 私が行きます」
イシマ将軍が聞こうとしたのを無視して、先の南方系の兵士が走りだした。
「おまかせください。そこですね……」
若い雇兵の言葉はそこで途切れた。由美歌が指した場所についた途端、雇兵の姿がかき消えたのだ。
イシマ将軍たちは緊張した。聖火香の罠だ。
「ああっ、なるほど。わからないわけだ」
由美歌はそれだけ言うと、法呪で罠を封印した。そしてなにごともなかったように前進を再開した。
「……ひでぇ」
兵士たちはあらためて汎神族が人間とは違うものであることを認識した。人間のことなど犬ほどにも考えていないのだ。
「雅流様はこんなんじゃないって聞くがなあ」
北方系の初老の兵士がぽつりとつぶやいた。
「……俺も、俺も聞いたことがあるぜ。雅流様って神様がいるって」
「お、俺もだ。なんでも人間に味方してくれるって話しだ」
東方の聞いたこともない国から来た兵士たちがうなずいた。イシマ将軍は驚いて聞いた。
「どこで雅流様の話しを聞いたのだ? この地に来てからではないのか? おまえたちの故郷は大地の裏側ほどに遠いではないか」
「いいえ。将軍殿。このあいだ里帰りしたときだけど、近所のじいさんたちがみんなで噂してましたよ」
東方の若い兵士が言った。北方系の初老兵士もそのとおりだとうなった。
「将軍様は知らないんすか?」
「…………」
実は自分も同じ噂を知っている。イシマ将軍はそのことに驚いたのだ。一柱の神の名を大勢の人間が知っていることがあるなど聞いたことがない。ほとんどの人間は自分の故郷に住む神しか知らない。遠い地の神はその名すら知らないことが自然な姿なのだ。
雅流とはどこかの地方に住む亜ドシュケ閥の神のはずだ。古い血と記憶を持つが、神としてはまだ歳若く修行中の身と聞く。
しかし雅流が人間に優しく慈悲深い、偉大な神であるという噂が、誰からともなく流れていた。
大勢の人間がそのことを知っていた。
多くの地、国で語られ、唄われていた。
大勢の人間の記憶にある神。
それはきわめて希有なことだった。
|