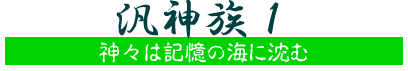|
「がふっ」
突然、巨大な生き物が後ろから抱きついてきた。
「…………ひっ」
アリウスは声もなく立ち尽くした。
寝室に向かう廊下の暗がりで、なにかが飛びかかってきたのだ。その強烈な体重に、マネキンのように押し倒されてしまった。
「うっ、わわわわ」
アリウスの眼前に、真っ赤な機械眼がぐるぐる回りながら迫っていた。
「わ、鷲喰犬……」
情けない悲鳴を上げてアリウスはのがれようとあがいた。
「うひひひぃ。だいじょうぶしゃあ。おまえさんなんぞ喰ったりせんよ」
兵庫が暗がりから踊るような足どりで現れた。いたずらを仕掛けた子供が、大成功したことに驚喜するように両手を打って笑いころげていた。
「お若いの。お若いの。おもしろいのぉ」
「ひ、兵庫様。お人が悪い。おからかいにならないでください」
「ところで食堂に集まれと大賀王が言っておったぞ。またパーティーじゃあ」
「はっ? また、どなたか……」
「おお、亭鶴朗(ていかくろう)の奴じゃ。あいつも難儀な奴じゃあな。もう三度目……」
アリウスはまじまじと兵庫の顔を見つめた。いま、この老神はなんと言った? 三度目?
アリウスは記憶をなぞり回した。しかしいま老神が言ったことの意味を理解できるものはなかった。
「なにを知っているのですか? 兵庫様」
「亭鶴朗は良い奴じゃった。ああ」
「兵庫様」
アリウスは老神に詰めよった。
「パ、パーティーじゃよ。お若いの」
「私の名はアリウスです。兵庫様」
「お? おお。もちろん。そうじゃとも」
「……おとろえておられるのか……」
アリウスは哀れみをもってささやいた。
「ば、ばかもの! わしを愚弄するか。グリュースト閥一級宮司のこのわしを」
「…………」
アリウスはどうしたものか迷い、じっと老神を見据えた。それを自分を軽蔑し責めるものと感じたのか、兵庫はうろたえて言葉を続けた。
「こ、来い! 若いの。わしが真実に近い者であることを教えてやる」
兵庫は鷲喰犬の首輪をつかむと、ひきずるように歩きだした。ときおり姿を見せる他神の目を盗むように、地下に続く廊下に降りていった。その先には茶茶音が安置された部屋があるだけのはずだった。
「いったいどこにいかれるのか」
しかしアリウスの言葉には答えず、兵庫は扉を開けた。ひんやりとした空気が、湧き出るようにふたりの顔に吹き付けた。
「兵庫様。ここは茶茶音様の。兵庫様」
アリウスは入ることをはばかり、その場に立ち止まった。
「ひひひ。びびっとるのか。恐怖か? くだらん。おまえはわしを侮辱することになるかどうかの際にいるんだぞ。おまえはわしと来る義務がある」
兵庫の言うことは一理ある。アリウスは意を決して地下室に足を踏み入れた。茶茶音の死体は、もうそこになかった。
「どこにいったと思う?」
アリウスの不安を見すかしたように、兵庫は笑った。
「戻りましょう。不敬です」
体を回そうとするアリウスの腕を取って、兵庫はすうっ、と左手の中指を奥の壁に向けた。
「…………」
アリウスは指の先に目を凝らしたが、灰色の軟石で組まれた壁にしか見えない。
すると尻のあたりをなにかがつついた。鷲喰犬だ。鼻先でアリウスを壁の前にまで押しだした。兵庫がなにかの法呪文をささやいた。
「……あっ」
目の前の壁がチリのような破片に変わり崩れ落ちた。それは小さな蟻が集まったものだった。蟻は一目散に両側の壁によじ登った。そこで足と足をからめて再び動きを止めた。
「その奥じゃ」
そこには天井の高い通路が延びていた。発光生物がまったく育っていない。人間の建物のように、建材の死の気配がひんやりと広がっていた。暗い奥から嫌な臭いが吹き付けてきた。えもいえぬ生臭い不吉な臭いだった。
「私はこれを知らない」
アリウスは自分の記憶にないものを知りたい、という汎神族の欲求に勝てなかった。ふらふらと取りつかれたように足を踏み出した。
通路は複雑な発音の法呪により、幾重にも守られていた。兵庫の法呪文を復唱しながら、時間をかけてやっと最後の扉にたどりついた。扉は巨大な木の一枚板で作られていた。通路の正面いっぱいの大きさである。まるで荷物の搬出入のためでもあるかのような作りだった。
中からは詠唱のような音がかすかに聞こえていた。その声はひとりではない。
「ただの引き戸だよ。入ってみな」
兵庫はアリウスの肩を抱き、逃がす意志のないことを強調した。
「…………」
アリウスは引き戸に手をかけた。
薄い褐色の戸はなんの抵抗もなく、かたりと左に動いた。
中は真の暗闇だった。肉と血の腐敗臭が水蒸気に混じって押し寄せてきた。汎神族の苦手とする臭いだ。
「うっ……」
アリウスは胸が悪くなり、あやうく嘔吐するところだった。
「いかん、いかん。ここだけは電気力で動いているんじゃった。うっかりしておったよ」
わざとらしげに兵庫は笑うと、アリウスの反応を楽しむように、壁から突き出た小さな突起を下げた。
黄色っぽい電球の明かりが一面を照らしだした。
アリウスは部屋の意味を理解できなかった。なにかのための機械室なのかと考えた。内部は金属と木材で作られた複雑な実験装置がうず高く積み上げられていた。
それにしても広い。部屋の形自体が迷路のように折れ曲がっており、全景が見渡せなかった。まるで幅広い通路を改造したような作りだった。
「入りなよ」
兵庫にうながされて、アリウスは歩を進めた。
「これは「授呪」の治療室でございますか?」
「まあ、そういうことでもあるけどな。ひひ。いいか。ここから先はあまり声を出すなよ。質の悪い連中がしゃべりだすからな」
あいまいな笑いを浮かべながら、兵庫は銅色に輝くチューブやタンクをいとおしそうに撫で回した。
「高度治療院の集中治療室に似ている。いや、化学反応調査房か……?」
アリウスは記憶を総動員して、説明してもらえぬ部屋の正体を推理した。部屋はかなり奥まで続いていた。もう幾度も角を回った。
「……臭いが……」
アリウスがうめいた。あの生臭い臭気が強くなってきたのだ。比例して詠唱の声が大きくなってきた。
いや、奇妙だ。詠唱ではない。汎神族の声に違いはないのだが、言葉をなしていない。
「……ぉ、が、るぅ、ぎだあぁーーっ……」
複数の神の声が、意味のない音をコーラスしているようすだった。
「兵庫様、あの声はいったい」
しかし兵庫は自分の目で確認しろ、と言わんばかりに、次の角を顎でしゃくって見せた。
強烈な好奇心にかられて、アリウスは一歩一歩前に進んだ。
壁の端から、向こうの部屋が見えだした。
おそろしく巨大な牛車の車輪のようなものが横倒しになって床にあった。それがゆっくりと回転していた。
外輪部分に点々と丸いものが乗っていた。
かすかに動いた。
「近づいてみな」
兵庫が神妙につぶやいた。
アリウスはゆっくりと近づいた。そのとき車輪のような台座がぐるりと回り、丸い塊が正面を向いた。
「が、るぅ、だあぁぁーー……」
肉と毛の塊が動いた。
神の生首。
口がぽっかり開いた。
小宇杏の首が獣のように叫んだ。
瞬間、アリウスは凍り付いた。
目の前のこれは、なんだ?
汎神族の、知識への逆らいがたい欲求が逃げることを許さなかった。
「………………」
生気のない首が五つ。台座の上に植えられた短い芝に置かれていた。まわりには蝶系のクンフが無数に乱舞していた。首はあきらかに生きていた。しかし意識はないのかアリウスに反応しない。
「……むぅぉ、が、ぢぃ、があぁぁーー……」
一斉に首どもが吠え立てた。
首につながった無数のチューブから、血の混じった白い液体が、どくんと流れだした。
首どもは恍惚とした表情を浮かべて喉を鳴らした。
「ひ、ひ、兵庫様。こ、これはいったい……」
振り返ったそこに兵庫の姿はなかった。
「ぐるるるるっ」
鷲喰犬が凶悪な獣の声あげているだけだった。のそり、と戦闘獣が肩を揺らした。
「ひ、兵庫様。おふざけはおやめください」
兵庫の忠告を無視して、大声をあげてしまった。
首どもの詠唱がぴたりと止まった。
「……ばぎ、ぜど、ごぃす……」
いっせいに首が目を見開いた。死体の顔色のなかに、生々しい両眼が光を帯びた。
ーー身体をよこせーー
アリウスにはそう聞こえた。
「う、わわわっ」
堪えきれなかった。アリウスは悲鳴をあげて走りだした。
周囲を圧する器具までが襲いかかってくる錯覚を覚えた。
床を這うケーブルや根までがからみついてくる。クンフどもが矯声をあげながらアリウスをからかう。
「なすは因果の巡る房、これ紫にーー」
防魔の法呪文が、高速言語となって口からほとばしった。
ふたつ目の角を曲がったとき、天井に無数に縛り付けられていた、首なし馬の巨体が降りてきた。
首に植えられたシダつるにぶら下がり、蜘蛛のように床に降り立った。
アリウスは再び足を止めてしまった。
「………………」
目を奪われずにいられない。
汎神族の業の深さはあさましい。
馬の腹がべろり、と割れた。そのなかから頭を下にして神が転がり出した。
髪の長い、たくましい朱神だ。
床につくと、神はすぐに自力で立ち上がった。全裸のまま、長い四肢がゆっくりと打ち振られた。
「……アリウス様。こんなところで」
その神はアリウスの名を呼んだ。
知っている顔だった。顔だけは。
馬の赤黒い体液を滴らせながら、女神の顔に男神の体を持つ、その神は近づいてきた。
「アリウス様。ご覧になりましたね」
茶茶音の首がしゃべった。
見知らぬ男神の体のうえに乗った、茶茶音の優しい顔が笑いかけた。
「……ひっ……」
アリウスは走り出していた。汎神族の好奇心も生存本能には勝てなかった。
あたりの器具をいくつも落としながら、アリウスは地下室まで、一気に駆け戻った。
階段を登ろうとしたとき、なにかが服のすそをつかんだ。
「ちゃ・……」
彼女が追いかけてきたのかと思った。
「るるるるるっ」
鷲喰犬があざ笑うかのように、彼の服を踏みつけていた。
「ガアッ!」
獣は躊躇することなく、彼に襲いかかってきた。
「た、たすけ」
アリウスは両手を上げて喉を守った。
その右腕に、鷲喰犬はかぶりついた。
「わあああっ」
漏電気が牙から腕に流れ込み、経験したことのない激痛が全身を襲った。
しかし手加減しているのがわかる。本気ならば前足の一撃で、彼など叩きつぶされているはずだ。
ゴーグルの下の機械眼がいやらしい黄色に光った。
……なぶられている……
絶望感と怒りが、同時に吹きだした。畜生にあしらわれて死を迎えるなど耐えられない。
「我が右腕の無辜なる血潮。この時のみにおきてあり酸に転じて還元せよ!」
彼の右腕が真っ赤にそまり、じゅう、という不気味な音を発した。
「ぐぎゃん!」
鷲喰犬は弾に撃たれたようにはじけとんだ。
凶悪な爪で自らの口をかきむしり悶絶している。口元からは白い煙が立ち登っていた。
「…………が」
アリウスは遠のきそうな意識をかき集めて階段を登った。使いものにならなくなった右腕をひきずるように廊下に転がりでた。
「閉じて再び破れず……」
扉に封印の法呪をかける。
しかし、そんなものは気休めにしかならない。鷲喰犬の物理的攻撃力は法呪をも打ち破ることを前提に設計されているのだ。
アリウスはうしろも見ず走りだした。途中で幾柱もの神が、負傷した彼をみとがめて声をかけたが、視野の狭まった彼はまったく反応しなかった。
ただ生への欲求のみがアリウスをつき動かしていた。
駆けつまろびつ玄関の扉にたどりついた。止めようとする神々を乱暴に振り払って鍵を開けはなった。
びゅう、と懐かしい外界の風が吹き付けてきた。通りのすぐ向こうに純白の鎧をまとった護国法兵士が立っていた。
「お、お助けください」
アリウスはその姿に走りよった。
この邪法の館から脱出するためには、彼らにすがるしかない。必死の想いで彼は兵士の足元に身を投げ出した。
護国法兵士は優しく彼の横にひざまずいた。
「お戻りください」
にべもない一言だった。アリウスは信じられないものを見る眼で護国法兵士の顔をのぞき込んだ。
ゆったりとした慈愛あふれる笑顔は、まだほんの少年のものだった。気品はあるが田舎育ちなのがわかる無骨な顔立ち。才能に恵まれて、どこかの地方から選抜されたのだろう。
「いまはまだ危険でございます。どうぞお戻りください。災禍凌ぎに御専心ください」
うむを言わせぬ強制力で、幼い神は言った。
「し、しかし。お聞きください。護国法兵士様。あの、あの館では、尋常ならざる……」
「お願いでございます。お戻りください」
あくまで優しい物言いではあるが、しかしまったく彼の言葉を聞いていなかった。
この少年が自分の運命を握っている。まさに今の瞬間は幼い彼がアリウスの命そのものだった。
「護国法兵士様。護国法兵士様」
大賀王が館から走り出してきた。扉の内側に他の神々の姿もある。迫りくるその巨体を見たとき、絶望感と右腕の激痛から、アリウスは意識を失っていった。
「アリウス様、アリウス様」
誰かが自分を呼んでいた。揺らぐ意識が理解を拒む。まるで眼をさますことから逃げているかのように。
「ああ、アリウス様。お気づきなされたか」
誰だろう? 自分はまだ眼を開けていないはずだが。なにを言っているんだろう。
「アリウス様!」
この声は知っている。アピアだ。彼女の声が泣いている。
「……アピア」
自分の声がどこか遠くで聞こえた。その言葉に呼応して大勢の歓声が上がった。安堵と祝福の声だ。
「……こ、ここは!」
アリウスはバネ仕掛けのマリオのように体を起こした。腕につながったチューブが引きちぎられてあたりにはじけた。
「まあ、まあ。元気だこと。まあ。もう大丈夫。安心おしアピア殿」
美しい老婆、真紀伊奈が優しくアピアの頭を抱き、髪をなでつけた。
「アリウス殿。大変申し訳のないことをした。鷲喰犬のシュートマが錯乱して、貴殿に危害を加えた。とっさの勇気と際だった法呪の才能が貴殿を救ったのだ。記憶とご両親に感謝されよ」
大賀王が全員を代表して祝福と記憶への賛辞を述べた。皆がそれに賛同の意を表して手を打ち鳴らした。
「シュートマは薬殺処分にし、身体を四つに分けて破棄した。これで貴殿の右腕が戻るわけではないが、どうか許してほしい」
「アリウス様。皆様が海神省への連絡を取ってくださいました。私たちは今からすぐに出発できます」
アピアがうれしそうに報告した。
「呪い札は……」
「ああ、アリウス殿。貴殿が事故に会われてから一週間が過ぎているのだよ。右腕には人間から培養した似手を接合させてもらった。しばらく違和感があるかもしれないが、辛抱してくれたまえ」
大賀王が申し訳なさそうに言った。
「…………」
自分はここから生きて出ることができるのか。信じられない想いで一杯だった。
あの秘密を知って……。
秘密ではないのか? あのテーブルの上の首は。茶茶音殿の首のすげ替えは。
「では準備をいたしましょう」
事情を知らないアピアは、嬉々としてアリウスをベッドからせき立てた。
出発の準備はすぐに終わった。もともと長居をするつもりなどなかった館である。となりの部屋ではアピアがまだ、ガダゴトとなにかを片づけていた。
そのときドアが小さくノックされて、長身の人影が入ってきた。
「茶茶音……殿」
アリウスは息を飲んだ。
男性の朱神の身体の上に乗る、優しい茶茶音の顔が微笑んだ。恐怖の記憶が蘇る。
全身を総毛立たせてアリウスは後ずさった。
「わ、私をどうするおつもりですか。帰さないのですか」
震える声でアリウスは言った。もし生き延びることがあったら、子孫は私の恐怖を笑うだろうか?
「……私は、あなたのことをよく知らないのです。お名前がアリウス様、だということしか存じません。どこかでお会いしていましたでしょうか?」
意外なことを言われてアリウスは返答に窮した。知らない? なぜだ?
「ここは「病の館」です。様々な治療と実験が行われています。私も幾度目かの治療をうけていました」
「…………」
アリウスは言葉もなく立ち尽くしていた。
「ご存知ですか? 呪い札は身体にはほとんど害を与えないことを。記憶が溢れることのみが、その害であることを。治療は別々に行うのが合理的なのです」
いかにも機械学の発達した安芸津国らしい言い分だ。
茶茶音は彼の洗濯物をきれいにたたみながら言った。
「これでお荷物はすべてですね?」
「は、はい。茶茶音殿」
女神は静かに微笑みながら、アリウスの顔を見つめていた。
あの慈愛に満ちたすばらしい笑顔で。しかし今は似つかわしくない朱神の身体の上から。
ネックレスの色が変わっていた。いまはそれが包帯のようなものだと知れた。
アリウスは有り得ない可能性を考えながら、その姿を見ていた。それは妄想といっても良い考えだった。
この女神は間違いなく記憶溢れを起こしたはずだった。しかし、いまこうして通常の会話を交わしている。錯乱した言動はただのひとつもない。
そんなアリウスの心を見すかしたように、茶茶音はとびきりの笑顔で笑った。そして彼の恐れていた言葉を発した。
「私はあなたを忘れたのです」
アリウスが階段を降りたとき、ホールではアピアが、別れを惜しむ老神たちにもみくちゃにされていた。
ホールは、階段の脇にあるサンルームから流れ込んだ日の光が、長い帯となって空中のほこりを照らし出していた。
ひさしぶりに見るまぶしい光に誘われて、アリウスはサンルームに目をやった。そこには長椅子に座った二柱の姿があった。二柱とも背を向けていたがだれかは一目瞭然だった。
「大賀王様。兵庫様……」
出ていくいま、兵庫に恨みごとのひとつも言ってやりたい気持ちもあったが、礼儀に反すると感じた。
大賀王がゆっくりと、ノースリーブのたくましい右腕を上げた。アリウスに見せつけるような奇妙な動きだった。
「大賀王……」
声を掛けようとしたアリウスは、次の動作を見て黙った。
大賀王の棍棒のような腕が、すりこぎのような兵庫の首に巻き付いたのだ。腕の動きは止まることなく、極限まで曲げられた。
ごきっ。
そんな音が聞こえた気がした。
兵庫の首が有り得ない角度に曲がっていた。
|
|