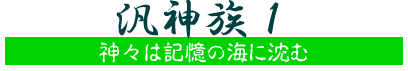|
朝、大きな堅いベッドで目をさましたアリウスは、自分がどこにいるのかすぐにはわからなかった。二重ガラスの外、どこか遠くから聞こえてくる護国法兵士の詠唱が心地よくまどろみをさそった。
「私は……」病の館にいる。
急に現実が重みを持って胸にせまってきた。
「しまった。今は何時だ!」
アリウスは枕元に置いたはずの懐中時計をさぐって飛び起きた。こういうところだ。朝は早いに違いない。
着替え終えて一階に続く階段を降り始めたアリウスは、異様な気配を感じた。
階下のホールに住人が集まっているのだ。しかもなにかを取り囲むように、丸く輪を作っていた。
「…………」
ひとりが黒いローブを身にまとい、銀色に輝く聖書ほどの金属の箱をおし抱くようにかざしながら、何事かつぶやいていた。
真紀伊奈と呼ばれた老婆がハンカチを鼻にあてて泣いているのが見て取れた。他の老神達も一様に暗く立ち尽くし頭を垂れていた。
「…………」
アリウスはしばし階段に立ち尽くしていた。しかし部屋にもどるわけにもいかず、足音を忍ばせながら彼らに近づいていった。
アピアの姿もかすかに見えた。彼らのほとんどよりも……大賀王以外の誰よりも長身の彼は、老神達の肩ごしに床にあるものをのぞき見た。
「……茶茶音……殿」
そこには白いドレス姿の茶茶音が自分のスカートの花びらに取り込まれるようにして倒れていた。その白い顔には生気がまったく感じられなかった。のけぞるように倒れ込んだその豊かな胸も彫像のように硬く、オブジェと化していた。
「茶茶音……殿。……大賀王殿、これはいったい」
強く唇をかみしめて拳を固めていた大賀王は、蒼白な顔をアリウスに向けて言った。
「気にされるな。ここにいるものは遅かれ早かれ、一度はこうなる。記憶溢れは避けられん道だ」
「さだめじゃあ」
兵庫がつぶやいた。
「茶茶音様の番だったんじゃ。ああっ、わしゃ見ておれんよ」
枯れ枝のような腕を振りながら、彼は自分の部屋に上がって行った。
他の老神たちもうなだれたまま、ぞろぞろとその場を去り始めた。
「……えっ……あの皆さん」
アリウスはどうして良いかわからずに去りゆく神々を目で追った。
大賀王が言った。
「アリウス殿、申し訳ないが、食堂脇の通路に担架が架けられている。取ってきてくれたまえ」
「は、ああっ」
この場を少しでもはなれることができるのはありがたく、小走りで通路にむかった。
通路は古い板張りで、食堂からの油煙が染み込み、見事なあめ色に輝いていた。よほどしっかりとした造りらしく、これだけの年代を感じさせながら、きしみひとつ立つことはなかった。
「担架、は、これか」
それはなぜか高い位置に設置されていた。アリウスは学生時代篭球の選手として活躍したこともあり、長身の部類である。その彼が腕を上げた高さに担架は架けられていた。
ふと気がついた。
「この建物はなぜこんなに天井が高いんだ?」
天井から下がる無数の照明球までの高さすら、普通の神の身長の三倍はありそうだ。不必要に高い。としか思えない
「まるで……」
居住の為ではない建物……。
「アリウス殿」
大賀王の呼ぶ声がした。
「あ、はい。すぐ」
アリウスは急いで担架を取ると、ホールに引き返した。
ホールでは、大賀王と小宇杏が彼の帰りを待っていた。
「小宇杏(こうあん)」
「ハンサムさん。たいへんな時にきちゃったわね」
アピアの姿が見えない。
「私の連れを知りませんか?」
アリウスは不安気に聞いた。
こんな場面で彼女がいなかったことはない。
「さあ、運ぶわよ。担架に乗せて」
それに答えずに、小宇杏はうながした。
茶茶音の遺体は地下室に安置された。
廊下の突き当たりから短い階段を降りた、頑丈な焼き物扉の向こうにその部屋はあった。そこはさらに奥へと部屋が続く、続き部屋の一室のようであった。いま奥への扉は堅く閉ざされていた。
地下室にもかかわらず、ひんやりとした空気は乾燥して心地よかった。
小宇杏は茶茶音を横たえたベッドの枕元に香炉を置き、甘い不思議な香りの練り香を炊いた。
「……ん?」
アリウスはすぐ近くに誰かがいるような気配を感じて後ろを振り返った。
しかし、そこには灰色の石組の壁があるだけだった。
「どうした?」
大賀王がアリウスの動きを見とがめて聞いた。
「いえ、誰かがいたような気がしました。申し訳ありません。不謹慎でした」
「さあ、アリウスさんも、茶茶音様のために黙祷をお願いします」
小宇杏がおだやかに言った。茶茶音の身体が甘い煙に包まれて、弛緩していった。
「…………」
深く長い黙祷の時間が過ぎていった。音の閉ざされた地下室にあって、神秘的な香の刺激だけが現実感を持って感じられた。
ピシリ……
はじめアリウスはそれが虫の音だと考えた。
ピリッ、キッ。
なにかが小さく裂けていく音がどこからかしていた。
「…………?」
アリウスは薄目を開けてあたりをうかがった。小宇杏と大賀王は深くこうべを垂れたままだ。
……ピシッ。
その音は、茶茶音の体から発しているようだった。
『ネックレス?』
いま気がついたが、茶茶音は小宇杏と同じネックレスをしていた。いや、大賀王も同じようなものをしている。
音は茶茶音の首から出ていた。
『首? 首が動いている?』
目の錯覚ではない。いま、たしかに頭が揺らいだ。生気の失せた仮面のような表情はそのままに、首の中でなにかが……。
「では、アリウス殿。戻ろうか」
大賀王はアリウスの肩をつかみ、強引に身体の向きを変えた。
「茶茶音殿も喜んでおられるよ」
「大賀王殿、いま……」
「さあ、喪の時間のはじまりよ」
小宇杏はなぜかうれしそうにつぶやいた。
「あなたはいいときに来たわ。ふつう、こんな経験できないわよ」
「…………」
アリウスは不謹慎と思いながらも、小宇杏の二の腕に手を置いた。
伝え聞く病の館の喪に服することを了解する作法である。病の館には国や宗派に関係なく神が収監される。そのために共通の儀礼として様々な作法が定められているとの話であった。
「うふふ、良い記憶をお持ちね。でも肝心なのは神を想い供養する心よ」
ほがらかに笑いながら小宇杏は言った。
一階に戻った彼らを待っていたのは、ささやかだが陽気な宴会だった。
老神ばかりの中で、小宇杏は明るく輝いていた。腰の重い彼らの間をひらひらと舞いながら酒をついで回った。
「マリオスナ地方の、十三号線沿いにある農家な。あそこの一族が作るワインが忘れられないのさ。川の右側の畑だ。左と土が違う」
「ああ、もちろん知っている。雑誌で見たね」
「雑誌にでるようじゃ、もう掘り出し物とは言えないよ。君。酒は蒸留酒に限る。しかも銅のタンクはだめだ。やはり、焼き物を使った九級以上の大きさのだね……」
老神たちは趣味の良いセーターを着て、思い思いに談笑していた。
愛想よくそれに参加していたアピアは、アリウスの姿をみつけると、丁重に老神たちのもとを離れて近づいてきた。
「アリウス様。どちらいらっしゃったのですか? ここは変です。お気をつけください」
笑顔をはりつけたまま、アピアはささやいた。
「茶茶音殿を安置してきた。変とは?」
「泥の匂いがするんです。しかも病んだ泥の」
「病んだ泥?」
「そう、記憶泥の匂い……だと思います」
「記憶泥?」
「まあ、あなたの記憶にないのですか? 記憶溢れを起こした神が垂らす、古い記憶の発酵物です」
「知らない。耳からでも垂れ出すのか?」
「ええ、そうです。知っているのですね」
「うっ、いやだな。その匂いだって?」
「……不思議ですね。記憶溢れを起こした神がいれば、それなりの施設に隔離されないはずはないのに」
「どうも気に食わないな。早くここを出たい」
「爆撃が終わるまで、たぶん無理です。護国法兵士にたちまち見つかります」
「じゃあ、いつタブーを破ってしまうかもしれないこの「病の館」にいると?」
「私はそうしたほうがいいと思います」
宴のさなか、どこからか一柱の男性の神が現れて席に加わった。廊下の奥から入ってきたようだった。
「紹介されていない神がいる」
アリウスが確認するようにアピアに言った。
「はい、聞きのがしではないと思います」
その神は実に奇妙な姿をしていた。顔は間違いなく男性なのだが、体付きがいかにも女性じみていたのだ。
身長も男性にしては低かった。中年にさしかかった年頃であろうか。細く骨ばった肉の薄い顔で、その肌はたったいま棺桶から這いだしてきたように不気味な土気色をしていた。
苦労しながら表情を作っているように見える。白いローブから覗いている首の色と真っ白な優しい手が取ってつけたように食い違っていた。脂肪がほどよくついたまろやかな体の線もひどく違和感があった。
「呪い札のせいでしょうか」
アピアがささやいた。
「おおっ、お客神に紹介が遅れたな。この男は火銅(ひどう)といってな。長く伏していたのさ」
「……火銅(ひどう)でございます。お客神」
その声は深く低い音で流れた。はっ、とするほど音楽的な音だった。
「アリウスでございます」
その場は、それきり言葉をかわすこともなく終わっていった。
三日目の夜になっても護国法兵士たちの泳唱はやまなかった。
それは決して不快なものではなく、むしろ心安らぐ響きを持っていた。おそらく市民は日常よりもおだやかな気持ちで夜を迎えているに違いなかった。
ゆっくりとした「病の館」の時間の流れをアリウスは持て余していた。多くの日が過ぎていったように感じる。室内への日光すら遮ることを求められるこの期間において、時間の感覚は希薄になっていく。
アリウスは寝つかれずに図書室を訪れていた。天井を覆う発光葡萄がおだやかな紫色の果汁滴らせていた。床もソファもほどよく湿り、甘酸っぱい香りを放って輝いていた。
アリウスは見るともなしに、手近の本を取ると、ブラインドの下ろされた窓際の椅子に腰掛けた。膝の上で開いた本の上に天井から果汁がぽたりぽたりと落ちて、光り輝く染みをいくつも作っていった。
後ろで扉の開く音がかすかに響いた。
「……これは。大賀王殿」
「おや、アリウス殿。眠れないのですか?」
先客がいたことに驚いた様子で大賀王は言った。
「ここはあなたのようなお若い方にはのんびりしすぎているでしょうね」
「いいえ。とんでもありません。記憶抑えに最適な環境かと思います。一度、恋の記憶について潜行して、たどり道を引いておきたいと考えていました。良い機会です」
「わっはははっ。それは粋なことだ。ちなみにアリウス殿は記憶潜行をどの程度に行っておられるのか」
「私の記憶経路系は主に商業、それも海産卸しによっております。その系については約百二十代程度まで降りたことがございます」
「それ以上はこれから?」
「いいえ。もう十分かと。あまり古いと役にたちませんので」
「……そうですね。まったくです。法呪、機械学、農業、漁業などの蓄積がものをいう分野ならばともかく、こと商業についてはこの記憶というものがあまり役に立たない」
「同感です。しかしもっとも多くの神々が従事しているのは、その商業や一般の家庭生活といえます」
「アリウス殿は家庭生活の中で五十代前の記憶に助けられたことはありますか?」
「そう……カニピーという南国の果物の皮の剥き方を思いだしたことがあります」
「カニピー? ああ、私も知っています。へたの部分を火であぶるのでしょう? これは……二百代と少し前の記憶ですね。ほお、役にたつこともあるわけだ」
「こんなおしゃべりのためですけれど」
ふたりは声をだして笑った。
「なぜ、我々汎神族は記憶を引きずるようなことをするのだろう」
大賀王はあらたまって聞いた。
「はっ? それは」
「こんな議論自体が記憶の中に山のように堆積しているね。いま自分がなにかを感じ、考えようとすることのほとんどに答えが用意されている。そう考えると自分が生きていることの意味はなんなのだろうと虚しくなる」
それを言うのは汎神族にとって、全ての閥にとって共通のタブーだった。しかし大賀王は胸のつかえを吐き出すように言葉を続けた。
「我々の生きる意味はなんなのだろう。子孫を残すために我々の身体は器としてあるのだろうか」
「いいえ、新しい発見を積み重ねて、世の真理をひとつでも多く発見することこそが万物の霊長たる汎神族の使命ではありませんか。そして新しい記憶を積むことが子孫への宝になるのです」
「本当にそう思うのかね? 記憶を積めば積むほど、子孫は記憶溢れの危険にさらされるのに。いや、それもしょせんは時間の問題にしかすぎない。いずれは必ず溢れるときがくる。もし記憶を堆積することが種の命題であるなら、記憶溢れを起こした者たちの命脈を絶つことは、本来許されないことなのではないだろうか?」
「こんな話しを聞いたことがあります。人間の間で信じられている原理なのですが。すべての人間は祖先の霊に守られている。祖先の霊はいつも彼らの回りにおり、知恵や運命を助けているのだと」
「ふむ? つまり汎神族のような記憶を持たない彼らなりの救いということかな?」
「人間の科学者は、幼いときから多くのことを学ばなければなりません。真に創造的なことをできる時間はわずかです。しかし彼らは懸命に努力しています。私たちがそんなことに耐えられるでしょうか?」
「けなげであることは認める。彼らはよくやっていると思うよ」
「導いていくべき者たちです」
「アリウス殿。なぜ我々が、汎神族が滅びないか。私はそれが不思議なのだよ」
「それは……記憶ロストの者たちが生まれてくるから……。そのことですか?」
「そうです。記憶をまったく継がずに生まれてくる記憶ロストの者たち。彼らが生まれずしては汎神族は遠からず滅びることを定めらた終の生物といえる」
「はい」
「しかし、なぜか彼らが生まれてくる」
「我々の救いです。彼らが汎神族の血を若返らせます」
「小宇杏(こうあん)がそうなのだよ」
「……小宇杏様が? それは……」
「貴重な記憶ロストの者が授呪するというのも因果なものだ」
大賀王は寂しそうに笑って言った。
アピアの意識にリンクした聖火香は、じれていた。無駄話など追体験しても記憶の無駄だ。転機を探していた。
アリウスの記憶にイベントが起きたのはそれから数日後の夜だった。
|
|