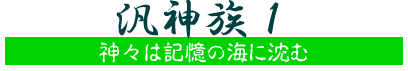|
「……これは、なんと立派な」
暗い室内に一瞬奪われた視覚が急速に回復していった。
そこに現れたしつらえは、宮内庁御殿のように重厚で立派なものだった。彼の立つ場所は、幅こそないが奥行きのたっぷりとられたロビーだった。
正面には幅の広い階段が二階へと続いていた。彼の立つ扉から二階までは、真っ赤な絨毯が滝のように続いていた。その先まで視界は届かない。
壁も床も黒く堅い木を厚くたっぷりと使った高価なものである。灯火管制のひかれた今、天井を覆う桃色の雲のような発光桜が照明として復権していた。
「もともとはホテルとして造られた建物ですのよ。必要以上の華美だとお笑いになられるでしょうね」
申し訳なさそうに茶茶音と呼ばれた女性は言った。
「いいえ、そのようなことは……」
かしこまってアリウスは言った。
「広いのだけがとりえですの。お部屋をご用意するあいだ、そちらの椅子でお休みくださいませ」
彼女はそう言って、白く長い指をきちんとそろえた美しい手で、入り口わきの応接椅子を指した。
「すぐにすみます。では失礼いたします」
足音もたてず、彼女は階段を上っていった。
残されたアリウスたちは、あらためて周囲を見渡した。つくづく高価な建築物である。いつの時代になんの目的で建てられたものか。本当にホテルなのか、いまひとつ判然としない。そもそも今はなにに使われているのであろうか。
「まいった。奇妙なことになってしまった」アリウスはため息をついた。
「違うな。奇妙なのは因縁だよ。若いの」
四つの応接椅子が向かい合う片隅から老神の声がつぶやいた。目を凝らすと、暗い灰色のかたまりが椅子のひとつにうずくまっているのが見えた。
「これは失礼した。私はアリウスという者です。このたびの空襲で……」
「挨拶などいいわ。おまえさんがたはどこだい。ふたりいっぺんなんて珍しいの」
「はっ?」
「どこからやられなすったね」
老神はいらつくように顔をあげた。その顔は首筋もひどくやせていた。
地肌が見えるほど短く刈り込まれた白髪が頭を覆っていた。深いしわにたたみこまれた目は、長くたれた眉毛と一体化していたが、はしばみ色の瞳だけが異様な生気をはなっていた。
「どこ……」ひどくせき込みながら続けた。
「どこからやられなすったね」
「……失礼いたします、なんのことでしょう」
アピアにも質問の意図がわからなかった。
老神の足元でなにかが動いた。別の生き物がそこにうずくまっていた。
「ほれ、シュートマまでじれておるぞ」
老神は手をのばして生き物の頭をなぜた。獣が息を吐き出す音がした。のっそりと黒いそれは立ち上がった。
「……わ、鷲喰犬……」
アリウスは凍りついた。それは戦場のための改造犬だった。獰猛な狼犬に機械学の粋をこらして手術を加えた戦争兵器である。けっして戦いたくはない相手だ。
固着された赤いゴーグルの奥で、機械化された眼が動いているのが見て取れた。法呪がきわめてききずらい恐怖の改造生物である。
こんな民間のなかにいてはならないはずだった。だいいち餌をどうしているのであろう。
「だめよ。この人を脅かしちゃ。ただの空襲避難なんだからね」
「うっ」
突然うしろから女性が抱きついてきた。
「ほら、このひと恐がってるじゃない」
全裸の身体をびしょびしょに濡らした、まだ少女と言っていい娘だった。
短いパーマのかかった髪の毛からぽたぽたとしずくが垂れてアリウスのシャツを濡らした。
アクセサリーなのか、ぴったりしたネックレス……チョーカーをしていた。
「ねえ、ハンサムさん」
くすくすと笑いながら娘は言った。
「お、おおっ、きみ。離れて……」
アリウスはどぎまぎと、彼女の肌に触れないように引き離した。
「そ、それは」
アリウスの眼に飛び込んできた娘の白い身体。その腹に呪文字があざになって張り付いていた。
「えっ、あ。これ? そう、私はここなの」
「わしはここじゃ」
老神が立ち上がり、やけに若々しい腕をさらけだした。その二の腕にも青い呪文字が焼き付いていた。
「……ここは」
アリウスたちは息を呑んだ。
「そうよ。「病の館よ」」
娘はアリウスの様を楽しむように言った。
「法呪に犯された神を隔離する施設。解呪の法が確立されるまで生きていられれば好運なことね」
アリウスははじかれたように跳びすさり、冷たい床に土下座した。
「知らぬこととはいえ、失礼いたしました」
アリウスは震える声で言った。
「聖戦の貴い犠牲となられた皆様に礼もわきまえぬ態度。鞭打たれ放逐されるべき所行の数々。なにとぞご容赦くださいませ」
受呪の神々は、公的施設解呪待機所、通称「病の館」に収容、隔離される。
神々はその住人に対して多いなる敬意をはらって接することが礼儀とされていた。本来自分が受呪したかもしれぬ運を代替してくれたと考えるのだ。
「病の館」の持つ神聖性はどんなやくざ者にも強制力を持った。
「やあね。特別扱いはやめてよ」
笑いながら娘は言った。
「小宇杏(こうあん)さん! なんですか、その格好は。恥を知りなさい」
厳しい声が階段の上から響いた。茶茶音が紅潮した顔で足早に降りてきた。
「やべ、じゃまたね。ハンサムさん。あとで私の部屋に遊びにきてね」
娘は床からタオルを拾うとすばやく身を躍らせて、茶茶音の横をすりぬけて階段を駈け上っていった。
「……ほんとうにしようがない娘だこと。アリウス様、大変失礼致しました。あの娘はここの生活が長いものですから、お客様がいらっしゃると、はしゃいでしまうんですの。どうかお許しくださいませ」
「いえ、私こそこちらがどういった場所かも知らず不躾な態度を取り、お詫びの言葉もありません」
「どうかここの住人を特別な眼で見ないでください。皆さんそれをとても嫌がりますから」
「は、はあ」
「努力してくださいませ」
断固とした口調で茶茶音は言った。
「では、入所されている皆さんをご紹介致しますわ。二階の食堂までどうぞ」
「わしは兵庫じゃ。見知りおけ」
鷲喰犬シュートマを連れた老神が意外な大声で言った。
食堂は二十畳ほどの広さで明るく、極めて清潔だった。
掃除が行き届いた青いタイル張りの床に、高い天窓からたっぷりと太陽がふりそそぎ、暖かい日溜まりをつくっていた。
老神と呼べる年齢の神ばかり、十人前後が集まっていた。若者がひとりもいない。古い石造りの建物独特の臭いに、老神の枯れた臭いが混じって漂っていた。しかしちいさな虫たちはさかんに床を走り回り残飯箱から食を得ていた。虫たちの酸っぱい臭いはほっとさせるものがあった。
「こちらが入所されている皆様です」
老神たちは首をねじ曲げるように、彼に視線を集めた。
「大賀王(たいがおう)さん。皆様をご紹介いただけますか」
茶茶音は、浅黒く筋骨たくましい男に頭を下げた。男は鷹揚にうなづいて立ち上がった。白いシャツから樹の幹のような腕がのぞいていた。
「俺は大賀王(たいがおう)だ。若いの、今回は災難だったな。短い間だがよろしく頼む」
「こちらこそ、よろしくお願いいたします」
「窓際のつるっぱげ爺いが森北男(もりきたお)。となりの厚化粧したばあさんが真紀伊奈(まきいな)だ」
「よろしくね。アリウスさん。なんでも聞いてちょうだい」
真紀伊奈(まきいな)は柔らかな栗色の髪をひるがえして陽気に手を振った。シルエットだけを見るとまだ若い女性にしかみえない。
次々と紹介される神々の顔と名前を、アリウスとアピアはよけいな記憶であると感じながらも覚えていった。
アリウスの肩に骨ばった手がかけられた。意外な力で首筋をぐいぐいともまれて、おもわずうめき声をあげてしまった。
ごましお頭の痩せた老神が、ひょいと肩ごしに顔を突き出してきた。
「俺ぁ、鯛富士(たいふじ)だ。へへへえ、若いの。あとで館を案内してやろう。いろいろと面白いものがあるぞ」
「鯛富士(たいふじ)。よけいなことをするな」
大賀王が小声で、するどく言った。そのあとを継ぐように茶茶音がつぶやいた。
「アリウス様。どうせ短い間です。病神のプライベートは尊重していただけますね?」
「は、はい。いや、はい。それは、もう」
アリウスはうろたえながら答えた。茶茶音が白いドレスのすそをひるがえして、ソファに座る彼の正面に立った。あまりに近くに立ったために、アリウスは仰ぐように見上げねばならなかった。
「あなたたちの普段の生活にはあまりなじみのない光景を見ることがあるかもしれません。しかしいたずらに騒ぎ立てることのないように。また、ここを出たあとにも、不用意な発言をしないようにお約束してください」
「ああ、はい。わかりました」
真意ははかりかねるものの、彼女の立ち居振るまいは威厳に満ちていた。
「では、これからお部屋にご案内いたします」
アリウスとアピアは、皆に一礼して彼女のあとについた。ちょうどそこに小宇杏がばたばたと駆け込んできた。
「あれぇ、もうおしまいなのーー? 急いできたのにぃ」
茶茶音はそんな彼女を無視して廊下に出ていった。
|
|