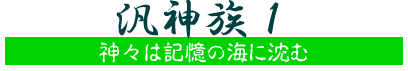|
それは老神の直接の経験ではなかった。
老神の遠い祖先が生きたひとつの時代にまつわる記憶だった。
汎神族がまだ世界中に溢れていたころ。
汎神族が街を作り国を持ち、今の人間のように戦争の歴史を持っていたころのことだった。
汎神族を万物の霊長たらしめる最大の特長であり、種の呪いである記憶遺伝。それはいつの時代も悲劇と誇りの根元を成していた。
解決の方法を見いだせぬまま積み重ねられた幾千、幾万の世代。汎神族は過酷なまでの法と道徳を持って、記憶溢れを起こした神々を切り捨ててきた。それは種の宿命であり本能が肯定する倫理感だった。
太古。もっとも古い記憶を有する汎神族たちが遡ることのできる深淵では、記憶溢れを起こした神々は容赦なく殺された。その身体は喰われることのないように、即座に燃やされた。
次の時代、神々は寿命の尽きるまで寺に隔離された。そこでは人間が雇用されて仕えていた。人間たちはその施設を聖墓として献身的に運営した。
寺では汎神族の死者よりも人間の死者が多かったという。そのことは記憶溢れ起こしたを彼らがいかに危険な存在であるかを如実に物語っていた。
気まぐれな汎神族は自分に尽くす人間たちに感謝することすらできなかった。自分の出した理不尽な命令をけなげに実行する人間を、次の瞬間には不遜であると言い出して、花を握りつぶすように殺していった。
アリウスは次の時代。汎神族が積極的に記憶溢れを解決しようと試み始めた時代に潜行していった。
グリュースト閥発祥の地である鉄士別の街は、かつて貿易港として栄えていた。しかし戦火拡大の著しいいま、産業の主力は造船業に移っていた。港に併設した巨大なドックでは海神省の指揮のもと、多くの軍船が建造されていた。
その歴史により外国との接触が長い鉄士別は、いたる処に異国の臭いを感じさせた。大通りは広い石畳に覆われ、両わきには丈夫そうなガス灯がどこまでも続いていた。
坂の多いこの街にびっしりと並んだ石と木で造られた建物物は、まるで一柱の建築家によるデザインのように美しく、調和が取れていた。電導モグルの走る主道路を外れた小路にまで、立派な石畳が続いていた。その町並みは、まるで写真本で知られる西方洋の風情であった。
緑錆で覆われたガス灯に火を入れる小使史が真っ赤な自転車で忙しげに走っていった。アリウスとアピアは、不思議なこの街の散策を楽しんでいた。彼らはこの地の港のはずれでひそかに訓練が進められている、鯨教化作戦を探りに訪れたのだ。
それは海神省により、かねてから隠密理に進められていた作戦である。
元来が高い知性を有するイルカ達を教化し、安岐津国民としての自覚を持たせると同時に、安岐津法呪を初歩なりともマスターさせて、敵国海域の高等海洋動物の文化的鉄士別市民化を進めようという、高度にして比類なき作戦事業だった。
初夏の鉄士別は乾いて暑い。内地と同じ重く垂れ込めた雲が頭上いっぱいに広がっているが、不快な湿度さは感じなかった。
青黒い暗闇がもうすぐそこまで迫っていることが、なぜか不思議に感じられた。
地響きをたてながら、砲筒を二本持つ紀元八六式戦車の列が過ぎて行った。
真っ白い防護呪装に身を包んだ護国法兵士たちが、巡礼者のようにつき従っていた。
純白の薄い希金属製鎧の上から、反抗呪文を内側にびっしりと縫い込んだ白く長いマントをまとっていた。敵国、那乃国の感染呪術による市街地攻撃から市民を守るために、陸軍少年兵のなかから特に選抜された彼らは、平均年齢若干十四歳と聞く。汎神族の寿命が三百歳をこえることからも、いかに彼らが幼いかがうかがい知れる。
帝国陸軍小等部時代に厳しい訓練を受け、巫詔を発音できることが認められた数少ない少年少女の中からさらに法呪才能に恵まれた者だけを残した、まさに帝国の生ける兵器である。
記憶と肉体の能力に相関関係はない。記憶のなかに栄光の護国法兵士のそれがあっても、たとえ詔を唱えることができても、正確な発音ができなければ意味がない。しかも最高機密が他に漏れることを防ぐためにごく一部を除いて、彼らは子を成すこと自体が許されていなかった。
その自己犠牲もあいまって国民の彼らに対する信頼は絶大であり、彼らの常駐しない地方では、神聖化が多いに進んでいると言う。
アリウスは立ち止まり、彼らの行列が過ぎるのをじっと見送った。
そのとき、サイレンが鳴りだした。
街中の動きが一瞬止まった。その瞬間を待ったかのように、市街地を北八画形に囲み配置された対空砲陣地が轟音をあげて朱色の火柱を吹き上げた。音も届かないはるか上空でいくつもの閃光がきらめくのが見えた。敵国の竜王爆撃機の爆発する光である。
「呪い札注意! 呪い札注意!」
青年団が集合売店屋上のやぐらから拡声器で絶叫していた。
感染呪術兵器である。竜王爆撃機は、撃墜される前に呪い札の投下に成功していたのだ。
呪い札とは、粘着性の塗料により書かれた奪幸招災の邪法呪である。
元来は個人的な怨念使用が主であったが、兵器として確立されたそれは、特殊樹脂性の燃えない腐らないやっかいな代物と化していた。しかも付着した対象物に有効なばかりでなく、ラヂウムのようにあたりかまわず奬気をまきちらした。
とりつかれたが最期、魂の腐りはてるまで神と街をむしばみ続ける。
戦争においてもっとも悪い状態である、助かる見込みのない病神を創り出すのだ。
助かる見込みのない状態。それは汎神族にとって最悪の呪いである、記憶溢れの促進である。授呪したものは加速度的に記憶をつのらせて、極めて短い時間で記憶溢れに至った。
死ぬのではない。それよりもやっかいであり、親族には耐えがたい恐怖。
いったい何者がその原理に至り、法呪として完成したのかは定かでない、記憶溢れの神為的実現。
時代を越えたあらゆる呪いを受け、身体を千にも分けられるにふさわしい邪悪にして偉大な発明神。その正体がいったい何者なのかを探る試みは数多く行われたが、意味ある結論はただのひとつも得られていなかった。
最高最邪の法呪を解けるのは、護国法兵士のみであった。
「来よ。来よ! とく来よ!」
市民は我先に近くの家屋、建築物に駆け込んで行った。札が地上に到達するまでの数分のあいだに逃げ込まなければならない。
家屋内の神々も大きく扉を開け放ち、ひとりでも多くを招き入れようと、口ぐちに叫んでいた。
「なんてことだ。こんなところで」
「急ぎましょう」
アピアが緊張して言った。
アリウスらは港にむかって走り出した。
軍事拠点となりうる港湾施設への爆撃は至烈を極める。大勢の神々が港から市街地に続く見晴らしの良い一本坂を駈け上がってきた。
流れに逆らうように、彼らは海へ転がり落ちそうな坂を走り降りた。下も見えない急な曲がり角をけつまづきながらまがったとき、すでに道が閉鎖されていた。
道いっぱいに護国法兵士たちが集結していたのだ。
「あっ」
アリウスは小さく悲鳴をあげて、道脇にそれようとした。こんなところで保護されている場合ではない。
「君、止まりなさい。ここからはいけない」
すばやく彼を見つけた兵士が印を結びながら声をかけた。
「いや、私は……」
あわてて道をもどろうとした彼の前に、ふたりの護国法兵士が立ちふさがった。
「お、お待ちください。すぐそこです。海神省で約束をしているのです」
「もう時間がない。ここからなら『あみの園』が近い。ご案内しろ」
アリウスの抗議を無視して兵士たちは彼を両わきから引き立てた。
アピアはすばやく身を翻して兵士の手を逃れたが、巧みに囲まれて動けない。
「お願いでございます。さきほどの爆撃は呪い札でございましょう? 警報が解除されるまで一週間はかかります。お願いでございます。海神省までいかせてくださいませ」
「那乃国の呪わしい侵略行為です。海神省もあなたの到着が遅れることを理解するでしょう」
隊長とおぼしき、孔雀の羽を束ねた飾りをつけた男が言った。
「我々は、報道にたずさわる者です。護国法兵士様のご活躍にはをあわせて報ずることが、私たちのつとめと考えます。どうか!」
アピアがでまかせを言って食い下がった。街を見物がてら歩いて行こうなどと考えた自分を呪う。
「お連れしなさい」
「はっ」
二柱の兵士は、有無を言わせぬ力でアリウスたちを引いていった。
「どうか、どうか。お願いいたします」
しかし彼女の言葉はもう聞かれることもなく、護国法兵士たちは、低い詠唱とともに対法呪用陣地を組み始めた。それは白い精霊たちの演舞のようでもあり、意識を取り込まれるほどに美しく現実離れしていた。
「ああっ、なんと。なんという……」
アリウスの焦りをよそに、兵士たちは有無を言わさぬ強引さで歩を進めていった。
「兵隊様、こちらでございます。兵隊様」
石畳の大通りにまでいつのまにか戻っていた。神の絶えた異様な街の風景のなかで、白い服を着た長い黒髪の女性がハンカチをしきりに振りながら彼らを呼んでいた。
「…………」
場違いなその美しさにアリウスは息を呑んだ。
一瞬、いまの状況すら頭から消え失せてしまうほどの衝撃であった。
彫刻家が己のイメージのままに造り上げた空想の女体のように、女性の美しさは完成されていた。
国種を感じさせない卵型の顔立ち、乳児のようなその肌の輝き、濡れて輝く黒い瞳。紅をひいているのかいないのか、唇は健康的に赤く、それ自体が観賞物となりえる完成度と彼には思えた。
たっぷりとした布地の上からでも、柔らかく、しかし硬く造形を維持する体の線が見て取れた。その姿は美しくなまめかしくもあり、神聖でもあった。
彼女が入り口に立つその建物は、高い塀に囲まれた古い大きな石洋館であった。函間柔石で組まれた重々しい塀と外壁は、大気の湿り気を吸収して碧灰色に濡れていた。間口はさして広くはない。道に面した壁には、異様なおおきさの玄関扉がそそり立っているだけである。しかし奥にむかっては、建物の全容がおよそ見当もつかなかった。
アリウスはついさきほどその前を通ったはずだった。しかし覚えがない。木造、白レンガ造りの異国折衷建築が多い街中にあって、純古代風の建物はなぜか印象が薄かった。
「茶茶音(ちゃちゃね)様」
彼の腕をつかんでいた護国法兵士たちが深々と頭を下げた。反射的にアリウスも腰を折った。常に超然とした姿勢を保つ護国法兵士が礼をしたことに驚いたのだ。
「隊長士様からご連絡をうけております。旅の方だとか」
ふせがちの視線がアリウスをかすめた。
「この街で難儀に会うのも縁のあること。私どもにおまかせくださいませ」
護国法兵士ふたりは、こうべを垂れたままアリウスの腕を離してあとずさった。
「さあ、どうぞ。外は危険です。あとは兵隊様たちにおまかせしてなかにお入りください」
茶茶音(ちゃちゃね)と呼ばれた女性はそう言ってアリウスの手を取った。
アリウスは反射的に腕を引いた。祖先の記憶が不自然なものであると警告を出したのだ。
「旅のお方。我々を信頼ください」
護国法兵士のひとりが韻を踏まない普通の声で話しかけてきた。
その声のあまりの幼さにアリウスはおもわず振り向いた。フードの奥の白いヘルメット越しに少年の顔があった。
十四、五才の少年である。緊張に紅潮した頬が幼さを如実に語っていた。
「わずか一週間のご辛抱です。海神省には、隊長から報告を入れさせます。私たちの使命は、たとえひとりでも那乃国の邪悪な法呪の犠牲を出さないことです。ご安心して災禍凌ぎにご専念ください」
自信に満ちたきっぱりとした口調で少年兵は言った。海神省でこの報告をどう受け取るかはわからない。しかし少年兵の誠意には感動で答えるしかなかった。
「お勤めご苦労さまです。ご武運をお祈りします」
アリウスはそんな言葉しか思いつかない自分を恥じた。これ以上彼らに手間を取らせるわけにはいかない。
「さあ、どうぞ中へ」
いざなわれるまま、扉の内に入っていった。
|