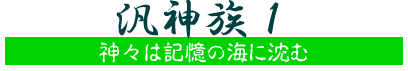|
彼らはそのまま闇に乗じて屋敷を脱出した。
アピアはラブドエリスの軽装鎧を付けていた。身長はあるため、さほど見苦しくはない。マシューは自分の防具を身につけていた。
「バッタ用の鎧なんて初めてみたぜ。意外にかっこいいな」
ラブドエリスはしげしげと彼の鎧を見た。マシューは自慢気に、玉虫色に輝く表面を叩いてみせた。それはなにかの昆虫の外骨格を加工したものだった。軽くしかも強靭だ。
「おまえが死んだら俺にくれよ」
「いいですとも。私の外骨格ごとさしあげますよ」
陽気に羽を震わせながらマシューは言った。
マシューとの話しに飽きたのか、ラブドエリスはアピアによりそっていった。
「よお、聞いていいか? サギマンの屋敷で窓のところにいたのっておまえだろ? なんで泣いていたんだ」
「泣いてなどいません。リ・ラヴァーは悲しくて泣くことなどありません」
「なんでさ。人間なんだろ?」
「リ・ラヴァーです。人間ではありません」
ラブドエリスはアピアの小さめの胸を人差し指でツンとつついた。
「この胸はかざりなのか。乳房は子供を育てるためについているんだろ?」
「さあ、試したことはありませんから。でも土くれが入っていても不思議ではありません。子供を作ったリ・ラヴァーはいませんから」
「八千人も人間といっしょに暮らしていて? ひとりも?」
「夫婦の契りを結んだ者がいるとは聞いています。でも、それだけです」
闇のなか、屋敷から奪った小麒麟にまたがって、一行は聖火香の城を目指した。
丘を三つ越えたそこに、聖火香の城があった。
「なんじゃ、こりゃ」
それを見上げてラブドエリスはつぶやいた。それは彼の知るものと大きく違っていた。まるで土石と材木の山。がれきの累積であった。
自然との調和が本来の姿であるべき神の城が見るかげもなく崩壊していた。
虫も植物もいない。
「結界で見せかけているのよ。ばかね」
ギュリレーネが竹の棒のようなものをバックから取り出しながら言った。
「どうやって入るんだ」
ラブドエリスは空中の見えない扉でも探るように両手を頭上で振った。
「アピアのソテーが、やっぱりいるのか?」
「あなたが望むなら」と、アピア。
「ナマがいいな、俺は」
「けだもの」
ギュリレーネは汚らわしそうに言いながら、棒を立体凧の骨組みのように組み上げていった。一メンツルほどの長方形を三面組み合わせたそれを、慎重に地面に立てた。
「なんていったっけ。マギーの門って奴?」
「そう。起動証に汎神族の属性にあるものが必要になるわ。さあ、ラブドエリス。私が法呪文を唱えるから、そのあいだ左手を門にかざして。あんたの内装兵器でもいいはずだわ」
「げっ、暴発したりしないだろうな」
「ラブドエリスのステーキでも門は開くんでしょう? どっちでもいいじゃない」
「人間様は繊細にできているんだぜ」
しかし彼の言葉を無視してギュリレーネは法呪文を唱え出した。
「……………キ……………」
人間にはまったく聞き取れない言葉の羅列が、かすかな耳なりとしてあたりに漂った。
マギーの門のなかに粘度の高い闇が現れた。それはあたかもベルベットでできた液体のようにどろり、と流れだした。
紙にインクが染みていくのに似た早さで、闇は彼らのつま先を浸していった。アピアが恐ろしげに後ずさろうとした。
「うごかーーないでーーっ」
間延びした声でギュリレーネが制した。黒い溜まりが全員の足元を飲み込んだとき、いままで見えなかったものが見え始めた。
巨大な人工の小山が彼らの眼前に現れた。頂上の端に城らしきものが建っていた。
「おいおい、前に来たときと違うぞ」
ラブドエリスは呆れて空にそそり立つプリンの形をした山を見上げた。
そう、まさしくカッププリンを、ぷるんと逆さまに皿の上に取り出した、あの丸い台形をしていた。ただし高さは百と四・五十メンツルほどもあり下部の直径は四百メンツルもあった。
しかも頂上の端をスプーンで一すくいしかけたまま凍り付いたように、巨大な一かけらが山からずれていた。いまにも滑り落ちそうな不安定なかけらの上に、聖火香の城は立っていた。それはラブドエリスにも見覚えのある城だった。長さの違う鉛筆を計算づくで束ねたような真っ白な城。
食べかけプリンの上に建つ、ロマンチックな神の城。
「しかし、まあ。こりゃあ趣味か? なにかの必然か? なんて形してるんだ」
ラブドエリスが誰に言うでもなくつぶやいた。
一行は山の周囲を巡って刻まれた階段を登っていった。頂上まではさして時間もかからなかった。朝日が海を照らし出すころ、彼らは頂上の平らな大地に立っていた。
「き、木……のような表面ですね。この地面」
マシューが足を踏みならしながらつぶやいた。彼はそわそわとしきりに体を動かしていた。関節がこすれて、鈴のような優しい音が絶え間なく流れていた。
「おちつけよ。相棒」ラブドエリスが笑った。
「は、はははい。良い朝ですね」
「この季節は、サンマが美味しいの」
アピアが突然に言った。ラブドエリスとギュリレーネは驚いてまじまじと彼女の顔を見た。
「だ、だって海が光っていて……」
白い顔は仮面のようにこわばっていた。表情どころか全身がでくの棒のように堅く硬直していた。
「こいつはたまげた。リ・ラヴァーでも神に緊張するのか」
ラブドエリスは本当に驚いて言った。
「わ、わたしは一度も神様にお会いしたことなどありません」
かわいそうなほどうろたえてアピアは言った。
「恐ろしいのなら帰りなさい」
ギュリレーネは彼らの緊張など気にすることもなく城に向かって歩きだした。
「ほら、こわいおねえさんは情け容赦ないぜ」
ラブドエリスもバッグをかつぎ直すと、すたすたと歩きだした。しばらくその場に立ち尽くしていたふたりは、やがて顔を見合わせた。勇気をかき集めてラブドエリスの後を追って歩きだした。
「あれっ?」
マシューの敏感な重層複眼に奇妙なものが見えた。先を歩くラブドエリスの背後を追うように、白い人影が漂っていたのだ。しかしそれは朝日に溶けるように、すぐに見えなくなった。
「アピア様、いまの見えましたか?」
「えっ、なにか?」
「いえ、いいえなんでもありません」
神の住処の神秘をいちいちあげつらうことの愚かさに思い至ったのだ。
やがて彼らがラブドエリスたちに追いついたとき、ギュリレーネがまたなにかの法呪文を唱えていた。城は目のまえなのだが、彼らが立つ地面と、城の建つ大地は十メンツルほども高低差があった。彼らの眼下に城の一階はあった。ちょうど一すくいが滑り落ちそうなまま固まったように下がっているのだ。
彼女の法呪文に応えて城は橋を差し出した。
橋を渡り始めた彼らは、城が立つ一かけらの大地が山から離れていることに気がついた。
「おいおい、浮いてるのかよ。この城」
さすがにラブドエリスも驚きを隠さなかった。ほんの数メンツルの距離ではあるが、この巨大な質量が宙に浮くことのすさまじさは、絶対に人間の技ではありえなかった。
「入っていいのでしょうか……」
できればやめたいと言いたげにマシューが言った。
「帰れば?」と、ギュリレーネ。
「やけにつっかかるじゃねえか」
ラブドエリスがマシューの第二肢を抱き込みながら言った。
「ラブドエリスもずいぶんしゃべるわね」
ギュリレーネが皮肉っぽく切りかえす。
結局全員が緊張しているのだ。
神の領域に入ることは、いかなる場合といえど、尋常ならざることだ。
城の中は四十年前とさして変わりはなかった。わけのわからない化け物がわさわさと闊歩し、そして生えていた。
「ラ、ラブドエリス様。こ、こ、これは」
マシューはますます縮こまって、ラブドエリスの後ろに隠れた。あえて言うなら以前より果物系のモンスターが増えているのか、攻撃を受けることはなかった。
「神の城とは、まことに偉大な……」
マシューが緊張に耐えきれず、しゃべりまくっているうちに、見覚えのある通路に出た。記憶ではこの先に聖火香の寝室があったはずだ。
「ギュリレーネ、おまえ来たことあるのかよ」
ラブドエリスが聞いた。
「いいえ、あるわけないじゃない」
「とりあえず寝室にでも行ってみるか?」
「あの……」
珍しくマシューが自分から言葉を発した。
「あの、さしでがましいようですが、私はこっちだと思うんですけれど」
マシューが左の壁に口を開けた下りの階段を指してきっぱりと断言した。
「私も……そう思います」
アピアも彼に続いて階段を指さした。全員が不思議な一体感に包まれて顔を見合わせた。
「いいわ。行ってみましょう」
ギュリレーネはあっさりと了解して歩きだした。階段は長く、かなり地下に深く降りていった。やがて行く手に十字路が見えてきた。
胸のあたりがもやもやするような空気が通り過ぎた。
一同は再び奇妙な確信にとらわれて顔を見合わせた。
「俺は右だと思うぜ」
ラブドエリスはそう言って正面の通路を指さした。
他の三人も言葉につられることなく正面を指さした。全員が同時に同じことを考えるほどメンタリティの近い者同士ではない。
「……こりゃあ、誘導されているな」
「そのようね。汎神族の意志の垂れられる様のありき。感じるままに進みましょう」
通路はますます植物がうっそうと生い茂るジャングルと化してきた。天井や壁からだけではなく、床からも見たことのない草木が伸び、良い香りを放っていた。
「…………」
マシューは時々立ち止まった。
「おい、よお、なに喰っているんだよ」
ラブドエリスが言った。
「あっ、はい。ちょっと……」
マシューの眼には、白い人間の姿が、ますます煩雑に見え始めていた。それをラブドエリスに言うべきかを迷っていた。
やがて彼らは巨大な調理場のようなところに出た。人間の王宮の舞踏会場ほどもある広大な空間のなかに、釜やオーブン、複雑な形をしたガラスの器が無数に配置されていた。天井は高く闇に呑まれて見えない。
植物の根らしいものがぱらぱらと垂れ下がっている。一抱えほどもある木の柱が不連続に立ち、床から天井につながっていた。
「ここはなんだ?」
ラブドエリスは警戒しながらあたりを見渡した。
「いやだわ。ここは隷ラディオの臭いがする」
ギュリレーネが鼻面をしかめた。その言葉にラブドエリスはあの恐竜の強力な戦闘力を思いだした。
「もう……どこかに進みたいとは思いませんね。ここが終点ですか?」
マシューが触覚をいっぱいにのばして言った。
「ギュリレーネ、あそこだ」
ラブドエリスが壁際にある人の背丈ほどもある木の樽を目線で指した。中から音が聞こえる。なにかが粘つくものの中から這い出ようとする不気味な音だ。
ぐぼっ、と空気の混じる音と同時に、巨大な筋肉の塊が顔を上げた。
それは不気味に濡れた、肉食の怪物の顎を持っていた。
「れ、隷ラディオ!」
ラブドエリスが反射的に剣を引き抜いた。ギュリレーネは、数メンツルも横に飛び鋼の桶に姿を隠した。
倒したはずの、あの戦闘生物が再び眼前に現れようとしていた。戦うために生まれた化け物は不死身であるのか。
「冗談きついぜ。聖火香! 俺達は雅流の実験を継ぐために来たんだぜ。隷ラディオのクソったれなんぞと遊んでる暇ぁねえぞ!」
悲鳴じみた叫びでラブドエリスは聖火香を呼んだ。
「ええい、どこかで聞いてるんだろう?」
そうしているあいだにも恐竜は牙をがちがちいわせながら、樽から這い出ようとしていた。全身を覆う濡れた鱗は、空中を漂う無数のクンフどもが発するかすかな光りを反射して美しく輝いていた。
「あ、あああっ。た、助けて」
突然、マシューが悲鳴をあげた。
「ぎ、りりりりりりぃ、けてぇ」
四肢がでたらめな動きを始めた。跳ね上がるように体がひっくり返り、床の上で柔らかな腹がむき出しになった。
長い左足がびくびくと激しいけいれんに襲われた。
「マシュー。なにやってるんだ。しっかりしろ、逃げるんだ」
ラブドエリスが剣を構えたまま近づいた。
「りりりんりりりぃん」
全身の外骨格から可憐な音をたてながら、マシューは床をころげまわった。
「ラ、ラブド……様、ああっ! たすけ……」
ひときわ大きい悲鳴と同時に、ばりばりと足の外皮が裂けた。
「キリリリリリッリリィィィィ」
筋と体液が飛沫を散らしてはじけ飛んだ。
「げげぇぇっく、げげげぇ」
マシューの細い足の筋肉から、隷ラディオの首が飛び出した。
まるで漫画のような滑稽な風景は、理不尽な恐怖を撒き散らした。
「…………!」
ラブドエリスはさらに数メンツルも後退した。
隷ラディオが二体。
どういうからくりかはわからないが、あの凶悪な恐竜が二体も現れた。戦えば間違いなく敗れるだろう。
もう意識もなく震えるマシューの足をさらに裂きながら、隷ラディオは腹中虫のように這い出してきた。それは脱皮する昆虫のように、器より大きな体がはみでてきた。
無駄とは感じつつ、ラブドエリスは短デュウを恐竜めがけて撃ち込んだ。しかし鉛弾はかすかな爪先の動きではじかれた。
「畜生、まえより強えじゃねーか!」
ごろり、と上半身が床に転がった。ギュリレーネが姿を隠したまま、山なりに鉄ビットを打ち出した。それも強化生物の反射のなせる技でことごとくたたき落としていった。
じゅう、と湯気を立てて、隷ラディオが立ち上がった。床に血の混じった液が広がった。
「かははぁ、げっぐぐぐ」
喉を鳴らす不気味な笑い声を立てた。
「ラブドエリス、見て、足が」
ギュリレーネがするどい声で言った。隷ラディオの両足首が砕けていた。己とマシューの血が混じり泡を吹く中に、白い骨がのぞいていた。間違いなくラブドエリスの攻撃を受けた奴自身だ。
「み、見つけた。ラブドエリス、ぐっぐっ、よくも、よくも私の美しい足を傷つけてくれたわね。に、人間の分際で。ぎきいぃぃ」
ずしゃ、と肉塊と化した足を踏み出した。
「アピアは逃げろ! ギュリレーネはこのいかれた隷ラディオに集中。対質量結界を三重展開、起動証を起こせ。奴を閉じこめる!」
「応」
ギュリレーネは両手両指を一杯に伸ばし、全ての爪を別々に動かしながら空中に起動証文を描いていった。驚異的な早さで五千音に及ぶ法呪文を唱えていく。ラブドエリスも可能な限りの早口で唱和する。
「ぐぎぎい」
ぎこちない動きのまま隷ラディオが飛びかかってきたが、ラブドエリスは剣をたたき込み、かろうじて退けた。
「起動」
ギュリレーネが言った。床一面に浮きだした起動証がぎりぎりと空中に渦をまいた。隷ラディオには見えていないのか、自分を取り巻きだしたそれをまったく無視していた。
「私にできることは。ラブドエリス様、私も」
アピアはけなげに踏みとどまっていた。
「床に見えている起動証を右回りに詠め」
「どこから」
「好きなところからでいい。でも絶対に詠み飛ばすな」
「は、はい」
三人の声は速さもテンポもめちゃくちゃで、ハーモニーのかけらもなかったが、確実に結界を形成しつつあった。
「なまいきぃ!」
結界に気がついた隷ラディオは尾の力だけで天井近くまでも飛び上がった。
しかし彼らは結界の完成まで陣型を変えることはできない。ラブドエリスは結界を放棄して再び時間遅延の法呪を結ぼうとした。
そのとき床から虹色の体が飛び上がった。
びしゃり、と鈍い肉の音を立てて、空中の隷ラディオに体当たりをした。
ふたつの身体はもんどりうって、テーブルのうえに落ちた。ガラス器具が派手に砕け散った。
不意を突かれた隷ラディオは怒りに我を忘れて虹色の身体にかぶりついた。首を激しく振りたてるごとに細かな肉片が飛び散った。
「……マシュー……!」
ラブドエリスは声にならない悲鳴を漏らした。瀕死のマシューが最期の力を振り絞って彼らを助けたのだ。
「攻防相い担う壁を築き再び破れず」
最後の法呪文が言いきられた。
半透明の杉目板が床、壁、天井から立ち上がった。それはめまぐるしく回転しながら、怒り狂いラブドエリスたちへの集中を失った隷ラディオを取り囲んだ。
板の一枚いちまいが「完結」の意味を粉のように散らしながら隷ラディオの動きを封じた。
「ぎききぃ、なんで? なんで人間の分際でこんなにこざかしい! ラブドエリス、ラブドエリス! ラブドエリス!」
「次だ。奴から知塩を抜いちまうぞ。ギュリレーネ。ビット用意」
「応」
かっ、とギュリレーネは耳まで裂けた口を開いた。
「号羅(ごうら)様ーー!」
隷ラディオが聖火香の城で違う神の名を呼んだ。
城が、びくっと震えた。なにかが城の存在をこじあけるように、力任せに進入してきた。聖火香の落ちついた優しい感触がめりめりと音を立てて引き裂かれていった。
「ばかな」
神の下僕たるギュリレーネには信じられない神の神に対する干渉だ。号羅という神が聖火香の城内に法呪を作用しようとしていた。
「号羅様。おおうぐ、号羅様!」
ばしゅっ、と空気が渦を巻いた。一瞬にして隷ラディオの姿が消えた。
「くそ、逃がした。ど畜生! 神がこんな大技を他神の城めがけてやるか? 死にぞこないのとかげのしっぽに!」
ラブドエリスは行き場を失って反呪をおこし、あらゆるものにからみついてきた結界の残骸を振り払いながら、だだん、と床を踏みならした。
「もう一匹の外道はどこいきやがった」
しかしもう一体の恐竜は姿を消していた。ギュリレーネの鋭い臭覚にも気配は感じられなかった。
「なんだってんだ。相変わらずわけのわからねぇ城だぜ。聖火香様はなにしてるんだ」
ラブドエリスは不完全燃焼の闘志を持て余していた。
「…………」
アピアが床にうずくまっていた。
「やられたのか?」
ギュリレーネがかたわらに膝まずいた。彼女のつま先に、引き裂かれたマシューの羽が打ち捨てられていた。
「マシュー、マシュー。しっかりして……」
アピアはずたずたになり、なかば体からちぎれかけたマシューの頭部をかき抱いた。黄色と朱の体液がぬらぬらと彼女の全身を染めあげていった。驚異的な生命力でマシューはかすかに意識をとどめている様子だった。
しかし言葉を発するちからは、もうない。
「助かるか?」
ラブドエリスがギュリレーネに聞いた。
「法呪媒体に使うのがせいぜいでしょう」
「ば、媒体って?」
アピアは涙で濡れた顔をあげて、必死の眼差しをラブドエリスに向けた。彼は自分がこんなふうに泣くのを初めて知った。
「いや、なんでもない」
おもわず目をそらしながら彼は言った。法呪媒体とは文字どおり、法呪の発動に必要となる滋養を得るための栄養媒体にするということだ。隷ラディオが行ったこともそのことに他ならない。
「隷ラディオはマシューの体に予約印を入れていたのね。移動と傍受を目的にしていたに違いないわ」と、ギュリレーネが言った。
「俺達に案内させたってのか。ど畜生め」
ラブドエリスはマシューの頭に手を置いた。
「マシュー。勇敢だったぜ。俺達はおまえに救われた。名を残すに値する。お前の美しく強い羽根を俺の盾としてマシューと名づけることを許してくれるか?」
「…………」
想像を絶する努力で、マシューは指先をわずかに動かした。筋肉が外骨格から剥離して体液が流れ出す。
「だめ! 動かないでマシュー」
アピアはわが子が傷つくのを目の当たりにした母親のように半狂乱になって叫んだ。しかしマシューのささやかな動きは、拒否を感じさせるものではなかった。
ギュリレーネがアピアの肩を抱き立ち上がらせた。
ラブドエリスはナイフを抜くと、柔らかな飛翔羽を包んでいた外羽を根元から切り放した。彼は若い神から奪ったアンプルを羽の上で割り、さらさらとした液体を垂らした。羽は海綿のようにエキスを吸収して、輝きを落とすことなく硬化していった。
「我を守ることを託す」
そのとき。
「げげっ、汝を倒す!」
巨体が天井の板目から湧き出た。
真っ赤な血しぶきをまき散らしながら、肉の塊はラブドエリスの上に覆いかぶさった。
「隷ラディ ……!」
ギュリレーネの悲鳴が途中で途切れた。するどい尾の一振りが彼女をかかしのように弾き飛ばした。
ラブドエリスは反射的に短剣を抜き、傷ついた恐竜のわき腹に突き立てた。しかしそんなものが容易に致命傷となる相手ではない。
「貴様! 逃げ出したんじゃないのか。隠れるなんてシャレた真似しやがって」
隷ラディオの鋭い牙がラブドエリスの肩に食い込み、鎧ごと筋肉を噛み砕こうとしていた。臭い息が死の恐怖をまき散らす。
「ぐがががっ、情け深い号羅様がチャンスを下さったのよ。貴様たち、ずるがしこい虫けらどもなんて、正々堂々と戦えば敵じゃないんだから」
隷ラディオはナイフのような爪をラブドエリスの腹に突き立てようとしたが、マシューの羽に邪魔されてとどかなかった。爪が硬化した羽を掻きむしり、きーきーっと、いやらしい音を立てた。
「……ちくしょう!」
ラブドエリスは全身、いたるところの骨が砕かれるのを感じた。法呪の攻撃を避けるために隷ラディオは完全に体を密着させたまま、打撃と噛みつきの攻撃を繰り返していた。すさまじい重量と堅いうろこのために、刃物は効果的なダメージを与えられない。
狙いも付けずに内装兵器を放った。強烈な熱球により、隷ラディオの肉と皮膚が消し飛ぶ。しかしまったくダメージにならない。
「むだ、むだぁ」
隷ラディオは巨大な口を大開きにして笑うと、ラブドエリスの首筋めがけて襲いかかった。
「ちっ! ……」
ラブドエリスは反射的にマシューの羽を首筋にあてがった。
隷ラディオの顎が、羽ごとラブドエリスの首を噛んだ。めきめきと羽が不気味な音を立てた。
「ひぃー、ぎぎぎっ」
勝ち誇ったように隷ラディオは笑った。羽が割れたとき、ラブドエリスの首も喰いちぎられる。内装兵器を放とうとして左手をあげかけたが、骨の覗いた隷ラディオの足がそれを踏みつけた。
「マ、マシュー!」
アピアの悲鳴が響いた。
隷ラディオは、ぎょっとして倒れたバッタに目をむけた。また邪魔をされるのかと。
しかしマシューは倒れたままだった。いや、まるで火をつき付けられた虫のように、ばらばらなけいれんに襲われていた。
断末魔のそれとは違ったなにかだ。
「な、なによ。なんなのよ! またなにを!」
不吉な予感を感じて隷ラディオが叫んだ。
マシューのずたずたの体が激しく収縮した。
滋養が抜けた。
なにかがマシューの躯を吸い尽くして姿を現した。人型のなにかだ。
真っ白な塊は、すいっと宙をすべると、上半身を起こしかけたギュリレーネの首筋を鷲掴みにした。
やさしく、しかし強引にギュリレーネの頭を隷ラディオに向けた。
「なにっ? なに、あんた! か、神様?」
隷ラディオが絶望的な悲鳴をあげた。その声をさえぎるように、ギュリレーネの口から神の高速言語がほとばしり出た。
「キ……ィィィ、ィアアアアッッーー」
隷ラディオの身体が弾き飛ばされるように空中に浮いた。
「ご、号羅様、お守りください!」
白い人型の姿は、ギュリレーネの改造された器官を使って高速言語を操った。彼女の首を砲台のように隷ラディオに向けた。
隷ラディオの回りに、半透明の防護幕が展開された。号羅の再三にわたる干渉だ。
「チィィ……ィン!」
防護幕が濡れ紙のように消し飛んだ。信じられない威力に隷ラディオは血まみれの顔を歪めた。
「あ、あんた。あの時の…………」
ごきっ、と不気味な音が部屋に響いた。
真っ赤な光が瞬間的に部屋を満たして引いていった。
巨大な肉の塊がテーブルを砕いて落ちてきた。
ばたん、びたん。と筋肉が床を叩く鈍い音が響いた。
「……れ、隷ラディオ……」
ラブドエリスは遠のきそうな意識をかき集めて信じられない光景を見た。
隷ラディオの首を失った躯が、潰されたミミズのようにのたうちまわっていた。
首だけを切り離して逃げたのだ。
「キィ、カアアアアン、シユユユュュュュ」
不発に終わった、とどめの法呪文がギュリレーネの口からゆるゆると流れ出た。
「か、神様…………?」
ギュリレーネのかたわらに立つ、頭の先からつま先まで真っ白な全裸の若者を見てアピアはつぶやいた。
「あなたは、聖火香様の卷族ですか」
「まて、おまえ……おい。アリウスか?」
ラブドエリスが苦しい息の下から言った。
「………………」
白い若者は、たった今自分が放った超絶の技を理解できないかのように、心の抜けた表情を浮かべて立ち尽くしていた。重傷を負ったラブドエリスの身体は、一世代、二世代前までの時間遡及でも快復できずに、いつまでも青い光りに包まれていた。
「……ラ……」
顔を歪めながら、アリウスはそれだけを発音した。ギュリレーネが倒れこんでいくアリウスをささえた。
「雅流様の実験は成功されたのですね」
ギュリレーネは尻餅をついた彼の傍らに平伏した。
「……じ、っけん」
アリウスはうつろな目をあたりに漂わせた。
「ふぬけちまってやがるぜ。そいつ」
ラブドエリスは剣を逆手に持つと、じたばたと暴れる首無し隷ラディオの心の臓にとどめをさした。
「……神様、ではないのですか」
アピアがおそるおそる聞いた。
「ああ? 聖火香に届ける荷物さ。荷物。よお兄弟、気分はどうだい」
「……ら、ラブドエリ、ス様。ギュリレーネ……様。ぼくは、ぼくはどうして、ここに」
「どうしてって。おまえが出てきて俺達を助けたんじゃないか。わかってないのか? 知塩を喰い終わったんだろう?」
「チ……エン……ええ、そう。食べました。美しい女官が大勢いる、美しい海辺の……まるで王様の別荘のようなところで。朝晩、繰り返される宴でした……ああっ」
アリウスは悩ましげなため息をついた。
「きれいな、見たこともない、天女のようなお姫様たちが僕の回りに大勢いました。音楽を奏でて、そう、昼も夜も……」
「な、なにをを。夜ぅ? 昼だあ」
ラブドエリスがじゃりっ、と床を踏みにじった。
「甘く、せつない、不思議な味の食べ物がたっぷりあって。良い気候と気持ちのよい夜具と……優しい異国の奴隷娘たちが、珍しい山海の珍味を」
「くぅおら。てめぇ。いい思いしてんじゃねーか。それ以上言うと隷ラディオの後を追わせるぞ。雅流め、ずいぶんおちゃめなサービスするじゃないか。人間どもとしゃべってばっかりいやがったからだぜ」
「人間? そう、人間の影響ね」
ギュリレーネが困ったように笑いながら、ラブドエリスを見た。
「なんだよ。イタチ娘」
「さすがは雅流様。人間の卑しい習性にも造詣が深くていらっしゃる」
と、ギュリレーネ。
「あの、もし、良ければこれを」
アピアが視線を反らしながら、自分のマントをアリウスに差し出した。
「ありがとう。君は?」
全裸のアリウスは恥じるようすもなくマントを受け取ると体に羽織った。
「わ、私はアピアといいます。アリウス様」
「だああっ、てめえ! 軟派してんじゃねえよ。アピアもアピアだ。なに赤くなってんだ」
「あ、赤くなんかなってません」
真っ赤になって彼女は答えた。
「いいから、行くぞ。こん畜生ども。聖火香様に雅流を渡しちまうんだ。なんならこの極楽道楽アリウス君も、(ピーー)の先っちょにリボン結んで置いてきちまおうぜ」
|
|