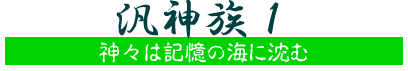|
「おかえりなさいませ。旦那様」
門についた小麒麟車を、大勢の使用人たちが出迎えた。立派な口髭をたくわえた初老の執事が男女に分かれた使用人の先頭に立って、深々と頭を下げた。
「ローリーセバスチャン。変わりはないか。半年の留守中苦労をかけた」
サギマンははじけるような笑い声をあげて言った。彼は寛容な主人らしい。縦にも横にも膨らんだ巨体をゆさゆさと揺らしながら、足早にローリーセバスチャンの元に進み、両手を握りしめて労をねぎらった。
「もったいのうございます。旦那様こそ長い御仕事の旅、お疲れさまでございました。ささっ、まずは湯殿のご用意も整いましてございますゆえ、ごゆるりとなされませ」
ローリーセバスチャンはそのときになって初めてサギマンの巨体の後ろに見知らぬ人間がいることに気がついた。
「これは、参り旅の方でございますか? 御主人様」
「ローリー? ローリーセバスチャンだって?」
にやにやと思いだし笑いをしながらラブドエリスは言った。
「俺はおまえを知っているぜ。なあ、夜の帝王のローリーセバスチャンだろう。花窓のお嬢さんの誕生日をみんな暗記しているのが自慢だったよな。あのときは世話になったな」
「はっ、失礼ですが……」
いぶかしげに彼はラブドエリスの顔を見た。
「うむ、皆にもみやげがあるぞ。さあ、屋敷に入ろう。マシュー。客人を朱梅の間に御案内しなさい」
「はい、御主人様」
マシューと呼ばれたバッタ男がラブドエリスの前に進み出た。よく訓練された給仕の身ごなしで彼らをうながした。まだ三齢幼虫程度の彼は意外と鮮明な発音で答えた。
「剣士様。のちほど晩餐の御案内を致しますゆえ、まずはお休みください」
サギマンはラブドエリスの名前を避けるように言い、使用人たちから彼らを引き離した。
「どうぞお客様。御案内致します」
黄緑色の触覚の華奢な少年は、ラブドエリスの手から米一俵ほどの重さもある旅具袋を受け取ると、よろよろと歩きだした。
「うん?」
ラブドエリスは、誰かの視線を感じて顔をあげた。そして屋敷正面のバルコニーに立つ少女を見つけた。
北方系のはかなげな少女だった。
ラブドエリスはしばし目が釘付けになった。
高等学生のはじめほどに見える、ほっそりとした背の高い美しい子だった。まだおさなさの残る身体つきに似合わず、落ちつきのある利発そうな表情だった。紅い唇がなにかを言おうとしてかすかに動いた。
海風が吹き、プラチナブロンドの長い髪が幾筋か頬に流れた。
少女は濃い灰色の大きな瞳いっぱいに、涙をうかべていた。
それがこぼれ落ちそうになったとき、柔らかなドレスをひるがえして、すばやく部屋のなかに入っていった。
「……サギ坊の……これか?」
ラブドエリスは不謹慎にも小指を立ててマシューに聞いた。
「お客様だとうかがっておりますが」
マシューは器用に困惑した表情を浮かべた。
その夜ラブドエリス達は、人気のないゲーム室でディナーをとった。
正確には人払いをして隔離された部屋でサギマンと向かい合った。ローリーセバスチャンとマシューが給仕をする中で食事をした。サギマンはきわめて慎重にラブドエリスと使用人達の接触を断っていた。
「ご満足いただけましたか。ラブドエリス様」
愛想の良い笑顔でサギマンは言った。
「うむ、こんなによく料理されたものを食べたのなんて何年ぶりだろう。うまかった」
ラブドエリスは手酌でデカンタからワインをそそいだ。酒は好きだが雅流の寺では蜂たちが作る蜜酒ぐらいしか口にすることができなかった。
汎神族の食習慣は、自然の新鮮なものを生で食べるというものだった。
汎神族の食性に合わせることは難しいことではなかったが、やはり人間の料理に焦がれることもあった。
「ああっ、腹いっぱいだぜ」
「飲み過ぎよ。ラブドエリス」
ギュリレーネが呆れたようにつぶやいた。
「うまい酒だぜ。おまえも飲めるんだろ」
「知らないわよ。そんなに飲んだら」
「ところで」
サギマンが小さく音を立ててグラスをテーブルに置いた。
「ラブドエリス様。これは私のげすな野次馬根性です。よろしければ、あれからのことをお聞かせ下さいませんか。父もあなた様のことをたいへん気にしておりました。あわれな父への供養と思っていただきたいのです」
「別に。つまらないぜ。なんにもない四十年だった。やることもないから、剣ばっかり振り回してたぜ」
「はあ」
「それより、ローリーセバスチャン。俺を思い出してくれたかい? 花窓の娘たちの顔役だった色男さんよ」
「いや、これは恐れ入ります。そのせつは私も若気のいたりで街のことしか頭になかったものですから」
全身をしゃちほこばらせて、ローリーセバスチャンは答えた。
「うん、なんの話だ? 私にはわからないぞ」
サギマンが察している様子で愉快そうに聞いた。
「いや、どうぞ御容赦のほどを……」
「なに?」
ギュリレーネがひとり事情もわからずに聞いた。
「俺が昔、この街でのせられちまったときに、夜のお嬢さんたちに昼夜をぶっ続けの説得を受けてさ。それを仕組んでたのが、この優秀な執事様だったのさ」
まんざらでもなさそうにラブドエリスが言った。
「まあっ、ああ、そう。お羨ましい。まあ」
ギュリレーネにはおかしくもなんともない話だった。しかし人間流のリアクションを返そうとして、変なことを言ってしまった。
「これは、御婦人の前で失礼いたしました」
サギマンは恐縮したようすで、小さく咳払いをした。
「サギ坊。俺からも聞いていいか」
「はい。なんでしょう」
「俺達のことを汎神族に知らせるとか、リボンをかけて届けるとかする気はないのか? 願い事の三つくらいかなえてくれるかもしれないぜ」
「私が? ラブドエリス様を? なぜ、そのようなことをする必要があるのですか。どこにいるかもわからない神様に」
「わからない?」
「神様の奇跡はいまでもあちらこちらに現れていますが、神様を見た人なぞ、もう何十年もいないのではありませんか」
ラブドエリスは意外なことを聞いてグラスをテーブルに置いた。
「そうなのか?」
「はい。ましてや神様が特定の人間に対して褒美を与えるなど、絵本の中の話ですよ」
「でも、リ・ラヴァーどもはいるぞ」
「はい。しかし神様が街角で配って回ったわけじゃありません」
「汎神族は数が減っているのか?」
「さあ、減っているのか、姿を見せないだけなのかは知りませんが、この街の人間は聖火香様しか知りません。その聖火香様も在城のときですら御姿をお見せになりませんでした。ただ、妖怪が出るから神様がいるに違いないと思っていただけで」
「聖火香様の姿を見た者がいないだって?」
「はい。私は商売柄、いろいろな国々の者どもと話す機会がありますが、神様の御姿を実際に見た人は、信頼できる話しとしては存じません。会っただの、触れただのは予言者を語るタカリどもぐらいなもので」
「……いや、聖火香様はたしかにいた」
ラブドエリスは噛みしめるようにつぶやいた。自分自身が聖火香の怒りに触れたのだから。そう、雅流の寺で彼女に会ったこともあるではないか。
「おお、それはもちろんです。ラブドエリス様が命がけで聖火香様を説得してくださったことは市民の忘れるものではありません。なによりも我々人間の誇りとするところです」
サギマンは大仰に両手を広げて言った。
「ただ、私たちとしては聖火香様にお戻りいただければ、とも考えているのです」
「わかるわ」
ギュリレーネが確信をこめて言った。ラブドエリスは驚いて彼女を見た。
「神は自然を愛します。この世のものすべてを愛しています。人間も懸命に生きようとする自然の一部です。しかし神の意志を感じ、わずかなりとも理解できる生き物は限られています。人間は希有な生き物のひとつです。人間が神を身近に持ちたいと考えるのは、とても自然なことなのです」
「ああっ、ギュリレーネ様はこの世のことわりに通じておられる」
サギマンは感動を隠さずに涙を流した。
「神は身近であり、崇高であり犯しがたく、しかも、そう、忘れがたい。忘れがたい。ゆえに存在をつねに感じずにはいられない」
ギュリレーネは静かに続けた。
「いじめられても尽くしますってか。人間は変態か? はっ?」
ラブドエリスは納得いかずに叫んだ。
「人間だけではないのです。ラブドエリス様。あれから高地の羊たちの乳の出も悪くなりました。鶏たちも卵の数を減らしました」
サギマンがおそるおそる言った。
「ばかな。奴らだって、メシを食ってくそをするんだぜ。そんな超越したもんじゃないぜ」
ラブドエリスの言葉を無視してギュリレーネは続けた。
「ルアーに、疑似餌にだまされる魚。ぬいぐるみにだまされる猿。人間も姿が似ているばかりに汎神族を自分たちに近しいものだと考えがちです。でもそれは大きな誤りです」
「ところでラブドエリス様、雅流様をご存知ですか?」
サギマンが急に話題を変えた。
「雅流? 様。なぜだ?」
「いえ、あの。雅流様は汎神族の中においても特別に徳が高いとか」
サギマンは急に目をぎらつかせて言った。
「それは、その通りですわ。まったく」
ギュリレーネは人間のサギマンの変化に気がつかないのか、調子を合わせたまま微笑んだ。
「そう。やはりそうですか。雅流様、雅流様を見ましたか」
テーブルに身を乗り出すようにサギマンが言った。
「雅流様は、あの御柱はどこにおいでですか」
彼の言葉は、にこやかな中にも他者を圧倒する迫力を秘めていた。
「……ええ? おい、サギ坊。なんだってんだ。俺たちが他の神様に会ったことなんてあるわけないじゃないか。……うっ」
ラブドエリスが肩を押さえてうずくまった。
「ど、どうなさいました。大丈夫ですか」
驚いたサギマンが立ち上がった。マシューはすばやく彼の後ろに駆け寄り、背中に手を当てた。
「剣士様?」
マシューはラブドエリスの肩から奇妙な光がもれているのに気がついた。
「いや、なんでもない。平気だ。戻ってくれ」
「でも……」
マシューは困惑した様子でラブドエリスとサギマンを見比べた。
ギュリレーネが優しく彼に声をかけた。
「彼は大丈夫です。疲れが出ただけですわ。サギマン様。たいへん楽しいひとときを過ごさせていただきました。失礼とは存じますが、今日はもう、休ませていただいてよろしいかしら」
「ああっ、これは気づかずに申し訳ありません。お部屋の御用意は整っております。マシュー。御案内を」
サギマンはこっけいなほどあわてて言った。
「はい。御主人様」
ふたりは続き部屋をそれぞれ当てがわれた。豪奢な調度品に囲まれたそれらの部屋は雅流の寺とは違う、人間くささの漂うものだった。
マシューは気をきかせてか、視線をそらせながら部屋の設備について一通りの説明をした。ギュリレーネはいちいちうなずきながら彼のサービスに応えた。
「これはエリエルの葉です。食べ過ぎに効きます。よろしければお使いください」
マシューはテーブルの上に干した葉を数枚置いた。
「ごていねいにありがとう。あなたももうお休みなさい」
「はい。奥様。失礼いたします」
マシューはおどおどと挨拶をして、後ずさるように下がっていった。
「まいったな。レンズが効いちまった。よりによって……いつのだ? 食事前の身体を持ってきやがったのか。……腹へった」
ラブドエリスはぐったりとベッドに倒れ込んだ。力がまるででない。
「ばかね。飲み過ぎたんでしょ」
ギュリレーネは同情の余地もないようすでつぶやいた。
「わからん。かわいこちゃんの酌もなしに飲み過ぎたことはないけどな」
「せっかくだからエリエルの葉でもたべたら? すこしはお腹のたしになるかもよ」
皮肉たっぷりにギュリレーネは言った。
「馬じゃあるまいし。人間様がエリエルの葉を食うのは毒消しのときぐらいだぜ」
「……毒消し?」
いぶかしげにギュリレーネは聞き返した。
「そう。動物毒を消すときのな。よかったら食っとかないか?」
「どう理解したらいいのかしら?」
娘の姿が透けて真っ赤な目が光りだした。銀ログム種の怒りの攻撃色だ。
「怒る前にさ。腹はなんともないのか?」
「いま腹中虫に調べさせている」
そう言ったつぎの瞬間。可憐な唇の端から大人の中指ほどもあるミミズのような虫が飛び出した。それは床に落ちて、びちびちと苦しそうにはねたあげく、紫色に変色して溶けていった。
「……人間風情が……この私に、私に毒を盛ったというのか!」
「ま、お互い気がつかなかったってなあ、おまぬけの証拠だぜ。出し抜かれたんだ」
ギュリレーネは怒りに目が眩み、なかば銀ログム種の姿をさらしたまま廊下に駆け出そうとした。ラブドエリスはすばやく枕を投げつけた。振り返りもせずに閃いた凶悪な爪が、それを空中で切り裂き、純白の羽毛を散らした。
「腹いっぱいのくせに怒りっぽい奴だな」
「なぜ、そこに黙って座っている?」
ギュリレーネの声は怒りに震え、人間の音をはずしかけていた。
「どうせ、もうすぐトンズラするつもりだからさ。毒を盛った奴がいたかどうかなんてどうでもいいや」
「なに?」
「ぐすぐずしていると、毒を仕込んだ連中が来て面倒くさくなっちまうぜ」
ラブドエリスは異常に陽気な様子で、バッグから軽装鎧を取り出した。うきうきと鼻歌まじりでそれを装備していく。ラブドエリスが短気なことを知っているギュリレーネは、納得いかなげに言った。
「いったいどこに行こうというの。けりをつけずに行くのは禍根を残すことにならない」
「けり? いいじゃねえか。俺もおまえも下痢腹かかえてトイレでうなったわけじゃなし。俺は早く聖火香様の寺に行きたいんだ。人間どもの相手はあとでゆっくりとしてやるさ」
ギュリレーネがなにかの気配を察して床に身を伏せた。首を長く伸ばすような身ぶりで階下の音を探った。
「……残念ね。かかわりたくないのかも知れないけれど。人間たちが大勢こっちに向かってきているわ。うかつな私たちを笑いにきたのなら、サービスすべきじゃないかしら?」
娘の姿を悪魔のように歪ませてギュリレーネは笑った。
ベッドのシーツを剥ぎ、等身大のランプシェードにかけて扉の正面に立てた。
「ああ、もう。頼むから殺しても食うなよ」
まだ支度のできていないラブドエリスは、肩をすくめて首を振った。
「ほら、ふたり。扉の外にきたわ」
コンコン、と分厚い柏の扉がノックされた。ギュリレーネとラブドエリスは左右に展開して、侵入者を待ちかまえた。
|
|