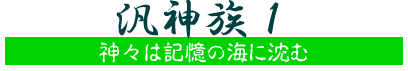|
ラブドエリスとギュリレーネの仕業は、汎神族各閥の知る処となった。雅流が記憶溢れを起こしたことに対する保護隊の不始末は、アリウスと雅流の実験結果が、未だ未回収とのこともあり不問に伏された。
位相遷移を施されたアリウスは、間違いなくこの世にいるのだが、何人も彼の存在を実在として認識できないでいた。
幽霊のようなあいまいな立場のもとで、彼は夢まどろみながら、老神の知塩を食べているはずだった。
知塩とは記憶を霊体化させた物質である。
汎神族のいくつかの閥は人間を生贄にしようとするとき、髪の毛を媒体として記憶物質を固定する。雅流がマロウンに施した処置もまさしくそれであった。
汎神族の記憶は質も量も人間とは比較にならない。それゆえに記憶の固定には肉を媒体としたのでは足りずに、霊媒物質を仲介することになるのだ。
知塩を食することは、神本人の記憶を得ることに等しい。しかしどれほどの量がそのなかに蓄えられているのか知れないために、神がそれを食するには、記憶溢れを起こすリスクを伴う。
かつて人間が知塩を食した記録はない。人間の記憶の仕組みは単純であり、汎神族はとうの昔にメカニズムを解明していた。基本は化学変化と電気的な刺激の組み合わせである。しかし汎神族の記憶の秘密はいまだ明らかにされていなかった。
あるとき、名の知れぬ宗派の修行僧がタブーを犯して妻の知塩を食した。そして得られた太古の記憶の断片のなかには、意外な秘密が語られていたという。
「知塩は甘く、苦く、脳髄を膨らまし、破裂させんがばかりの法悦なり。かけがえのなき妻の味は格別」
その神は神を喰うことすら修行と称していた。
「食の衝撃は情報の多きに圧されて、混乱のすさまじきを言うに言葉なし」
「我、ただちに記憶潜行を試みたり。時間は二ヶ月に及び、衰弱を覚え、生命の尽きかけしときにかろうじて今世に帰する」
「語ることの多きは、我が命あるうちに果たせぬほど。我が子を成すを許されれば、伝えることを可とする」
「妻の記憶のいかほどか知れずとも、我が記憶となるを知る」
他の神の記憶が、知塩を食することにより自分のものになる。それは予想されたこととは言え、初めての実例だった。しかし汎神族を驚かせたのは、次の証言だった。
「……この記憶を語るは、我が精神の正常なるに疑念を持つも正なり。しかし我は言う」
「五十四世遡及の記憶にあり。人間に知塩を与えし者あり」
「人間はそれを受けいれ死せず。全身これ白蝋のごとき色に変じて、なお生命を長らえ、知塩の記憶を、すべて正確に継ぐ」
「我が汎神族の記憶は神秘にあらず。任意処理の可能性を秘めたものであり」
「記憶溢れからの救いは絵空言にあらじ」
その意味するところは定かではない。あまりに古い記憶のために、それ自体が混乱した情報なのかもしれない。デマを記憶しただけのことかもしれない。
雅流は慈悲深く、人間を愛する神であった。しかしそれはあくまで神の高みからの愛であり、人間個々人への切ない愛情ではない。アリウスを実験体とすることへのためらいなどあろうはずもなかった。
知塩を食することによるアリウスの変化は汎神族のための貴重な症例となりうる。まさに数多くの実験のうちのひとつにすぎなかった。
神にとって自分の記憶こそが、真に研究の価値を持つと考えられていた。雅流がラブドエリスとギュリレーネに、自分の首を託したのも、おそらくそのような自惚れがあってのことだった。
しかし各閥の中枢は、アリウスと雅流の首を別の実験とは取らなかった。アリウスの位相遷移が解かれたときに、すぐさま捕獲できるように、雅流の首は探された。
人間のラブドエリスと銀ログム種のギュリレーネが、首をどこかに運び去ったことだけは知れていた。にもかかわらず行き先がいまだにわからなかった。
保護隊を派遣したにも関わらず失敗し、あまつさえラブドエリスに総本山をゾンビロウで汚されるという失態をさらしたグリュースト閥は、宗派間による調停賢委員に直訴して、汎神族流の復讐を許可された。
すなわち八千人ものリ・ラヴァーを人間界に放ったのだ。
リ・ラヴァーとはラブドエリスの性転換複製体である。
歳の頃は十五、六歳。娘の姿をしたラブドエリスがあらゆる国に突然現れた。それが汎神族の技だと知る富豪、貴族のなかには意味することを意に解さずに、養女として迎えたり、嫁として取る者まで現れた。
人間にはそのことがなにほどの意味を持つか想像もつかなかった。
しかし汎神族にとっては、それが最高級の懲罰だった。
「よお、大将。あんたリ・ラヴァーどもに似てるな。よく言われないかい?」
ロスグラードに向かう連絡船の船長が言った。神社参り者の服を着たたくましい男がまぶしそうに顔を上げて答えた。
「誰も信じてくれねぇけどな。俺がオリジナルなんだぜ」
変装したラブドエリスだった。
「そいつぁいい。きれいなねーちゃん連れたあんたが神様の怒りを買った野郎だってかい? わはははっ、ねーちゃん、あんた果報者だね」
船長は熊のような髭と体毛に覆われていたが、頭だけは磨き込んだように見事な禿だった。やたらと陽気で、自分の人生を他人に覚えてもらうことを生きがいにしているようなしゃべりっぷりだ。
「無愛想なねーちゃんだね。女は愛敬のいいのが一番だぜ。それとも実はこのホラ吹き野郎にそそのかされた良い処のお嬢さんだってか? だははははっ」
いまギュリレーネは、普通の街娘の姿をまとっていた。すっかり男の話に飽きた彼女はマストに干されていたニシンの干物を無心にかじっていた。
「さっきから気になってたんだけどよ。お嬢さん変な喰い方するね。こう、さ。ネズミみたいによ」
船長が面白そうに言った。ニシンに残る歯形を敏感に見とがめたらしい。
「ばかやろう。この娘はやんごとなき御方に御仕えしてたんだぜ。宮庭風ってなマナーを知らないのか、あんた」
ラブドエリスは鼻で笑いながらフォローをした。
「あっ、やっぱりいいところの娘っ子をだまくらかしたってクチか。悪党め。お嬢さん、いまからでも遅くねえ。俺みたいに堅実な職を持ったまじめな男ん所に嫁に来るのが幸せってもんだよ。こんなやくざな参り者なんざ、いつおっ死ぬかもしれないぜ」
船長はかぶりを振って言った。まるでとなりの家のおばさんのように心配そうに。
ギュリレーネはそれまでの純情そうな娘のうえに、娼婦のイメージを投影して艶然と笑いかけた。
「あんたの良い人にユリの花束でもプレゼントしに行きましょうか?」
船長は生唾を飲み込んでのけぞった。
「わあお、こいつぁたまげた。俺のつつましやかな家庭をそっとしといてもらおうかな」
そしてまた爆笑した。
ラブドエリスとギュリレーネは、聖火香が住むロスグラードの寺を目指していた。神と知恵比べをしても仕方のないことだ。正面から彼らは聖火香を目指していた。
船は気持ちのいい風をつかまえて、快調に走っていた。
彼らはビャッコの国からロスグラード市に移動するために海路を選んだ。それらふたつは陸続きではあったが、治安の悪い街道を通るよりも、比較的安全な海路の利用が一般的だった。
連絡船とはいえ、海流に乗り早く移動するために、陸も見えない沖合いを進んで行った。それでも海は透き通って青かった。アリウスの故郷の冷たく暗い海しか知らないギュリレーネにはいつまで見ても飽きない風景だった。
「どうして、俺たちは捕まらないんだ」
唐突にラブドエリスが言った。
「俺達のことなんか本気で捕まえるつもりもないのか? こんなにまっすぐ来てるんだぜ」
「あんたはともかく、雅流様の首はかけがえのないもののはずよ」
「リ・ラヴァーをバラまいたんで満足しちまったのか? だいたいあの娘たちになんの意味があるんだ?」
「あんなって、もう見たの?」
「俺と同じ顔してるんだろ? いくら美人でもデートするわけにもいくまい? 近親相姦ではりつけにされちまうぜ」
「たしかに究極の近親相姦ね。実験してみたら? たぶんためしたことのある人なんていないわよ。博士号も夢じゃないわ」
「だからさ。リ・ラヴァーってなにさ」
「この世の全てのものは姿形が属性を決めるのよ。火山石はぎざぎざしたなりに、水晶はきれいななりに。すみれの花はあざやかななりにね」
「あ? ちょっとまてよ。人を見た目で決めつけちゃいけねぇって、よくばあちゃんが言ってたぜ」
「ばあちゃん?」
「あと、神主さんもよ。俺はいじめっこだったからな」
「それは人間を、でしょう?」
「……そうかな?」
「価値観の軸を定めて、共通のルールがある前提でなら、別の見た目を探ることも意味があるわね」
「前に雅流が言ってたけどよ。虫の眼と人間の眼じゃ見ている光が違うから、花の色も全然違ってるってはなしだったぜ」
くすっとギュリレーネは笑った。
「あたりまえでしょ。あなたは花の蜜を吸う気? レンゲの花のありがたみは蜂と人間じゃ比べものにならないわ」
「よくわからねぇや」
「人からレンゲを見たときと、虫から見たときと、魚性クンフが見たときと、そして汎神族が見たときでは、当然見た目も意味も価値観も全然違うわ」
「ちょっと待った。神様の価値観はともかくクンフどものそれが人間様より優れてるかもしれないってのは納得しかねるな」
「えっ? ときどきあなたの考えてることが理解できないわ。わかってる? 汎神族も私たち銀ログム種も人間の言葉を使っているけど、違う種族だって」
「だからなんだってんだよ」
「視覚に訴える姿形は、意味を伴う記号だということよ。自分が見た目で受ける好き嫌いの直感は、大事にするべきということよ」
そのとき彼らの上にすっと影がさした。
「お話し中、失礼します。よろしいか」
でっぷりと太った男が、彼ら二人分の太陽をさえぎって立っていた。
「ラブドエリス様……ではありませんか?」
「あっ? ……なあに、言ってんだあっ?」
ラブドエリスは逆光の中、男を見上げた。知らない男だった。いや、遠い過去の記憶にかすかにかすめるものがあった。
「だれだ? あんた? ラブドエリスって……」
だれだ、と言おうとする言葉をさえぎって太った男が両手を広げて抱きついてきた。
「ああっ、やはり。そうなのですね。私です。サギマンです。サギマン・ハワイです」
「ーーハワイ……。サギマン……。おおっ、貴様、サギ坊主か!」
バッタのように跳び起きたラブドエリスは、コブラのような早さで両手を男の首に巻き付けた。
「ラ、ラ、ラブド」
饅頭のように太りきった男はじたばたと両手を振り回した。次の瞬間、雇兵風の男たちが四人、ばらばらと回りを取り囲んだ。
「ほう、ぬいぐるみを離せなかったサギ坊主も出世したもんだな」
ラブドエリスはやる気まんまんで男達をねめ回した。
「ま、まちなさい。おまえたち。この御方は我々の命の恩人なのだ。ユーモアがお好きなだけだ」
サギマン・ハワイは、用心棒たちを引かせた。すばやくマストの影に隠れた船長が、ほっ、とため息をついてその場にしゃがみこんだ。
「おい、こら。サギ坊主。顔がユーモアぶっこいてたおまえの親父に乗せられたおかげで、俺はえらい目にあったんだぜ。親父は元気か」
「父は昨年亡くなりました」
「ちっ、そうかい。俺が引導を渡してやるつもりだったのによ」
ギュリレーネが全身のバネを蓄えた姿勢のまま聞いた。
「だれ?」
「俺を聖火香様の寺にけしかけた張本人だった市長のガキだ」
「ラブドエリス様が聖火香様の寺に向かわれたあと、すぐに街の化け物どもは消えました。市民は皆、あなた様の偉業に感謝してあなたさまの帰還を祝う祭の準備を進めたものです。しかしあなた様はお戻りになられなかった」
「おう、死ぬかと思ったぜ」
「父は亡くなるまでひどく後悔していました。そしてあなた様を讃え、功績を後生に伝えるために、街中に銅像を建てたのです」
ギュリレーネが吹き出しそうな顔をラブドエリスに向けた。
「すごい。銅像ですって。あなたの」
「記念写真を撮らなくちゃな」
ラブドエリスは頭に昇った血のやりばをなくしてわなわなと震えた。
「父に替わりまして、あらためてお礼をさせていただきたいと思います。どうか拙家にお立ち寄りくださいませ」
「ハワイ様」
ギュリレーネが小さく手を挙げて言った。
「はい。奥様。なにか」
「……おく……ひとつ伺いたいのですが。なぜ。ラブドエリスの容姿のことをお尋ねにならないのですか? 彼が以前この街を訪ねたのは、もう四十年も前のことのはずですが」
「おおっ、奥様。勇者ラブドエリス様と同行されるほどの御方ともなれば、ひとかどの御人と御見受けいたします。我々凡夫には神と法呪の世界のことわりは測りかねます。神の神秘がラブドエリス様の御身に奇跡を残そうとも、その秘密を理解できるはずもありません。奥様」
「だってよ。奥様」
こんどはラブドエリスがにやにやしながら、ギュリレーネの肩に手を置いた。
「人間の世界のルールは単純でいいわね。しばらくはそういうことにしておいてあげるわ。でも図にのったら承知しないわよ」
ギュリレーネはラブドエリスにだけ聞こえるようにつぶやいた。
「あっ、サギ坊主。彼女はね。まだ婚約者なんだ。式はまだ。部屋は別にしといてね」
「はっ? はあ。なにやらむつかしい御関係のようですな」
「結婚するまではキスもバージンじゃないと、地獄におちるんだとさ」
彼らは港まで迎えに来ていた小麒麟車に乗って、街を見おろす丘のうえの屋敷に入った。
ロスグラードの町並みは四十年前と、あまり変わってはいなかった。古い建造物の保存が、行政により厳しく管理されているのだ。
しかし建物は数をおおいに増やして、海岸線に沿って左右に大きく広がっていた。
海は様々な国からやってきた船の帆と旗がひるがえり、祭のような活況を呈していた。
不思議な形の異国の船、凶悪なへ先を持つ異国の軍艦。極彩色ののぼりとロープ。どれをとっても観光資源になりうるすばらしさだ。
大きく湾曲した内海の奥に位置する港は、一年を通して波もおだやかで風もほどよい。周囲をとりまくゆるやかな山々の上昇気流で天候も申し分ない。
かつてこの港を巡って多くの国が争ったこともよくわかる。そこはまさに天然の良港だった。
ラブドエリスの記憶では緑豊かだった丘の連なりも、かなりの部分が切り開かれて住宅地となっていた。サギマン・ハワイの屋敷は丘の頂上に広い敷地を占めて建っていた。
「あいかわらず景気が良いんだな。おまえんところは」
ラブドエリスが口笛を吹いて言った。
「いっちゃあなんだけど、汎神族の城よりも立派だぜ」
「おお、なんと畏れ多いことを。しょせんは人の住む家。木と石の死骸でございます」
それまでじっと外を見ていたギュリレーネが屋敷の裏手の丘を指して言った。
「サギマン様、あの方々はどうしたことでしょう。戦でも近いのですか?」
丘の上の切り開かれた広場に、大勢の武人たちが集まっていた。ただの軍事訓練というには装備が実戦的だった。
修練用ではない、すぐにでも出撃できそうな本物ばかりを携帯していた。
「なんだ? 海賊の城攻めでもやるのか? 足の短い武器ばかりだな」
ラブドエリスの言葉通り、槍や長剣を持つものは一人もいない。指揮官クラスまで短デュウや長ナイフを携帯していた。臼砲が広場の後ろにずらりと並んでいた。明らかに城攻めの構成である。
「なに、ほんの演習でございます。我々のような貿易都市は自衛が必須でありますゆえ」
サギマンはそのことに触れたくない様子で、視線を反らした。
|