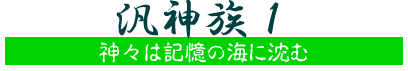|
「おおおぉっ……ぁああああーー」
「お
ギュリレーネがまた吠え出した。誇り高い銀ログム種があさましい獣の素性をさらしたまま、感情をむき出しに吠え立てた。
「保護隊とは記憶溢れを起こした我が種を回収するための者たちではないか。いったい私の知らないうちになにがあったというのだ」
雅流はおろおろと椅子を立った。
「誰か神がこの城に来ているのか。……そうか隷ラディオがいたな」
泣きそうな、笑いだしそうな歪みが表情に浮かんでは消えていった。アリウスは神はこれほど表情豊かなものであることを知らなかった。
「聖火香がいるのだな。彼女になにかあったのをかくまっていたのだな? ラブドエリス。なぜ話してくれなかったのだ」
「…………」
ラブドエリスは黙ったまま、歩み寄る雅流を見上げていた。おぼつかない足どりで彼の前に立った雅流は、白い柱のようにアリウスの視界をもさえぎった。僧衣と同じに青白い二本の腕がラブドエリスの肩にかけられた。
「ラブドエリス? 彼女か? ああ、なんと哀れなことだ。同じ血を持つ彼女が、より古い血の私よりも早く記憶溢れをおこすとは」
雅流の眼はすがりつくような焦りを浮かべていた。乳香に似た甘い神の汗の臭いがアリウスの全身に染み込んだ。
「ラブドエリス。なぜここに人間がいるのだ。私は入城を許した覚えはないぞ」
突然、雅流はアリウスを指さして叫んだ。
「えっ、ぼ、僕は」
アリウスは雅流の言葉の意味を理解しかねて後ずさった。
「アリウス。いけないな。たとえ君が私の村人といえど、ルールは守らなければ」
優しいが、容赦のない口調で雅流は言った。
「ばかやろう。なにすっとぼけてやがんだ!」
ラブドエリス雅流から目を反らしながら叫んだ。
ひゅるり……。
なにかが揺らめいた。
かちん、と音を立てて銀のスプーンが床に落ちた。
……スプーン? ……
緊張した空気の中で小さく響いた音に、アリウス、ラブドエリス、ギュリレーネの意識がシンクロした。
『つかまえた』
小さな声が彼らの耳もとでささやいた。
それはたんぽぽの種のようなクンフだった。 強力な意識侵食力を持つ半妖精植物が部屋中の空気から無数に滲み出してきた。
動物の意識に根をおろし、寄生するヨギモと呼ばれる活動的なクンフである。
複数の動物に対しても、同じものに意識を集中した瞬間を狙って、同時に支配力を行使することができた。
しかし小さく下等なヨギモの動機はあくまで生存のためであるため、第三者が自分の奴隷を作ることには使えない。ヨギモは複雑な命令を理解する知性など持ち合わせていないのだ。神は動物の捕縛に好んで用いた。
雅流たちはそのときの姿勢のまま、上半身をゆらゆらと揺らして立ち尽くした。
いまや船は城のすぐ上空まで近づいた。
隣国にまで聞こえるような華々しいファンファーレが鳴り響き、神が二柱、船の全面の空中に現れた。
一柱はまだ若い、神にしては珍しく屈強な体格の持ち主だった。手には背丈の二倍はある細く刃の長い鎌を持っていた。
連れの一柱は、歳老いた毛のない神だった。両手一杯に木簡を持ち、背にも丸太のような巻物を芝刈りのように負っていた。両神とも神々にとって死を意味する青銅色のローブをまとっていた。彼らの首からはグリュースト閥であることを示す堅い木のメダルが垂れていた。
船のまわりに付き従っていたのは人間の死体だった。
ぐすぐすの腐乱死体が三体、すうっと下降を始めた。それは二人の神を守るよう取り巻き、雅流らのいるサンルームの窓枠に降り立った。
「人間臭い」
若い神が鼻面をしかめて言った。
老神もローブの袖を鼻にあててつぶやいた。
「どうやら雅流は長く人間と暮らしていた様子だな」
「貴奴は亜ドシュケ閥だな。だから貴奴らは堕落するのだ」
若い神は汚らわしそうに言い捨てた。
「雅流は古い血の一族だ。長く記憶溢れの研究を続けている。彼らはそのための実験体なのやもしれぬ」
「人間を実験体にすることは禁じられているのではないか」
「亜ドシュケ閥では禁じられていない」
「なんと野蛮な」
「ただし、この美しいゾンビロウを造り、所有することは禁じられているがな」
哀れむように老神はかぶりを振り、若い東洋系女性のゾンビロウを振り返った。
老いた指先を延ばし、ワックス質の表皮をいとおしそうになであげた。
「彼らはおかしいのではないか? 汎神族としての正常な感覚が、美観が歪められているのでないのか」
「彼ら自身の問題だ。ただしそれに続く者どもがいることこそが、真に憂うべきことだ」
「不快だ。貴奴らが考える人間などを使ったアプローチで、我種の特異な問題を解決できるわけがない。……人間だぞ」
「どの閥も記憶に関する真理にたどりついていない。それゆえにに誰も禁止する強制力を持たない」
「いまいましい。雅流の研究の成果を巡る争いを始めるために、各閥の衆老院がやきもきしている。我々は自身の義務のみ果たして立ち去るべきだ」
若い神は不快感に身を震わせながら言い、汚らわしそうに雅流をにらみつけた。その手前にアリウスが立っていた。
「邪魔な人間風情が!」
鎌を大きく振るうと台尻でアリウスを殴り飛ばした。彼の身体は大きく飛んで壁に叩きつけられた。
美しいカーテンを引きちぎりながら彼は床に沈んだ。
上半身の骨が全て砕け散った。一瞬でアリウスは死んだ。
「……うっ」
アリウスの胸のレンズが青い光を灯した。
急速に身体が復元されていく。原理は過去からの肉体の転送である。
ヨギモの綬縛が行われる以前の肉体が再生された。
「これは……」
意識を取り戻したアリウスは、あやうく飛び起きるのをこらえた。
雅流、ラブドエリス、ギュリレーネが不自然な姿勢のまま立ち尽くしていた。雅流の前に老神が詔を朱書きした木簡を突きつけていた。
「ヒィ、キィィァッーー」
高速言語で神の言葉を唱えた。
雅流の身体が、たちまち淡い光に包まれていった。
「が、雅流様が」
人間にとって神は皆、貴い。逆らうべくもない存在である。しかしわけても知る神が最も貴いことは、自国の王を愛することと変わりない。
「亜ドシュケ閥雅流を記憶溢れにより保護する」
若い神が高い声で宣言した。ふたりの神はトランス状態に陥ったかのように、神々特有の植物性クンフの死臭にも似た、むせかえるような甘くせつない体臭を発散させた。
「イィィーーッン」
老神の声が一段と速くなり、雅流の輪郭が霞始めた。
「あ、うわあああっ」
アリウスはまとわりついたカーテンを両手で鷲掴みにすると、絶叫をあげて走りだした。
両眼を固くつぶり、彼より数十サンツは大きい老神めがけて体当たりををかけた。
「おうっ」
意外にもろく、老神は息のつまるような声をあげて床にころがった。
木簡が騒々しい音を立てて砕け散った。
アリウスはカーテンを幾重にも老神にかぶせた。完全に姿を隠してから、細い筋肉質の腕を叩きつけた。
がすっ、と首のあたりで鈍い音がして老神は動きを止めた。
「ラブドエリス!」
アリウスは跳ね起きると、拳を固めてラブドエリスに殴りかかった。
海で鍛えぬかれたアリウスの腕力はすさまじい。ラブドエリスは鼻骨を砕かれて床につっ伏した。
「おおおっ、人間が!」
外界に意識を結び直した若い神は、アリウスの仕業を見て激怒した。
「信じられん。人間が神に手をあげるか! 雅流の仕業か!」
大鎌が天井近くまで高く振りあげられた。そして次の瞬間にすさまじい速さで振り下ろされた。
「うっ」
アリウスは神の怒りを目の当たりにして避ける気力さえ失った。手をかざすことさえできずに死を身構えた。
ガキンッ、という金属音が響きわたり、刃が空中に止まった。
「き、貴様」
若い神は信じられないものを見たようにうろたえた。
「なめるな、若造」
ラブドエリスだった。
アリウスの頭上わずかに迫った鎌を長剣で受けとめていた。
「神といえど、その身体に肉を持つならば、畏れるものではない! 未熟を知れ、小僧」
「な、なにを」
人間から思いがけない言葉を聞いて若い神は耳を疑った。
自分はなにかとてつもない発見をしたのではないかという、奇妙な興奮すら脳裏をよぎった。
「問答無用!」
ラブドエリスの長剣が赤い糸を引いて半弧を描いた。
そのさきに若い神の首が舞っていた。
ぼん、と鈍い音を立ててそれは床を跳ねた。ラブドエリスは素早い動きで己のマントを剥ぐと、視線をそらしながら首をくるんだ。
ゾンビロウはあらぬ方向に首を振っていたが、誰かの命令を受けたかのように、ラブドエリスに向かって猛烈な速さで歩きだした。
憑かれたような目は白濁し、生物として究極の違和感を醸し出していた。腕を振りあげるでもなく、柱のように迫ってくる。
「うっ、腐れマグロどもめ。まだじじいが生きてるぞ。アリウス。なんとかしろ」
身をかわしながらラブドエリスが叫んだ。
「で、でも」
アリウスは若い神の死に目を奪われて硬直していた。
神の死。それは子供にとっての親の死ほどにも現実感のない、想像さえ及ばない出来事だった。
神の前で死ぬのは人間であって、神の死など非現実的な、本にすら書かれない理屈の上だけのことだった。
「クソ袋め!」
避けきれずにラブドエリスは剣でゾンビロウの一体を切りつけた。
びしゃっ、とぬるい汚物の飛び散る音がした。風船がはじけるように男のゾンビロウは内容物をまき散らした。
「うっ……かあ、たまらねえ」
ラブドエリスは悲鳴をあげて飛沫を避けた。この世のものとは思えない悪臭が押し寄せてきた。残りのゾンビロウは臭気に刺激されたのか、急に動きが速くなってラブドエリスに迫っていった。
「アリウス! 雑巾かけるとか、ぶん殴るとかしやがれ!」
ラブドエリスは悲鳴を上げながらも、ゾンビロウを雅流に近づけないように誘導した。
「わ、わかりました」
アリウスは若い神を見ないようにしながら長い鎌を拾い上げた。
漁師は殺生をなりわいとする。アリウスも鮫や鯨を何匹もしとめてきた。生き物の息の根を止める自信はあった。
老神がくるまったカーテンめがけて鎌をふりかぶった。
ヒュッ、と空気が鳴った。
カーテンの隙間から木簡が飛び出した。それはアリウスの額に吸い込まれるように貼り付いた。
「わっ」
かすかな悲鳴を上げただけでアリウスは凍り付いた。
彼の眼前に老神が、天井から引き上げられたマリオネットのように跳ね起きた。
「歴史に名を残すことになるぞ。人間どもめ」
老神は背負った巻物のひとつを、火筒のようにかつぎ直してアリウスに突きつけた。先端が炎を帯びたように揺らめきだした。いままさに必殺の炎が吹き出そうとした。
「かっ!」
けだものの気合いを込めて、ギュリレーネの鋭い爪先が、アリウスの額から木簡をはじきとばした。とたんに身体の自由が戻った。
振り上げたままの鎌が動きを得て、鈍い光を反射しながら老神の足元に突き立った。
「亜ドシュケの外道どもは神の尊厳を犯すのか!」
狼狽した細い声を上げて老神は窓近くまで後退した。
助けを求めた窓枠が突然に色を変えた。美しい銀細工に覆われていた表面に深紅のひびが走り、大きく開いた窓に鋼鉄の網が降りた。
「うっ、これは」
老神は木簡をアリウスたちの後ろに向けた。腕は恐怖に抗するかのように精いっぱい伸ばされていた。
「雅流!」
ラブドエリスが名を叫んだ。
「逃がすな。ラブドエリス。我が城に不当な進入を行い、あまつさえおぞましきゾンビロウを招き入れたるは、我が種と言えど許しがたい」
「雅流様、御記憶が戻られましたか」
アリウスは走りより足元に身を投げ出した。雅流は以前と変わらずに威厳と自信に満ちて立っていた。
長身によくバランスした美しく白い腕が光の玉を握り天にかざした。
指が微妙な動きをするごとに窓が床が変化した。堅いタイルが生木のように枝を伸ばして、大人の腕ほどもある鋳鉄の棒を形作った。逃れようと右に左に走る老神を取り囲むと、鋳鉄はメッキを始めて金に色を変えていった。
「きぃゆああぁぁぁ」
雅流の唇から高速言語が流れ出た。床の複雑な文様が幾何学的なパターンを明滅させていく。それ自体が呪法起動証となっていた。老神が緑がかった暗いまだらに染まっていった。
殺虫剤をかけられたクンフのようにみるみる動きが遅くなっていった。
「雅流、やめよ。宗派間調停院の命により我らは訪れた。貴公に仇なすものではない」
「無念である。我に猶予無し……ラブドエリス。アリウスに命ずる。我が実験を継げ」
雅流の顔面に不吉な震えが走った。老神が眉をよせて高速言語でなにごとかつぶやき、木簡に手を置いた。
ギュリレーネが走りより、ぐらつく雅流の身体をささえた。
「凍結処置を施す。ギュリレーネ。撃て」
「ま、待て雅流」老神が手を上げた。
「キシャアァ」
みっつの声が重なった。ギュリレーネの口から金属製のビットが飛び出した。黄銅色の光をまき散らしながら、老神の額に突き刺さった。
小さな十字架の形をしたそれは、後端から白い細かな粉末を吹きだした。身悶えして抗う老神の全身が青っぽい白に染められていく。
「が、雅流ぅぅーー」
老神が間延びした悲鳴を上げて動きを止めた。
「ィッチチィィィィィーー」
汗にまみれた雅流が、ギュリレーネにすがるようにして法呪文を唱えた。イントネーションに反応するかのように、老神の頭の上に黄色い輪が浮きあがった。輪は激しく回転しながら形を作り出して行った。
老神の全身がみるみる透き通っていった。色あるものを吸い上げて、複雑な反応が進んでいるかのように、頭上の冠だけが輝きを濃くしていった。
雅流は長身を反らすように棒立ちとなった。
老神は、もう自らの意志で動ける状態ではなかった。それが神のひとつの死の形なのか、奇妙なポーズのままガラス細工の塊となって床に伏した。
「少年よ……アリウスに命ずる。知塩を食せよ」
呆然と立ち尽くすアリウスの前でギュリレーネがすばやく動いた。老神の頭上冠を両手で掴み取り、空中からむしり取った。
その瞬間、冠は光を激しく放ち、ひどく身悶えをした。
「うわっ」
アリウスとラブドエリスは激しい頭痛に襲われて頭を抱えた。同時にテーブルの上の可憐なグラスが音を立てて砕け散った。
人間の耳には聞こえない老神の悲鳴が部屋に充満したのだ。
ギュリレーネは見せかけの姿を苦痛に歪めつつ、足早にしかし慎重に冠をアリウスの元に運んだ。
「血が、雅流様、血が」
アリウスは近づいてくる冠から大量の血が滴り落ちるのを見た。
黄金から白銀に、そしてまた金属色の金色に。目まぐるしく色を変えながら光輝く冠。輪の下から生首を持ち上げたような鮮血が垂れていた。
「か、神の御身を。神の御身を……雅流様。が……」
呼吸すら止まる恐怖に捕らわれたアリウスは、雅流とまともに視線を合わせてしまった。苦しい息の下で雅流は言った。
「アーッリウス。我が実験ーーへの参加を。我が種、人間ーーの言う汎神族は、か弱き生き物なり。人間の協力ーーがなくば、滅びに瀕する。伏して請う。ーー救済の手をためらわずあたえてーーっ、欲しい」
雅流の巨体が床に沈みこんでいった。
力尽きたものと皆が考えた。雅流の記憶溢れが自律神経をも犯し始めたのだと。
しかし駆け寄ろうとしたラブドエリスもギュリレーネも、アリウスも次の瞬間、足を止めた。
両手を揃える不自然な動きで、雅流は両膝を屈したのだ。
ゆっくりと、とてもゆっくりと黒髪が流れ落ちていく。
両手が床につくと同時に美しい顔が伏せられて、頭が両手に触れんばかりに下がっていった。
神秘の瞳はすでに見えない。
「…………」
人が従属生物が、吸いつけられるように、神にあらざる行為に魅入られた。
「伏して請う」
雅流の声がたしかにそう呟いた。
神の神聖をみじんも疑わないアリウスにさえ、その姿の意味するところは理解できた。
「重ねて請う。少年よ」
「ガ……リュウ様」
「我が実験の、意図するところーーを察し、勇気を持っーーて、哀れな、ひ弱なーー我が種の救ーー済に尽力をーー賜り、たい」
神の願いを耳にした人間がいるだろうか。ましてやそれが己に向けられたとき、抗う術を持つ者が存在しえようか。
ラブドエリスは恐怖と畏れに発する言葉もなく、ただ剣を握りしめていた。
「請う。知塩を食せよ」
静かに甘く、雅流は繰り返した。
ギュリレーネが知塩と呼ばれる冠を押し頂き、アリウスの前にかしこまった。薄らいだ人の姿の幻影越しに、ギュリレーネの銀白色の毛皮が鮮血に染まっていくのが見て取れた。
「……はい」
アリウスは応諾した。
彼の姿が知塩とともにかき消えた。
一瞬遅れて、たったいままでアリウスのいた空間が、悲鳴をあげて空気をかき集めた。
アリウスの身体は彼らの眼前から消失した。 ラブドエリスはなにが起こったかを理解しようとする気持ちなど、はなから捨てていた。
次は自分に無理難題がふりかかるだろうことを予感し、かつそれが己の命を差し出すことであろうと応じる決意を固めていた。
神に頭を下げられて人間の我を通すなど、道理が通らない。
「心配、ない。アリウスはーー知覚変換をほどこすために、位相遷移した。……食べやすいように、感覚をすり替えて、いく。彼には、せめて楽しいーーっディナー。心安らかなひとときを、としてーー欲しい」
雅流の身体がわずかに透き通りだした。
ラブドエリスは、記憶溢れは汎神族にとって病であり、長く苦しむと聞いていた。しかしいま雅流の身に起こっている変化は激烈を極めた。
「我が身に記憶溢れが、発現した時期は古い。対記憶溢れの延滞、処置を幾度も施してきたが、限界ーーと見る。我が実験の、さらにひとつを御身に託す」
「どうすればいい。ごたくを並べてないで、はやく言え! 雅流。おい、雅流!」
ラブドエリスは床に這うように身を投げ出した。頬をざらつく床にすりつけて、頭を垂れる雅流の顔を、さらに下から見上げた。
ゆとりと愛に満ちた、いつもの瞳が揺れて笑った。
「愛する人間よ。小さくも賢く、命溢れる頼もしいーーラブドエリスよ。この地の、生きとし生ける、者にして、御身以外に、この願いーーっ、を叶える者なし」
「ばか野郎。かいかぶるのもいい加減にしろ」
苦しい息の下で、神の笑いが漏れた。愉快そうな、悲しそうな。しかし人間の耳にも満足気な色がにじむ豊かな笑いだった。
「……躊躇した身が、愚かしい……」
静かに神の瞳が見開かれた。
「ラブドエリスーーッ、に請う。我が首を断ち、聖火香の元に、運び、奉ぜよ」
ラブドエリスの眼前で眩しい光が炸裂した。
動画芝居のように、切れ切れの鮮やかなシーンが幾つも閃いた。
白いアリウス。
神々の首が並び唄うテーブル。
宙に浮かぶ聖火香の城の最期。
偉大な神の断末魔の叫び。
そして雅流の…………。
それが予知なのか。記憶なのか。あまりに鮮明な光景はなにも語らない。
「せりゃあっ!」
気がついたときには気合いを発していた。
振り切った長刃の後を、断ち切られた髪と首が、床までの僅かな距離で追いすがってきた。
「があああぁぁっっ」
ギュリレーネが妖魔のごとき叫びを上げて走りより、床の青いタイルに触れたか触れないかの首をかき抱いた。小型獣のすばやさで法呪具らしいトグルを切断面に押し当てた。
たちまち雅流の首は、紅い光を発しながら収縮を始めた。人間の拳大に至ったそれは、真球と化していた。
まったく光を反射しない、新月の闇のごとき真球。
「ギュリレーネ。雅流の実験を継ぐ。俺達は聖火香に雅流の首を預けなければならない」
「人間の指示など受けない。私は雅流様の銀ログムよ」
己を取り戻したギュリレーネは、いつもの神仕修道女の姿できっぱりと言った。しかしラブドエリスはそんな返答を無視して続けた。
「隷ラディオはチクリやがった。聖火香の命令なのか、あのド畜生の思い上がりなのかは知らん。ゲスの仕業なぞ気にするにも及ばん。雅流の意志を果たすのが筋だ」
「…………」
ギュリレーネもそのことに異論はない。
「とにかく、ここから脱出することが第一だ。見ろ、ゾンビロウのケツより臭ぇ汎神族の穴ったれどもが、ここを潰しにかかっているぞ」
ラブドエリスが指さした窓の外では、突如水平線の彼方から沸き起こった、どす黒い入道雲が、水面を流れる墨のような速さで城を覆い尽くそうとしていた。たちまち稲光と大粒の冷たい雨が、屋根瓦を叩きだした。
「あらゆる国に扉をつなぐ神の廊下は使えないわ。どうせ手が回っているはず」
ギュリレーネが思案気にささやいた。
「すかったら! まともに俺やお前が考えつくようなことは、全部抑えられてるにきまってら。相手を誰だと思ってるんだ」
ラブドエリスはすばやく辺りを走り回り、武器になりそうなものを回収していった。若い神、老神の持ち物には得体の知れないものが多かった。彼に理解できるものはごく限られていた。
若い神の死によって、左腕から分離した熱線を吐く内装兵器。生前は掌に埋め込まれていたはずだ。
ラブドエリスがそれを手に取ると、生き物のように身震いして、肉に食い込んでいった。少しも痛みは感じない。レンズも時間還流を起こさなかった。体に受け入れられたのだ。そして刀に一種の構造場シールドを施す呪液アンプル二ダーツ。その他用途の不明なもの幾種類かをまとめて背嚢に詰め込んだ。
「ギュリレーネ。汎神族どもを出し抜く冴えたやりかたは一つだけだ」
「ラブドエリス?」
「奴らのタブーを犯すんだ」
息が白く煙った。気温が急速に下がっていた。壁一面にびっしりと霜が付いている。空気中の水蒸気が凍りつき、きらきらとダイヤモンドダストが輝きだした。
「タブー?」
「そうだ。こい」
ラブドエリスは剣を鞘に戻して、老神の持っていた太い巻物を両脇に抱えた。
文字の意味力を使うと言われる法呪文結姿巻である。神の偉大な発明のひとつに数えられていると言う。
以前に雅流がその概念を人間の言葉で説明してくれたことがあるが、万分の一も理解できなかった。ただ野蛮な人間の性か、破壊兵器としての効能と操作だけは理解できた。
「どんな馬鹿でもハンマーでメロンは割れるってな」
ラブドエリスは巻物を十メンツルも床に広げると、固まりかけた若い神の血を、自分の三編みの先に浸して、命令を書き付けた。
『公平にして聡明なる保護隊に付き従う忠実なるすべてのゾンビロウ諸氏は、船の持つ滋養と法呪力のすべてを帯びて、グリュースト閥総本山に降り立つべし』
すばやく巻物をまきなおすと、台尻を窓の外に浮かぶ巨大な船に向けた。
「うおおっ! くそ重てえ。ギュリレーネはやく撃て!」
「ガッ!」
ギュリレーネは反射的に金属ビットを吐きだした。それは艶やかな毛房に覆われた台尻に命中した。
巻物の先端から虹色に渦巻く歌炎がほとばしった。
「ギィシュアアアン…………ン」
神の遠届声のように、高くそして低く、大地を震わす圧倒的な轟音が大気を裂いた。
すべてのゾンビロウの骨の随まで。船の意識階層構造の芯まで命令は突き刺さった。
「応」
言葉にするとそんな反射を船は返した。
意志ももたずに空中にたゆたうゾンビロウどもが、ざわざわと手足を動かし出した。空気が蜜のように粘るがごとく、宙を掻きわけて、船の左脇の一点に集まりだした。不器用なプランクトンが水の粘度に逆らうように、無心な努力はけなげであり滑稽だった。
後を追うように、眼前を圧する船の巨体が傾きだした。植物によく似た根の先、おそらくなにかを噴射するための機関がある下端が上をむき始めた。やがて楼炎を上げる先端は、ゾンビロウが蛾虫のように集まる空中の一点を向いて止まった。
「なにをする気だ」
法呪文結合をしたラブドエリスにも船の意図は計りかねた。高級法呪は因果法までを命令者に求めない。つまり法呪文発行者は手段を提示することなく結果を手にすることができるのだ。
発動された法呪自体が手続きを予定して実現していく。
いまや完全に横だおしとなった船は、たんぽぽの根のようにまっすぐ伸びた下部機関を、松の根のように展開した。
空中に浮かぶゾンビロウどもは広げられた根に覆われて視界から消えた。
次の瞬間、根のすべてを吹き飛ばす大爆発が起こった。オレンジ色の閃光が船を包んだ。
煽りを受けて城の瓦が無数に飛び散った。
「うわ!」
ラブドエリス達は空中に投げ出されて、激しく床に叩きつけられた。
ゾンビロウどもは木っ端みじんに砕け散った。肉汁と汚物の混じりあったスープは、腐臭を放つ雲となって、爆発の猛烈なスピードに乗ったまま飛び続けた。
やがて三時の後、若い神、老神の属するグリュースト閥総本山城に、ゾンビロウだった汚物が降り注いだ。ぬぐっても舐めても消えない不潔な染みが、数えきれないほど広がった。
雅流の城を覆っていた不吉な雲は、現れた時と同じ唐突さで、水平線に飲み込まれていった。
城に巣喰う様々な生き物達がカサコソと一斉に活動を始めた。壊れた天井やひび割れた壁を、自らの分泌するロウや蜜で塞ごうとしているのだ。
ギュリレーネが神仕修道女の姿を取り戻して立ち上がったとき、外はすっかり景色を取り戻していた。この季節特有の暗く湿った、しかし確かな生命力に満ち溢れた海風が吹くいつもの風景だった。
「ラブドエリス?」
彼の姿が消えていた。
いつのまにか窓がひとつ開き、長いカーテンが風で外に吸い出されて、ゆっくりと翻っていた。
老神を閉じ込めた窓の結界は、とうに消滅していた。ギュリレーネは身を乗り出して外を見た。
城の建つ断崖の下、手を伸ばせば届きそうな砂浜に船は落ちていた。早くも海に沈んだ部分は砂に捕らわれだしていた。巨体の半分は跡形もなく消し飛んでいたが、残りの部分でさえ人間の造りうるあらゆる建造物よりもはるかに巨大だった。
「ラブドエリス。なにをしているの?」
強い風のなか、ギュリレーネは叫んだ。ラブドエリスは窓づたいに船の上に降りたっていた。
妙に腰をつき出した不自然な姿のまま、じっと立っていた。
足元から、ちょろちょろとなにかが流れだした。
「汚れを……!」
ギュリレーネは仰天して言葉を飲み込んだ。
彼は神の船の上で立ち小便をしていたのだ。
「ざまあみろってんだ。これでこの船は人間様のもんだぜ」
ラブドエリスは愉快そうに大声で笑った。
汎神族は人間の汚れを受けたものを決して使わない。いかに価値あるものでも、いとも簡単に放棄してしまう。
危機が去ったことを敏感に察した村人達が小さな船を幾隻も連ねてやってきた。しばらくは遠巻きに見ていた彼らも、やがてひとり、またひとりと船に近づき、手を触れたり自分の名前をナイフで刻みつけて、思いおもいに汚れを重ねていった。
もはやいかなる神もこの船を船として使うことはないだろう。そしてこの村の人々は船を資源の山として切り刻み、人間の世界に売っていくことになる。様々な新しい産業が関連して起こされていくことになるだろう。
街が広がり人々が集まり、港が改装される。小さな漁船は隅に追いやられて、大きな商業船が我がもの顔で行き来する。
もう厳しい冬の季節に恐れることもない。冬眠しているような時間の流れは消えて、誰もが豊かに、しかし忙しく生きることになるのだ。
祭で奉じられる神の種類も変わっていくだろう。
|