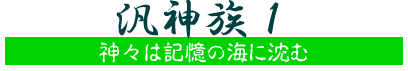|
「雅流の実験は順調のようね。ラブドエリス」
ドスの効いた奇妙な声が言った。
「隷ラディオか。いつ来たんだ」
「あなたに会いに来るのに約束なんていらないでしょ」
人間大の肉食恐竜、に見える物騒な生き物がサンルームから降りてきた。
「モ、モンスター!」
アリウスは悲鳴を上げて、ラブドエリスのうしろに逃げ込んだ。
「だいじょうぶだ。これでもこいつは聖火香様の従属生物なんだ」
ラブドエリスが説明した。
「あらあら、まああっーー。失礼な子ね。この子が今度の実験体なわけ? 頭悪い子のデータも取ろうってのかしらね」
隷ラディオと呼ばれた恐竜は、オーバーな身ぶりでため息をついた。
咽がふいごのように動くたびに、ごろごろと生き物離れした音が響いた。長い二本足がステップを踏むように巨体を運んだ。
「ばかやろう。まともな人間だったら、お前のこと見て考えることはふたつだけだ。殺して皮を売り飛ばしてステーキにしちまうか、干し肉にして面の皮で大根おろすかだ」
派手な光物の下着をつけた小型肉食恐竜、というのがもっとも適切な表現だろう。よく発達した長い腕と、だちょうのようなたくましい脚。筋肉の束がつまった長く美しい尾。そして小さめの頭部には高い知能を感じさせる大きな瞳が輝いていた。
しかし両手両足の爪先と牙は、ペティナイフほどもあり、銀ログム種とはくらべものにならないほどの攻撃力を誇示していた。
「このマッスルな肉体美を理解しないなんて、ラブドエリスのい・け・ず!」
言うが早いか隷ラディオと呼ばれた恐竜はラブドエリスの右腕を噛みちぎった。
三角の頭を軽く人振りしたあとには、ラブドエリスの肘から先がなくなっていた。
「う、腕が、腕が喰われた!」
悲鳴を上げたのはアリウスのほうだった。床にへたりこんで、懸命に後ずさろうともがいた。
「いてえじゃねーか。ハンドバッグ野郎!」
ラブドエリスは悪態をついて、右腕で隷ラディオを殴り飛ばした。
「う、腕、右腕……えっ?」
アリウスはなにが起きたのか理解できないでいた。いま、たしかにラブドエリスの右腕は喰いちぎられたはずだ。
「つまり、こういうことだ。わかったかい? ぼうず」
ラブドエリスは見せつけるように、右腕を握って開いて見せた。
「俺達は死なないんだ」
ようやくアリウスにも彼らの言葉が、頭のなかに染み込んできた。
……不死身……
永遠の時間。王や諸候が望んで、なお人の力ではかなわない奇跡の技。
愛するリューとその時間を過ごせたら。
しかし床に倒れたリューの亡骸は、消えることなく血溜まりに沈んでいた。あの惨劇が夢ではなかったことを確認するだけだった。
リューは死んでしまったのだ。
そして自分は雅流の実験が終わるまで生き続ける。
ラブドエリスのように。
すべては神の御心のままに…………。
「ところで、ラブドエリス。雅流がマロウンに贄の法呪処置を掛けていたわよ。ギュリレーネが止めようとしていたみたいだけど」
隷ラディオがついでのように言った。
「なに? 贄の? まさか。おまえんとこの聖火香様に泣き言言うまでは、処置しないと贄の儀で言ったはずだぞ」
「へえ、そうなの? 贄の儀で?」
「ああ、聖火香様ともそういうことになっているはずだ。儀での宣言は契約と同等だぜ。破れば宗派間調停を受けちまうぜ」
「そんなこと言ったってーー。じゃあ行ってご覧なさいよ。ねえ、それよりもこの娘。食べていい? 天国に送ってあげなきゃ」
そう言って、恐竜は血にまみれたリューの上にかがみこんだ。人差し指の鋭い爪を一杯に伸ばして、ぐっしょりと重く濡れたシャツをつまみあげた。
「還元をなせ。ことわりとならん」
ラブドエリスが儀礼的につぶやいた。しかし視線は宙をさまよっていた。
「私とともに巡らん」
隷ラディオは口早に応えると、リューの腹にかぶりついた。
「あっ……」
アリウスは声にならない悲鳴をあげて目を背けた。神と従者に食人の習慣があることは広く知られていたが、目の当たりにした人間は少ない。ましてや自分の恋人を、である。純朴なアリウスには耐えられない光景だった。
「リュー、幸せになって」
ふりしぼるように言い放った。
そんなアリウスの気持ちを少しも気遣うことなく、ラブドエリスは自分の思考に集中していた。
「まさか……ばかな」
隷ラディオの話しに思い至ることがあったのだ。
「まさか、記憶が……」
ラブドエリスは戦士の敏捷さで走りだした。
「ま、待って、ください」
この場を離れられることなら、なんであれ歓迎だった。
リューは召されたのだ。もう人間が思い悩む対象ではない世界へ。野に果てるではなく、しかるべき神の手配で去ったのだ。
アリウスはラブドエリスの後を追った。
ふたりは不思議な冷たい炎が照明として揺れる廊下を走り抜けていった。至るところに置かれた見たこともない植物の鉢植えが、ぴちぴちと音をたてて小さな種をはじかせていた。
蟻のような赤黒い虫が隊列を組んで、雨のように降り注ぐ黄色い種を運び去っていった。城自体が様々な生き物の巨大コロニーとなっていた。しかし建築物としての痛みはまったく見えない。
駆け抜けた多くの広間、階段そして廊下は植物と虫の甘酸っぱい臭いに満ちていた。それは生命の満ちあふれる壮大な世界だった。
人間の作る家は人間以外のものの生活を許さない。そんな狭量な考えとは違う、なんと慈愛に満ちた空間であることか。
しかし、いまこの城全体に広がる不吉な空気はアリウスにも感じられた。
「ラ、ラブドエリスさん。いったいどこへ」
息を切らしながらアリウスは尋ねた。
「雅流のやろうが、イッちまったかもしれん」
「はい?」
イッちまう? 神が? それがどういうことなのか想像もつかなかった。
「奴のサンルームだ。あいつはそこが生活空間のすべてだ。いそげ」
どれほどを走り、城のどの位置を目指したのか、すでにかいもく見当がつかなかった。
かすかな明かりを頼りに長い階段を登りきったとき、突然まぶしい陽光のなかに出た。
「うっ」
アリウスはまぶしさのあまり背を向けた。
扉もないのに光があふれ出した。通路からいきなり大きな部屋に出たと思ったら、そこは暖かくまぶしい太陽の光が満ちた空間だった。
部屋には奇妙な音が流れていた。高い抑揚にかける悲壮な哭き声であった。人ならぬ生き物の絶望の悲鳴だった。
「が、雅流ーー!」
ラブドエリスの絶叫が、天井の高い部屋に響きわたった。
やっと目が慣れてきたアリウスが見たものは、天井から垂れた無数の白いレースにからめとられて、力なく立ちつくすマロウンだった。
彼女の明るい茶色の豊かな髪が色を変えていた。腰まであった一メンツルもの長い髪が、噴水のように立ち上がっていた。
垂直に逆立つ部分は雪のように真っ白に染まっていた。ほとばしる水のように広がる先端部分だけが、元の茶色を保っていた。
まるで純白の氷が髪の一本一本を下から固めていっているかのようだった。アリウスには不思議な、それでいてひどく意味深いもののように見えた。
意識を失っているのか、彼女はラブドエリスの絶叫にもまったく反応を示さなかった。
マロウンのかたわらで、座面の高い細い椅子に腰掛けて、雅流が茶を飲んでいた。
バルコニーで銀色の獣が哭いていた。
細く悲しい声。種を越えてもなお心をかきむしる絶望を叫んでいた。
ギュリレーネだ。
けっして見せないと言われる、獣の姿をさらしていた。銀色に輝く濡れた毛皮が、太陽の下ではなぜか不自然に生々しかった。
「ラブドエリスか。どうしたのかな? ギュリレーネがおかしいのだ。泣くわけを話してくれないのだよ」
雅流が優しく微笑んで言った。
「お茶をいれてくれなかったのだよ。自分でいれたのなんて何年ぶりだろう」
「雅流、マロウンを。どうして処置しちまったんだ」
ラブドエリスが力なく言った。
「となりの少年はだれだね? ああ、アリウスではないか。人間とは驚いた。君が城の外に友達を持っていたとは知らなかった。友人として招待したのかね?」
慈愛に満ちた、いつもの雅流がそこにいた。
「えっ、ぼ、僕は、あの」
アリウスは状況が掴めずにおずおずと口を開いた。
「マロウンかい? 彼女は贄にすると決めていたはずだよ。ああ、君は人間だったね。わかっているはずなのだが。人間は忘れることができることこそ、最大の美徳だ」
「雅流……いいか、俺はあんたが大っ嫌いだから言ってやるぜ。あんたはマロウンとの約束を忘れちまったんだ」
雅流は不思議そうにラブドエリスの顔を見ていた。そしてマロウンの白い髪に手を延ばすと、堅く固まったそれを数本たおった。
髪はガラスのように簡単に折れて彼の手の中に残った。雅流はそれをハッカ菓子のように、ぽりぽりと食べ始めた。
「やめろ、雅流! 食べるんじゃない」
ラブドエリスは大股で雅流の前まで進むと、結晶化した髪をたたき落とした。それは氷砂糖のように床で粉々に砕け散った。
「……う……む」
わずかに食べたそれだけで、髪は雅流に強烈な影響を与えていた。
「ああ、マロウンの記憶が見える。取るに足りない、平凡な人生の記憶だ。しかし感情のなんと豊かなことか。あの小さな村のいつも繰り返す季節の景色が……すばらしい感受性に彩られて輝いている」
「だめだ。記憶を増やすな。あんたはもう、そんなことのできる身体じゃないんだ」
「なにを言っているんだね? 私は健康だよ。だからこうしてマロウンを贄に選び、記憶結晶を作ることができたのではないか」
自信に満ちた笑顔で雅流は言った。
「ラブドエリスさん、にえって、こんな……」
アリウスは起きていることの意味をやっと理解しつつあった。
「そうだ。彼女の髪が白いのは脳味噌のせいだ。脳の記憶体が処理された髪に吸い上げられているんだ。マロウンは、まだ生きてはいるが、もう死ぬしかない身だ」
「まさか」
「人間の記憶は感情の塊だ。場面や事象は人間の魂しだいで、なんとでも記憶される。主観的だからこそ芸術の名がある。神は人間のケチな知識なぞあてにしていない。魂に彩られた記憶が芸術なんだ。意図的に創ることも、再現することもできない唯一無二の、形にならない宝なんだ」
「じゃあ、じゃあ人間は神様の道楽のために生贄になっていたんですか」
「それは違う。アリウス」
雅流がよく通る声で言った。
「我々はあらゆる生物の記憶を取り込み、感受性を共有することによって、この世界の生き物が望むものになってきたのだ。それが種としての我々の義務だ」
「もういい! 雅流、なにもしゃべるな。考えるんじゃない。それ以上記憶を増やすな」
ラブドエリスが爆発するように大声をあげた。
「マロウンの魂はなんと美しいことか、彼女の心のなかでは世界は叙情詩と絵画の彩りに満たされた長い絵物語のようだよ。長いながいそれは壮大なひとつの国の歴史を見るようだよ」
恍惚とした表情で雅流は言った。手がさらにマロウンの髪に伸びようとした。
「いあぁっ!」
鋭い気合いとともにラブドエリスの刀が宙をないだ。
スパゲッティの束をまき散らしたように、マロウンの髪が全て刈り取られて床に散乱した。ラブドエリスは濡れたように光る刀の切っ先を雅流に突きつけた。
神に武器を突きつけることの非現実性にアリウスは全身を硬直させた。いったい彼はなにをしようとしているのか、自分の意志を神に強要することが人間に可能なことなのか、それはアリウスの想像と理解を越えていた。
「……なんということをするのだ」
雅流の声がうわずった。
「うおおおっ」
ラブドエリスは頭を深く下げた姿勢で刀をかまえ、マロウンめがけて突進した。
「ラブドエリス!」
高く鋭い神の声が空気を切り裂いた。
雅流がかすかに身じろぎした瞬間、薄緑色のガスがラブドエリスの前で炸裂した。
たくましい体が紙細工のように吹き飛ばされて、アリウスの近くの床に叩きつけられた。
しかしラブドエリスはバネ人形のように跳ね起きて、再び雅流に向かいあった。
「ラブドエリス。君といえども許さないよ」
魂まで凍てつかせるような強制力を持つ声で雅流は言った。普通の人間が神からそんな言葉を突きつけられたならば、たちまち心臓が止まってしまうに違いない。
それほど強烈な暗示力を秘めていた。
アリウスはラブドエリスの踵ががくがくと震えていることに気がついた。
神ならぬ生き物ならば一瞬たりと目を開けていられない圧倒的な空間だ。
人間であるラブドエリスが神の正面に立ち、恐怖と闘ってまで雅流に伝えようとしていることがある。ギュリレーネはラブドエリスに肩入れすることを視線で訴えていた。
しかし肝心の雅流は彼らの思惑など意に解するつもりすらないようだった。
それがなにか、アリウスは知りたかった。突き上げる好奇心が神への敬意に勝った。
「雅流……。やめろ」
ラブドエリスの声が変だ。
「ラブドエリス? 泣いているのか」
雅流が意外そうに聞いた。
「ガアアァァッーー!」
そのとき、獣のすさまじい悲鳴が緊張した空気を切り裂いた。
ギュリレーネだ。いままでバルコニーで哭いていたギュリレーネが正気に戻ったように、警戒音を発したのだ。
「雅流様! 教団の船が」
ギュリレーネが娘の姿を取り戻して言った。
「畜生! 隷ラディオがチクりやがった」
ラブドエリスがすばやく窓にかけよった。つられて走りだしたアリウスは、青銅色に鈍く光る重厚な窓枠越しに身を乗り出した。
真っ青な空に土から引き抜いた草のようなものがぽっかりと浮かんでいた。
それは金色に太陽を反射しながら、ぐんぐんと近づいてきた。遥か眼下に広がる村では、人々が異変に気がついて走り回っていた。
海の仕事で鍛えられたアリウスの視力は常人に勝る。ゆっくり大きくなる姿の細部まで、かなり早い段階で見て取った。
それは花壇に咲くセージに良く似ていた。葉がつき、堅い茎がつき、小さいが豊かな花が咲きほこっていた。
巨体の回りの空中には、小さなものが数え切れないほど浮かんでいた。船の力場に乗っているのか同じ速度で飛んでいた。アリウスの目にはそれが人間の姿に見えた。
どんどん大きくなる姿はいつまでも膨張を続けた。遠近感が狂っているのかと錯覚させるほどに巨大化は止まらない。
「ラ、ラブドエリス、あれは……」
アリウスは呆然とつぶやいた。
「教団の保護隊だ。俺も初めて見るぜ」
「どうすればいいんですか。僕たち」
「……知るか。神どもの内輪のことだ。どうこうできるもんじゃない」
「保護隊? なぜだ? ここに? ギュリレーネ?」
雅流が動揺をあらわにして聞いた。
|