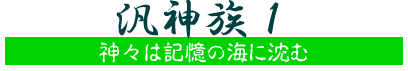|
聖火香(せいかこう)にとって異宗教を志す雅流は愛憎半ばする存在だった。
彼らの先祖は約五千年前の一時期の記憶を共有していた。つまり同族の時期があったのだ。
聖火香の最古記憶は、ほぼこの付近と考えられていた。
神々の記憶は、基本的に親から子へすべてが伝わって行く。
しかし学者や宗教家を多く排出する家系においては、まれに記憶溢れが生じるために、過去の記憶が完全に子孫に伝わらないことがあった。
雅流は祖先の記憶を継ぎ、聖火香は断絶を経験していた。その差は個体の努力で埋められるものではなかった。
それゆえに聖火香は共に学んだ同族出身の雅流と袂をわけたのだった。
彼女は長くロスグラードの女神として人間に畏れられていた。
ロスグラードに城をかまえたのは、もうニ百年も前のことになる。エッジオン閥に属する彼女は、神々にとっての永遠のテーマである「記憶溢れ」克服の研究を志していた。
派閥こそ違え、雅流もまたそのひとりであり、彼らはまったく違うアプローチから研究に取り組んでいた。
雅流は彼の血統から来る、古く膨大な正当古典法呪の記憶を継いでいた。
雅流の記憶にあるもっとも古いものは、汎神族自身がまだ自然を畏れ、神話を持っていたころのことである。
それが正確にいつの時代か、何代前のことなのか。いまだ記憶潜行を行ったことのない雅流には知る由もなかった。また必ずしも重要なことではなかった。
しかし彼自身が過去数万年に及ぶ想像を絶する法呪の伝承をうけていることに違いはなかった。
人間がいかなる才能を有し、修行を積もうとも生まれ落ちたときから雅流が持つ知識の万分の一も得ることはかなうはずもなかった。今を生きる神々においてもおそらく最高位の記憶を持つ彼は、時間循環の法呪を完成させることに研究目標を定めていた。
時間循環の着想自体は決して新しくはない。
法呪で時間をある程度に制御できることは古くから知られていた。それをさらに押し進めて生物の時間をある一瞬で固定し、必要最小限の記憶のみを加算していこうというのだ。
この処置を受けた者は事実上、不死身の身体を持つこととなる。
たとえ身体に傷を負っても、固定された時間から健康な肉体が転送されるために、死ぬことがありえないのだ。
しかし聖火香はそんな彼の方法論に賛同できなかった。彼女の感覚には、あまりにも不自然に思えてならなかった。
記憶溢れを畏れるあまり、自然の時間の流れを逆行させたのでは、種としての彼ら汎神族の未来はありえないと考えていた。汎神族といえども、しょせんは世界に生きる一つの種にすぎない。永遠の時間の流れからとり残されたとき、それは種の滅びと同義に違いないはずだ。
彼女はまったく違うテーマを掲げて記憶溢れに挑戦していた。聖火香の研究方法は過程で様々なモンスターを発生させてしまった。
不可抗力であり、人間の生活に無頓着だった彼女は、城の回りに住む人間にいつしか危害を加えていたことに気がつかなかった。
実験のたびに発生したおびただしい数のモンスターはロスグラードの人々の生活をおびやかすまでになっていた。
そんなある日、彼女の城にひとりの人間が乱入してきた。
「ど畜生! ガス抜き野郎のすね毛のり!」
赤黒いくらげの塊が天井からぼたぼたと落ちた。
若者は両手と背中に持てるだけの飛び道具を抱えて通路を突っ走った。
溶解液を仕込んだ破裂弾を、短デュウから連射しまくった。
「ぎゅふふっーっ」
破裂音とも悲鳴ともつかない音をたてて、くらげのモンスターが弾け飛んだ。
体液と混じった溶解液が激しく降りそそぎ、若者を包む甲鎧の表面処理を焦がした。
「臭え息ぐされの汚れ皿のカビが!」
通路の天井近くに密生していた葡萄のつたが、鞭のようにひゅんひゅん音を立てて跳ね回り始めた。
たわわに実った房が、パイ投げのように顔面を狙って飛んでくる。
はじけた濃い紫色のジュースで視界を奪われた。しかし少しも速度を落とすことなく通路を駆け抜けた。
口に飛び込んだ粒を咬みつぶした。すると実が激しく身悶えをした。
「げげぇ、ワインのばい菌どもにかけて。酒樽のアク抜きみてぇな味じゃねーか。腹ん中でブランデーになりやがれ!」
四十年前のラブドエリスだった。
修験武者を気どっていた彼は、ロスグラードの災厄と呼ばれた混乱の時期に、たまたま街を通りかかってしまった。
ロスグラード市長の甘言と、膨大な報償と街を愛する花窓の女性達の幾夜の説得で、ラブドエリスは後戻りできない羽目に陥った。
気前の良いロスグラード当局は、戦争中のアンファス国に輸送すべき、最新式の射出武器を一小隊分も拠出してくれた。
しかも本来ならば法呪戦専心兵にしか与えられない純白の高張力焼結甲鎧まで仕立ててくれた。兜には極楽雀の羽飾り付きの本格仕様である。
純真な子供達が小学校の図画工作の時間に画いてくれた「勇者様」の絵と、聖歌隊のご婦人たちのかなきり声に送り出されて、彼はいまここにいた。
「神様のスカッたらぁ! ここじゃ客にデザートしか出さんのか。尻っぺたハムエッグでアイロンしちまうぞ! とっとと顔見せやがれ!」
モンスターといえども、それらは戦闘用に造られたわけではない。数ばかりで、ちっとも強くはなかった。
すっかり調子に乗った彼は、おもしろいように倒せるモンスターどもを叩きつぶしながら、古く巨大な木造りの通路を走り抜けた。
聖火香の城は、青みがかった自然石で組まれていた。いかにも神の好みそうな、複雑な曲面を組み合わせた肉厚な造りである。しかし内部はすべて木で造り込まれていた。堅く重い不思議な木は、長い年月を経ているように見えたが、すがすがしい森林の香りを漂わせていた。
汎神族の建造物は、生きた木と植物を構造材として作られていた。それは彼ら美意識の産物だった。
神々は圧倒的な技術力、知識をなぜか通常の生活に生かそうとはしなかった。
移動手段は通路と階段であり、照明も発光生物の水槽を天井近くに吊るす人間の田舎なみの設備であった。それゆえに城の構造は単純だった。また何者も神の城を犯すとは考えないためか、防犯設備と呼べるものもなかった。
ラブドエリスは拍子抜けするほどのあっけなさで、聖火香の寝室までたどりついてしまった。
そのとき聖火香はたまたま着替えの最中だった。
「ぜいぜいっ」
神様の下着姿を見た人間の数は知られていない。しかし彼はそのひとりとなった。
「あ、あー、ええと、聖火香……様?」
ラブドエリスはどぎまぎとつぶやいた。
頭の中が真っ白になってしまった。知らず知らずに直立不動の姿勢をとっていた。人間が神に抱く理屈抜きの敬意は、傍若無人な彼も例外ではなかった。
ロスグラードの人々が用意した抗議の言葉も、口にすることはできなかった。
「きみは。人間か。なぜ、ここに。いるの?」
聖火香はゆっくりと髪をかきあげた。
深紅の髪に褐色の肌。神々に共通の大きな瞳は瞳孔が見分けられないほど黒かった。均整のとれた筋肉質な身体は、しかし細い骨のせいで少しもたくましくは見えなかった。
美しい女性神。
月並みではあれ、ラブドエリスにはそうとしか表現できなかった。
人間は一生の中で何柱もの神に会うことはない。ましてや顔と姿をじっくり見ることなどできるものではない。
人間にとって神個々人の美しさを比較することは極めて困難であった。神であるだけで人間の価値判断を越える強烈なプレッシャーをふりまいていたからだ。
しどけない寝乱れた姿さえ近づきがたく、畏れ多いものに思えた。
「失礼な。人間ね。あれ、キィィ……シュルルッー、イィーンッ」
神の高速言語がかん高い音となって、ラブドエリスの耳を襲った。それは人間に聞き取れない音を含む暴力的な音だった。
「うっ……つ」
高速言語は、人間を含むすべての生き物に激しい威嚇効果を持っていた。
ラブドエリスは両手の武器を床に投げ出してひれ臥した。
「お、お許しを!」
「マロウン。アクの部屋に。行きなさい」
聖火香が誰かに向かって言った。
マロウン、それは人間風の名前だ。
「はい……」
ベッドから少女の声がした。素肌に冠頭衣だけを着ている。まだ幼いといってよい十数歳程度の人間の少女だった。
……にえか……
ラブドエリスは身動きひとつできない緊張の中でかすかに考えた。
少女の白いちいさな素足が目の前を横切り彼方の扉に消えていった。少女は色とりどりのコードを冠頭衣の裾から引きずっていた。
「名前は。なに」
聖火香は不思議そうに聞いた。
「私の記憶に。初めて現れた。汎神族の寝室を襲った人間よ。おまえの。知能は高そうだ。しかし猛々しいいでたちは。私の城に。につかわしくない」
ラブドエリスは木瘤のように固まったまま息を吸い込んだ。話をできるチャンスは一度だけだ。とてもこの状況に耐えられない。
「お、畏れながら、ロスグラード市民はモンスターに難渋して……」
「わかった」
聖火香は優しい声でラブドエリスの言葉をさえぎった。
「私が。至らなかった。迷惑をかけたようだ」
「……はっ」
聖火香は神の優れた知性ですべてを理解した。
自分の実験の結果が人間に害を及ぼす可能性は十分に心得ていた。単に気に止めていなかっただけのことなのだ。人間が蟻の巣を畑といっしょに耕してしまうように。
「責任を持って。対処しましょう。きみが勇気をもって。伝えに。来たことは。私の記憶するところ。となった」
ほおっ、とラブドエリスはため息をついた。
「しかし、私の。実験を見たことは。許せない。きみを帰せない」
ーー神の怒りに触れた! ーー
ラブドエリスは絶望で目の前が真っ暗になるの感じた。
「きみを処理。することで。記憶に汚点は残したくない。きみのからだは。私の。実験にも。使えない。実験体を必要と。している。尊敬すべき。異教徒・雅流に渡そう」
そして眼前で白い光がひらめいたことまでが記憶のすべてだった。
次に意識を取り戻したとき、彼の肩には時間循環のレンズが光っていた。
|