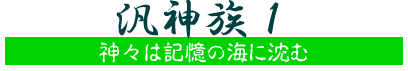|
意識がわずかに戻った。
アリウスはぼやける視線をさまよわせた。
そこは幼いときに見た雅流の城の講堂のようだった。神の見えない乗り物でいつのまにか運ばれたらしい。
神の乗り物はサボテンの樹よりも大きい薄紅色の氷のようなものと言われていた。しかし実際のかたちを、人間はなぜか理解できなかった。乳のプディングのように形が定まって見えないのだ。
講堂は椅子もテーブルもすべて取り除かれて広いひとつの空間となっていた。アリウス達の船なら百槽も入りそうな部屋である。遥かかなたに黒く冷たそうな石造りの壁が見て取れた。天井付近に小さな天窓がいくつもあり、美しい色ガラスがはめ込まれていた。
アリウスは自分が講堂のちょうど中心に立っていることに気がついた。彼の足元から放射線状に、複雑な文字と記号が床一面に書かれていた。ところどころになにかの植物が鉢ごと置かれて、枝には神秘的な光が揺れていた。
「…………うっ」
身体が動かなかった。全身がびっしょりと濡れていた。なにかぬるぬるしたものが頭からつま先までを濡らしていた。視線だけをそっと動かすと、自分のうしろに誰かが立っているのが感じられた。
「…………」
わずかにもれる震えるため息から、それがリューであることがわかった。彼女も身動きできないでいるらしい。ずいぶん長いあいだ立っていたのか、それとも全身に浴びたなにかの薬のためか、身体中が堅く冷たく固まっていた。
彼の目覚めを感じたかのように、ふたりの立つわずかの広さの床が淡く光りだした。
「…………あっ……あ」
神の仕業である。
人間にとって神とは信頼すべきものである。アリウスも生まれたときからそう言われて信じて生きてきた。
それゆえに理解できないこの状況も、畏れはあったが恐怖は感じなかった。
人間にはわからないなにかがあるに違いなかった。仮にも神の仕業が神にとって無益であるわけがない。人間は必ずしも理解する必要はない。
アリウスの緊張は匂いを発していたに違いない。
院の神座敷の暗がりから銀ログム種が姿を現した。
神の造った従属生物である。実態は四つ足の大型いたちだ。
しなやかで長い胴体に力強く短い後ろ足。長めの前足には、くの字に曲がった大人の指ほどもあるルビー色の鋭い爪。
口は短い鼻面をぐるりと回り、耳から耳まで達していた。そこには深海魚にも似た、針のように細く鋭い牙がびっしりと生えていた。
銀ログム種を象徴するもっとも大きな特徴は、水晶球のように美しく大きな眼球にあった。
鼻先から耳の近くまでアーモンド型に裂けた眼架いっぱいに瞳のない眼が光っていた。朱に近く虹色に輝く濡れた目玉は、じゃこう鹿が匂いを発するように、強力な暗示力をまき散らした。
天然の根銀ログム種は天敵に対して、自分が無害であることを信じ込ませるために能力を発達させた。
神によって造られた銀ログム種は、その能力を自然とは比べものにならないほど完壁に使いこなした。
ほとんどの場合、彼らは他の生物を装って現れた。
アリウスに見える彼女の姿は、汎神族に似た神々しく若い女性だった。神仕宗道女のように清楚な白いローブをまとっていた。
美しい雌の銀ログムは、アリウスの前に立つと興味深げに鼻を鳴らした。
雅流の美しい声がアリウスの背後から問いかけた。
「リュー。君は永遠の生命に耐えることができるだろうか」
……永遠の? ……
「我々は君たちの協力を必要としている」
しかし全身を麻痺させたリューはなにも答えない。雅流はさらさらと黒いマントを鳴らしてアリウスの前にやってきた。
「アリウス。君の勇気を私は信じたい。どうかこれを受けてくれたまえ」
そういって雅流は銀小判ほどの楕円形の宝石を取り出した。長い爪の指先で宝石をくるくると回しながら彼の前にかざした。それは中に液体でも封じられているかのように、奇妙な流れる光を帯びていた。
「レンズだ。君の時間を記憶して不死身にする。君の大いなる勇気を少しだけわけてくれたまえ」
雅流はしなやかな指先で摘んだレンズをアリウスの左胸。けんこう骨のすぐ下にあてがった。
「……! ……っ」
アリウスは声にならない悲鳴をあげた。
レンズが彼の身体に食い込んだのがはっきりと感じられたのだ。
痛みはなかった。しかし強烈な違和感が全身を襲った。自分の身体に別の意識を持つなにかが、むりやり進入してきたような嫌悪感だ。
雅流はリューにもレンズを与えた。
「……五フンたった。時間を固定する。覚悟はいいかね?」
覚悟? 人間に神の仕業に対する意志の発現はありえない。受け入れるだけだ。アリウスにもリューにもそれが自然だった。
「ギュリレーネ」
雅流は銀ログムを呼んだ。
「処置をしなさい」
表情も変えずにギュリレーネと呼ばれた銀ログムは近づいてきた。
……処置? ……
アリウスは緊張して、唯一動く目線で美しい娘の動きを追った。
人間の娘の姿を纏った銀ログムは、しなやかな指をゆっくり動かしながらリューに近づいていった。
立ち止まることもなく、彼女は白い腕を横に振り切った。
ごすっ、と聞いたこともない音がした。
なにか重い肉の塊がアリウスの背中にぶつかってきた。それは熱い液体をまき散らしながらアリウスにすがりつくように床に倒れ込んでいった。
一瞬、波打つように震えて静かになった。
……血? ……
頬にべったりとかかった液体が口のはしから流れ込んできた。むせかえる匂いと味が胸いっぱいに広がった。
ギュリレーネがスウッと眼の前に回り込んできた。
舞うような動きにはわずかの躊躇もない。とぎれることのない優雅な足さばきのまま、小さく開けられた口がアリウスの喉もとに近づいてきた。
小さい口は見せかけのものだ。彼女の口が、頬が、耳までがアリウスの喉に食い込んだ。
そして銀ログム種の鋭い歯の感触が皮膚にあたった。あっけないほどやすやすと、牙はアリウスの喉に深く刺さり込んでいった。
「…………!」
しとめられる瞬間の獣のように、アリウスは無抵抗だった。
自分の喉がまくわ瓜ほどの大きさで、アイスクリームのようにえぐり盗られて行くのを感じた。
外気に触れるはずのない組織が、冷たい講堂の空気に触れて湯気を立てた。
重心が狂い、身体が床に倒れ込んで行った。視界が異常に鮮明になるのを感じた。
すごい勢いで床が近づいてきた。床には頭半分を吹き飛ばされたリューが横たわっているのが見えた。
そして、なにもわからなくなった。
戦士の身体と精気を持つ若者が、中二階のロビーから降りてきた。
「悪趣味だぜ。ちっ、悪趣味だ」
人間だ。北方系の色の薄い髪と、濃い灰色の瞳を持つ、それは人間だった。
彼は倒れた二人の近くまで歩いてきた。
ギュリレーネが屈み込み、床に広がった血の海を無心に嘗めていた。
「うまいか? イタチ娘。血なんざな。栄養ねぇぞ」
「ラブドエリス。見ていたのか。感想は?」
雅流が満足気に尋ねた。
「ああっ? なに言ってるんだ? 拍手でもほしいのか」
くすくすと雅流は笑った。汎神族に対してこんな口の利き方をする例をほかに知らない。
彼の継ぐ全ての記憶にない、新たな記憶を得られることがたまらなくうれしかった。
汎神族において、記憶を継ぐ者に重複しない情報を伝えることの困難さは重ねて語られていた。それゆえに神は圧縮できない新規情報の獲得に貪欲であった。過去の誰も知らない記憶が自分の存在に付帯されて引き継がれていく。それによって雅流は不死を得るに等しい身となれた。
「あーあっ、かわいそうに。まだ二人ともガキじゃないか。もっと大人の人生楽しんだ奴にでもすりゃいいのに」
「そういう種類の人間として、先に君を実験体としたのだ。違うかね?」
いとおしそうに雅流はラブドエリスに視線を向けた。ギュリレーネが名残惜しそうに立ち上がった。
「ほら、ラブドエリス。君の仲間の誕生だ」
雅流は床に倒れた二人を指さした。二人の身体が光っていた。いや、光を発しているのは、彼らの胸に埋め込まれたレンズだった。
アリウスのレンズからは青い光が。リューのレンズからは黄色い光が、蛍のような淡さで漏れだしていた。
「……けっ」
ラブドエリスの白いシャツの下からも、緑色の光がにじみ出していた。場所こそ違い左の肩からだったが、まったく同じ種類の光だった。それは二人のレンズに呼応するかのように、静かに、しかし力強く明滅を繰り返した。ラブドエリスはいまいましそうに光を拳で隠そうとした。
アリウスとリューの身体から傷がみるみる消えていった。床に広がるおびただしい血と裂けた服はそのままに、失われた肉が、骨が紙絵芝居の逆回しのように身体に戻っていった。
「……うっ……」
アリウスは急速に戻った意識に気持ちが悪くなり、しばらく眼を開くことができなかった。
「アリウス……」
リューの声が耳もとでした。
「リ、リュー。大丈夫なのか」
アリウスは驚いて身体を起こすとリューの両肩をつかんだ。服はぐっしょりと血で濡れそぼっていた。
「う、うん、あたし……」
さっき彼女は確かに銀ログム種に殺されたはずだった。
アリウス自身も鋭い牙でのどをえぐられたはずだった。そっと手を首に当ててみたが、掠り傷ひとつない。
「雅流様。神の御仕業に感謝いたします」
「雅流様……愚かな私たちにお慈悲を」
アリウスとリューは床に額をすり付けてひれ伏した。その光景を見ていたラブドエリスは、荒っぽい足音をたてて二人の前に立った。
「なにかの罪で自分たちは銀ログム種女郎のギュリレーネに襲われたに違いない。それを雅流が神の奇跡で救ってくれた」
ラブドエリスは乱暴に言い捨てた。
「アリウスとかいったな。ま、おまえ達の想像力じゃ、いいとこそんな程度だろうぜ」
「……はっ?」
アリウスは心の中を見すかされて全身を緊張させた。神の言葉とは思えない無神経さが信じられなかった。
「バカ野郎。こいつらを尊敬するなんてな、娘と見れば借金のカタに売り飛ばす貴族や、人様の家に土足であがり込んで、カメを叩き割って宝を強奪する勇者様を信じるのと同じぐらい、すっとこどっこいなんだぜ」
ラブドエリスはずかずかとアリウスのいる円陣のなかに入り込んでいった。
「うっ」
彼は乱暴にアリウスの前髪をつかむと、自分の顔を突きつけた。
「いいか、聞け。俺もおまえもそこの嬢ちゃんも、みんなこいつらに殺されたんだ」
「な、なにを」
「さっきおまえが見たギュリレーネの殺しは冗談でも事故でも、ましてやおまえらが悪いんでもなんでもない。奴の都合だ」
「あ、あなたは……神様ではないのですか」
「こいつらを信じるな。おまえは実験体にされたんだぞ」
アリウスはうろたえて雅流とラブドエリスに視線をさまよわせた。
「馬鹿やろう。どうして人間ってやつはこんな自分勝手なくそ野郎どもをありがたがるんだ。いいか。おまえらはな」
ラブドエリスはくいっ、と頭をめぐらすと、力一杯頭突きをかました。
「殺されたんだ」
言葉が彼らの意識に染み込むのに、わずかの時間が必要だった。
「い、いやぁーーっ」
意識の表面で、異常な事態を理解したリューは、火を突きつけられた動物のように暴れた。
「止めろ」
雅流がギュリレーネに命令した。
ギュリレーネは後ろから襲うように飛びかかり、リューをはがい締めにした。
「だめだ! 円陣から出るな。死ぬぞ!」
ラブドエリスも戦士の巨体で彼女の前に立ちはだかり肩を鷲掴みにした。
「……キィ……」
信じられない力でリューは二人をふりほどいた。
「ラブドエリス!」
雅流は反射的に名を呼んだ。
リューは糸草のようなしなやかさで、さらに引き留めようとするラブドエリスの腕をすり抜けて走りだした。
「いくな!」
ラブドエリスが矢尻のような鋭さで叫んだ。
瞬間。リューの身体がめくれるようにずれた。それは胸のレンズが放出した膨大な光のせいだったのかもしれない。
「ああっ……」
リューはレンズを押さえて棒立ちになった。
足はすでに円陣から出ていた。
少女の顔が胸の光に照らされて、デスマスクのようにこわばった。小さな指が光を隠そうとあがいたが、太陽のような輝きは体を通り抜けて周囲を照らした。
リューはなにかを感じてアリウスを振り返った。幼い表情が悲しげに歪んだ。
ぐしゃっ、と音が聞こえた気がした。
少女の美しい金髪がはじけるように飛び散り、白い頭蓋骨の破片と眼球のかけらが宙に舞った。
「……リューーッ……」
アリウスは、絶叫で恋人の名を呼んだつもりだった。しかし声は抜けるようにか細く、誰の耳にも届かなかった。
円陣から出た瞬間、水をかけられた熱ガラスのように、リューの頭が割れてあたりに中身をぶちまけた。
さきほどの光景が繰り返された。
「なんということだ。五フンを待たずに円陣を出たのでは、時間固定が完成できない」
雅流は血を避けて、立つ場所を変えた。
「アリウス。君は動いてはいけない。あと二フンだ。それで君は永遠の時間循環を手にすることができる」
「リ、リュー……」
雅流の声も耳に入らず、彼女のもとによろよろと近づこうとするアリウスの前を、頭ひとつ分、身長の勝るラブドエリスがさえぎった。
「いま、動いたら彼女と同じになって死ぬぞ。聞け。おまえは本当はもう死んでいるんだ。あと一フンだ。レンズの力がおまえを生き延びさせてくれる。レンズがおまえの時間を固定するために、あと一瞬が必要なんだ」
「…………リューが」
「彼女はもうだめだ。時間循環に入る前に時間を進めてしまった。レンズはいかれちまってる。二度は時間固定ができない。気の毒だがあきらめろ」
……目の前のこの男はなにを言っているんだろう……。
アリウスはショックでまともに考えることができなかった。
「リューが死んでしまったんだ。神様のお考えなんだからしかたない。……贄に召された……。ありがたいことだ」
視点を失った瞳からはらはらと涙がこぼれ落ちた。
「……そう、ありがたいことだ」
少年は自分に言い聞かせようとするかのように言葉を繰り返した。
「やめないか。胸くその悪い」
吐き捨てるようにラブドエリスは言った。
「ラブドエリス」
蜂鳥の羽音のようなビブラートの効いたか細い声が彼を呼んだ。
「雅流様がーー」
ギュリレーネが雅流の腕を支えるようにして立っていた。
巨大な神の体を支えるには彼女の体はかよわすぎた。重心の狂う雅流に翻弄されて上体がふらふらと揺れていた。
「……気分が悪い」
雅流が長い髪を垂らしてうめいた。
「おまえ、喋れるのか。知らなかったぜ」
ラブドエリスは獣を素体にした従属生物にすぎない、と思っていたギュリレーネに話しかけられたことが驚きだった。
「血の見すぎだぜ。天罰があたったんだ。いたち娘、奥の部屋に転がしてきな」
「……む……」
雅流は額に両手を当てて、見当違いな方向によろよろと歩きだした。ギュリレーネはあわてて後を追った。
「ラブドエリス、たすけて」
ギュリレーネは動転した様子でラブドエリスに視線をむけた。
雅流に禁じられていたのか、彼の前で口を開いたことのないギュリレーネが助けを求めていた。
銀ログム種は長命な種である。雅流とは長いはずの彼女がこれほどうろたえるのは、よほど異常なことに違いなかった。
「すぐに行く。サンルームにつれて行け。おい、雅流! しっかりしろ。聞こえているのか?」
しかし彼は答えずにギュリレーネに抱えられるように階段にむかったいった。
「……神も病いをわずらうのですか」
放心したようにアリウスがつぶやいた。だが涙に曇る眼は、床に倒れた冷たいリューから離れていない。
ラブドエリスは問いに答えるかわりにアリウスの手を取って自分の肩に触らせた。そこにはレンズの無機質な感触があった。
「これはーー」
「そう、俺もおまえと同じに奴に実験体にされた口さ」
|