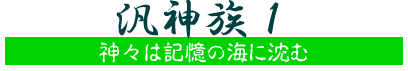|
神々は忘れない
……黒く重いマントを垂れて、涙をながすあなたの姿を見てみたい……
それは少女が見た夢である。
夢の中で雅流(がりゅう)に言った言葉である。
しかし少女は不遜な望みをかなえることはなかった。
雅流が少女を喰ってしまったのだから。
「雅流様、私を食べてください。指も顔も、髪の先まで残らず食べてください。雅流様お願いします。私の味を忘れないで。私がどれほど美味だったかを忘れないで。そしてあなたにつかのまでも満足をあたえたことを」
「娘よ。海の風と魚の奇跡に情けを受けて生かされてきた漁師の娘。豊かな海の命を喰らってきた身体を私に差し出せ。その記憶に私が生かされるときだ」
「あなたの滋養となり、記憶に加えられることを誇りとします。雅流様、あなたの豊かな黒髪の先まで私はまいります。白く美しい指先、貴い緑の瞳、宮殿の鑑賞姫たちも嘆息する淡くなめらかな肌まで私はまいります」
雅流は恋人をかき抱くように、やさしく娘に覆いかぶさった。
「やめろ。雅流。喰うな」
人間の男が雅流に言った。畏れげもなく男は雅流に意見をした。
「邪魔をするな。ラブドエリス。私には必要なことだ」
「必要? それは娯楽だ。あなたの寿命を縮めることだ」
「捨ておいてくれ。ラブドエリス。人間に我が汎神族のなにが理解できよう」
「あなたは死ぬぞ。雅流」
人間の娘は、ラブドエリスと呼ばれた男を恨みがましい眼で見た。
贄に選ばれた自分の名誉を邪魔する人間を。
「雅流様」
少女は雅流の美しい指を両手で握りしめ、自分の喉にあてた。
「明日の朝、眼をさます英気となり、遠い未来まで記憶されることとなり、魂と交わることの喜びを」
それが少女の最期の言葉だった。
少女の記憶のなかで、雅流は少女の夢を知った。
それは彼を感動させるに足りる美しく豊かな光景だった。
「……雅流。また喰ったな……」
ラブドエリスが言った。
雅流(がりゅう)は汎神族の修行僧である。汎神族はいたるところに住まうが、その数はきわめて少ない。
人間の言葉を解し自在に操るが、彼らの言葉は別にある。貧弱な人間の言葉では、彼らの概念を表現し得ない。
汎神族は世界の霊長であり、この世の生き物すべては彼らを生かすために生まれてくる。すべての生き物にとって彼らは神聖であり、彼らの意志は己らの稚拙な思考の及ぶところではないことを知っている。
汎神族の寿命は長く、比ぶる生き物はほかにない。
彼らの姿は人間とよく似ているが明らかに人を越えている。
その証拠に生きとし生けるあらゆる生き物が、汎神族の姿に美を感じとり畏れいる。
小さな漁村があった。
村は古く、呼び名をレンスファといった。
海岸線をなぞるように曲がりくねって走る細く白い十二街道に沿って、長くまばらに石積みの家々が並んでいた。
街道のすぐ裏側には切り立った山々がせまり、人間の住むわずかな地を圧迫していた。
人影は少なく、畑も住民を食わすがせいぜいのちいさなものにすぎない。
住民のほとんどは粗末な船で、冷たい海流が運んでくる海の生き物を採って暮らしていた。
海からの風は冷たく厳しいが、いつも紺碧の空が村の上に広がっていた。太陽ははるかに高いところから、ぬくもりを感じる程度の光を落としていた。
村のはずれに山がそのまま海に没したような岬があった。すそ野はすでに波に洗われて、土を失い岩肌をむき出しにしていた。季節ごとにやってくる高い波が、岩の隙間を割って伸びる松の根を叩いていた。
岬の中ほど、かつては山の頂上であったろう所に雅流の塔、人間は城と呼ぶ大きな建物があった。そこが彼の住処であり、修行と研究の場であった。
それは長身の汎神族の大きさに作られているために、人間のスケールで言うなら、小さな城ともいえる威容を誇っていた。
人間は宗派を持たない。なぜなら人にとって、神は汎神族にほかならないため、宗派という考え方自体が意味を持たないのだ。
現実に自らを越える者がいるのに、なぜそれ以外の超越者を必要としよう。
汎神族は明らかに人間より優れた知性を持ち、人間のあらゆる問題に現実的な、極めて現実的な回答を用意してくれた。
しかし当の汎神族は多くの宗教を持っていた。彼らにとっての神秘を追求し、深く探求するための手段は学問であり、宗教でもあった。
人の世界でいう学閥に近い概念として明日雲閥、エッジオン閥、グリュースト閥、亜ドシュケ閥があった。それを四大閥として、下には多くの宗派を抱えていた。
雅流は亜ドシュケ閥偶枢宗の修行僧として、すでに百八十年の間、この地に暮らしていた。
汎神族の大勢にもれず、雅流も人間の近くに住まうことを好んだ。
神と呼ばれる彼らは人間を愛していた。
わずかの寿命を懸命に生きる人間がいとおしく、大いなる愛を持って接した。
その夜から村は暗いノウムの季節に入った。
これからの一か月間、海からの霧が絶え間なく村を覆い、じめじめとすべてのものを腐らせようとした。
「こりゃあ、ひどいな。波もみえんぞ」
船の陸揚げ作業を始めた漁師たちは、もう何度目かのつぶやきをもらした。
厚く着込んだ海着を無視して染みてくる冷たい湿気は、下着までをぐっしょりと重く濡らしていった。
「アリウス。網は全部取り込んだか」
若頭のマッシュオがうなるように叫んだ。呼ばれた十五、六の少年は、自分の体より大きな網の塊を肩にかつぎあげた。
「あと四つです。若頭」
「おう、いそげよ」
赤銅色に焼けた肩までの髪と褐色の肌。たくましく成長するであろう、長い手足を持った少年は、動きずらい海着を嫌って、腹、腕、すねに荒く黒い布を巻き付けただけの姿で働いていた。
野菜と光が少なくなるこれからの季節をたくましく生き延びるためには、健康で抵抗力のある身体がなによりも必要とされた。
少年は無意識のうちに、自分を鍛える方法を学んでいた。
「女衆がノウム祈願祭の準備をしているぞ。はやく切り上げないと、歳ばっかりくって元気を持て余している爺いどもに酒を呑まれちまうぞ」
マッシュオは流木のように堅くたくましい腕を振り回しながら悪態をついた。漁師たちはわざと下品な笑いをあげて焦る彼をからかった。
「マッシュオの許嫁のスーウェは、じいさん達のマドンナだからな。それを寝とっちまって、恨まれてるんだぜ」
「ばかやろう。雅流様の小指に掛けて、てめぇらとアリウスなみに清い関係だぜ」
「呼びましたか? 若頭。網は終わりました」
絶妙のタイミングでアリウスが答えた。皆は豪快な爆笑で彼をこづきまわした。
仕事を終えて村に帰った一同は、村全体が異様な興奮に包まれていることに気がついた。
祭のゆったりとした活気とは違う、もっと緊迫したなにかだ。
「おい、どうした。なにがあったんだ?」
マッシュオは、近くを通りかかった女をつかまえて聞いた。
「あれ、おかえり。たいへんだよ。雅流様の次の召し者が、贄の者が急に決まってね。祭どころじゃないよ」
男たちは、ざわっと色めき立った。
「だれだ」
「ほれ、リューんところのばあさんのマロウンだってよ」
「マロウン……だって? でもマロウンは、もうばあさんだぞ。若い娘じゃなくてもいいのか」
うめくようにマッシュオは言った。雅流の決めたことは絶対だ。間違いのあろうはずもない。
「んだども、雅流様はもうお城を降りてきてるよ」
なにも言わずにアリウスが走りだした。
「おい、アリウス!」
「お頭。俺、リューのところに行ってきます」
「だめだ、アリウス。雅流様の邪魔になるぞ。アリウス!」
しかし、少年は聞く耳をもたなかった。
「リューとアリウスは」
漁師のひとりがつぶやくように言った。
「添う約束をしているらしいからな……」
村中の人間という人間が通りに出ているようだ。街道は祭のまっさかりのようにごった返していた。見慣れない顔もいる。噂を聞きつけてはやくも近隣の村人まで集まってきたらしい。
マロウンの家のまわりには、締め縄が二重に張り巡らされて結界が創られていた。
「リュー!」
アリウスはそれにかまわず、村人の制止を振り切って家の扉を開けた。
そこには極彩色の布の洪水が舞っていた。
嗅いだこともない香が幾重にも立ちこめ、不思議な色を放つ蝋燭の炎がゆらゆらと妖しく揺れていた。
空気の色が、漂う気配が日常とまったく違った。都市の神官たちが大勢で醸し出す祈りのオーラすら及びもつかない世界がそこにあった。
巨大な神がいた。天井にも頭がとどきそうな姿がゆっくりと彼に振り返った。
少年の視界と魂を圧倒する存在が、長い黒髪を流しながら彼を見た。
高い処から見下ろす黒い瞳が、蝋燭の光を集めて蛍のように輝いた。
「……ガ、雅流様」
膝をつき、ひれ伏したくなる強烈な衝動が身体の底から突き上げた。耐えがたい圧力が全身を襲った。
「アリウス、アリウスーー」
少女がとなりの部屋から出てきた。小走りに彼のもとにくると肩にすがりついた。
「リュー、だいじょうぶ。心配しないで」
アリウスは震える手で、少女の頭をなでた。
十五歳の少女リューは白い祭服に着替えていた。雅流の儀式に立ち会うために、精一杯の装身具で身を飾っていた。
祭でも使わないわずかばかりの宝石を首から下げて、サイズの合わない指輪を両手にはめていた。灰色がかった金髪も、本物の銀粉がまぶされて美しく輝いていた。
アリウスは自分の手につく紅や銀粉にすら気づかないほど興奮していた。
「……少年。アリウス」
雅流が人の言葉で話しかけた。
「はい」
名前を呼ばれて、アリウスは反射的に目を上げてしまった。
「…………!」
そこには命の奥底をゆさぶるほどの威厳を放つ神がいた。
神は人間の女性を抱いていた。
御柱の腰ほどの背丈。貝裏のように白い肌の美しい女性だった。女性はしかしアリウスの知るだれかに似ていた。淡い桃色の長い布にくるまれて立つ姿は……。
「マ、マロウンばあさん」
うろたえてアリウスはつぶやいた。そう、生贄は彼女だと聞いていたはずなのに、あまりの美しさに認識が追いつかなかった。
「少女リュー、少年アリウス。マロウンの反春の儀式は終わった。これからの三ヶ月、マロウンは昔に帰り、贄としての修行を積むこととなる。三月後の朝に招魂しよう」
それだけ言うと雅流は、ふっと表情を緩めた。圧倒される気配がかすかに緩んで、ふだんに畦道ですれ違うやさしい姿に還った。
「……アリウス。リューよ。マロウンをよく助けるように。彼女は胸に秘めた想いを解決していないため、贄となることが叶わない。反春の限界たる三月後までに想いを果たし、悔いなき身に清算するのだ」
はっ、とアリウスは身体を堅くした。
「悔い……を?」
雅流は、感慨深げな笑みを浮かべながら、ゆっくりと両手を広げた。
「私の教たる亜ドシュケ閥。かつて彼女を贄と希望せしエッジオン閥。そして博士聖火香(せいかこう)氏。聖火香氏はまだ幼かったマロウンを愛し、実験の完了後、贄の任を解いた」
「……あれは不名誉な、私にとって残酷な仕打ちでした」
マロウンは若返った美しい娘の声でささやいた。声は涙に震えていた。
「贄の指名を受けながら、それを訳もなく取り消され……。そのあとの私は辛い想いを受けました。村の中でそれは……」
「マロウン。小さく愛しい人間よ。それは違う。おまえはリューを得たではないか」
「…………」
マロウンは涙を浮かべた眼で雅流をそっと見上げた。
雅流はしばらく美しい娘の眼差しを受けとめていた。やがて感極まったように彼女の小さな身体をかき抱き強く揺さぶった。神の長身をかがめるようにマロウンの胸に顔を埋めていった。
「が、雅流様……!」
マロウンはいたたまれずに神の名を呼んだ。白く長い美しい指で雅流の黒い髪を抱き頬を寄せた。
しかし言葉は途中から鋭い悲鳴に変わった。
「……ひっ、あ……ああっ」
彼女の身体をつつむ桃色の布を伝って紅い滴がぽたりと床に落ちた。
あとを追うように真紅の血が、糸のように彼女の指と床を這う布をつないだ。
「が、雅流様」
アリウスはうろたえてリューをきつく抱きしめた。
「愛しい娘よ。汚れなき魂…………!」
雅流は天を振り仰ぎ、その言葉を途中から人間には理解できない汎神族のものとして愛の呪を叫んだ。
口元には、血の糸を引く細い肉が咥えられていた。
……マロウンの薬指だった……
「…………あっ!」
リューは小さく漏れかけた悲鳴をかみ殺してアリウスにしがみついた。アリウスも全身の筋肉を緊張させて、人ならぬ神の仕業に魂を凍らせた。
雅流は真っ白なケープを肩ごしにはね上げて、銀色に輝く胸飾りを引きちぎった。
複雑な星型の鋭い一辺に、咥えた薬指を突き刺すと、両手で強く握りつぶした。金属の縁が雅流の掌を深く傷つけた。痛みを味わうように、なおも力を込めていき、やがて真っ赤な血に染まった手を開いたとき、それはマロウンの指を包み込んだ金属塊と化していた。
「…………」
アリウスとリューは声もなく抱き合って目の前の光景……あるいは儀式を見ていた。神の行為になんの意味があるのかなど、想いもおよばなかった。
マロウンと雅流の鮮血に濡れて、鈍い銀白色に輝く金属塊。細い眉をよせてきつく眼を閉じたまま、雅流はそれをアリウスの眼の前に差し出した。
「……お、御時のかまはし、かしこの……」
アリウスはあわててうろ覚えの謝神詔をつぶやいた。
「アリウス」
雅流がためいきのようにつぶやいた。
「は、はい」
「いま、聖火香(せいかこう)に君のことを告げた。マロウンの想いを果たすことを君に託したいと、彼女も考えている。君はマロウンを助けて聖火香の元に行ってほしい」
「マロウンとふたりで聖火香様をお尋ねすればよろしいのですか」
「三ヶ月のうちに戻るように。反春の限界を越えるとマロウンは、自ら動くことのできない身体となる」
雅流は腰までもある長い黒髪を数本無造作にひきちぎり、魔法のようなすばやさで細い縄をつむいだ。
髪のネックレスを血にまみれた金属塊にまきつけてペンダントにしたてあげると、そっとアリウスの首にかけた。
「役に立つものでもないが、聖火香への挨拶代わりくらいにはなる」
「は、はい……でも」
アリウスは自分がなにをすべきかを考えることができなかった。
マロウンと聖火香を訪ねる。言葉にすればそれだけのことかもしれないが、彼は生まれてこのかた村を出たことすらなかった。商人か兵士でもなければ、自分の村か、せいぜい国のなかの移動しか経験しないのが今の人間だ。
少年の不安は雅流にも理解できた。
「お、俺はものを知らない若造です。ほかの国に行って神様に会ってくるなんてできっこありません」
「そ、そうです。雅流様。家を売ってでもお金をつくります。傭兵をやといます」
リューがアリウスにしがみついて言った。
「…………」
雅流はじっとふたりを見おろしたまま、なんの反応も示さなかった。
「アリウスじゃなきゃだめなんですか? 魚しかとったことのないアリウスじゃなきゃ」
リューは涙で顔中ぐちゃぐちゃにして、ふり絞るような声でつぶやいた。
アリウスは悲しげなマロウンの視線につかまった。雅流の胸元に包まれながら、祈るような瞳で懇願していた。
「アリウスでなければならない」
優しい、しかし断固とした神の声で雅流は告げた。
「では! 私も行きます。私もいっしょに。アリウスひとりじゃ……死んじゃいます」
「リュー、それは……」
アリウスは驚きさえぎろうとした。男手こそほしいが、娘では足手まといになるのが目に見えていた。しかも恋人を自分すら恐れる危険な旅になどさらしたくない。
「よかろう」
意外なことに雅流は了承した。
「アリウス、リュー。私の城に来るがいい。わずかだが助けることができるだろう」
言うと同時に雅流は、ふたりに向けて手をかざした。手首に巻かれたリングから黄色い蜘蛛の糸のようなものが激しく吹きだした。
みるみるうちにふたりは不思議な糸にくるみこまれていった。
「が、雅流様」
わずかにあらがったアリウスの声も一瞬にして糸の渦に覆われた。
黄色い闇がふたりをやさしく包んでいった。
|