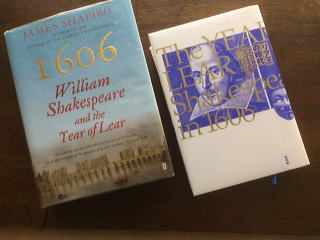1606 William Shakespeare and the Year of Lear
『股倉から見る『ハムレット』―シェイクスピアと日本人』
(京都大学学術出版会)
20年以上、月4回、シェクスピアを読んできた「雑司が谷シェイクスピアの森」が、このコロナ禍のため休会中で、シェイクスピアとすっかりご無沙汰になってしまった。ふとこの本を読んでみようという気になったのは、著者がバーバラ・ピムの訳者でもあったからである。park18.wakwak.com/~aliceintokyo/pym/pym..html
書名からは軽いエッセイと思って手にしたが、立派な学術書である。内容はシェイクスピアの日本での受容を「ハムレット」の翻案という面から捉えたもので、楽しく読めた。シェイクスピアの翻訳史とか上演史とか既にあると思うが、「ハムレット」「翻案」に絞った論考はちょっと珍しいと思う。前半が文学的な受容、後半は演劇的受容を扱う。
トップバッターは漱石である。これは翻案作家ではないが、「猫」や「草枕」などに、ハムレットの影を探る。この章は漱石/シェイクスピア・ファンには物足りないかもしれないが、原作に正面から対峙することなく、「股倉から見」るような、ちょっと変わったアングルからのアプローチをしている翻案作品の導入となっている。
以下、志賀直哉については、『クローディアスの日記』などに見られるグローディアス擁護、アンチ・ハムレットの態度は、漱石に比べ、挑戦的、対峙的であり、この視点はグレッグより5年早いという。
小林秀雄『おふえりや遺文』はオフィーリアに焦点を当て、言葉の問題に取り組む。彼女の饒舌は、「おしゃべり王子」の自己中心性、横暴に対抗する彼女の内なる憤りで、これをフェミスト的翻案の先駆けと捉える。
太宰治『新ハムレット』と大岡昇平『ハムレット日記』とは、対比した形で論じられている。前者は私小説的に自己をハムレットに託して、個人的・家庭的側面の前景化するのに対し、後者は政治劇側面を着眼し、マキャベリとしてのハムレットを描き、政治・社会の前景化しているという。両者の西洋文学への態度の差異にも論じている。
久生十蘭は私には未知な作家であるが、ハムレットに昭和天皇を仮託しているようで、かなり、込み入っている。
後半は、演劇での受容であるが、そのタイプは3つ:第一に正統的シェイクスピア、第二に土着化されたシェイクスピア、第三に両者の折衷―インターカルチュラル・シェイクスピアがあり、第三の事例をいくつか取り上げ、論じている。
仮名垣魯文『葉武列士倭錦絵』(1886年)は、陽の目を見なかったが、その後100年以上を経過した1991年に織田紘二による舞台化されている。仮名垣魯文では西洋文化の日本の伝統との融合化の姿を見るのに対して、織田による書き換えは、シェイクスピアがもはや見知らぬ「侵略者」でなくなった日本演劇界で、正統シェイクスピアも取り入れ、国際演劇マーケットに通用する商品とする動きと捉える。
宗方邦義の『英語能ハムレット』はシェイクスピアの原詩と能の様式美を融合する試みで、1990年代、シェイクスピアは文化的・演劇的伝統の一部として確立しており、より自由で創造的シェイクスピアを上演できるようになっていた。To be or not to be is no longer the question.が示すように、この宗方ハムレットは原作を乗り越えた境地にも足を生み入れている。演劇翻案作品の最後は堤春恵の『仮名手本ハムレット』(1992年初演)で、これは、日本の「ハムレット」の初期受容史そのものを、演劇作品にしたもので、「虚実ない交ぜ」のストーリで、著者が紹介している筋書きだけ読むだけでも面白い。
以上は本書の雑駁な紹介である。著者も断っているように「ハムレット」翻案の網羅的な研究ではないが、逆に作品を絞って丁寧に論じていており、1章1章が小論文として読みごたえがあった。
何より。各作品に対して、シェイクスピ解釈の先進的な側面を捉え、好意的で、温かいまなざしが、読んでいて気持ちがよかった。受容史研究の良いお手本になることだろう。2020・12・24
つづく
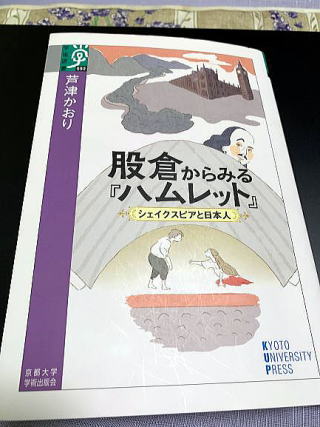
その2 「翻案」について
「股倉からみる『ハムレット』」という書名を著者はどう英訳するのだろうか?
「股倉からみる」は、漱石の「猫」の引用からきている。
「天の橋立を股倉から覗いてみると又格別の趣が出る。セクスピアの千古万古セクスピアではつまらない。偶には股倉からハムレットを見て、君こりや駄目だよ位に云う者がいないと、文界も進歩しないだろう。」
本書は「ハムレット」に限定して、「股倉からみた」いくつかの「翻案」作品を取り上げ、「受容史」的に考察しているのだが、まず、正面からシェイクスピアの原作に対峙し、評価し、余裕も持って股倉から眺めことのできる人がどれだけいるだろうか?その当時、それができるのは、漱石か逍遥くらいではないか?その後、続々と出てきたのだろうか?
私などは、「翻案」とは、原作の知名度、評価、その物語の筋書き、登場人物を借用し、または借景的に利用し、自分の創造力を補い、あるいは、原作と無関係な自分の想いを吐露すること思う。短く言えば、原作の評判に便乗する行為となる。パロディーもその一つ。
「翻案」に価値がないという訳ではない。シェイクスピアも多くの先行作品の翻案なのであるが、先行作品より優れおれば良い。もともとシェイクスピア作品はお芝居の台本で、役者によって上演されて初めて完成する半製品なのである。上演は演出家や役者による翻案ともいえる。黒沢明。蜷川幸雄を頭に描けば良い。
ピーター・ミルワードによると、「『こころ』を読んでいて、とくに強い印象を覚えるのは、それが『ハムレット』と似ていることである。」(『シェイクスピアの日と日本人』〔120頁〕としている。
著者も黒沢明の『悪い奴ほど良く眠る』の『ハムレット』との類似点を見ている。どこまでを「翻案」とするか?換骨脱胎して、原作との関係が分からなくなると、明らかに創作となる。
翻案を多く生み出す作品が偉大な作品ともいえる。
この著作の良いところは、幾つかの「翻案」作品に絞り、原作の持っている潜在的な力を引き出している点に着眼していることである。あくまでも、原作に軸足をおいた考察で、シェイクスピア理解の深化に結びついている。
2020・12・26 つづく
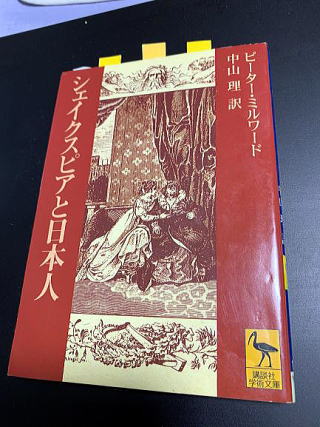
その3 「受容史」について
著者がシェイクスピアの日本受容史に足を踏み入れた経緯が「あとがき」に書かれていて、興味深い。
留学中、英語「ネイティブ」には太刀打ちできないが、志賀直哉の翻案を紹介したとき、評判が良かったという体験があり、「日本に関することを研究すれば、それなりの自分の「領域」「題材」「強み」を安直な思いが脳裏をよぎった。」とある。
原典の十分な理解を行った上行うべき領域といったアドバイスも受けるが、やがて、「この20年ほどの比較的短い間に、シェイクスピアの異文化圏受容は、一大研究分野へとめざましい急発展を遂げている。」
「本書は、シェイクスピアと日本文学・演劇との境界線上に位置し、両者をつなぎ合わるような作品群を扱う点で、英文学や横文字を敬遠しがちな<内向き>志向の日本人に、シェイクスピアが意外と身近なものであることを再認識させ、現在の日本文化・文学が、異文化や外国文学との絶えざる接触・融合・妥協から形成されていることを再認識させ、その結果、読者の方々の意識や関心をすこしでも<外なるもの><異なるもの>へ向けさせることができるかもしれない、そんな願いも抱いている。」ということになる。
英文学専門家のちょっとアンビバレンスな気持ちを感じるが、このことに、私は、何も申し上げることはない。
受容史と言えば、原作と離れることが出来ないが、シェイクスピアを含むんで、さらに高い次元の文芸評論もありうると思う。
以下は、私の好みを書くのであって、本書の評価とは関係はありません。
アリス・ファンの方々とつき合って気付いたことは、原作や著者ルイス・キャロルそのものを追う「求心派」と元の作品からの派生物(翻訳、パロディー、挿絵、映画、グッズなど)を追う「遠心派」とに分かれるが(もちろん両派兼ねる人もいる)これは、多くの、マニアックなファンのいる領域で同じことである。私が余り「受容史」が好きでないのは、私が求心派のせいかもしれない。それは、こんな経験による。ある外国の作品、同好の士を求めて見ると、そこでは、翻訳比較、映像、挿絵、・・・といった派生物(日本での受容形態)のコレクションを楽しむ人たちであった。学問的には受容史の研究ということになるのだろうが、私の求めるものとは異なっていた。原作と無関係とは言わないが、日本的派生物の研究と言ってよい。
シェイクスピアの受容といえば、誰が最初にシェイクスピアの名を知ったのか?誰が最初に読んだのか?訳したのか?最初に上演したのは?・・・そんなことにはじまって、既に長い歴史を持っているので厄介な領域なのである。原典講読史、翻訳史、上演史、翻案史、翻案上演史、作品論・評論史・・・・これを「ハムレット」に絞っても大変なことなる。「ハムレット」の中の“To be, or not to be.”の翻訳史だって書けるかもしれない。書誌の研究も文学研究の一分野であるが・・・
著者はその幾のいくつかを、参考文献に注、参考文献掲げているが、本書では上記に示した「翻案」作品に限定しているのは、賢明な選択であったかもしれない。
あることにコミットし、情報、物を集め、好事家、コレクター、オタクとして楽しむことに、反対するものではない。それ独自の文化を形成するとも思われる。 私が嫌いなのは、そのようなことを受容史の名のもとに派生物を研究し、原作から離れていくことである。
外国語や外国文学の先生にお願いしたいのは、原作を、翻訳や翻案を通じて接するのではなく、直接、その国の言葉で接する能力と歓びを身に着けるように、後進を導いて欲しいことである。日本は、江戸時代までは漢籍教育で中国文化を、明治から戦前までは、旧制高校の語学教育などで西洋文化を直接摂取し、日本文化を豊かにしてきたのである。
「異文化受容」というテーマは、大きいが、その先端を担うのは、やはり、語学や外国文学の先生方だと思う。、頑張って欲しい。
2020・12・31

自然教育園にて:在来種も外来種も環境に合わせて茂り、ひとつの森をなしている。
時々、外来種が古来の森を破壊することもある。
この公園では棕櫚が一つの問題。
1606 William Shakespeare and the Year of Lear
by Lames Shapiro
河合祥一朗訳『リア王の時代 1606年のシェイクスピア』
同書の河合祥一朗訳が出たという関場理一先生の紹介の中で〈小説のように読める珍しい学術書だ。ページを繰るごとに少なくとも一つは大きな発見のある小説だ。〉(『タイムズ文芸付録』、「今年最良の本」)という引用があったので、私は早速、原書を取り寄せ、半ばまで読み進んだところです。
本書は、1600年初頭の エリザベス一世からジェイムス一世への交代の時期の、ペストの猛威、王のブリテン統合の意図など、社会状勢をリアルに点描しながら、『リア王』の先行作品から、シェイクスピアがどのように作劇していたことが描かれて行きます。そして、Gunpowder plot(王、議会の火薬による爆破陰謀)が、発覚と、この事件の波及が細部にわたり描き出され、その中で、シェイクスピアもその作品も、巧みに触れて行きます。その時大きな話題となったequivocation(二枚舌)論議の所を今読んでいるところです。私には通俗小説を読むほどやさしくはありませんが、「ページを繰るごとに少なくとも一つの発見がある。」というのは本当です。
数日前、図書館に予約していた、河合祥一朗訳も手にすることが出来ました。よくぞこの大著を翻訳されたものだと思いましたが、さらに原書にない、解説や、家系図6種、70頁強の訳注(原書へのAlexander Waughなどによる攻撃本などを引きながらの注なので、より深い理解へと導きます)参考文献も索引も立派で、特に索引は人物事典ともなるので便利です。暫くは、この訳書を脇において読み進めます。