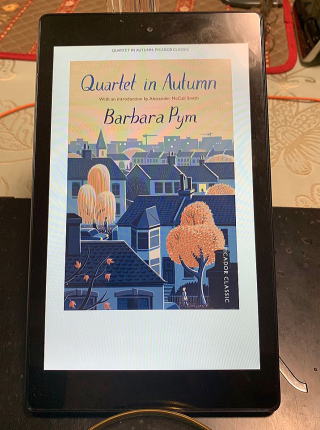Barbara Pym
Excellent Women by Barbara Pym
読書好きのEさんからのメールに「バーバラ・ピム『よくできた女(ひと)』は 何度読んで、もどこから読んでも面白く、20世紀のオ-スティンと言われているそうです。・・・・・ 時々読んで楽しんでいます。芦津かおりという人の翻訳で読んでいます。」とあったので、原文を覗いてみたら、いつの間にか物語に引き込まれていた。30過ぎの未婚の女性が主人公で、そのアパートの下の階に、文化人類学者の女性と海軍将校の夫が、引っ越ししてくるところから物語は始まる。トイレが共同で、このアパートが高級なものではない。彼女の通う教会のバザーの準備の様子など、細部を積み積み重ねながら、水が流れるように読ませる文体は大したものである。彼女の巻き込まれる、男女の恋情や破綻など、途中で、つまらないもにに付き合わされている気分になることもあるが、音楽で言えば、バッハの無伴奏チェロ組曲を小さな音で聞いているようであった。
主人公が、食器を洗いながら、ふと「もし、自分が小説を書くとしたら’Stream of consciousness'タイプかな」と思っているのも、おかしい。まさしく、この小説はこの女性の意識の流れそのもので、男女間の細やかな感情表現を追っているうちに、私は女性になってしまった。
彼女の枕元にはクリスチナ・ロセッティの詩集があって、その中に:
Better by far you should
forget and smile,
Than that you should re-
member and be sad...
他にも、13世紀の古詩の引用などのがあって、文学少女には格好の読み物かもしれない。
Wodehouseとは、ある意味で対照的で、こちらは、誇張のない易しい英語で、市井の人々のつつましやかな生活が淡々と描き出されている。翻訳で読んでも原作との乖離はあまりない思う。私はこの作品をベッドのなかでkindleで読み継いだのだが、それにふさわしい作品だった。
私はこの作品を契機に、2つの点で、転換期を迎えた。
-------------

Excellent Women by Barbara Pym (続きーその1)
この作品を読んで、2つの点で、私は転換期を迎えたと書いたが、その一つは、
「私はEnglish humourがわかっていない」という自覚である。私はこれまで、イギリスの文芸を少しは読んできたつもりだが、English
humourを殆ど意識してこなかった。若い頃、翻訳で読んだ、露、仏、独の小説は面白かったが、いつの頃から、英米の文芸に傾斜していったのは、英語に少し馴染んできたことにもよるが、実は、私を惹きつけてきたのは、このEnglish
humourだったのか?!この点、少し前から気づいていたのだが、この作品で顕在化した言ってよい。
多くの日本人はピムのこの作品をユーモア小説だと思うだろうか?
この本の序文をAlexander McCall Smithという人がか書いていて、それは、English humourとAmerican humour の差異から説きはじめ、アメリカのそれは、とんでもないことを当たり前に、イギリスのユーモアは当たり前のことを飛んでもないこと(extrordinary)に変えていく。ジェン・オースティンもそうだが、バーバラ・ピムもこちらに属するという。A.M.Smithがこの小説をhumourの視点で捉えていることは明らかである。
また、たまたま目にした、2009年に英国ガーディアン紙が発表した「英ガーディアン紙が選ぶ必読小説1000冊」
https://www.theguardian.com/…/2…/jan/23/bestbooks-fictionの中で、Pymのこの作品がComedyのいうカテゴリーの中に、Wodehouseの作品と並んで、顔を出していることである。
ああ!私はEnglish humourがわかっていなかった!と悟ったのである。
では、English humourとは、なんだ?
私はスタートラインに立った気分になった。(つづく)
Excellent Women by Barbara Pym (続きーその2)
この作品が私の転換点となったもう一つの事は、これを電子書籍(Kindle)で読んだことである。手元には「紙の本」はない。
私は本を買うのを無上の楽しみとする男である。本は「紙の本」のことだと信じて疑ったことがない。電車の中で、本を広げている人には温かい眼差しを送り、タブレットで何か読んでいる人には冷ややかな視線を投げていた。まさか、自分が、電子書籍を読む時代が来るとは! 若い人は今ごろ何だと言うかもしれない。
これは徐々に始まっていた。Wodehouseを読むときも、「紙の本」以外に、Kindle本も買って、ベッドではもっぱら後者で読んだ。
最大の理由は、辞書機能が付いているので、2,30%早く読めることである。
ベッドの中、電車の中で、辞書を引く煩わしさがほとんどなくなる。わからない言葉をクリックすると、辞書にぶ。
ベッドの中で、電灯を点けずに本が読めるのも有難い。年を取ると、夜中に目が覚める。タブレットで1時間ほど「本」を読むのにちょうどよい。ちょっと秘密めかした感じも楽しい。
考えてみれば、メール、FB、Webなど、多くの情報を、「紙」を介さないで、デジタルで受け取り、また、発信しているのだから、本がデジタル化してネットを介して読めて何の不思議はないのだが、私にやっとその時期が来た感じである。
私は紙の「本」を買って手元に置くことを無上の楽しみとしてきた男である。
その男に、例えが悪いが、本妻以外に愛人が出来た感じなのである。
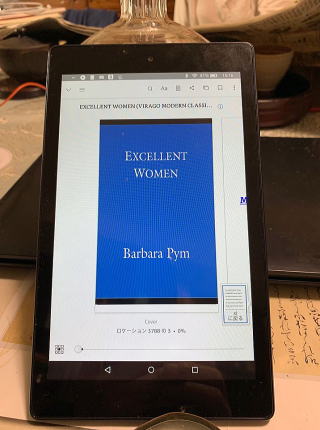
Excellent Women by Barbara Pym (続きーその3)
では、English humourとは、なんだ?!この設問には、英文学の先生たちは苦笑されるかもしれない。「そんなの、FBで扱えないよ!」と。
英文学に造詣があり、物事を明快に説く名人の外山滋比古先生の『ユーモアのレッスン』(中公新書)を覗いてみる。話はイギリス式ユーモアから始まるのだが、ユーモア一般に拡大し、最初の48頁をユーモア論に費やし、その定義に苦戦しておられる。後は、先生の面白いと思われる事例を列挙しておられる。駄洒落あり、機智あり様々なのだが、半分は日本の事例である。最後の「あとがき」に「ユーモアの正体は、少し調べてみるると、古来、難事となっていること分かった。」と述べておられる。
多くのユーモアは言語を介するので、その言葉がわからなければ、笑いは起きない。最近、私の出会った例で言えば、ジーヴス・シリーズの一つ、The Code of the Woosters の冒頭:主人公バーティ―が二日酔い朝、従僕ジーヴスに「お早ようございます」と挨拶され、朝だって?外は暗いではないか、と言うと、ジーブスは「霧が出てます。今は秋―霧と芳醇な稔りの季節(season of mists and mellow fruitfulness)だということを思い出して下さい」と答える。バーティはそれに曖昧に相槌をしているが、これは読者にとってとても面白い。多くの英国人は、Keatsの詩 To Autumnの冒頭の句の引用だと分かるからである。主人公は分かっているかな?というおかしみ。
言葉とか文化の伝統を理解しないと笑えない。ユーモアが言語を異にする国に伝わらない。つまり翻訳では失われてしまう。
私が今回気づいたのは、実はそのような事ではない。
イギリス人の生き方、感じ方、それを見る味方の、本質をなす部分にEnglish humourがあるのではないか、という事に気づいたのである。

Quartet in Autumn by Barbara Pym 1977
『秋の四重奏』
人生の秋を迎えている男女4人の心の四重奏。
エドウィン、ノーマン、レティ、マーシャは、同じ事務所で働いているというだけで、強いつながりはない。各人の頭の禿具合、白髪とその染方などから、話は始まり、一人暮らしで、ごくありふれた男女の生活の細部が、彼らの心理とともに描き出されてゆく。まずレティとマーシャが定年退職する。男たちの定年も近い。
身寄りのない独身の孤独、老後の心配、死の影が忍び寄る。
凡庸な人たちの日常に、付き合うのも、途中で嫌気がさすが、筆先を4人それぞれに巧みの切り替えて、リアルに描いて行くので、結局最後まで読まされる。
未読の方のために、粗筋を紹介することを控えるが、後半、事件らしいことも起こり、盛り上がり、これも、English humourなのだなあ!とちょっと明るい気分にさせられて、終わる。
ブッカー賞候補になっているので、イギリス人は随所にユーモアを感じるのかもしれない。
時代は戦後、会社から昼飯の食券が支給され、テレビが白黒からカラーに変わろうとしていた頃の話である。不思議なことに、彼らがどんな仕事をしているのかの記述はない。女性2人の退職後も補充がないところから、あまり重要な仕事でないのかもしれない。ある意味でこれにもペイソスを感じる。
今回も電子書籍で読んだが、これにはAlexander McCall Smithの素晴らしい序文が付いていた。
邦訳は小野寺健訳でみすず書房から出ている。