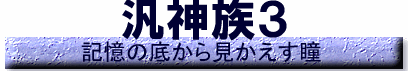|
姫は狂おしいまでの情熱で、ネイミィ・ルオウを求めた。
「ネイミィ・ルオウさま」
リーテンドゥース姫が七歳のときに聞いたネイミィ・ルオウの物語は、血湧き肉踊る英雄の冒険物語だった。
銀の甲冑に身を包み、聖剣ルーコーを振るう勇気ある若き騎士。
清らかな修道士女よりも美しい金髪をなびかせて、魔物の森を紅い瞳で睨みつける。
黒い魔物達は、たちまち烏に姿を変えて空に逃げた。
小さな子供たちを喰らおうとする獣どもは、槍よりも鋭い法呪で千にも貫き倒した。
ネイミィ・ルオウのマントの下は、鉄の城より安全だった。
「姫様。サンダルのままベッドにあがるのはお行儀が悪いですよ」
乳姉妹のメリスが言った。彼女はリーテンドゥース姫よりも一歳だけ年上だが、ずいぶんとしっかりしていた。
リーテンドゥース姫はそれに応えずに、うつぶせになったまま顎の下で手を組んだ。
そして美しくカールのかかった髪の毛先をいじりながら言った。
「ねえ、ねえ。メリス。ネイミィ・ルオウ様は私の髪の色はお好きかしら?」
「はい。姫様の赤く豊かな御髪は、どんなドレスよりもおきれいです」
「ネイミィ・ルオウ様」
十一歳のときに読んだ記事は、神の秘事に触れる男のゴシップだった。
十四歳に聞いた街の娘たちの噂は、彼が美しくたくましい男であることだった。
神々のように甘い香りをまとい、長い髪をなびかせて。
港街にたむろする、熊獣よりも臭い傭兵たちと腕相撲をとってもけっして負けない。
王族の前に立っても堂々と立ち振るまい、従属生物にすら暖かい言葉を忘れないという。
そしてたくさんの若く美しい姫たちの求婚を、優しい微笑みでかわしつづけた。
その理由は、いつか見た幼い少女に恋をしているからだと言う……。
「メリス、どう思う。ネイミィ・ルオウ様は、一人の女の子に恋するなんてことあるかしら? 私はそんなことありえないと思うのよ。だってどんな子がネイミィ・ルオウ様のお心に残れるの? ありえないわ」
メリスは優しく微笑みながら言った。
「きっとネイミィ・ルオウ様が姫様にお会いになられたときの物語を、遠い昔の予言者がつづったのですよ」
「まさか! いやね」
自分は、いつかどこかでネイミィ・ルオウに会っていたのではないか。そんな甘い空想は、姫をとても幸せにした。
「でも……そんなだったらどんなに素敵でしょう」
ネイミィ・ルオウの年齢はわからない。
しかし年頃の娘の多くは、自分の記憶をかき回して、幼いときに出会ったはずの彼を思い出そうとした。
ネイミィ・ルオウに恋い焦がれる娘たちは、みんな彼を覚えていた。
母の乳房に吸いついた幸せな想い出のように、彼の記憶は娘たちに幸福をもたらした。
リーテンドゥース姫はネイミィ・ルオウに恋をした。
それは子どもじみた憧れから、やがてまだ見ぬ恋人への渇望へと変わっていった。もちろん彼女にもそれがおろかな恋心であるほどの分別はあった。
リーテンドゥース姫には許嫁がいた。彼女の国の大財閥の長男だ。
しかし姫は幼い身体に、ひとりでは癒せない渇きを覚える恋をしてしまった。
夜に冷たいバルコニーを踏むたびに、遠く暗い眼下からネイミィ・ルオウが、マントをなびかせて自分をさらいにくる幻を見た。
小さく軽いこの身体を、彼は小兎のように抱きしめて走るのだ。身を切る冷たい夜気の中を甘い風を巻いて。
素足の指先は千切れるほどに冷たいけれど、彼の胸に抱かれた身体は、ベッドの中のように温かい。
そして彼女の知らない立派な部屋で、彼女は毛足の長いカーペットに下ろされる……。
ぱっ、と汗の香りが散ることさえはしたないことに思えて身を堅くした。
ゆっくりと身体を起こしていく彼の長い黒髪を見て、彼女の心臓は破裂しそうだ。
彼の指がゆっくりと唇に触れる。
彼女は肉から魂まで稲妻が走り抜けるのを感じた。
全ての指がこの世のかけらにしがみつこうと爪を立てた。
そして……。
リーテンドゥース姫の想いは、いつもそこでとぎれた。
その先はいつかかならずこの身に受ける現実でなければならない。
「ネイミィ……ルオウ様……」
十六歳になった彼女は、もうメリスに心の内をさらけだすことはなかった。
やがてネイミィ・ルオウが現れた。
彼は若い貴公子の姿で、リーテンドゥース姫の国であるバカリアに現れた。
よく飼い馴らされた黄色い毛皮のボルゾヒ豹にまたがり、供の者も連れずにやってきた。
小股のきりりと切れ上がった美しいボルゾヒ豹。しなやかな背骨は複雑にたわみ、彼の腰を南洋舞踏のようにシェイクした。
ネイミィ・ルオウの黒く長い髪は、ボルゾヒ豹のたてがみであるかのように豪奢になびき、肩のポッドに活けたユリ花は、まぶしい白と赤に輝いた。
金色の花粉がキラキラと光りながら宙を舞い、クンフに化けて飛び立った。
黒い瞳が、道行く市民を優しく見渡した。
人々は飛びのくように道の両側に下がった。
娘達は伝説の男の美しい顔に見とれ、マントもつけずに晒す腰の動きに頬を染めた。
ネイミィ・ルオウはバカリア城の門を叩いた。そして王への謁見と滞在を求めた。
王はネイミィ・ルオウを信じなかったが、一人娘にして王位継承権を持つリーテンドゥース姫は貴公子の言葉を信じた。
城に招き入れられたネイミィ・ルオウは、貴族に準じた歓待を受けた。
彼は南方の珍しい香辛料を五種類も献上した。
はりきった料理部は、図書官の尻を蹴り上げて、秘伝の料理本を探し出した。
その日。城ではささやかだがすばらしいパーティーが遅くまで開かれた。
夜も更けて、ロンド塔の幽霊すら眠る時間。
リーテンドゥース姫はネイミィ・ルオウの寝室を訪ねた。
姫は処女だったが、沐浴で身を清めて夜のドレスをまとった。
「ネイミィ・ルオウ様。名高き法呪の王にして奇跡の実現を身に映す貴き方」
白いドレスの裾を翻して、誰よりも優雅に頭を垂れた。
幼いころからたたき込まれた堅苦しい礼儀作法に、生まれて初めて感謝した。
「ネイミィ・ルオウ様。私を愛してくださいませ。私の肌は玉の肌。髪はこれこのとおり絹の糸」
姫はクリスタルのグラスにワインをそそぎ、震える手で東方の媚薬を混ぜた。
白い素足が絨毯を踏み、ベッドに座る若者の元に進んだ。
十七歳のリーテンドゥース姫は、自分が美しいことを知っていた。しかし男性を惑わす魅力を持っているかは知らなかった。姫は勇気を振り絞って言った。
「ネイミィ・ルオウ様。この杯の輝きも貴方様の瞳の輝きには及びませぬ。ワインの赤も貴方様の情熱には及びませぬ」
黒く長い髪が垂れるネイミィ・ルオウは、顔を伏せたままつぶやいた。
「歳若く汚れを知らぬ姫よ。そなたは子が望みか? ネイミィ・ルオウの名が望みか?」
その姿は、リーテンドゥースが数えきれないほど空想した姿をすべて編み上げたよりも、なお美しかった。彼女はうっとりとつぶやいた。
「ネイミィ・ルオウさま……」
「姫よ。国のために子を望むならば、私はそなたの夫となろう。全能を望むならばネイミィ・ルオウを与えよう」
美しい黒の瞳が姫をみつめた。その色には、なぜかすがるような、救いを請う匂いがあった。
リーテンドゥースは白状してしまった。
「……私には美しいあなた様をくださりませ。私たちの愛しい子供には、あなた様の全能をくださりませ」
ネイミィ・ルオウは天を仰ぎ笑い声をあげた。
「欲深い娘よ。素直な魂よ」
「ネイミィ・ルオウ様。私は重ねてお願いがあります」
「興が乗った。聞こう」
「ネイミィ・ルオウ様の証拠を見とうございます」
「おまえは私がネイミィ・ルオウであると信じて城に留めたのではないのか?」
「おろかな私に真実のなにが見えましょう。私の目には美しいあなた様がネイミィ・ルオウ様に見えるのです」
「賢い姫よ」
「しかし私の処女は一度きりです」
ネイミィ・ルオウは、じっと姫の目を見つめながら言った。
「おまえの純潔には、どれほどの価値があるというのだ」
人の悪意に慣れていない姫は、自信がぐらつく思いをしながら応えた。
「一国にも値すると母から教えられました」
ネイミィ・ルオウはベッドから立ちあがった。さほど長身ではない。リーテンドゥースとかわらない高さの視線が、まっすぐに飛び込んできた。
まるで今から狩りにでも行くかのように、白いブラウスと黒のロングブーツを履いていた。
無防備なナイトドレスのリーテンドゥースとはひどく不釣りあいだった。
ネイミィ・ルオウは、袖もとからタバコのようなものを取りだして火を着けた。
ゆっくりと立ち昇る紫煙は、二重螺旋を描いた。彼は慣れた手つきでタバコを吸った。
小さく開けた彼の唇の奥に、白い煙が渦を巻いた。喉が動き音のない法呪文がつむいだ。
口の中の煙は、積乱雲のように白い稲光を見せた。
やがて煙は唇を離れて上昇を始めた。
「白き菓子、柔らかし、悩まし甘露、征きて化し」
煙を追って法呪文が唱えられた。
無数のクンフが天井の暗闇から湧きだした。
ほとんどが植物性の自ら発光するクンフどもだ。
人の手のひらほどの、ひときわ大きな動物性クンフが混じっていた。小人がヤツデ葉のような羽をつけた姿だ。
それら十匹が、手にした剣のような松葉を振り回しながら、ネイミィ・ルオウに近づいてきた。
大きく口を開けて、お互いを威嚇しあう姿は、ひどく人間くさかった。
ネイミィ・ルオウは、しばらくクンフどもを見ていたが、やがて二匹をひょいと掴み取り、一匹を頬張った。
「きゃ……」
リーテンドゥースは、驚いて声を上げた。彼女のわずかな唇のすきまに、ネイミィ・ルオウはもう一匹を放りこんだ。
吐きだそうとあわてる彼女の舌の上で、クンフは砂糖菓子のようにとろけた。
その様子を見ていた残りのクンフどもは、残念そうに天井の闇に消えていった。
「私の声が聞こえるか?」
ネイミィ・ルオウが聞いた。
「はい」
リーテンドゥースは答えながら、彼の唇が動いていないことに気づいた。
「私の心の声がまっすぐにおまえに届いている。おまえの声も私は聞く」
「…………」
あまりのことにリーテンドゥースの心は真っ白になった。
そして。甘やかな衝動が腹の深いところから突き上げてきた。
なにかを伝えたいという感情が、理性をまたぎ越して現れた。
唇が小さく震えたが、言葉のためではなかった。触れるものを欲したわななきだった。
リーテンドゥースは自らドレスを帯をほどいた。
白いナイトドレスの前が二つに割れた。その下には、ほんのりと朱に染まった素肌がのぞいた。
彼女は左足を前に進めた。ドレスの暗がりから白い脚が現れた。
向かい合って立つネイミィ・ルオウの両足の間に、きれいなつま先を挿しいれた。
止まらない身体は、すがりつくように彼の胸に抱きついた。
柔らかい太股が、彼の足の付け根にぴったりと押し付けられた。
「ネイミィ・ルオウさま」
憑かれたようにつぶやくリーテンドゥースを見て、ネイミィ・ルオウは静かに笑った。
彼は片ピアスを外した。青く輝く美しい宝石を棒状に加工したものだ。
リーテンドゥースの髪を優しくかきあげて耳を探った。鋭い通しの部分で、桜色の耳たぶに、ブツッと穴を開けた。
ピアス穴のない彼女の耳に、青い宝石を縫いとめた。
かすかににじんだ血に、唇を寄せて赤い舌先でなめとった。
「……あっ……」
傷の痛みとキスの驚きで正気が戻った。
リーテンドゥースは息を飲んで身を引いた。自分の淫らな姿に気が動転して言葉がでなかった。
「わ、私はいったい……なにを……」
心臓がドキドキと鳴り、隣の部屋に控えているだろうメリスにまで聞かれそうだった。
「私はなんと……なんてはしたない……」
彼女は、くすくすと笑うネイミィ・ルオウを見て悟った。
「ネ、ネイミィ・ルオウ様。私に媚薬の術を掛けましたね」
「みだらな処女姫を見るのは、奇跡の名にふさわしい」
リーテンドゥースは、カッと頬が染まるのを感じた。
「奇跡の気分はいかに」
「はい……ネイミィ・ルオウ様」
ネイミィ・ルオウは、鮮やかな瞳を姫にむけた。
そして少年が甘いクッキーを口にするように、リーテンドゥースの赤い唇を口に含んだ。
「……ん……」
生まれて初めてのキスに目がくらんだ。
彼は優しくなんども唇をついばんだ。リーテンドゥースは、キスが音をたてることを初めて知った。
暖かい大きな手が肩に触れた。五本の指先が、肌をなぞって乳房の脇に降りてきた。
飛び上がるほどの感触に声がもれた。
くすぐったい。しかしぞくぞくするほどの心地よさ。
肌の産毛は、彼の愛撫をこがれて雛鳥のように立ちあがった。
「……ひっ……」
信じられないほど恥ずかしい声が漏れた。彼の唇が首筋を噛んだのだ。
リーテンドゥースは、きっと子犬のように早い心臓の鼓動を聞かれているに違いないと思った。
……たまらない……。
「おまえの処女をもらおう」
ネイミィ・ルオウは、瞳から溢れる青白い光を隠しもせずに言った。
「……はい。ネイミィ・ルオウさま……」
隣の部屋ではメリスたち侍女が、耳をそばだててドアに張り付いていた。
興奮に紅潮した顔を見合わせながら、リーテンドゥースの悲鳴が上がるのを、今かいまかと待っていた。
|