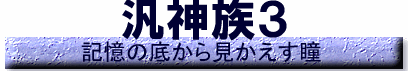|
真っ青な瞳の若神が言った。
「法呪の娘。クァンツァッドよ」
名前を呼ばれた人の娘は、まつげを震わせて顔をあげた。
美しく賢明な瞳は、高ぶる気持ちを押さえられずに涙を流した。
「……羅々紗(ららじゃ)様……」
「私の従属生物にならないか?」
それは問いかけではなかった。ひどく軽い物言いは、人にとって絶対の命令だった。
「神よ。貴き羅々紗(ららじゃ)様。私は御柱のためになにができましょう」
「私はおまえに苦痛を与えよう」
「痛いのは……嫌いです」
甘くとろけるような仕草でクァンツァッドは目を伏せた。
汎神族の身長は人に倍する。二階の高みから見下ろす視線は圧倒的だ。彼女は巨大な力になすすべのない自分に幸福を覚えた。
今この時。
私のために神がいる。神が私を求めている。
「ああ、羅々紗(ららじゃ)様」
なんという晴れがましさであることか。
彼女が立つのは、黒曜石を張り巡らせた広い部屋だった。人間の学校の体育館ほどもありそうだ。
足元を小さな小川が流れていた。いたるところに見たこともない植物が葉を茂らせていた。
無数の花々が咲き乱れて、昆虫型クンフがゆっくりと飛び回っていた。
空気は、香を炊いているでもないのに甘く、霧もないのにしっとりと心地よかった。
しかし床の遥か下から立ちのぼり、たえまなく足裏をくすぐる重い音の振動が、ここは普通の部屋ではないことを物語っていた。
優れた法呪使いであるクァンツァッドは、無意識の内にこの場所が人の出入りできない地下深くであることを感じ取っていた。
クァンツァッドには、視界を圧する羅々紗(ららじゃ)がすべてだった。
羅々紗は、銀色のマントを割って両手を広げた。
舞台の幕が開くように左右に流れていく柔らかなマント。
白銀に輝くたくさんの指輪が火花のようにきらめいた。
神の甘酸っぱい体臭が、香をくゆらせるように広がった。
クァンツァッドは、自分の肩にむかって伸びてきた神の両手を、信じられない気持ちで見つめていた。
羅々紗は、長い黒髪をきつくカールした美しいクァンツァッドを抱き上げた。
肌を覆っていた白いシーツが、絹の音を立てて滑り落ちた。
「羅々紗さま……」
クァンツァッドは、驚きと悦びで身もだえした。
神は白い肌の娘を、軽々と放りあげた。
小さな悲鳴をあげて、彼女の身体は空中でくるくると回った。
「ィィイキイイィィィィィィァァアアアアアアァァンン」
羅々紗の口から高速言語による法呪がほとばしった。
べしゃり、と音を立てて、柔らかい物が羅々紗の足元に落ちた。
クァンツァッドは気づかなかったが、それは彼女の心臓だった。
そしてクァンツァッドは羅々紗の従属生物となった。
容易には死なないように調整された従属生物。
彼女の役割は、人を素体として作られた「法呪の剣」。
クァンツァッドは、長い時間の後に意識を取り戻した。
彼女は全身から湧き起こる得体の知れない痛みに驚いた。
全身の筋肉と関節に針を埋め込まれたような、絶え間ない痛みが襲いかかった。
しかしクァンツァッドは、その痛みに歓喜した。
羅々紗の従属生物となった喜びと誇りの証しと信じた。
彼女は黒曜石の壁に縫いとめられていた。
大の字に伸ばされた四肢には、何本もの細剣でつき立てられていた。
まるで残酷な子供が面白半分に作った虫標本のようだった。
クァンツァッドの白い肌は、痛々しく傷つき何本もの血の筋を残していた。
剣にはわずかな毒が塗られていた。傷はいつまでも癒えることなく、じくじくと苦痛を生みつづけていた。
「あわれなクァンツァッドよ」
さらなる細剣を手にした羅々紗が言った。
「苦痛を受けよ」
顔を上げたクァンツァッドは美しかった。しかし生き物の顔として、ひどく違和感があった。
眼だ。彼女の眼は、眼球の体裁をとっていなかった。
まるで人形のように、頬の延長として眼が描かれていた。
白目と目尻の皮膚が繋がっているのだ。まばたきすらできないに違いない。
しかし視線はあきらかに神の動きを追っていた。
ゴムマスクに美しく描きだされたような顔が聞いた。
「この剣はどなたに……」
神は剣の切っ先をクァンツァッドの肩にあてがい言った。
「この剣は、汎神族グリュースト閥である桜葉(さくらは)に」
「桜葉……さくらはさまに……」
熱いナイフがバターへ滑り込むように、鋭い剣の切っ先はクァンツァッドに刺さりこんだ。
「ん……ああ……」
彼女の唇から切ない声が漏れだした。こらえきれない甘い吐息は、苦痛のためなのか快感のためなのか。
羅々紗の美しい口が開かれた。クァンツァッドに口付けをするかのように顔が近づき、愛のささやきにも似た高速言語が放たれた。
「キィィィアィィィイイイアンンン」
その法呪文は、呪をかけるべき神を特定した。
羅々紗のきらびやかな付け爪に仕込まれた毒のアンプルが割れて、剣の握りから毒液が流れた。紫色に発光する毒は、刃に刻まれた精巧な法呪的有為紋章を意志ある者のように辿った。
紫毒は化学的毒性に加えて、法呪的毒性を帯びて黄金に輝きを変えた。
クァンツァッドの美しい顔は苦痛に歪み、汗に濡れた身体が震えてのけぞった。
指輪と腕輪で飾り立てられた両手の指は、四肢を縛る松の根を情熱的に掻きむしった。
汎神族・桜葉は悪意ある呪が来ることを知っていた。
彼は宗派を一にする神々三柱と共に荒野に立ち、対反射が襲い来るのを待ち構えていた。
激痛は突然に襲い来た。
ビクンと、身体が跳ね上がった。理由もわからずに感じた痛みに、神の健康な肉体が抵抗した。
羅々紗がクァンツァッドに与えた傷と同じ苦痛が桜葉を襲った。
従属生物として調整されたクァンツァッドは、身体をつらぬく剣の痛みを悦びと感じた。
しかし桜葉にとっては、純粋な苦痛以外のなにものでもなかった。
桜葉は感覚を噛みしめるように、固く瞼を閉じ拳を握りしめた。
肩が焼けつくように痛んだ。神経を竹串でえぐられるような激痛が全身に広がった。
主人の苦痛に驚いた彼を護るクンフ達が、わらわらと姿を現して敵を探そうとした。
しかしそのような者はどこにもいなかった。
「羅々紗……哀れな者よ」
桜葉は、こぼれ落ちそうな涙を、歯をくいしばってこらえた。
高度な神経を持つ汎神族は、人よりも痛みに弱い。
ともに荒野に立つ老いた女神が言った。
「桜葉。対反射(ついはんしゃ)を防ぐ法呪は知られていない」
もう一柱の少年神は、遺伝により受け継いだ膨大な記憶を慎重に探りながら言った。
「対反射(ついはんしゃ)の呪は、記憶断絶の彼方から来た科学である」
三柱目の少年柱が残酷な言葉を告げた。
「桜葉様。時間遅延の闇に包まれることを望むか?」
それは究極の対処療法だ。
桜葉の固有時間の流れを遅くすることによって、痛みから逃げようと言うのだ。
時間遅延法呪が発行されている内に、対反射(ついはんしゃ)法呪を取り除ければ良し。さもなければ死にも等しい永遠の闇に捕らえられることとなる。
「…………」
しかし剣と毒の痛みは、繊細な汎神族には耐えがたいものだった。
記憶を遺伝する神々・汎神族には、過去に大きな記憶断絶のあったことが知られていた。
幾柱もの神々が命懸けの記憶潜行により得た事実だった。
記憶潜行とは、汎神族が自身の持つ膨大な記憶に潜り、過去を思い出すことだ。
それは先祖の人生を追体験することに他ならない。すなわち数百年、数千年に及ぶ時間を旅するのだ。
「忘れる」ことがなく、しかも記憶を子孫に「遺伝」する汎神族の記憶量は膨大だ。
記憶潜行を行う者は、自分を強く持ち、先祖の記憶に呑み込まれないことが肝心だ。記憶潜行と現実の区別を失ったとき、術者の意識は記憶の迷宮から二度と帰還することはない。
命がけの研究によって、汎神族の記憶は世界中で、ほぼ4,100年前に大きな断絶を経験していることがわかった。
4,100年前から始まる記憶は古く、非常に不鮮明だった。
4,100年を長いと見るかわずかと見るか。
神々の記憶は苦難の元に始まっていた。
多くの研究者は「大断絶」の原因を探ったが、いまだに成功をみなかった。
「大断絶」にまつわる記憶に共通してあらわれる名前があった。
その名は世界中の神々に記憶されていた。
しかし正体が不確かだった。人間風にも聞こえる名を「ネイミィ・ルオウ」と言った。
多くの研究者は「ネイミィ・ルオウ」を探した。
大断絶の彼方にある法呪は、ほとんどが失われていた。
しかしわずかな法呪の記憶が遺伝されていた。
その中には、現代では理屈因果不明なものがあった。
「対反射(ついはんしゃ)」は、ごく一部の神にのみ知られた強力な法呪だった。発行理屈も解除理屈もわからない。
失われた記憶の法呪「対反射(ついはんしゃ)」は、感覚を他者に転嫁する作用を持つ。
対反射を結んだ個体同士は、一方が痛みや快感を感じた時に、もう一方に同等の感覚を伝える。
それは性愛の法呪として生まれたものだという。対反射を結んだ恋人同士の性交は、この上もなく大きな悦びであり、互いの絆を限りなく深いものにしたと考えられた。
しかし羅々紗は桜葉を殺すために用いようとしていた。
羅々紗の手に再び剣が握られた。銀色の切っ先がクァンツァッドの乳房に押し当てられた。
薄い皮膚が破れて、小さな血の玉が膨らんだ。
「ら、羅々紗様……切ない……です。ああっ……わたしは……」
クァンツァッドは、まるで恋人の愛撫を待ちこがれる娘のように、太股をすり合わせて切っ先を望んだ。
「ィィイイアアァァァ」
「あああああっ!」
羅々紗の法呪文と唱和するように、クァンツァッドの甘い声が流れた。
クァンツァッドの悦びは、対反射のシンクロニティーを増大させた。
残酷な剣は彼女の心臓に食い込んだ。
強化された心臓は止まることを知らない。しかし痛みは生身と変わらない。
「……ぐぐっ……」
はるかな荒野に立つ桜葉は、絶えられない激痛に胸を押さえて膝をついた。
「わ、我を時間に捕らえよ……」
桜葉は、いまにも止まりそうな心臓を抱きしめて言った。
彼の柱の回りに立つ三柱は短い高速言語で会話した。
ちぃちぃと、小鳥のさえずりのように声が飛び交った。
桜葉の心臓は存在しない剣によって貫かれようとしていた。
見えない言葉が空を越えて襲いかかった。
神の唇から発せられた時には、かぼそい音にすぎない法呪文が、物理的な粒となって、桜葉の心臓の細胞を左右に押しのけた。
押しのけられた心筋は、まるで剣に切り裂かれるように、ぱっくりと口を開けた。
三柱の口から甲高い高速言語がほとばしった。
「アアアァァァァァァンンンンンンンンン」
たちまち桜葉の全身は、墨を流したような闇に覆われていった。
闇はすなわち極限まで遅くなった時間の視覚化だ。桜葉は極めて遅い時間の流れに乗った。
さらに大きな虹色の光が空中から巻き起こり、闇の上から桜葉を包み込んだ。
三柱は、時間遅延の闇を、物理障壁で包んだのだ。
桜葉は、荒野の中で貝裏に輝く柱となった。
「あっ……!」
クァンツァッドは悲鳴をあげた。
胸に刺さった剣が黒く固まった。
じわじわと時間遅延の闇がにじみ出てきた。
強制的に中断された対反射の反呪が、クァンツァッドに襲いかかった。
「なんと」
羅々紗は、さも驚いた顔で、しげしげとクァンツァッドを見つめた。
クァンツァッドは、心臓をむしり取られるような激痛に声も出せずに口を開けた。
「羅々紗様! 女を殺す気か!」
人間の戦士がドアを蹴り開けて乱入した。
貴重な植物を踏みつぶし、すばらしい跳躍で羅々紗とクァンツァッドの間に着地した。
「基礎なる相踏み踏みわけて、名層色紙重ねて濡らす。透けし色見て九重八重に。なるを知りぬる層に圧す」
男は、舌を噛みそうな早さで法呪文を唱えた。左手で印を切りながら右手で腰のポーチを探って数枚の板符を取りだした。板符が字面を指の腹でなぞっただけで確認して、クァンツァッドの両肩に突き刺した。
「圧して丸く光る転がり」
たちまち板符が昇華して、クァンツァッドの身体が光に包まれた。
綿菓子に水をかけたように、彼女の輪郭が崩れた。
光は小さくちいさく縮んで、やがてコインほどの磁器のようなものに変わった。
男はコインをつま先が蹴り上げると、両手でパン! と、挟んで取った。
「羅々紗様。呪いの色気娘は失敗したな」
人間の男が言った。
豪奢な神は、唇の両側を上げる笑みで応えた。
「やられた。まさかグリュースト閥の者たちが、あそこまでするとは思わなかったね」
羅々紗はマントを翻して茂みの中を歩き始めた。
「ネイミィ・ルオウ」
神はすでにクァンツァッドのことを忘れたかのように話し始めた。
「ネイミィ・ルオウという名の者がいた その者は不死だったという」
「…………」
人間の男は人肌のぬくもりを持つコインを握りしめた。
男は奇妙な服装をしていた。
黒と赤の薄い河蛇皮のつなぎを来ていた。その上からレンガ色の重そうなコートを着ていた。
首には、猛獣につけるような、分厚い首輪をしていた。首輪には太い鎖が一本ついていた。
奇妙なことに、鎖は下には垂れずに、空中にむかって立っていた。
まるでマフラーが風になびくように、鋼鉄の30センツルの鎖が彼の顔の左でゆらゆらと揺れていた。
羅々紗は、ゆっくりと言葉を続けた。
「すでに永い時を生き、汎神族の生き死にすら見てきたという」
汎神族はネイミィ・ルオウの謎を欲した。
「不死である者が、いかに記憶を処理しているのだろうか。なぜに記憶溢れを起こさないのか。人間のように記憶を忘れるのか?」
「人間がいなければ、汎神族は「忘れる」という概念を持たなかったであろう」
「悪かったな。頭悪くて」
「知りたいと思わぬか」
羅々紗(ららじゃ)は、真っ青な瞳で言った。
「ネイミィ・ルオウは、過去を忘却するのか? 永遠を記憶するのか」
「羅々紗様。永遠の記憶を人の身に蓄えられる道理がない」
「いつからそのような不思議が始まったのか。なぜそのような不思議が成立したのか。現代においてもネイミィ・ルオウは存在するのか?」
汎神族の博士は多く存在するが、ネイミィ・ルオウを解明した柱はいない。
神の英知を持ってしても答えを得られなかった。
羅々紗は新しいおもちゃを見つけた子供のような瞳で言った。
「ラブドエリス」
羅々紗は、真っ青な瞳を見開いて彼を見つめた。
ラブドエリスは、神の圧迫に耐えながら顔をしかめてみせた。不吉なことを言われると感じたのだ。
「言ってきます。ぬか味噌納豆の食い残しスフレに賭けて。次のセリフはお断りしますぜ」
しかし若神は言葉を続けた。
「ラブドエリス。私の従属生物にならないか?」
|