
一九三〇年五月、天人社から刊行された『機械芸術論』(*1)の緒言は、次のように述べる。
機械と芸術との関係を考察することは、現代の芸術を理解する上に、是非とも必要な条件である。一九二九年以来、此の種の考察を試みることが急激に流行しはじめた。
この言葉は、おそらくは『機械芸術論』の編者板垣鷹穂のものであることが推定される。板垣は、当時東京美術学校などで教鞭を執りつつ評論活動を精力的に行っていた、美術史家・美術評論家である。彼はこれに先立つ一九二九年の春から秋にかけて、『思想』『新興芸術』『東京朝日新聞』などに連続して五本の論文を発表し、それをまとめて『機械と芸術との交流』(岩波書店、一九二九年十二月刊)を出版している。この本は「機械文明と現代美術」「機械と芸術との交流」「航空機の形態美に就て」などを目次として掲げ、板垣自身の言葉によれば「「機械文明」と云ふ一個の確定的な媒介物を前提して、現代美術の特質を推定する試み」と規定される。牧野守氏は同書に対し、「このテーマに於ける我が国のパイオニアとしての役割を果たすマニフェスト」と評価を下しているが(*2)、実際これ以降、『都新聞』に機械をテーマとして文学、映画、写真、建築などの諸分野から十本の論文を集めて掲載する企画ものが連載され(*3)、それがまとめられて「新芸術論システム」の一つとして前掲『機械芸術論』が出版されたり、板垣がさらに天人社から『新しき芸術の獲得』『優秀船の芸術社会学的分析』の二冊を出版したりしている。これら一連の動向を考慮に入れれば、冒頭引用した言葉は、その流れの先頭を走っていた板垣自身の示した、自負混じりの現状俯瞰図であったと推定してもよかろう(*4)。
これら流行はいったい何を物語るのか。さらにもう少し、板垣の言葉に耳を傾けよう。
機械的環境は、社会人の環境を新たにし、新しい形態美の存在を教へる。そして同時に、機械は自己の形態を純化しながら、新鮮な糧を芸術に供給する。「機械と芸術との交流」がかくてはじまる。機械技師と芸術家との限界が消失する。
工場は寺院に代り、住宅のエレヴェシヨンは、汽船のブリッヂを模倣し、自動車は工業美術に変り、起重機に記念性が認められて来た。そして、歯車形の室内装飾が流行し、高速度輪転機の諧調が陶酔を誘つた。(*5)
ここで述べられているように、板垣がこの時期の一連の著作の中で語ろうとしているものは、ある新しい美の発見である。これまでは単なる物であり道具にすぎなかった機械を芸術の表象対象として見いだすという発見、それは言い換えればその発見を可能にする新しいパースペクティヴの獲得にほかならない。彼が告げているのは、このような新しい感性の誕生なのだ。
むろんこの感性の変革は板垣個人に限って現れたものでないことは言うまでもない。次に挙げるいくつかの言表の中にも、我々は同様の誇らしげな発見の息づかいを聞き取ることができる。
自動自転車のスナツプ・シヨットは一つの事実として発表された。有機体のスナップ・フォトが、我々の感覚と遠ざかる。機械的建造物の有する新しい魅力は此処に於て胚胎した。我々の見る目が開けたのである。
堀野正雄「機械と写真」(*6)
野の彼方に弧を描く虹の美しさを何人も否まないであらうけれども、又私達は実験室の闇の中に交錯する鋭い光の線条に対して特殊の魅惑を感ぜずにゐられないであらう。そしてそこに新しき詩の形態を感ずるであらう。そこにこの半世紀に於いて見ることの意味が、己自ら何物か他のものに姿を変へつゝあることを知らなければならない。中井正一「機械美の構造」(*7)(斜体は原文傍点)
工場の美、汽船のブリッジの美、歯車の美。自動車は工業美術品とされ、実験室の光は虹と比べられ、高速輪転機のリズムが陶酔を呼び、「機械技師と芸術家との限界が消失する」。あるいはまた、城左門のテクストも、「仏蘭西美術展」を見に行った人間に、窓枠に切り取られた三井銀行の工事現場を見せて、「白状すれば、僕には、ロダンや後期印象派の青白い夢よりも、此の白日下の、生々たる、建築過程の「画」の方が、余程興味深いものに、感ぜられたのでした。」(*8)と告白させる。中井正一の述べる「見ることの意味」の変化は、まさしく同時代の感性の変革を名指しているのだ。
そしてそれら「見ることの意味」の変革のなかから見いだされ始めた「新しき詩の形態」(中井)は、たとえばガスタンクや、鉄橋、車、レコード盤、幾何学模様などの上に見つけられていった。それらの〈機械〉たちは、絵画、写真、詩などジャンルを問わず表象対象として積極的に取り上げられていく。東京ガス千住工場のガスタンクは一九一四年には完成しており、〈物〉としては存在していたわけだが、この時期になるまでそれは芸術家達の視線の対象として浮かび上がってこなかった、と小泉淳一氏は指摘するが(*9)、このことはそこで起こっていたことがまさに文字どおりの「発見」であったことを示している。かつては「美的」ではなかったものが、新たに「美」を持つものとして見つけ出されてゆくのだ。藤牧義夫の『墨田川絵巻No.2 白鬚の巻』(1934)は白鬚橋のたもとのガスタンクから始めて、起重機や鉄橋など〈機械〉たちのひしめく隅田川を河岸沿いに毛筆でスケッチを試みる。長谷川利行は「先夜寺島カエリニ千住タンク地帯ガ気ニ入ッタモノデスカラ、昨日ト今日、油絵ヲ描キニ出カケル所デス」(*10)といって、ガスタンクを油彩で描く[図1]。

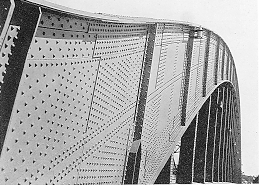 図2 堀野正雄「鉄橋」(『カメラ・眼×鉄・構成』木星社書院、1932年、所収)
図2 堀野正雄「鉄橋」(『カメラ・眼×鉄・構成』木星社書院、1932年、所収)
堀野正雄の写真にもガスタンク・鉄橋・起重機の連作がある[図2]。文学ジャンルでも川路柳虹「起重機」(*11)、島本久恵「春の可動橋」(*12)など同様の傾向を示すテクストには事欠かない。堀野と板垣の共同作業「大東京の性格」(*13)や村野知義監督編集の「首都貫流――墨田川アルバム」(*14)も、写真と詩、あるいはタイポグラフィーによって機械化された東京を描きとろうとしたルポルタージュとして興味深い達成を見せている。
徐々に都市生活のなかに浸透してきた機械が、芸術領域において獲得された新しいパースペクティヴによって、美的表象の対象として浮かび上がってくる。そして一九二九年には、板垣が述べ、彼自身の活動が明かしているように、機械を取り上げ表現し論じることが小さな流行を見せ、「機械主義」という言葉が流通する。そしてまたこの動きは、文学ジャンルにおいて「形式主義文学論」と呼ばれたりもする中河與一や横光利一らの問題意識と興味深い交渉をもっているようだ。本稿は、この時期に流通した機械をめぐる想像=創造力の類型のうちのいくつかを分析し、その後それら「機械主義」の言説がもっていた話型を、横光利一「機械」が周到に下敷きとして取り込み、その同時代の感性の変革を刻み込みつつ、横光自身の独自の問題意識の中にそれを解体移築していっていることを論証しようと試みるものである。そのタイトルに「機械」の名を戴く横光の作品と同時代の機械主義の諸芸術との交渉は、指摘はなされつつもいまだほとんど正面から論じられていない(*15)。そこへ新たに視線を向けなおすことによって、この時期に〈機械〉をめぐってなされた文化的交流の一端に光が当てられればよいと思う。
さて、この新たに発見され直すこととなった機械という存在は、それでは具体的にはいかなる様態で捉えられ、再現=表象されたのか。ここではまずその一つとして、人間と機械との関係を問題とし、それを再編制していったテクスト群のうちのいくつかを取り上げてみたい。
このように問題を立てたときにまず検討の対象として浮かび上がるのはロボットである。米沢嘉博氏によれば「一般に広く知られるようになったのは、昭和三(一九二八)年改造社の大衆文学全集の一冊として「メトロポリス」(ハルボウラング夫人)が出、翌年フリッツ・ラングの映画「メトロポリス」が公開されたあたりからだろう」(*16)とされる。この同時期には「東洋産ロボット第一号「学天則」」(同米沢氏)が京都で開かれた「大礼記念博覧会」(1928)などに出展され見せ物として話題を呼んでいたりもする。いま人間と機械との関係の再編制という点においてこのロボットものを考えるときに、水島爾保布「人造人間時代」(*17)の示す想像力は興味深い。これはナンセンス・コント風の短いテクストでストーリーとしては、人造人間が増えて人間がだんだん圧迫されて行く――という夢を見る、という単純明快なものだが、そこではその人造人間に生殖能力が与えられ、人間との間に「混血児」が誕生して行くという想像力が働いているのだ。「愚図愚図していると、本ものの人間と人造人間の混血児などが出来出し、だんだんと本ものの影が地球の上から薄くなって、しまいには月球の裏っ側へでも行かぬ事にゃ、神様を信じたり、夢を見たり仲間お互いに階級を設けたり、チョイと傷がついても血を出して痛がったりするような弱い皮膚を有った人間ってものが見られなくなるかも知れない。そうなっちゃ大変だと、苦労性の人間達が結束して純粋人間擁護団ってものを設け(後略)」。「混血児」という隠喩を成立させているのは、一組の対(人間と人造人間)のもつ同一性を基盤とし、その上で成立する差異を問題にする、また逆に差異を前提とした上での同一性を見いだす、という「同じだけれど違う、違うけれど同じ」式の認識構造である。人型に造られたロボットを見て、人は自らのロボット性を認識し、また、はねかえるように自らの人間性を確認する。ロボットを取り巻き、また可能にしているのはこの人と機械との間にかかるあやうい均衡である。
人間の想像力が生み出したロボットという存在は、人間の想像力の豊さを示していると同時に、その貧困さも示しているといえるかもしれない。想像力は羽をひろげるが、その足場は既成の知の基盤に立たざるを得ない。未知のものを人間は既知の言葉で測るしかない。たとえば、一九二三年創刊の科学グラフ誌『科学画報』の表紙には、魚のような〈顔〉をもつ列車や、巨大な蛸の姿をした海上で作業する鉄塔などが描かれている(*18)。新たに登場した機械を人間は生物的なメタファーで捉え理解しようとし、また逆に、機械が定着し出せば、生物・人間が機械のメタファーで捉えられたりする。そこでは当然人間と機械の境界がぐらつくことも起こりえよう。たとえば中井正一は前掲「機械美の構造」において「「人間」は機械の出発点であるとともに深い機械の小宇宙であらう。」とし、自然は機械、人間も機械としてそのあいだの弁証法を強調している。
これら機械と人間との境界領域を問題化するテクスト群のなかで、もっとも輝かしい達成を示しているものの一つであろうテクストが、花輪銀吾のフォト・コラージュ「複雑なる想像」[図3]である。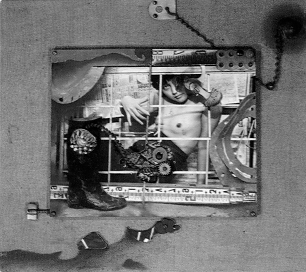
図3 花輪銀吾「複雑なる想像」(「創造主の機械観」)(1937~8)フォトコラージュ
女性のはだけた胸や腕、唇や鼻筋の持つ生物的なやわらかな曲線、そして肌の肌理の細かさと、それを取り巻くさまざまな硬質な機械たちの輪郭の持つシャープな鋭さ、無機質な冷たさとザラつく鉄錆の抵抗感とが対比される。檻と化した障子の格子に閉じ込められ、上半身裸の無防備な姿を曝す若い女性は、周りを機械たちによって厳重に固められ、縛り付けられている。この「閉じ込められた少女」のイメージは、この作品の持つ、断絶した空間的多層性とでもいうべき特徴によって増幅させられている。このテクストではさまざまなレベルの平面が互いに交差し合うことなく重層化されている。少女の後ろには、新聞紙を乱雑に張り合わせた壁の平面がある。少女を挟み、例の檻としての障子がありその平面上にパンプスや測量用らしき巨大な定規や歪んだ円形の鉄板が張り付けられている。そしてそれらが総体として、写真のパネルの平面をなしており、さらにそれが、少々浮いた形で麻布らしきバックの平面に留められている。これら複数の平面は互いに平行であり、重なり取り込みあいながらも、交わることはない。これらの窮屈に重複した平面の間に少女は挟み込まれている。しかしながら注意してみれば、これら厳重に取り仕切られた対立・境界は、ことごとく〈機械〉によって侵犯されているのに気づかされる。機械たちに縛り付けられているかに見えた少女のやわらかな下腹部には、巨大な穴が開き、歯車が姿を曝している。その着色されたとおぼしき鉄片の集積はなにかしらメカニカルな内臓の表面を連想させる。あまつさえ、少女の左目に当たる部分からは、だらりと鉄塊がこぼれだしている。そして、これらの肉体としての機械は、作品の断絶した多層性を破壊する。少女の肉体の内部から延びたコードは、障子のなす平面と、写真パネルの平面を越えて、グロテスクな化け損ねたケンザンのようなものへと接続されており、そしてだらりと垂れる鉄の左目もまた、同様に境界を越えて飛び出してきている。
このテクストの別名を「創造主の機械観」という。取り囲む機械群に閉じ込められているかに見えた少女は、じつは鋼鉄の、機械の肉体を持っている。彼女は圧迫された弱々しい存在ではなく、その鋭く見つめるもう一方の右目の語るごとく、人間―機械の境界を侵犯する、一種の強度を持った存在として提示されているのだ。「創造主の機械観」というタイトルは、このとき人間と機械との関係の再編制が進行する時代の感性の変革を鮮烈なイメージで表現していると言えよう。
ここでまた別の一群の機械をめぐる想像力の様態を考えてみたい。それは機械に託して表象される〈支配〉あるいはそれにまつわる〈恐怖〉に関するものとなろう。
新居格は前掲「機械と文学」において次のように言う。
機械の機能を荒馬の如くに放任すればそれは何をなすかも分からない。イデオロギーによる社会組織の訂正は意識的、意思的であるが、科学の進歩、機械の冒険的驀進は無意識であり、社会法則の無視であるからそのまゝに放置すれば血に飢ゑることゝもならう。
機械は例えば〈学天則〉のように賛美、感嘆の対象であったと同時に、また恐怖、恐れの対象でもあった。そもそもロボットを最初に創造したチャペックのテクスト『R.U.R』(1920)は人間が創造したロボットが逆に人間を支配するという結末を持つものであった。このテクストの持つ影響力は無視できないほど大きなものではあろうが、逆にそのことはロボット・機械に支配され圧倒されるのではないか、という恐れが共有できる感受性の基盤の存在を示しているともいえよう。平野零二「空に踊るロボットとその顛落」(*19)は、人間の代わりに飛行機を操縦するロボットを開発していた軍人が、その開発が成功したと思えたときに「飛行機はね、人間のものなんだ。」といって、テスト飛行中の飛行機を落とす、というものであったし、海野十三「深夜の市長」(*20)には、夜になると地下から延び出て、暗視カメラで街を監視する塔が描かれている。
このような〈支配する機械〉という話型の変奏は、広汎に流通していたように思われる。むろんこの時代、機械を表す象徴的な地位にあった「歯車」というメタファーは現在でも「運命」を示すことができる生きた隠喩であるし、それはまた「支配される人間」を共示することも可能である。たとえば岸田国士「ゼンマイの戯れ」(*21)には、過酷な労働のもとに虐げられた職工たちがゼンマイに寓意化されながら描かれている。
この〈支配する機械〉という物語をほぼそのまま視覚化したといえそうなフォト・モンタージュが、松原重三「無題」(1935)[図4]である。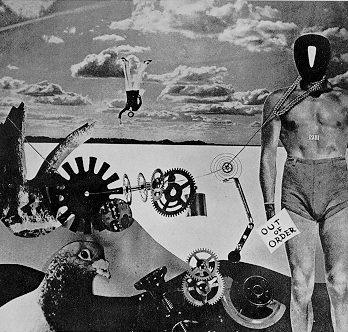
図4 松原重三 無題 (1935)フォトモンタージュ
無防備な半裸体で直立した男が画面右端におり、その首には太い鉄鎖が巻きつけられている。鉄鎖はワイヤーへとつながり、そのワイヤーには多数の歯車が接続されている。男には顔がなく、中心あたりが白く空虚に切り抜かれているばかりだ。よく見れば男は右手に「OUT OF ORDER」のレッテルを貼られ、みぞおちあたりには「931」とナンバリングがされている。男は秩序オーダーから外れたために鎖へとつながれ、顔も衣類もなく脱個性化されて歯車に従属しているのか。あるいはまた、前景化されて画面下半を占める歯車たちが、男の顔を喪失させ、ナンバーを振ったのか。とすると、「OUT OF ORDER」は、ありうべき秩序から機械のために疎外され、「故障アウト・オブ・オーダー」してしまった男の助けを求める叫びなのか。後方では奇妙にリアリティを失った人間が文字どおり宙吊りにされてさえいるのだ。いずれにせよここでは人間たちは〈支配する機械〉の下で静かに抑圧されているばかりだ。
さて横光利一の「機械」(『改造』一九三〇年九月号)もある面でこの運命論の物語を踏襲するものの一つだといえよう。そもそも「機械」という語を一九三〇年というこの時期にタイトルとして掲げた事自体、これまで確認してきたこととそれらの出現時期とに照らしあわせれば優れてタイムリーなものであったことがわかる。
では横光のテクストはどのように機械を物語るのか。このテクストが掲げた「機械」というタイトル語は、冒頭すぐに「家の中の運転が細君を中心にして来ると細君系の人々がそれだけのびのびとなつて来る」(*22)という、「家」をひとつの機械に見立て、その管理運営を「運転」と呼ぶ語り手の言葉によって、ストーリーと関連づけられる。これにより読者はこの「家」において起こる出来事を、機械となんらかの形で結びつけて解釈するよううながされる。そしてストーリーがクライマックスを迎える少し前、語り手は次のように語り、字義通りに受け取ればとりあえずこの物語の主題と呼びうる解釈の枠組みを提示する。
だが此の私ひとりにとつて明瞭なこともどこまでが現実として明瞭なことなのかどこでどうして計ることが出来るのであらう。それにも拘らず私たちの間には一切が明瞭に分つてゐるかのごとき見えざる機械が絶えず私たちを計つてゐてその計つたままにまた私たちを押し進めてくれてゐるのである。
「私たち」には見えないところでゆっくりと動き続け、「絶えず私たちを計つてゐてその計つたままにまた私たちを押し進め」ている機械。固定された視点により、同僚の軽部や屋敷などの心の裡をのぞき見ることが許されず、おのれの内部で明滅する心理過程を執拗に描き出す〈私〉は、その限定された視野の外部に「見えざる機械」を想定する。その機械は、溢れかえり錯綜する言葉の外から、明晰に〈私〉を計り押し進めているというのだ。これまで検討してきた〈支配する機械〉という、他のテクスト群が踏襲し、語り直していた物語を横光「機械」もまたその運命論のフレームとして採用している。むろん引用部分のような明示的な言辞だけではなく、舞台を「町に並んだ家家の戸口に番号をつけて貼つけ」るネームプレートを作る工場においていること(これは先ほどの松原重三のフォト・モンタージュを連想させる)、〈私〉が薬品を混合する過程で「無機物内の微妙な有機的運動の急所を読みとることが出来て来て、いかなる小さなことにも機械のやうな法則が係数となつて実体を計つてゐることに気附き出」すことなど、この話型を固める小道具が周到にちりばめられていることは、少し細部に目を向ければ容易に気付くところである。テクストは〈支配する機械〉の物語を愚直なまでに辿り直し、一直線に終結部の「私はたゞ近づいて来る機械の鋭い先尖がぢりぢり私を狙つてゐるのを感じるだけだ。誰かもう私に代つて私を審いてくれ」という叫びへと収束して行く(*23)。
さらに、この〈支配する機械〉というフレームは、登場人物達の動きを規定する基底構造としても据えられている事が指摘できる。この基底構造によって読者は散発的に字面上に現れる「機械」という言葉をテクスト全体に敷衍してゆくことができるようになっている。少々大づかみに把握すれば、「機械」という作品は、「1 主人とそれを大切にする使用人Aがいる。/2 優秀な使用人Bが現れる。/3 AとBとの間に軋轢が起こる。」という構造を持っていることがわかる。そしてこの構造が物語内で反復されるようになっているのである。最初はA=軽部、B=〈私〉であるわけだが、これがA=〈私〉、B=屋敷となって反復される。これはかなりあからさまな構造であり、〈私〉自身、「前には私は軽部からそのやうに疑はれたのだが今度は自分が他人を疑ふ番になつたのを感じると、あのとき軽部をその間馬鹿にしてゐた面白さを思ひ出してやがては私も屋敷に絶えずあんな面白さを感じさすのであらうか」とその反復を確認するところまであることから、読者にはある程度透けて見える構造になっている。つまり約言すれば、人物たちの行動を規定しているのは、彼らの主体的選択ではなく、彼らの位置関係の構造であるということが、読者へと伝達されるように語られているということである。これがすなわち「機械」というテクストの基底構造として存在する〈支配するものとしての構造=メカ・ニズム〉であり、これにより〈私〉の最後の叫びが、リアリティをもつことになる。
横光の「機械」というテクストが、同時代に流通していた〈支配する機械〉というある種の運命論を、その骨組みとして採用していることは間違いないと言えそうだ。また先行論(*24)の指摘するとおり、絡み合った登場人物たちの相互の心理作用を指して〈機械〉と呼んでおり、その点において横光「機械」は人間と機械との関係性を再編制していっていた同時代の感性の変換(第2節参照)のなかの産物であったということも可能のようだ。だが「機械」というテクストがそのなかに刻み込む同時代の感性との交渉は、このような物語話型の踏襲・変形のレベルのみにとどまるわけではない。
機械主義と横光「機械」との交渉を見定める時に、さらに指摘しなければならない面がある。それは「機械」というテクストを可能にした、横光自身のパースペクティヴの移動を検討してゆくことで浮かび上がることになる。この移動は一九二八年から一九三〇年あたりの横光の評論テクストを読んでゆくときに、はっきりとうかがうことができる。たとえば一九二八年に書かれた次のテクストは言う。「それなら芸術家は何んであらうか。/「人間的機械である」/人間的機械よりも、人間の方が、人間にとつては尊むべきものではないか。/「それは尊むべきものである。さうして、人間は左様に人間にとつて尊むべきものであるが故に、芸術家は、即ち人間的機械となつて人間をより他の何者よりも完全に知らねばならぬ」(*25)。ここにある「人間的機械」という隠喩=認知形式もまた、ロボットの問題群を前節で検討してきた我々にとってすでになじみ深いものであるが、いまここで問題となるのは、横光の述べる、人間をより完全に知るために芸術家は「機械」にならねばならない、という点である。人間から機械へ、この移動はさらに次のテクスト(*26)にも引き継がれる。
総て現実と云ふもの――即ちわれわれの主観の客体となるべき純粋客観――物自爾――最も明白に云つて自然そのもの――はいかなる運動をしてゐるか、と云ふ運動法則を、これまた最も科学的に、さうして、それ以上の厳密なる科学的方法は赦され得ざる状態にまで近かづけて、観測すると云ふ、これまた同様に最も客観的に、いささかのセンチメンタリズムをも混へず、冷然たる以上の厳格さをもつて、眺める思想――これをメカニズムと云ふ。(中略)さうして、文学に於ては、形式主義がメカニズムの現れとなつて現れ出した。
人間をより知るために機械になるという発想は、ここでは「それ以上の厳密なる科学的方法は赦され得ざる状態にまで近かづけて、観測する」という形で変奏されている。科学的に正確に見る/知るということが、これらのテクストでは理想的な認識方法として称揚される。そしてその科学的という際に「人間的機械」あるいは「メカニズム」という認知形式が導入されているのだ。そして横光はさらに論を進め、その「メカニズム」が文学において現れたのが、自らも密接にかかわる「形式主義」だというのである。「メカニズム」と「形式主義」という取り合わせは、なにも横光の独断というわけではない。横光と同じく形式主義文学論を担った中河與一による形式主義の定義もまた以下のようなものであった。「そこで私は形式に就いての定義を左のやうに試みる。/形式(form)とは様式ではない。形を持つたものである。物質的なものである。経過を持つた頂点である。具体である。/形式とは素材の飛躍したものである。飛躍したものであるが故に新鮮である。緊密である。アプリオリでない。メカニズムである。能率的な美である。」(*27)。現在の我々にとって必ずしも「メカニズム」と「形式主義」とを結びつけるのは容易ではない。「メカニズム」という語もそれぞれの文脈で独特の意味を付与されている。だが、横光や中河にとって、それら二つは「科学的」という理想のもとで文学を「唯物的」(*28)に捉え、その求めるありようを記述してゆく上で理論的な必然性を持った結びつきであったのだ。
このような「科学」への横光の立脚点の移動は、一九三〇年に発表されたテクスト「芸術派の真理主義について」(*29)によって明確に定位される。
そこで、新しい芸術派の真理主義者たちの一団は、彼ら自身を出来得る限り科学者に近づけなければならなくなつたのだ。いや、寧ろ反対に、科学者を彼ら自身の中へ産み出し始めたのである。人生に対して、芸術家ほど科学者でなければならぬものはない。
芸術家が科学者となる。横光のやや煽動的な口吻は「機械技師と芸術家との限界が消失する」と宣言した板垣鷹穂の口調といかに似かよっていることか。横光はすでに別のテクストでも「芸術の究極の殿宇が風流にあると云ふ美学者」に不必要を宣告していた(*30)。芸術から科学へというポジションのスライドは、むろん横光の、文壇という力場内でのイデオロギッシュな選択という面がないわけではないだろうが、科学への関心は同時代的な嗜好でもあったのだ(*31)。
そしてポジションの移動は必然的にパースペクティヴの変化を伴い、新しい対象の発見をもたらさずにはいない。同じ横光のテクストは、その発見をも物語る。
私は此の一ヶ月間煙草を吸はない。今迄一日にチエリーを五箱のんでゐたのに、ぱつたり煙草を吸はなくなつてから頭の廻転も変化して来た。人と言葉を交へるのがいやになり、思はぬときに思ひがけない表情が顔の上で拡がつてゐたり、注意力が対象を忘れて霧散したり、夜が来ると眠気に抵抗するのが第一の務めとなつたり、とに角ひどくいつもと変つて来た。ペンを持つても一字を書くのにまごまごした骨折を感じる。意識と意識との継目から身体を支配しさうな無意識の運動が間断なく行はれてゐるのを感じるやうになつた。煙草を吸ふ肉体と、煙草を吸はない肉体との感覚の落差の中で、私はそのどちらが実体を計量する上に於てより正しい肉体であるのかを考へる。(中略)譬へば、今、私のこの体内に於ける禁煙からの変化とその運命を最も確実に示し得るものは、芸術家以外にはないのである。科学者そのものよりも、芸術家の方が正しいのだ。
この評論からフィクション「機械」へと進む過程の中で、ひとつのことが明確に横光の視野の中へと入ってきていることがわかる。それは「意識と意識との継目から身体を支配しさうな無意識の運動」に注目を向けるということだ。横光が同じ「芸術派の真理主義について」の中で「その時間内に於ける充実した心理や、心理の交錯する運命を表現し計算することの出来得られる科学は、芸術特に文学をおいて他にはない」と述べるように、彼の考えた「科学」としての「文学」というスタンスが産み出したものが、この「無意識の運動」への注目とその描写であった。そしてここで重要なのは、「意識」ではなく「意識と意識の継目」であるということ、「心理」のみではなく「心理の交錯」を「表現し計算する」ということ、すなわち〈関係〉を見据え、それを「科学」的に描き出すというパースペクティヴのとり方である(*32)。さらに、補足すれば、同様の視線は横光ひとりのものではなく、たとえば前掲『機械芸術論』に「機械美の構造」を書いていた中井正一などと共有していたものであったことも指摘できる。
この「道具」としての尺度を、その空間的量の測定の手段として運用する場合、それは功利的道具である。しかしもし、その目盛りを、「もの」の中に見出す数の運用性、即普遍なる対象的関係性の surrogate (代入)として、「ものの関係」そのものを見出すとき、感覚はそこに一つの反省的判断として秩序即叡智的計量を見出す。(中略)それを美としも云ふならばそれはシルラーの云へる意味に於いて、「最も十分なる意味における真」である。機械のもつ美はしさのもっとも始源的な、そしてしかも類型的なるものをそこに私は見出すかの様である。
(同書p160)
「尺度」を「道具」としてではなく、「ものの関係」そのものとして見い出す。さらにただ見い出すのみならず、そこに「秩序即叡智的計量」を見い出し、それを「機械のもつ美はしさ」として語る。このような関係性への注目とそれを科学的に「計算・計量」しようする姿勢とが、人と人との間で錯綜する心理へと向けられることによって、「機械」というテクストは誕生した。
「芸術派の真理主義について」というテクストは、「体内に於ける禁煙からの変化とその運命を最も確実に示し得るものは、芸術家以外にはない」というポジションをとる。このテクストの冒頭にある詳細な禁煙の心理と肉体の反応の記述は、その立場からの試みの一つとみてよいだろう。そしてここで試みられていることを、フィクションというジャンルへと移入し、大がかりに展開したものこそが「機械」というテクストなのだ。この点で二瓶浩明氏の「「新心理主義」は、文学の「科学」性をもって「人間」を描く横光の「メカニズム」という方法論の処理技法に過ぎなかった」という指摘(*33)は非常に鋭い。ただし、氏が続けて言う「それは衣装(メカニズム)の模様に過ぎない」という見解は少々横光の達成に対する過小評価であると言わねばならないのではあるまいか。
横光はただ単に評論テクストで粗述したパースペクティヴを、フィクションというジャンルにそのまま移したというわけではない。二つのジャンルを越境する際には当然その二つのジャンルのルールのあいだをも跨がねばならない。人間の心理を科学としての芸術という地点から描こうとする目論見を、フィクションへと移入するときには、フィクションという形式の要求する、語り手や視点人物やプロットやというさまざまな要素を満たしたうえでそれを行わねばならない。それを乗り越えるために横光が編みだしたものが、登場人物の〈私〉と語り手の〈私〉とを完全に切り離し、その両者の間を視点が往還するという方法であった。これによりテクストの語りは、ジュネットのいう「後説法」のように過去の出来事を振り返って説明的に述べることにとどまらず、登場人物の〈私〉の心理・運命を、語り手の統御を超えたものとして描き出すことを可能にした。つまり視点が登場人物の〈私〉に近づけば、オーソドックスな「後説法」的語りに近くなり、語り手の〈私〉に近づけば、メタフィクション、饒舌体的な語りを可能にするのである(*34)。例えば次の文章を見てみよう。
なるほどさう云はれれば軽部に火を点けたのは私だと思はれたつて弁解の仕様もないのでこれはひよつとすると屋敷が私を殴つたのも私と軽部が共謀したからだと思つたのではなかろうかと思はれ出し、いつたい本当はどちらがどんな風に私を思つてゐるのかますます私には分からなくなり出した。しかし事実がそんなに不明瞭な中で屋敷も軽部も二人ながらそれぞれ私を疑つてゐると云ふことだけは明瞭なのだ。だが此の私ひとりにとつて明瞭なこともどこまでが現実として明瞭なことなのかどこでどうして計ることが出来るのであらう。それにも拘らず私たちの間には一切が明瞭に分つてゐるかのごとき見えざる機械が絶えず私たちを計つてゐてその計つたままにまた私たちを押し進めてくれてゐるのである。
先に〈支配する機械〉という話型の分析の部分で一部引用したこの文章もこのような観点からみると、また別の相貌を帯びはじめる。「弁解の仕様もない」と思っている〈私〉の視点は登場人物としてのそれであるのに対し、「見えざる機械」の存在を関知している〈私〉の視点は語り手のものである。語り手〈私〉は登場人物〈私〉の心理を紹介しつつ、みずからの見解をもそこに織りまぜていく。そして特徴的なのは通常ならば「一人称」という約束上、登場人物〈私〉の心理はその後身(時間的に一致する場合もあるが)である語り手〈私〉によって把握されていてしかるべきなのだが、ここ「機械」においては登場人物〈私〉の心理は必ずしも語り手〈私〉の理解・統御のもとにあるわけではないのだ。
さうだ。もしかすると屋敷を殺害したのは私かもしれぬのだ。私は重クロム酸アンモニアの置き場を一番良く心得てゐたのである。私は酔ひの廻らぬまでは屋敷が明日からどこへいつてどんなことをするのか彼の自由になつてからの行動ばかりが気になつてならなかつたのである。(中略)いや、もう私の頭もいつの間にか主人の頭のやうに早や塩化鉄に侵されて了つてゐるのではなからうか。私はたゞ近づいて来る機械の鋭い先尖がぢりぢり私を狙つてゐるのを感じるだけだ。誰かもう私に代つて私を審いてくれ。
語り手〈私〉は、登場人物〈私〉の心理・行動が把握できず、その視点を自らの内にとどめたまま自らの意識を語り出す。このような横光の編みだした語りが、自意識を際限なく饒舌につむぎだし語り起こす、昭和初期の一連のテクスト(*35)の登場の準備の一端をなしたことはすでに周知のことであろう。
以上見てきたごとく、横光利一「機械」はその保持する運命論や、人間/機械の境界を見据える問題意識、表象の対象を見つめる眼差しのあり方など、同時代流通していた機械主義と密接な交渉をもち、その話型や感性を巧みに取り込み刻み込みながら、それを独自の形式へと解体再構築していったのだということができるだろう。横光「機械」はそのような面から、より丹念に読みなおされねばならない。
(*1) 同書は「新芸術論システム」と銘打たれ一九三〇年五月から天人社より刊行されたシリーズのうちの一冊である。一九九一年七月にゆまに書房から復刻されており今回はそれを用いた。詳しくは同復刻書所収の牧野守氏の二つの解説を参照。
(*2) 前掲『機械芸術論』解説による。
(*3) 一九三〇年一月五日から。
(*4) これら板垣の活動に対する反応が板垣『芸術的現代の諸相』(六文館、一九三一年一〇月)所収の「現代芸術考察者の手記」に紹介されている。ここで述べたのは〈機械を表象対象とした芸術についての分析〉の流行であり、機械芸術そのものの発生・流行はもうすこし前まで遡ることはできるだろう。
(*5) 板垣「機械美の誕生」(前掲『機械芸術論』所収)。
(*6) 前掲『機械芸術論』所収、p125。
(*7) 前掲『機械芸術論』所収、p154。
(*8) 城左門「我がネオン・サイン」(『ドノゴトンカ』一九二九年七月)。引用は『モダン都市文学Ⅵ 機械のメトロポリス』(海野弘編、平凡社、一九九〇年七月)による。以下『機械のメトロポリス』と表記する。本稿は同書から大きな啓発を受けている。
(*9) 小泉「都市をめぐる芸術家達のロンド」(カタログ『都市風景の発見』茨城県近代美術館、一九九二年)。以下の記述もこのカタログに示唆を受けている。
(*10) 昭和4・6・2付「矢野文夫宛書簡」(長谷川利行著・矢野文夫編『長谷川利行全文集』五月書房、一九八一年)。
(*11) 『風俗雑誌』一九三〇年七月。
(*12) 『女性時代』一九三一年四月号。
(*13) 『中央公論』一九三一年一〇月。
(*14) 『犯罪科学』一九三一年十二月。
(*15) 「「機械主義」の影響」の指摘は、はやく神谷忠孝氏の「横光利一集注釈」注一(『日本近代文学大系 42 川端康成 横光利一集』角川書店、一九七二年七月)にある。石田仁志「横光利一の形式論――都市文学の時空間」(『人文学報』No.243、一九九三年三月)は、「町の底」他の横光の作品が機械化された都市空間において変容した人間の感覚を描いている、と指摘している。
(*16) 米沢「ロボット・ブーム」(『別冊太陽』88 平凡社、一九九四年冬、p52)。
(*17) 『現代ユウモア全集・第十五巻 水島爾保布集』(一九二九年、現代ユウモア全集刊行会)。引用は『機械のメトロポリス』による。
(*18) 會津信吾「「科学画報」と通俗科学」(『別冊太陽』88 平凡社、一九九四年冬)を参照。
(*19) 『中央公論』一九三〇年九月号
(*20) 『新青年』一九三六年二~六月号
(*21) 『改造』一九二六年七月号。引用は『機械のメトロポリス』による。
(*22) 以下横光のテクストの引用は、基本的に『定本 横光利一全集』(河出書房新社、一九八一年)によるが、「機械」に関しては雑誌発表時、周囲に与えた衝撃を勘案して、適宜雑誌発表形を参照した。また引用の際、漢字は新字体に直した。
(*23) この結末は前掲神谷忠孝「横光利一集注釈」の指摘するごとく、芥川龍之介「歯車」(『文芸春秋』一九二七年一〇月)という、これも〈支配する機械〉という物語を借り受けて織られたテクストの末尾「誰か僕の眠つて居るうちにそつと絞め殺してくれるものはないか?」という言葉と近い位置にあるだろう。
(*24) たとえば川端康成「九月作品評」(『新潮』一九三〇年一〇月)。
(*25) 「愛嬌とマルキシズム」(『創作月刊』一九二八年四月)。/は原文改行を示す。
(*26) 「形式とメカニズムについて」(『創作月刊』一九二九年三月)。
(*27) 中河與一『フォルマリズム芸術論』(天人社、一九三〇年五月)pp18-19。「新芸術論システム」のシリーズのひとつ。/は原文改行を示す。
(*28) 横光利一「文学的唯物論について」(『創作月刊』一九二八年二月)。
(*29) 『読売新聞』一九三〇年三月十六、十八、十九日掲載。
(*30) 「客体への科学の浸蝕」(『文芸時代』一九二五年九月)。
(*31) この点に関しては、小森陽一「エクリチュールの時空――相対性理論と文学――」(『構造としての語り』新曜社、一九八八年四月)、前掲石田「横光利一の形式論」を参照。
(*32) 「機械」が〈関係〉への注目の上に書かれていることは諸氏の論考も一致して指摘するところだ。たとえば栗坪良樹「横光利一『機械』再読」(『評言と構想』一九八一年六月)、玉村周「横光利一・「機械」その他――《関係性》の中で――」(『土浦短期大学紀要』一九八五年五月)。
(*33) 二瓶浩明「横光利一『機械』論――「マルキシズムとの格闘」をめぐって――」(『山形女子短期大学 紀要』12、一九八〇年三月)。
(*34) 川端柳太郎氏はこの「機械」を横光自身の後年の概念「四人称」から分析を試みられているが、氏自身「年代的に五年後の「四人称の設定」という発想が、創作当時にあったかどうかは、問題になる」と述べられているように、やはり〈科学者としての芸術家〉へという横光自身のポジションの移動から生まれてきた語りとして説明するべきではあるまいか。川端柳太郎「四人称の現代性」(『近代』(神戸大)一九七五年七月)参照。
(*35) 安藤宏『自意識の昭和文学』(至文堂、一九九四年三月)参照。