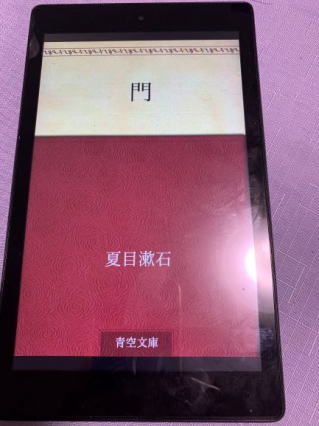Youtubeでこの方の講演を聞いて、面白いと思って、著書を取り寄せた。15年も前の本だった。ロボット工学がご専門で、「意識」とは何かと探求して、私という主体があるわけではなく、脳細胞が作りだす錯覚だ」というのである。
受動意識仮説と呼んでおられる。
意識と言えば、〈私〉というものがあって、それらが、、知、情、意、記憶などを統括しているように思っているが、これらは、脳のニューロンのネットワークが作り上げた、錯覚に過ぎないというのである。
意識が受動的であることを、幾つかの例を挙げて説明されると納得します。〈私〉がすべてを統括することは困難で、むしろ傍観者として、意識の流れを見ています。
この人の意識のモデルは、それなりに一貫性があり、「心の地動説」として、とても刺激的です。
第5章で脳の仕組みをやや専門的に述べておられてます。ここでは、
AIとかディープラーニングと行った言葉は出てきませんが、考えは同じで、意外と単純な原理がそこに働いています。
自立分散型のニューロンが、民主的にことを決定しており、難しく言うと「任意の非線形演算を行える万能機械」となりますが、このAIが発達すると、心の仕組みについて、さらに簡明な説明を工学畑の人から聞く時代が来ると思います。
2021・7・29
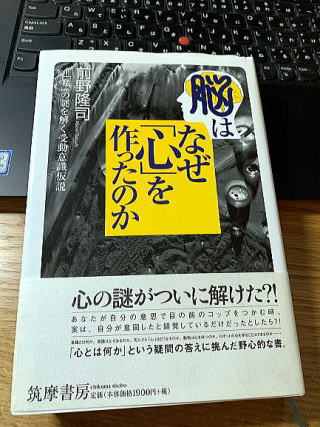
「父母未生以前の本来の面目」という公案を、人はどう捉えているか知りたくて、図書館から、「禅問答」の本を3冊借りだしたら、それは、偶然、僧籍にある人ではなく、文筆家、大学の先生の本であった。大悟していない人が、大悟した人の問答を解説できるのだろうか?3冊とも冒頭の公案に触れるものはなかったが、備忘として、書名を書いておきます。
1952~97 文筆家
公案30則を取り上げる。求道の熱意を感じられるが、著者は45歳で逝去。
「往生人列伝」で良寛、芭蕉、浅原才市、宮澤賢治。山頭火の臨終を紹介しているのも不思議。
1959年生まれ 弘前大学教育学部教授
「百個の禅問答をながめ、ああでもない、こうでもない、とヒネくりまわしてみた。こころがけたのは、おもいっきり妄想することである。どう転んでも「わからん」のである。」(同書あとがき)
私はこのような著者の妄想に付き合う時間はない。
1958生まれ 駒沢大学学長
代表的な問答をいくつかのカテゴリーに分けて懇切な解説。禅思想史も概説し、豊富な学識に驚く。この先生の教科書かも知れない。
ーーーーーーーーーー
調べているうちに、一休禅師の2つの歌が目についた。
闇の夜に 鳴かぬ鴉の声聞けば 生まれぬ先の父ぞ恋しき
本来の面目坊の立ち姿 一目見しより恋とこそなる
つづく

夏目漱石 『 門 』
久しぶりに読む漱石は、心地よい滑らかさで、読み始めたら止まらなかった。
宗助と御米という、平凡な夫婦の日常の中に、時間、季節を巧みに織り込んで、リアリティーがあるうえ、詩情さえ感じられた。百年以上の前の新聞小説という古さは全く感じさせない。
私がこの作品を読もうと思ったの「父母未生以前の本来の面目」という公案が、出てくるからである。宗助は友人安井の恋人御米を奪って、ひっそりと暮らしている所へ、その安井が出現するということで、心の平穏を失い、禅寺へと赴くのである。この参禅の記述は、漱石が明治27年(1894)、27歳の時、円覚寺帰源院へ投宿し、釈宗演老師について、参禅した時のことを写していると言われ、世話をする僧侶宣道の描写を含め、細やかな描写は、漱石の参禅体験を知るには面白い。その時は公案を透過出来ず、小説では、老師に別れ際、「少しでも手がかりができてからだと、帰ったあとも楽だけども。惜しい事で」と言われている。
心の平穏は未解決のまま、宗助と御米の静かな生活が続く。
小説としては尻切れトンボの感があるが、後は読者が考えなさいということかも知れない。
2010・11・15
つづく