映画メモ 2009年9・10月
(劇場・レンタル鑑賞の記録、お気に入り作品の紹介など。はてなダイアリーからの抜書です)
あなたは私の婿になる / カンフー・マスター! / 私の中のあなた / ファイティング・シェフ / アニエスの浜辺 / ATOM / ムルと子犬 / カイジ 人生逆転ゲーム / BALLAD 名もなき恋のうた / リミッツ・オブ・コントロール / オー!マイ・ゴースト / 幸せはシャンソニア劇場から / キャデラック・レコード〜音楽でアメリカを変えた人々の物語〜 / グッド・バッド・ウィアード
あなたは私の婿になる (2009/アメリカ/監督アン・フレッチャー)
ニューヨークの出版社で働くマーガレット(サンドラ・ブロック)は、ビザの問題で国外退去を命じられたため、こき使っているアシスタントのアンドリュー(ライアン・レイノルズ)との結婚を宣言。週末を彼の故郷アラスカで過ごすはめになる。
ライアン・レイノルズの首から上が私の好みなら、もっと観がいがあったけど、犬が可愛かったので許す(笑)
サンドラ・ブロックは、最後に降ろした髪をゆるく巻いてるのが可愛かった。心が柔らかくなったことの表れなんだろうけど、私なら、冒頭のひっつめ&黒スーツも好きだから、どっちのタイプの格好もできる人生がいいな。パーティでのグレーのワンピースも良かった。
それから、ライアンの母親役のメアリー・スティーンバーゲン(最近では「俺たちステップ・ブラザーズ」でウィル・フェレルの母親)。いつまでも見ていたい顔、白いセーターが似合う顔だ。
会社に戻ってからの「ハッピーエンド」に際し、同僚がかける「どっちがボスか分からせてやれ!」というお祝いの言葉が印象的。男女逆なら何とも思わないけど、ほほえましく感じられる。また、ライアンの告白に「ほうっ」となってるのが女性だけだというのも面白い。
それから、この終わり方には、全然違う話なんだけど、スーザン・サランドン&ジェームズ・スペイダーの「僕の美しい人だから」('90)を思い出してしまった。原作小説より映画らしく派手なラストシーンが好きで、何度も観たなあ。
数日間で恋におちることって実際あるけど、この場合、見ず知らずの相手じゃないし、素地もあったんだろう。冒頭の描写でも、「鬼チーフ」と部下という間柄とはいえ、ちゃんと心の内を言い合ってるし、ある意味、互いに気を遣ってるのが分かる。
付き合い始めてしばらくは…もしくは何年も、付き合う前の相手を思い出すことで、新鮮な気持ちが得られるから、お得なものだ。
それにしても、離れて暮らしてる親とたまに会った際、あらたまって切り出される話というのは、楽しくないことばかりだなと思った(笑)
(09/10/29・新宿ピカデリー)
カンフー・マスター! (1987/フランス/監督アニエス・ヴァルダ)
上映中の「アニエスの浜辺」がとても良かったので、アニエス・ヴァルダの未見の作品を…と借りてきた。
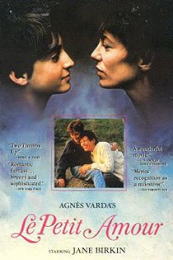 ジェーン・バーキン原案による作品。バーキン演じるマリ・ジェーンが、娘の同級生の少年と恋に落ちる。
ジェーン・バーキン原案による作品。バーキン演じるマリ・ジェーンが、娘の同級生の少年と恋に落ちる。
バーキンの娘をシャルロット・ゲンズブール、その妹も実際のバーキンの娘、夏に訪れるロンドンで彼等を迎えるのはバーキンの実の父母。恋のお相手は、アニエスとジャック・ドゥミの息子のマチュー・ドゥミ、といった具合のファミリー・ムービー。
「カンフー・マスター!」は日本製のテレビゲームのタイトル(原題は「Le petit
amour」)。オープニング、柔道着姿のマチューが、ぴこぴこした音に合わせて、路上でゲームの再現をするのが可愛い。そこだけ4、5回繰り返して観てしまった。
「アニエスの浜辺」を観た後だと、このシーンがいかにアニエスらしいお遊びかが分かる。
ここでのジェーン・バーキンは、スタイルのいいミック・ジャガーといったふう。短い髪にシャツとパンツ。気に入った少年に会いに出かけ、コーラとゲームで彼を釣る。恋人に対してはもちろん、娘たちに対しても、恋人のように振る舞う。
終盤、マチューが思い出のゲームセンター?を訪れるシーンにぐっときた。そしてバーキンの方は、恋が終わってから、ほんの些細なこと…「彼のいとこは、本当にあそこにいたんだろうか?」なんて、どうでもいいことが心に引っ掛かる。ああいうのってよく分かる。
この映画に、大人の男は出てこない。あるシーンで姿は映るけど、登場人物としては出てこない。バーキンとマチューは、無人島でひとときを過ごし、寝袋で眠る。なんていう、甘く目隠しされた世界。
(09/10/28)
私の中のあなた (2009/アメリカ/監督ニック・カサヴェテス)
白血病の姉ケイト(ソフィア・ヴァジリーヴァ)に臓器を提供するドナーとして生まれた、11歳のアナ(アビゲイル・ブレスリン)。母サラ(キャメロン・ディアス)は「家族のために」と当然のようにその体を使用してきたが、ある時アナは、腎臓提供を拒むべく、弁護士を雇い両親を訴える。
 母親が管理しようとしていたのは、意図的に産んだアナの体と心だけではなかった…ということに気付いた時の衝撃。自分の鈍さにショックを受けた。少し考えれば想像できることなのに、途中まで思い及ばなかった。ケイトが最後に母親にかける言葉に、あんな「よく出来た」子どもがいるだろうか?と思いつつ、涙がこぼれた。
母親が管理しようとしていたのは、意図的に産んだアナの体と心だけではなかった…ということに気付いた時の衝撃。自分の鈍さにショックを受けた。少し考えれば想像できることなのに、途中まで思い及ばなかった。ケイトが最後に母親にかける言葉に、あんな「よく出来た」子どもがいるだろうか?と思いつつ、涙がこぼれた。
映画は11歳のアナのナレーションで始まる。自らが生まれた経緯を語る際、「天国では魂たちが肉体に入る時を待っている」というようなことを言うので、これがアメリカの子どもの一般的な考え方なのかな?と引っ掛かったものだけど、彼女と姉がひなたぼっこしながら共に過ごす時間、交わすやりとりに、ああいう体験をしていれば、ああいう考え方をしても不思議じゃない、と思わせられた。
予告編から、裁判劇が話のメインかと思っていたら、全く違っており、ふとした拍子に各人が思い起こす家族の体験が、バラバラに積み重ねられていく。映像も音楽も心地良くて、趣味がいいなと思った。
裁判を起こす時点で、アナを含む子どもたちは、ある段階に来ている。物語は彼等のそれまでを描きつつ、そこへ到達していない母サラが裁判を切っ掛けに前進することで終わる。ちなみに父親とアナの兄ジェシーは、登場する女性たちを「動」とするなら「静」であり、もしケイトとアナが男兄弟だったら、どんな映画になったろう?と思わせられた。父親は結果的に「美味しいとこ取り」してるように感じられたので。
終盤、ケイトの病室に「祝日かトラブルのときしか集まらない」親族の数人が訪れ、「気のもちようが大事」というようなことをしきりに言う。対する「ファミリー」のうんざりした表情が面白かった。こういうシーンのある映画っていい。
病院の先生や裁判長(ジョーン・キューザック!)のキャラクターや服装…ギター柄のネクタイや、バラが散りばめられた上着…も良かった。
ケイトとボーイフレンドのテイラーがパーティを抜け出すシーンに、「ラスト、コーション」を観た際、もうすぐ死ぬと分かっている相手とのセックスはどういう感じがするだろう?と考えたのを思い出した。さらにはこのように、自身と相手の死を互いに意識している場合は?この映画からは特別な感じは受けなかった(それがいい・悪いというわけではない)。
初対面の二人が「○○のテイラー」「○○のケイト」と病名をアタマに付けて自己紹介するくだりが、可笑しくも切ない。これが老人映画なら、病気もギャグにできようというものだけど…って、そういう感覚もおせっかいか。
ジェイソン・パトリックはますますおっさん化が進んでいたけど、その職業は消防士。アナが仕事場を訪れ、皆と一緒に食事をするシーンが羨ましい(笑)ちなみにその際、この間コストコで買った、でかい粉チーズ(コレ)が登場。これまでも映画に出てきてたのに、気付かなかったんだろうな。
(09/10/19・新宿ピカデリー)
ファイティング・シェフ (2008/スペイン/監督ホセ・ルイス・ロペス・リナレス)
フランス料理の国際大会「ボキューズ・ドール」を舞台に、スペイン代表シェフの奮闘を描いたドキュメンタリー。
ボキューズ・ドールは名称を知っているだけなので、終盤に繰り広げられる大会の様子が面白かった。学園祭の出店のように設営されたキッチンで、体育祭のような声援(日本勢は日の丸ハチ巻きにしゃもじ/「おれはキッチンではラジオも付けないのに…」と言うシェフも)を受けながら料理に臨む出場者たち。結構安っぽい、音楽や火花などの演出。司会者のあおり。勿体つけてポール・ボキューズが現れると、料理中に握手しなきゃなんないのも大変だ(笑)
フランス料理、あるいはこの大会のテーマの一つが、「食べる側が皿を選んでしまうようではだめ」というセリフに表れている。完璧に制御され、均等でなければならない。あるシェフの見方では「スペインは、何をするにも即興で不規則だから入賞できない」。
劇場で観た予告編は「万年冴えないスペイン勢が、今度こそはと頑張る」という内容が、軽快なコメディタッチでまとめられていたけど、実際は淡々とした記録映像で拍子抜けした。とはいえ演出の無さゆえのリアルさも感じた。
主役?のヘスースについても、料理人としての姿しか映されない。本番終了後、白衣にリュックを背負ってたのが可愛かった(笑)
大会を控えての試食会では、居並ぶ先輩シェフたちが、ケータイで写真を撮った後、厳しいコメントを次から次へと口にする。宙を泳ぐヘスースの視線。でもねちねちした雰囲気ではない。たんに「シェフというのは行動的だし、意見を言わずにいられない」らしい。
 原題は「El pollo, el pez y el cangrejo real」…鶏肉、魚、そして蟹。作中思い出したように、テーマ食材であるおひょいとタラバガニ、鶏の産地が紹介される。ノルウェーにあるおひょいの養殖場(右写真)は、地球の果てって感じで心奪われた。
原題は「El pollo, el pez y el cangrejo real」…鶏肉、魚、そして蟹。作中思い出したように、テーマ食材であるおひょいとタラバガニ、鶏の産地が紹介される。ノルウェーにあるおひょいの養殖場(右写真)は、地球の果てって感じで心奪われた。
ラストシーンは、調理場であれこれ指図していたヘスースが、台所に立つ母親に「お水取って〜」と言われ、いそいそと従うというもの。作中、このシーンのパエリヤが一番美味しそうだった(自分の作るのがもっといいとも思ったけど・笑)。コンクールでの「料理」は、普段の食事と違う、芸術的・退廃的なものだから、そう思わせて正解なんだろう。
各国シェフの料理の写真が、映画の公式サイト内のギャラリーで見られる。フランスのコレを目にした時のヘスースの表情、ああいうのを見られるのが、ドキュメンタリーの最もシンプルで強い楽しさだ。
(09/10/16・TOHOシネマズシャンテ)
アニエスの浜辺 (2008/フランス/監督アニエス・ヴァルダ)
「80のホウキ」を迎えた映画監督アニエス・ヴァルダが、自身の生涯を振り返る。
 冒頭、浜辺に登場するアニエスは、ワインレッドのスカーフとコート。染めた髪も同じ色合い。潮風に激しくなびくスカーフを頭に巻き付け「こういう姿で映るのもいい」とふざける。彼女が惹かれるのは「動くもの」や「周囲の人」だ。
冒頭、浜辺に登場するアニエスは、ワインレッドのスカーフとコート。染めた髪も同じ色合い。潮風に激しくなびくスカーフを頭に巻き付け「こういう姿で映るのもいい」とふざける。彼女が惹かれるのは「動くもの」や「周囲の人」だ。
楽しいものって発想と行動力で作れるんだなあと感動させられた。しかもそれらがCGなどの技術でなく、リアルタイムでカメラの前に現れる面白さ!
アニエス自身が普段着で、あるいは衣装を身につけ、喋り、動き、過去を再現し、あるいは再現シーンの傍を通り抜ける。当時の写真や作品、撮影風景が、次から次へと「落穂拾い」さながらに画面を彩る。
パリの路地に砂浜を作り、製作会社のオフィスに見立てたシーンがとくに好きだ。「映画には資金の回収がつきもの…あるいは映画祭で賞を取るか」。砂にささった、「ドゥミと私がもらったトロフィー」の数々。
誰にも好きなもの…種類、イメージがある。アニエスは「パズル」が好きだと言う。この作品においては、彼女の手によるジェラール・フィリップの分割された写真や、「今はもう見かけない」子ども用の地図パズル(私も好きだった!)などが例として登場する。また「映画なんて出来るの?断片しか撮ってないのに」と冗談めかして言われた彼女は、「映画はパズルのようなもの」と返す。
観ているうちに、この作品自体がパズルのようなものに感じられた(埋まっていくのがきっちり年代順だけども)。また、ある作家の全ての作品、あるいは世の諸々の作品が、全体でパズルのように何かを成すのではないかと思わせられた。
「モノクロでお金を掛けず」と頼まれた「5時から7時までのクレオ」(私が初めて観た彼女の作品。といっても他にあまり観てないけど)の撮影話あたりから、ちょっとした映画史を垣間見ることができる。名だたる映画人が出てくるのを見るだけで面白い。
ノミの市で、パートナーだった故ジャック・ドゥミと自分自身の「映画カード」を見つけるシーンには胸がつまった。「ジャック・ドゥミの少年期」の撮影中、彼の手を取りながらカメラに向かう写真も印象的。
アメリカを訪れたアニエスが、でかいパンケーキを手づかみで助監督によこした後、コーヒーに浸したナプキンで口をぬぐう姿に少々ぎょっとさせられ、晩年のドゥミが、カップのソーサーで猫にミルクをやる姿に頬がゆるんだ。
アニエスは「映画とは…」と語ることはしない(「映像に言葉が付いているだけではない」というようなことは言う)。「映画の内側の人」は、そんなことを語る必要がないのかもしれない、と思っていたら、ラストシーンで「映画の中に住む」(観てのお楽しみ)が出てきたので、びっくりしてしまった。
(09/10/14・岩波ホール)
ATOM (2008/アメリカ/監督デビッド・パワーズ)
公開初日、ユナイテッド・シネマとしまえんにて吹替え版を観賞。
(日本での公開は吹替え版のみだと思ってけど、いま調べたら、関東では新宿ピカデリーのみ字幕版を上映。ビル・ナイやドナルド・サザーランドが喋ってるの、聴いてみたかった…)
「鉄腕アトム」についてはほぼ何も知らない。生みの親はお茶の水博士で、「悪者」が現れると戦いに赴く…というような内容だと思っていた。
この映画は(手塚治虫の原作ともまた違うようだけど)、人間とロボットとの要素を合わせ持つ「アトム」が、自分の居場所を見つける話。盛り沢山の内容がうまくまとまってるけど、心理描写はあっさりしている。でも観ていて少々の哀しさを感じた。
冒頭、色々あって生み出されたアトム(この時点では「アトム」じゃないけど)と「父親」のテンマ博士との二人きりのシーンには、息苦しいほどの閉塞感を覚えた。少年は必然的に放り出され、世界を広げ、やがて「自分の居場所」を見つける。
当初アトムは、自らがロボットだと気付かない。自覚したらどうなっちゃうんだろう、とはらはらしていたら、大して驚かず、悩みもせず、空を舞い岩を砕いて、無邪気に飛びまわる。このシーンにはびっくりしてしまった。
ラストシーンで「これがぼくの使命なんだから」と「皆の敵」に向かっていく姿には、彼がまだ…永遠に「子ども」であるのをいいことに、世の中が「町のヒーロー」を持ち上げているように感じ、少し哀しくなってしまった。あるいはこういうのって、宗教的な感覚なのかな?よく分からない…
自らも気付いていない身体の機能が、状況によって意思と関係なく発露してしまう、というシーンには、何とはなしに性的なものを感じた。マシンガンが尻に付いてるから、というわけじゃないけど(笑)
絵柄にはあまり馴染めなかったけど、登場人物はわりと無国籍風。一筆ですっと描かれたようなアトムのアイライン?と眉毛には、オリエンタルな感じを受けた。
(09/10/11・ユナイテッドシネマとしまえん)
ムルと子犬 (2008/フィンランド/監督カイサ・ラスティモ)
ほのぼのとした作品ながら、ペットを飼うことの空恐ろしさを感じてしまった…ので記録。
 フィンランドに暮らす7歳のムルのもとに、父親が子犬を持ち帰る。「ミルスキィ」(嵐)と名付けられたその犬は、「最も凶暴」とされるコーカサス・シェパードだった。
フィンランドに暮らす7歳のムルのもとに、父親が子犬を持ち帰る。「ミルスキィ」(嵐)と名付けられたその犬は、「最も凶暴」とされるコーカサス・シェパードだった。
バイオリニストの父親は、仕事先のベルリンで処分されそうになっていた子犬を可哀そうに思い連れ帰るが、犬種も調べなければしつけもしない。ムルが「ミルスキィのパパとママ」へ宛てた手紙に、サンタさんよろしく都合のいい返事をする(ミルスキィがムルの人形を壊してしまうと「まだ子どもだから大目にみてやって」という具合)あたりで、不穏なものを感じていると、案の定、大きく育った犬は家族の手に余るようになる。それでも父親は、しつけの重要性を説く専門家に対し「家族の序列だなんて…うちは皆平等です」と言ってのける始末。
ペットと一緒に問題なく暮らせるのって、たまたま条件が整った場合なんだなあと思わせられる。またペットであれ何であれ、新たな要素が加わることによって、人間関係って変化していくものだ。
ミルスキィの出自は、亡命者を捕えるために訓練される「スターリンの犬」。ベルリンの壁崩壊と共に役目を失い、処分されそうになっていた。作中では、そのことを知ったムルが学校の先生に「スターリンって何ですか?」と聞き、自分でも本で調べるが、話の展開にはあまり関わってこない。でもこういう犬が出てくる映画って、他にあったかな?
監督は「ヘイフラワーとキルトシュー」のカイサ・ラスティモ。私としてはこちらの方が、フィンランドの普通の家庭(姉の恋人いわく「中流」)の暮らしが垣間見えて楽しい。子どもの金切り声がうるさくてカンに障るけど(リアルではある・笑)
ムルの姉の「パンクロッカー」なボーイフレンドが可愛い。よく見るとデコも広いし大したルックスじゃないんだけど、純朴な感じが良く、忘れかけてた心のドアから久々に侵入された感じ(笑)
(09/10/01)
カイジ 人生逆転ゲーム (2009/日本/監督佐藤東弥)
試写会にて観賞。終了時に拍手が起こってた。私も楽しかった。
(藤原竜也と松ケンが並んで鉄骨渡るシーンを見られただけで嬉しいかも・笑)
30目前のフリーター・伊藤カイジ(藤原竜也)は、知人の借金の保証人になったことから多額の負債を背負わされ、半ば強制的にギャンブルクルーズに参加することになる。
原作のギャンブル「限定ジャンケン」「鉄骨渡り」「Eカード」、間に地下労働の部分を挟んで映画化。身体的に残酷な部分はカット。
展開は早く、冒頭数分でカイジは「エスポワール」に乗り込む。一試合に掛けられる時間も短いけど(ほぼリアルタイム進行)、内容をうまく省略・変更してるな〜と思った。もっとも次から次へと繰り出す(繰り出さざるを得ない)戦略や、「本当の敵」を討つための命がけの戦い、という部分も省略されているため、カイジのキャラクターはごく普通の青年といったふう。
全体の印象は、悪い意味でなく「藤原竜也一座の公演」といった感じ。冒頭に相対する天海祐希を始め、出てくる誰もかれもが、彼の周囲で舞台っぽい演技をする。皆上手いし、荒唐無稽な話だからそのほうが観易い。藤原竜也の現実味の無さ、痛めつけられてもあまり悲惨でない、くさってもどこか愛嬌のある雰囲気も合っている。
漫画「カイジ」から私が受ける第一の印象は、「自分で考えて自分で決めることが何より大切」ということだけど、映画にそういう要素はない。ギャンブルでしか味わえないであろう心の動きもそう描かれない。
その代わり、鉄骨上でのカイジと石田のおっさん(光石研)とのやりとり(それだけ喋れるならもっと頑張れと言いたくなる)や、Eカード対決に臨むカイジに対する労働者達の応援(これは有り得なさすぎ!)、搾取側へのカイジの叫び(何を言ってるか所々分からず)など、「仲間との心のつながり」「非情な人間への非難」といったものが盛り込まれている(だから奴隷が皇帝を討つという「Eカード」の仕組みがやたら強調される)。
更には遠藤(天海祐希)がかなり大きな役割を果たす。このキャラクターのおかげで、映画はさわやか・ほのぼのともいえる終わりを迎える。
原作とは関係なく、細かなことながら引っ掛かる場面も色々あったけど、一番気になったのは、鉄骨渡りのシーンにおいて、参加者が「俺も」「俺も」と言いながらチケットを掲げる場面。どう考えても変だ。
漫画の「比喩を実際にやってるコマ」(「泥沼にはまる」というので沼にはまったり、「煮え湯を飲まされる」というのでお湯飲んだりしてる絵のこと)が映像になったら面白いなと思ってたけど、それはなかった(笑)
(09/09/28・新宿厚生年金会館試写会)
BALLAD 名もなき恋のうた (2009/日本/監督山崎貴)
戦国時代にタイムスリップした少年とその家族が、小国の武士たちと一時をすごす話。
クレヨンしんちゃんの劇場版シリーズは「オトナ帝国」しか観たことがない。この映画の原案「戦国大合戦」も観てみようかな?
まず面白かったのは、作品のかなりの部分を占める戦闘シーン。サブタイトル通り「名もなき」国同士の戦いだから、規模が小さく、見ていて楽しい。「レッドクリフ」のように画面の見渡す限り人・人・人…ということはなく、全員が何をしてるか分かる。春日のお城の、大家族が暮らす砦といった感じの素朴さも魅力的だ。
疲れ切ってよれよれの者同士のやりとりや終盤の長い槍での攻撃などは、これまであまり目にしたことがなく、本当にこうだったのかも、なんて思ってしまった。「戦に関わる者は皆勘定に入れる」という又兵衛(草なぎ剛)のセリフや、それを裏付ける炊き出しの描写も楽しい。戦闘中の城内の様子に、なぜか「ワイルドバンチ」の村を思い出してしまった(笑)
それから、これは「クレヨンしんちゃん」、あるいは漫画・アニメというジャンルの味なのかもしれないけど、タイムスリップの扱いが大仰じゃないところが好み。タイムパラドックス?の数々は、あまりにもあっさり回収される。石仏の傍でしんちゃんがあるものを取り出した際には、「え〜これだったの?」と声をあげて笑ってしまった。
戦国時代に現代人がクルマで乗り込めば、びっくりされるに決まってる。それをそのまんま描く楽しさ。しんちゃん一家が過去で活躍できるのは、たんに未来人だから。それが良かった。戦いに明け暮れる時代に生きてるわけじゃないんだから、あんなに「普通」でいいんだ。
主役の男の子は、左目だけまつげがくるんとしてる。これまで「逃げて」ばかりだったしんちゃんが何事にも立ち向かうようになる、というのもテーマのようだったけど、そこのところはよく分からなかった。
しんちゃんの両親を演じた筒井道隆と夏川結衣は、くたびれ具合がいい。目が血走って見えたのは気のせい?春日の城主(中村敦夫)に対し「現代にはあなたたちの名は残っていません」というようなことをあっさり口にしてしまう(これはとても重要なシーン)、気のきかない可笑しさも、筒井道隆の朴訥なな感じに合っていた。
又兵衛の弟分(家来の息子)の文四郎を演じた吉武怜朗も印象的。戦場では気合十分で構えてるのに、まだこわっぱで誰からも狙われず、一人空回りしてるのが可愛い。ちなみに敵方の大沢たかおの陣営にもまだ幼な顔の少年がいて、映画では珍しいなと思った。
エンドロールの映像中、武士たちが現代のあるものに触れる場面で、「原始のマン」の同じようなシーンを思い出した。「原始のマン」のあれは、私にとって「観ると元気になれる映画のシーン」の永久第一位だから(それほどブレンダン・フレイザーが超・超キュートだから)、この映画のあれだってもっと可愛らしく撮れただろう、と思ってしまった(笑)
(09/09/23・新宿ピカデリー)
リミッツ・オブ・コントロール (2008/アメリカ/監督ジム・ジャームッシュ)
「最高の映画とは、決して見なかった夢のこと」
 「夢」という言葉が、(少なくとも日本語と英語では?)眠っているときのあれと、こうなりたいと望む自分の姿とを表すなんて、考えたら混乱する。
「夢」という言葉が、(少なくとも日本語と英語では?)眠っているときのあれと、こうなりたいと望む自分の姿とを表すなんて、考えたら混乱する。
予告編もチラシも目にしなかったので、当日まで、ジャームッシュの新作が公開されてるなんて知らなかった。劇場は結構混んでいた。
とある仕事を請け負った男が、スペインを訪れ、幾人かの仲間と接触を繰り返した後、目的を達する話。
話は同じことの繰り返しで、サスペンスもゆるやかなので、寝不足もあり少しうとうとしてしまったけど、映像と音楽が力強く惹きつけられた。
オープニングの映像には少し意外な感じを受けたけど、その後に映る主人公(以前の作品でも見かけた俳優)の顔、彼が去った後の空間、全てがジャームッシュ。そして会話があり、音楽が流れ、旅が始まる。想像力でどこへでも行ける。
主人公に順に接触してくる仲間たちが豪華キャストだ。登場する際、主人公側からの視点でなく、彼等の背後からのショットで登場するのに、心がぐらっと動かされる。
中でもティルダ・スウィントンは、ヘアメイクのせいか?エルフみたいで、これまでで一番可愛らしく見えた(だからこの作品がベストってことじゃなく、単純に、可愛く見えて楽しかったということ)。
ジョン・ハートが「美しい映画を観たんだ、フィンランドの…」というのは、勿論アキ・カウリスマキの「ラヴィ・ド・ボエーム」のこと。このシーン(セリフ)が一番興奮したかも(笑)
(09/09/21・バルト9)
オー!マイ・ゴースト (2008/アメリカ/監督デヴィッド・コープ)
オープニングタイトルにビートルズの「I'm looking through you」が流れるのが、タイムリーで楽しい。
 歯科医のピンカス(リッキー・ジャーヴェイス)は、仮死状態を体験後、自分にしか見えない人々の存在に気付く。ニューヨークの街中をうろつく彼等は、現世に未練を残す「幽霊」たち。問題を解消してくれとピンカスを追い掛け回し列を成すが、人間嫌いの彼は相手にしない。しかし、とりわけしつこいフランク(グレッグ・キニア)の、「妻(ティア・レオーニ)の再婚を阻止してくれ」という頼みに乗ることに。
歯科医のピンカス(リッキー・ジャーヴェイス)は、仮死状態を体験後、自分にしか見えない人々の存在に気付く。ニューヨークの街中をうろつく彼等は、現世に未練を残す「幽霊」たち。問題を解消してくれとピンカスを追い掛け回し列を成すが、人間嫌いの彼は相手にしない。しかし、とりわけしつこいフランク(グレッグ・キニア)の、「妻(ティア・レオーニ)の再婚を阻止してくれ」という頼みに乗ることに。
リッキー・ジャーヴェイス演じる主人公のヘアメイクや、マンハッタンの集合住宅の雰囲気も手伝って、全体の雰囲気はクラシカルな「幽霊譚」という感じ。
でも登場人物の言動は極めてコメディ仕様で、周囲に対するピンカスの言動などいちいち可笑しく(病院での受付での一幕など)、「人間嫌いの偏屈男」が次第に心を開いていく…という話にも関わらず、あんなに頭使って口も動かすなんて、人間嫌いというより、世の中とセンスが合わないだけじゃん?と思えてしまう。もっとも映画を観る身としては、必ずしも現実味を感じたいわけじゃないけど(笑)
ピンカス自身だけでなく、周囲の方も少々現実離れしており、例えば彼が仮死状態となるのは自身が掛かった病院の医療ミスが原因なんだけど、病院側とのやりとりは「麻酔医と話させろ!」「うちの病院は3回失敗するとクビになるので…(もうおりません)」という具合。「必ず同時に口を開く」シーンも笑える(ああいうスケッチってあるのかな?あの「先生」はきっとコメディアンだ)。調子のいいグレッグ・キニアも、その妻で一本気ぽい学者のティア・レオーニも、枠の中におさまってるタイプじゃない。
嫌な人って、普通の人って何だろう?ピンカスは嫌な奴というより、いつも苛々してるだけだ。そういうのが「変な奴」と呼ばれる。
…なんて、ケチばかり付けてるみたいだけど、キャストが良いので観ていて楽しい。なぜかBGMを「実際に演奏してる人」がいるのも楽しい。
「名案ってのは、最初は突飛に聞こえるものさ」(←「名案」を聞いてつい驚いてしまった側が言うべきセリフ・笑)
(09/09/13)
幸せはシャンソニア劇場から (2008/フランス-ドイツ-チェコ/監督クリストフ・バラティエ)
39年のパリ。下町に建つ「シャンソニア劇場」が、不況で閉館に追い込まれた。裏方のピゴワル(ジェラール・ジュニョ)は、別れた妻に息子を取られたことでやけっぱちになり、仲間と共に再建を宣言する。
フランス映画には詳しくないけど、昨年劇場で「赤い風船」を観てから、パリが舞台のどんな映画を観ても、あの幾つかのシーンを思い出してしまう。今回もそうだった。「パリを一望する」シーンなど、やりすぎなほどキレイ。最初は三谷幸喜の「マジックアワー」のセットが頭をよぎったけど(笑)
「フランス」に関する知識が多い方が楽しめるだろうなと思う所がいくつかあった。
冒頭、警察に取り調べを受けるピゴワル。「私は下町の出だ」「どこの下町だ?」「『下町』は一つしかない」…このニュアンスが私には分からなかった。ちなみに原題は、劇場の名である「faubourg36」(faubourg=下町)。
「ものまね王子」が無知をいいことに演じさせられる政治コントの内容も、ピンとこなかった(これは笑いのセンスの問題?)。最後に彼は檀上で反抗する。無知であっても、いやなやつというのは分かる。
労使交渉により「週40時間労働、土曜は休日、有給休暇は2週間」という条件を勝ち取るシーンには、70年前にこれかあと、日本との違いを感じてしまった(人生のほとんどは働いてない私が言うことじゃないけど・笑)
映画の「紅一点」は歌姫のドゥース。恋人と逢い引きする際の芝居がかった登場の仕方に、昔読んだ「日本人は女の顔を上から見るのを好むが、フランス人は下から見上げるのを好む」という文章をまた思い出した。
終盤、舞台で歌う彼女の顔がアップで延々と流れるシーンは怖かった。造作がどうというわけではなく、一つの顔ばかり見てると、頭の中の認識装置?がおかしくなってくる。映画において、こういうことってたまにある。
ピゴワルの息子ジョジョを演じたのは、ジャック・ペランの息子のマクサン・ペラン。資産家と再婚した母の元では全然ぱっとしないのに、髪を乱した下町っ子の時はとてもキュートだ。
フランス映画らしいといえばそうなのかもしれないけど、劇場に立つ役者は、ドゥースの歌以外大した芸もなく、ショーのシーンもそう多くない。終盤いきなり、裏方だったピゴワルや闘士?のミルーが役者として活躍し出すのが可笑しい。また、ラストシーン自体が、最後を飾る「ショー」のように演出されており、楽しかった。
(09/09/07・シネスイッチ銀座)
キャデラック・レコード〜音楽でアメリカを変えた人々の物語〜 (2008/アメリカ/監督)
40年代の終わりに誕生した「チェス・レコード」の興亡を描いた作品。創設者レナード・チェス(エイドリアン・ブロディ)とマディ・ウォーターズ(ジェフリー・ライト)を中心に、リトル・ウォルター(コロンバス・ショート)、チャック・ベリー(モス・デフ)などが登場する。
 「ブルースは不条理を歌うものだ」…とは作中のマディ・ウォーターズの言。英語で何と言ってたか分からないけど、哲学的な意味ではなく、黒人の立場のことを指してるんだろう。
「ブルースは不条理を歌うものだ」…とは作中のマディ・ウォーターズの言。英語で何と言ってたか分からないけど、哲学的な意味ではなく、黒人の立場のことを指してるんだろう。
登場人物もエピソードも多いので、全ての描写がさらっとしており、レナードとミュージシャン達の間の溝が深まっていく過程がよく分からなかった。中盤、実の母親を亡くしたウォルターにマディが言葉を掛ける場面のちょっとした説教臭さや、「レニもガールハントに精を出していた」というナレーション→エタ・ジェイムス(ビヨンセ・ノウルズ)登場、というようなユーモア?センスなどもあまり好みじゃない。でも音楽が色々流れて楽しかった。
ビヨンセの存在がかっこよくて見とれた。私はエタ・ジェイムスについてよく知らないんだけど、作中披露されるのがいずれも「恋に破れた」女の心情を歌ったものだったので、ブルースってそういうものなんだろうか(そういうのが好まれたんだろうか)?と思った。ビヨンセの声ってどうしても「現代」っぽく聴こえて、ああいう歌詞にはそぐわなく感じる。
登場人物の多さに加え、作中わりと時間が経ってから登場することもあり、彼女についての描写はそれほど深くない。そのため、薬物に倒れたエタと、介抱しに駆け付けるレナードとの暖呂前でのシーンは唐突に感じられた。でも、二人の顔がドアップで延々と映るだけのその場面が、一番印象に残った。少ししか関わりがなくても、(性的な意味でなく、もしくは身体的でなくてもそれ以上に性的な)濃密な関係ってあり得るから、あれはそういうことなんだ、と勝手に解釈すると、心動かされた。
(09/09/05・新宿ピカデリー)
グッド・バッド・ウィアード (2008/韓国/監督キム・ジウン)
1930年代の満州を舞台に、「いい奴」の賞金稼ぎ(チョン・ウソン)、「悪い奴」のギャングのボス(イ・ビョンホン)、「へんな奴」の泥棒(ソン・ガンホ)が宝の地図をめぐって争う韓流ウエスタン。
 冒頭、仕事の依頼を受けたイ・ビョンホンが、差し出された乗車券にナイフで切りつけ「こんなものはいらない、自分で止める」と言うのに心が躍った。
冒頭、仕事の依頼を受けたイ・ビョンホンが、差し出された乗車券にナイフで切りつけ「こんなものはいらない、自分で止める」と言うのに心が躍った。
1対1対1の話だと思ってたのが、イ・ビョンホンに大勢の手下、ガンホには相棒がいるのに拍子抜けした。とにかく登場人物が多くて、「悲しき願い」に乗せての追跡劇は、グッド&バッド&ウィアード、よく分からない人達、更には日本軍が入り乱れて、ウエスタン版キャノンボールといった感じ。
死んでいく人の数も相当なもの。作中最初に「無抵抗の人を大勢殺す」のがガンホだというのが、ちょっと面白い。
せっかく複数の男が出ていても、絡みがなければ面白さは半減だ。対面すればいいってもんじゃない、互いに「意識」してる感じが欲しい。それが足りないんだよな〜と思っていたら、唐突に「ヤツ」の名前をつぶやくシーンがあって笑ってしまった。最後にその理由である因縁が明かされるんだけど、取ってつけたようで全然ロマンや色気がない。
そのつまらなさを偶然救っているのがイ・ビョンホンの浮きっぷりで、他の二人とは…というより見渡す限りの人間とはセンスも違えば話も通じず(ガンホは「話の通じない『やつら』だな〜」とあきれるが)、一人プレイのあげく、「合わないならオレに合わせろ!」と強引に割り込んでくる。あんなに(「悪い」というより)「異常」な奴なら、絡みがなくてもしょうがない、と思わせられる。かっこいいお坊ちゃんが、普通の遊びをしているクラスメイトの中に入りたいんだけど世界が違いぎくしゃくしてしまう、という雰囲気が醸し出されており可笑しい。
予告編にある、イ・ビョンホンが纏っているものを脱ぎ捨てる場面は、ストーリーに全く関係ないサービスシーンだった(笑)
チョン・ウソンはさり気なくガタイがいい。寝転がってガンホを狙うときのお尻に見とれた。ロープにぶらさがっての、また馬上からの射撃シーンもかっこよかった。
ソン・ガンホは演技でも食べ方が汚すぎ(笑)跳び蹴りの後、自分も倒れるのが良かった。
(09/09/01・バルト9)
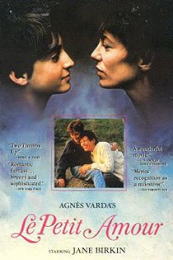 ジェーン・バーキン原案による作品。バーキン演じるマリ・ジェーンが、娘の同級生の少年と恋に落ちる。
ジェーン・バーキン原案による作品。バーキン演じるマリ・ジェーンが、娘の同級生の少年と恋に落ちる。 母親が管理しようとしていたのは、意図的に産んだアナの体と心だけではなかった…ということに気付いた時の衝撃。自分の鈍さにショックを受けた。少し考えれば想像できることなのに、途中まで思い及ばなかった。ケイトが最後に母親にかける言葉に、あんな「よく出来た」子どもがいるだろうか?と思いつつ、涙がこぼれた。
母親が管理しようとしていたのは、意図的に産んだアナの体と心だけではなかった…ということに気付いた時の衝撃。自分の鈍さにショックを受けた。少し考えれば想像できることなのに、途中まで思い及ばなかった。ケイトが最後に母親にかける言葉に、あんな「よく出来た」子どもがいるだろうか?と思いつつ、涙がこぼれた。 原題は「El pollo, el pez y el cangrejo real」…鶏肉、魚、そして蟹。作中思い出したように、テーマ食材であるおひょいとタラバガニ、鶏の産地が紹介される。ノルウェーにあるおひょいの養殖場(右写真)は、地球の果てって感じで心奪われた。
原題は「El pollo, el pez y el cangrejo real」…鶏肉、魚、そして蟹。作中思い出したように、テーマ食材であるおひょいとタラバガニ、鶏の産地が紹介される。ノルウェーにあるおひょいの養殖場(右写真)は、地球の果てって感じで心奪われた。 冒頭、浜辺に登場するアニエスは、ワインレッドのスカーフとコート。染めた髪も同じ色合い。潮風に激しくなびくスカーフを頭に巻き付け「こういう姿で映るのもいい」とふざける。彼女が惹かれるのは「動くもの」や「周囲の人」だ。
冒頭、浜辺に登場するアニエスは、ワインレッドのスカーフとコート。染めた髪も同じ色合い。潮風に激しくなびくスカーフを頭に巻き付け「こういう姿で映るのもいい」とふざける。彼女が惹かれるのは「動くもの」や「周囲の人」だ。 フィンランドに暮らす7歳のムルのもとに、父親が子犬を持ち帰る。「ミルスキィ」(嵐)と名付けられたその犬は、「最も凶暴」とされるコーカサス・シェパードだった。
フィンランドに暮らす7歳のムルのもとに、父親が子犬を持ち帰る。「ミルスキィ」(嵐)と名付けられたその犬は、「最も凶暴」とされるコーカサス・シェパードだった。 「夢」という言葉が、(少なくとも日本語と英語では?)眠っているときのあれと、こうなりたいと望む自分の姿とを表すなんて、考えたら混乱する。
「夢」という言葉が、(少なくとも日本語と英語では?)眠っているときのあれと、こうなりたいと望む自分の姿とを表すなんて、考えたら混乱する。 歯科医のピンカス(リッキー・ジャーヴェイス)は、仮死状態を体験後、自分にしか見えない人々の存在に気付く。ニューヨークの街中をうろつく彼等は、現世に未練を残す「幽霊」たち。問題を解消してくれとピンカスを追い掛け回し列を成すが、人間嫌いの彼は相手にしない。しかし、とりわけしつこいフランク(グレッグ・キニア)の、「妻(ティア・レオーニ)の再婚を阻止してくれ」という頼みに乗ることに。
歯科医のピンカス(リッキー・ジャーヴェイス)は、仮死状態を体験後、自分にしか見えない人々の存在に気付く。ニューヨークの街中をうろつく彼等は、現世に未練を残す「幽霊」たち。問題を解消してくれとピンカスを追い掛け回し列を成すが、人間嫌いの彼は相手にしない。しかし、とりわけしつこいフランク(グレッグ・キニア)の、「妻(ティア・レオーニ)の再婚を阻止してくれ」という頼みに乗ることに。 「ブルースは不条理を歌うものだ」…とは作中のマディ・ウォーターズの言。英語で何と言ってたか分からないけど、哲学的な意味ではなく、黒人の立場のことを指してるんだろう。
「ブルースは不条理を歌うものだ」…とは作中のマディ・ウォーターズの言。英語で何と言ってたか分からないけど、哲学的な意味ではなく、黒人の立場のことを指してるんだろう。 冒頭、仕事の依頼を受けたイ・ビョンホンが、差し出された乗車券にナイフで切りつけ「こんなものはいらない、自分で止める」と言うのに心が躍った。
冒頭、仕事の依頼を受けたイ・ビョンホンが、差し出された乗車券にナイフで切りつけ「こんなものはいらない、自分で止める」と言うのに心が躍った。