映画メモ 2009年5・6月
(劇場・レンタル鑑賞の記録、お気に入り作品の紹介など。はてなダイアリーからの抜書です)
人生に乾杯! / MW -ムウ- / 築城せよ! / 真夏のオリオン / レスラー / サガン―悲しみよこんにちは― / ターミネーター4 / 消されたヘッドライン / ベルサイユの子 / スター・トレック / セブンティーン・アゲイン / 夏時間の庭 / 天使と悪魔 / ウォーロード/男たちの誓い / チェイサー / ある公爵夫人の生涯
人生に乾杯! (2007/ハンガリー/監督ガーボル・ロホニ)
81歳のエミルと70歳のヘディは二人暮らし。年金だけでの生活は難しく、とうとう思い出のイヤリングまで手放すはめに。エミルは愛車のチャイカを飛ばし、強盗の旅に出る。
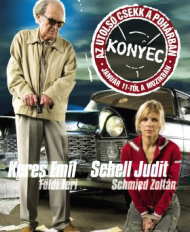 予告編やチラシからイメージするより、ずいぶんハードボイルドな映画だった(逆に言うなら、日本の予告編は、うまく切り取って「ほのぼの感」を出してるなと感心した・笑/画像はハンガリー本国のポスター)
予告編やチラシからイメージするより、ずいぶんハードボイルドな映画だった(逆に言うなら、日本の予告編は、うまく切り取って「ほのぼの感」を出してるなと感心した・笑/画像はハンガリー本国のポスター)
冒頭、あれこれあってヘディが自宅の玄関を開けると、エミルは持病の腰を痛めて身動きとれずにいる。大きな容器から薬を出して塗ってやる。いきなり「年を取ることの大変さ」を見せつけられ、どきっとしてしまった。
彼等は二人だから、助け合って何とかやっている。しかし途中何度か、「二人」でいることの怖さを感じる場面もあった。ふとしたことで、どこかに帰りたくなる時だってあるけど、「二人」で生きていたんでは、帰るところがない。あぐらをかいて、覚悟するしかない。
少なくともこの映画で見るハンガリーは、何もかもが古い。「誰もいない」銀行、バンガローのしょぼさ。二人が泊まるホテルも、室内はそれなりに充実してるのに、外観は素っ気ないマンションのようだ。また二人のニュースを流す「テレビ」が何度も出てくるけど、どれもこれも古い(ホテルのものなんてモノクロ!)。
ただ、「年金が少なくてお金が足りない」なんて大変だなあと思ったけど、自宅での食事シーンなどがないため生活感が伝わってこず、いまいちぴんとこなかった。
印象的だったのは、「セックスで男から金をとる女」が何度も出てくること。まずは冒頭、「男の集まり」に呼ばれて仕事をこなすストリッパー(このシーンが妙に長い)、次に一仕事終えてモーテルの前に車を泊めたエミルに「15なんとか(これが幾らくらいなのか?知りたかった・笑)で90分」と話をもちかけてくる売春婦、最後に二人が泊まったホテルのプールサイドで「男の人はマッサージが好き」と声をかけてくるアジア系の女性。そして、いずれの場合も一応、男の方に気がないという結果になる。何か示唆的なものを感じた。
(09/06/27・シネスイッチ銀座)
MW -ムウ- (2009/日本/監督岩本仁志)
とても面白かった。疑問に思うシーンも吹き出しちゃうようなシーンも多いし、音楽は煩いし、冒頭の長丁場のアクションシーンには飽きちゃったし、クライマックスでは何をやってるのかよく分からかったけど、ともかく観ていて楽しかった。最初から最後まで、玉木宏を応援してた。
16年前、離島で兵器がらみの虐殺事件が起こり、政府によって隠蔽される。唯一逃げ延びたのが結城美知夫(玉木宏)と、彼に助けられた賀来裕太郎(山田孝之)。現在、結城は銀行員として社会生活を送りつつ凶悪犯罪を重ね、牧師となった賀来は悩みつつもそれを手助けしていた。
ストーリーは手塚治虫の原作にかなり忠実だけど、性的な部分をそっくり避けているので、全くの別物になっている。だから私が感じた楽しさは、原作の面白さを味わえた、というのではなく、たんに映画として面白かった、ということだ。
かりに原作の「年長の男が少年をレイプ」「女とみまがう美少年」という要素をそのまま観せられたら、陳腐で古臭く感じてしまうだろう。他の諸々の要素についても、実際に体感するならともかく、少なくとも普通の映画においては、分かりやすい「猟奇」にはいやらしさを感じない。
また原作では、美知夫は賀来を誘惑するときは「女」になって「抱いて」と迫り、女性を誘惑するときは「狼」になって(実際に狼として描かれてるコマがある)絶倫ぶりを発揮する。こういうふうに男女の役割が(その実態が男であれ女であれ)きっちり分かれてるというのも、映画で描くには古臭い。
(そもそもフィクション中の「同性愛」に関わる男が、女っぽいか、あるいは過剰に男っぽいのは、異性愛者が「『普通』じゃないならしょうがない」と納得するための装置でもあるんじゃないか?/「ムウ」原作の場合、漫画ならではの表現で、美智雄の女装が通用することが面白い要素になってるけど)
「命の恩人」という条件はあれど、ただ二人の男がいる、というだけの本作はエロい。「直接描写ができないからなんとか…」というわざとらしいシーンも幾つかあるけど、馬鹿馬鹿しい感じはしない。作中二人が初めて対面する場面(原作と通じる)はとても素敵だし、息も絶え絶えな美知夫が明日の悪事について告げる場面も良い。
作中の毒ガス兵器・ムウにことごとく「ムウ」の表記があるのには笑ってしまった。映画版には美知夫が賀来や女性を性的に誘惑する描写は無いんだから、彼が執着する「ムウ」自体、あるいは彼とそれとの関係くらい、エロティックであればよかったと思う。
玉木宏も山田孝之も、シルエットだけで誰と分かる役者さんだ。実際、暗がりからの登場シーンが多い。
それにしても玉木宏の顔の小ささには度肝を抜かれた。石橋凌と初対面のシーンでは、いったい何が起こったんだと思ってしまった。それにルックスが漫画っぽく、眼鏡をかけた顔つきや寝姿は、原作の美智雄にそっくり。
石田ゆり子は、「頑張れば報われる」世界の人、というイメージがあったので、私には意外な起用だった。新聞記者である彼女と後輩との関係に、数週間前に観た「消されたヘッドライン」を思い出した。私は男が後輩っていう映画の方が好き(笑)
(09/06/22・よみうりホール試写会)
築城せよ! (2009/日本/監督古波津陽)
以前チラシを見掛けて、一人でお城を作った郵便配達人シュヴァルの話みたいだな、と思い興味を持った。観てみたら、愛工大が中心となって制作(リメイク)した作品で、舞台は愛知県猿投地区の架空の町・猿投(ロケ地は瀬戸市)。出演者の多くは住民や大学関係者たち。(愛知出身の)私にもあまり馴染みのない場所だけど、一箇所だけわざとらしい名古屋弁が聴けた(笑)
 猿投の領主と部下の霊が現代に蘇り、400年前に潰えた築城の夢を果たそうとする。とあるヒントから導き出されたその材料は、段ボール。領主の熱意に心打たれた町民らの手で計画が進むが、同地に工場誘致をもくろむ行政側は、城を壊そうとたくらむ。
猿投の領主と部下の霊が現代に蘇り、400年前に潰えた築城の夢を果たそうとする。とあるヒントから導き出されたその材料は、段ボール。領主の熱意に心打たれた町民らの手で計画が進むが、同地に工場誘致をもくろむ行政側は、城を壊そうとたくらむ。
観ていて、80年代の映画館にタイムスリップしたような感じがした。BGMは控え目だし映像も素朴。領主の恩大寺(片岡愛之助)と岩手教授(津村鷹志)が、過疎の町を通り過ぎる高速道路を眺める場面など、本当に「そのへんの田舎」の一コマだけど、悪くない。クライマックスで「こんなにきれいだったなんて…」と言われる夜景は、そんなセリフさえなきゃと思わせられたけど(笑)
映画の中の建築というと、大好きな「刑事ジョン・ブック 目撃者」でアーミッシュたち(と主役のハリソン・フォード)が納屋を建てるシーンが一番に思い出される。気ごころの知れた仲間が協力して力仕事をする。
この作品では、領主の目的はたんに「城を作る」こと…さらに言うなら、住民たちが自分に賛同して心を合わせ築城すること…である(だからしゃちほこが画竜点睛として大きな意味を持つ)。「敵」の狙いもシンプルで、とにかく人力でもって城を破壊しようとする。画面の中に、字面そのままの「作る」と「壊す」が現れるのが気持ちいい。ただし「お城」「段ボール」にまつわる建築のあれこれが殆ど描かれないため、そういう方面の好奇心は満たされないけど。
そしてラスト、築城の舞台となった土地は、使い道の決まらないまま住民の手に戻ってくる。
冒頭、建築学科の教授である藤田朋子が板書をしつつ、授業を抜け出すナツキを咎めるシーンの古臭いギャグ?センスに心が冷えてしまったけど、そのうち慣れてきた。エキストラの子ども達の自然な感じも良い。
キャラクターに悪人がいないのもいい。「敵」の町長(江守徹)も自分なりに町のためを思っている。城を壊す一般市民たちは、そうと知らず無邪気に彼の「手下」となる。
領主(領主に体を乗っ取られた青年)を演じた片岡愛之助の演技は「安心」の一言で、霊が去った後の別人ぶりもすごいけど、がっしりしたふくらはぎの立ち姿は、肉体を遣う役者さんだなと思わせられた。
愛知県内の女子高校生は、親から「車買ったるで、うちから通える大学にしやあ」と言われる…という伝え話?がある(実際に聞いたことはない)。それを私に聞いて知ってる同居人は、ナツキが学校から帰るのに車を出すシーンで笑っていた(もちろん自分で稼いで買ったものかもしれないけど)。車通学の描写が日本映画では久々のような気がして、楽しかった。
加えて大学生活といえば、私は文学部(しかも哲学専修)に在籍してたので、建築学科の授業の様子やその団結ぶりも、よくある描写ながら面白かった。
(09/06/20・新宿ピカデリー)
真夏のオリオン (2009/日本/監督篠原哲雄)
あまりいい意味じゃなく、こんなに分かりやすい潜水艦映画は初めてだと思った。戦争映画って感じもしなかった。戦争映画じゃないと思えば結構面白いかも。
でも「椿三十郎」のリメイク版を観たときにも思ったけど、映画をあまり観ない人にとっては「昔の作品」というだけでとっつきにくいだろうから、面白い作品や題材を現代風に作り直すことには意義がある…って、そうしてどうなるかは分からないから、無責任な物言いだけど。
潜水艦映画好きとしては、映画のほとんどの舞台が艦の内部というのは嬉しかったけど、例えば海上からの視点で、画面に駆逐艦と潜水艦の影がばっちりおさまってるという構図は、ゲームの展開を追ってるみたい。
それから、キーとなる「真夏のオリオン」の譜面が、小学生が描いたようなものなので、出てくるたびに白けてしまった。
映画に出てくる直筆ものって結構気になる。どんな人がどういう状況で記したのか。ふと映画版「HERO」を思い出した。松たか子のつけてるノートの中身が、いかにも彼女(の演じるキャラクター)らしいものだった(というか、よく見かける感じのキャラクター、よく見かける感じの文字だったというだけか)。スタッフの誰かが書くんだろうけど、そういうときって何か含むところあるものなんだろうか?分業だからたんになぞって書くだけなのかな。「オリオン」の場合はどうだったんだろう。
(09/06/14・新宿ピカデリー)
レスラー (2008/アメリカ/監督ダーレン・アロノフスキー)
80年代に人気プロレスラーとして一世風靡したランディ(ミッキー・ローク)は、今ではトレーラーハウスを寝床に、スーパーマーケットのアルバイトで得た金を薬に変え、週末のインディーズショーに出演する日々。しかし心臓発作を起こして倒れてしまい、リングに立てば命の保証はないと宣告される。
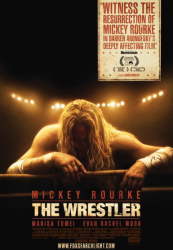 冒頭から胸がぐっとしめつけられるようで、中盤、ランディがキャシディ(マリサ・トメイ)に「息子にあげてくれ」と、冒頭に目を引いたあるものをプレゼントする場面で、涙がこぼれてしまった。
冒頭から胸がぐっとしめつけられるようで、中盤、ランディがキャシディ(マリサ・トメイ)に「息子にあげてくれ」と、冒頭に目を引いたあるものをプレゼントする場面で、涙がこぼれてしまった。
だって、あれを喜ぶと思う無邪気さ(実際喜ばれるんだけど)、また彼にとっては大切なものであり、他にあげられるものもないのだ。泣けてしまう。
映画の前半は、とあるプロレスラーの日常を追うドキュメンタリーといったかんじで進む。彼等の本当の生活がどうだか分からないけど、まずは知らない世界を覗き見できて楽しい。
「床屋」や日焼けサロンに通って自分なりのレスラー仕様の身体を保ち、ホームセンターで仲間と用具を物色。そして当日、めいめいが段取りを付け、細工を施し、試合が始まる。コメディとして撮ってるわけじゃないのに笑えてしまう。プロレスラーってそういうものなんだろうか?
(試合シーンはどれも真実味たっぷりなので、そういうの(ホチキスを打ち込まれたり)が苦手な人は注意が必要かも…同居人は始終私にしがみついてたし、隣の女性もうつむきっぱなしだった)
こんなふうに淡々と進んでいったらそれはそれで面白いなあ、と思っていたら、馴染みのストリッパーのキャシディや、離れて暮らす娘のステファニー(エヴァン・レイチェル・ウッド)が登場し、人間関係が進展する。でもそれは、あくまでもこの映画の「背景」。これは彼の物語、いいとか悪いとかでない、ああいう人間の物語だ。
当たり前ながら、ある面で素晴らしい人間が、ある人にとっていい親、いい恋人、いいパートナーであるとは限らないし、愛と呼べるものが存在しても、一緒にいることが必ずしもベストではない。めいめいが自分の選択をする結末には、とても感動した。
これはランディの物語だから、キャシディについてはほとんど描かれない。でもつい想像してしまう、毎晩あんなふうに男を誘い続けなきゃならないなんて、めんどくさくて頭が痛くなる。
映画自体じゃなく、宣伝文句の問題だけど、彼女の仕事について「ランディ同様に身体を張っている」ですまされていると、そんな簡単に説明できるものなのか?(というか、対比する必要があるのか?)と思う。「キャシディの」仕事への意識やその消費のされ方は、ランディのそれとは全然違う。問題を広げて言えば、年をとったストリッパーというテーマでこういう映画は作れないし、「女のロマン」という冗談は通じない。映画はあくまでもランディ視点で進み、そのへんはさらっと流されてるので良かった。
面白いなと思ったのは、冒頭に流れる、全盛期の彼を紹介するセリフに「真のアメリカ人…」という言葉が使われていたこと。最後の試合でも、ファンは彼を「USA!USA!」と応援する(対戦相手は「中東の怪人」)。日本なら、「真の日本人」だからといって人気が出るとは思えないから、アメリカってそういう国なんだなあと思った。
一人の人間の時間は限られており、老いは誰にも押し寄せてくる。
同居人は観終わっての感想を「感動して、じゃあ明日からがんばって創作活動するかっていうと、できないんだよなあ、それが哀しい」と言っていた。
(09/06/13・TOHOシネマズシャンテ)
サガン―悲しみよこんにちは― (2008/フランス/監督ディアーヌ・キュリス)
また「海」と「死」で終わるフランス映画を観た。
「夜会は退屈だが、印象に残る出来事もある」
 起伏やクライマックスはなく、走馬灯のように人生の出来事が描かれる。場面が切り替わると何年、何十年も経っており、生活形態が変化した理由がセリフで説明されるので唐突な感じも受けるけど、エピソードに沿って挿入されるサガン自身の文章が心地良い。
起伏やクライマックスはなく、走馬灯のように人生の出来事が描かれる。場面が切り替わると何年、何十年も経っており、生活形態が変化した理由がセリフで説明されるので唐突な感じも受けるけど、エピソードに沿って挿入されるサガン自身の文章が心地良い。
サガンの作品は、中高生の頃好きでたくさん読んだけど、今では内容を覚えていない。本人についての知識はもとより無い。でも作中引用される文章の切れ端のどれもが、心にすっと入ってきた。だから読んでたんだなあ、と思った。
(少なくとも作中では)フランスでは町や田舎の様子も人々の服装も時代差がなく、シルヴィー・テステュー演じるサガンと周囲の者だけが時を経て変わってゆく。とても「個人的」な映画だ。社会や政治の変化も描かれない。ただし、五月革命を報道するニュース番組を皆で観るが、サガンのみが皆と同調せず部屋を出るシーンがあり、実話なのか否か、なぜあのエピソードを取り入れたのか、気になった。
「寄り添う肩が欲しい、そのために人は愛するのだ
そしてそれを意識することこそ、本当の悲しみ」
彼女が最初の結婚の際に暮らす家は、静かで冷たいアパートメントだ。あんなんじゃ楽しくないよなあ、と思うけど、やはりその結婚はうまくいかない(いわく「恋の挫折は人生の挫折」)。その後、彼女は800万フランで田舎に衝動買いした家に住み続ける。「後付けの家族」にこだわり、自分の家で、自分を愛してくれる人たちと暮らそうとする。
サガンは「人生をともにする人」を求め続ける。予告編では意図的に?隠されてるけど、彼女が求めるのは「男」に限らない。ただし性行為そのものについては触れられず、いつも人恋しくてたまらず、また新しい物事にときめく快感も欲しているふうに描かれている。
サガンが最愛のペギー(ジャンヌ・バリバール)を見舞って出てくると、「新しい相手」のアンドリッドが車を泊めて待っており、どこかに出かけようと誘う、その目つきは明らかに性的なもので、このシーンのみ異質な感じがした。
フランス映画らしく、会話の数々が面白い。「意見が合わない」と思えば自ら退場して切り上げることもある。サガンとペギーが部屋の模様替えに際し、テーブルについて話し合うシーンなんて最高。
サガンを看取るのは、彼女の作品などにはおそらく興味のない、年をとった女中さんだ。普段は薬物中毒の主人の面倒を適当に見ていたらしき彼女だが、最後には「私がいます」と涙を流し、手を握る。どんな人でもあたたかさを持っており、誰かに与えることができる。
作中のサガンは、エル誌の編集長であったペギーによれば「パリで唯一の、買い物嫌いの女」だけど、初めての結婚式が白いスーツというのもすてきだし(ウェディングドレスっていいと思ったことがない)、黒いドレスなどはどれも着てみたいと思わせられた。ああいうゆったりめの服は嫌いだけど、私なら肉でちょうどよくなるだろう。裾のすぼまったパンツにペタ靴という、フランスの女の子スタイルは、出来そうもないけど(笑)予告編の最後にも挿入される、家の前の塀に横になって本を読む彼女の姿(上の画像)はやっぱりいいなあ。
(09/06/08・シネスイッチ銀座)
ターミネーター4 (2008/アメリカ/監督マックG)
「ターミネーター」って、私にとってはまず「人間っぽいけど人間じゃない機械が出てくる」というのが面白い。シュワちゃんが自分の腕を縫ったり目玉を取り出したり、データに沿った言動しかしなかったりというあたりが、ほほえましく楽しい。今回はそういうのが入る余地がなく、少し寂しかった。
それから「追われる者、追う者、守る者が一定である」ってこと。より「個人的」な話が好きだから。例えば一作目では、彼一体がサラを執拗に追ってくるのがいい。それに比べて今回は、「一番に狙われるのはカイル」とはいえ、「人間vs.マシン」の話になってるから、どこを向いても人間が機械に襲われてるって感じで、あまり心動かされなかった。
お馴染みの「マシンの目で見た世界(ターゲット)」画面が何度も挿入されたけど、少なくとも「ターミネーター」においては、不特定多数のマシンの視界には興味が持てない。特定のターミネーターの目だから、こんなの見てるんだ〜って面白く感じる。
目当てのクリスチャン・べールについては、未だに、こんな人がリーダーの役なんて…と思ってしまう(笑)
マーカス・ライト役のサム・ワーシントンとカイル・リース役のアントン・イェルチンは、どちらもすごく魅力的に撮られてて、出演してよかったね〜と思った。前者は同行者いわく「ディカプリオとヒース・レジャーを足して2で割った感じ」。後者は「チャーリー・バートレット」「スター・トレック」に比べ、好かれる要素しかないキャラクター。少し(1・2作目の)マイケル・ビーンの面影もあるけど、なぜか彼よりも80年代ぽく見えた(笑)
スカイネットの中枢に忍び込むに至り、マシンによるマシンのための施設ってことは、人間的な快適さは必要ないわけだから、どんな所なんだろう?と期待していたら、いたって「普通」のデザインだったのでちょっとがっかり。大体なぜ照明があるんだろう?なんて、考えたらキリがないけど…
(09/06/06・新宿ピカデリー)
消されたヘッドライン (2009/アメリカ/監督ケヴィン・マクドナルド)
同日に発生した二つの死亡事件。ワシントン・グローブ紙のベテラン記者カル(ラッセル・クロウ)のもとを、死んだ女性と不倫関係にあった議員コリンズ(ベン・アフレック)が訪れる。二人は学生時代のルームメイトだった。取材を進めるカルは、二つの事件が関連していることに気付く。
ストーリー、映像に音楽も手伝って、どこか70年代の映画の匂いがする。「紙媒体からウェブへの移行」や「軍事企業と政府の癒着」といった要素が現れようとも、「2006年から云々」というセリフを聞いても、現代の話であるとなかなか実感できなかった(だから良くない、と言いたいわけじゃない)。
主役で頑張るラッセル・クロウも今っぽくない。ぼろい車を運転し、ジャンクフードをむさぼり食いながら登場する姿に、「アメリカン・ギャングスター」で斧を片手に現場に乗り込むシーンを思い出した。また、夜の駐車場で殺人者の手からすんでの所で逃れるシーンには、ふと「コンドル」('75)の似たような場面が浮かんだ。ああいうシチュエーションって70年代ぽい。もっともラッセルのやり方は、レッドフォードよりかなり強引だけど(笑)
カルが編集局長(ヘレン・ミレン)に吐き捨てるように言うには、「オレはデブで給料が高くて仕事は遅い」。とくに前半は、運よく彼の元に情報が集まっているようにも感じられた。
エンドロールに刷られるのあの新聞まで、カルは記事をひとつも仕上げないけど(だからデッドラインのスリルはないけど、彼の執念深さは際立ってる・笑)、それで回ってるんだから、大きな会社ってすごい。
カルとコンビを組む新人記者のデラ(レイチェル・マクアダムス)については、会議(オンライン組?なのか、若手ばかりが机を囲んでいる)の最中にカルに呼ばれるシーンに、私なら「自分と同じような仲間といるときに、違うステージの人に接触されたときの心の揺れ」を覚えるだろうに、何も感じていなさそうだったのが面白かった。ヒール履いて外回りしてるのも意外だった。
一つ不満だったのは、「実は妊娠していた」というくだり。セリフで説明されるだけなら、なぜそんな必要があるのか?と思う。
それから、この映画には「子ども」は出てこないけど、ワンシーンだけ、背景として大きく子どもの姿が映る所があり、なぜかはっとさせられた。
(09/06/03・新宿ピカデリー)
ベルサイユの子 (2008/フランス/監督ピエール・ショレール)
シネスイッチ銀座では、主演のギョーム・ドパルデュー追悼で「ランジェ公爵夫人」「ポーラX」も上映しており、ポスターを観て、そっちに流れそうになってしまった…
 ベルサイユ宮殿の森に暮らす、多くのホームレスたち。ある日辿り着いた親子が、ダミアン(ギョーム・ドパルデュー)の小屋で一夜を過ごすが、母親は仕事を求めて姿を消した。仕方なく彼は、残された息子エンゾの面倒を見ることに。
ベルサイユ宮殿の森に暮らす、多くのホームレスたち。ある日辿り着いた親子が、ダミアン(ギョーム・ドパルデュー)の小屋で一夜を過ごすが、母親は仕事を求めて姿を消した。仕方なく彼は、残された息子エンゾの面倒を見ることに。
予告編からは「あったかホームレス生活」を描いた作品という印象を受けたけど、全然違ってた。しみじみ「フランス」っぽい映画。夜中にホームレス仲間が火を囲み「愛なんてものはあるのか?」などと話し合う場面は、上映前に流れた「サガン」の予告編とだぶってしまった(どっちもこんな会話、冗談まじりってこともある)。エンゾ役の男の子の狆っぽい顔が、サガンを演じるシルヴィー・テステューに見えた(笑)
冒頭に出てくる母子の路上生活(車の狭間で用を足す姿に、生理のときはどうするんだろう?と思った)をはじめ、それぞれの事情や暮らしぶりが簡潔に描かれる。タバコを吸う彼女の前を流れる川の水面、ホームレス仲間が還る「森」の暗闇など、「人」以外を捉えたシーンに、ふと惹かれる箇所が多かった。
起こる事の説明はほとんどなされないため、他の映画に比べて唐突な印象も受けるけど、それはただ、皆が「自分の考え」に沿って行動しているだけなのだ。
ガタイのいいギョーム・ドパルデリューはほぼ全編、ワークパンツ姿。ワークパンツを履いた男の人って大好き(というより、肉体労働の似合う人が好き、というべきか)。小屋を作るのに、木の棒をぐるぐる結えつけるシーンに見惚れてしまった。そのポケットはいつも重そうにふくらんでおり、そっか、こういう人のための格好でもあるなあと思った(笑)
「許しや暖かさなんてもの、この家にはないんだ」
「お父様はそんな人じゃないわ…私たちは互いを選んだのよ」
(09/05/29・シネスイッチ銀座)
スター・トレック (2009/アメリカ/監督J.J.エイブラムス)
ドラマは観たことないけど、面白そうだな〜と思って。カーク船長とミスター・スポックが出会った頃のお話だった。
前半はおいてけぼりにされたようだった。突然「敵」が登場するんだけど、敵にせよ味方にせよ、皆が何のために行動しているのか分からず、結局最後までぴんとこなかった。彼等が普段は何を目的として働いてるのかも説明されなかったし。
クライマックス前に、狭義にというか当面の行動の「意味」がはっきりして、それからは楽しめた。
観賞後、ドラマ版を少しは知ってる同行者に色々聞いて、最も「そうだったんだ〜」と納得したのは、あんなに経験浅いうちから艦長になっちゃっていいの?と思ってたんだけど、彼いわく「無数の艦の中の一つなんだよ」。ああいう艦がいっぱいあると思うとロマンチックだけど、作中ではそういうの、分からなかった。
それから、「セブンティーン・アゲイン」(感想は一つ下↓)の主人公の親友がスター・ウォーズおたくだったことについて、「あれがスタートレックじゃだめなんだよな〜」と言うので、なんで?と聞いたら「(スター・ウォーズの方が)一目で分かるパフォーマンスがあるから」(ライトセイバーでの戦いとか)。それもそうだなと思った。
クリス・パイン演じるカークについては、自信満々でイヤなガキって感じで魅力を感じられず(バーでウフーラに声を掛けるシーンなど、愛嬌がないから嫌がらせにしか思えない…)、最後まであまり応援する気になれなかった。
スポック役は「HEROES/ヒーローズ」のサイラー(ザカリー・クイン)だったから(耳うちされて初めて気付いたんだけど/そういや「HEROES」とはジョージ・タケイつながりもある)笑えてしまった。佇まいは良かったけど、言ってることは(彼らの人種の特徴である)「論理的」には思えず。「哲学」という言葉を「人生哲学」と遣ってるようなものかな。
その他のクルーはサイモン・ペッグ、アントン・イェルチン、ジョン・チョーなど面白味のある人ばかり。
それから、「敵」のネロがかっこいいなあと思ってたら、エリック・バナだった!スキンヘッドと特殊メイクのせいで分からなかった。2時間映画じゃしょうがないけど、連邦軍側は皆で和気あいあいって感じなのに、ネロはほぼ一人ぼっちで、結局仲間はいいねってことか〜と少し同情してしまった。
「スタートレック」の存在のパロディである「ギャラクシー・クエスト」は何度も観てるから、敵艦の中にはピストンみたいのが待ち構えてるのかな?と観てたけど、そんなものはなかった(笑)
冒頭、カークの父親が乗った艦が攻撃される場面では、あんなに科学・医療?技術が発達してるのに出産は昔ながらのやり方なんだな〜と違和感を覚えた。もっと楽になりそうなものなのに。むしろ「人間的」なやり方を尊重してるのかな。
(09/05/18・日本教育会館試写会)
セブンティーン・アゲイン (2009/アメリカ/監督バー・スティアーズ)
ザック・エフロン好きだし予告編が面白そうだったから、楽しみにしてた。実際とても良かった。こんな映画に出演できた彼は幸せだと思う。
 37歳のマイク(マシュー・ペリー)は、妻に家を追い出され、子どもたちに無視され、職場では認められず、人生どんづまり。バスケ部のスターだった17歳の頃を懐かしんでいると、不思議な力により肉体だけが若返ってしまう(ザック・エフロンが演じる)。そこで全てをやり直すべく、高校に編入することに。
37歳のマイク(マシュー・ペリー)は、妻に家を追い出され、子どもたちに無視され、職場では認められず、人生どんづまり。バスケ部のスターだった17歳の頃を懐かしんでいると、不思議な力により肉体だけが若返ってしまう(ザック・エフロンが演じる)。そこで全てをやり直すべく、高校に編入することに。
「入れ替わり」もの(広義に本作のような「変化」ものも含む)にも色々あるけど、例えば浮浪者のロブ・シュナイダーと女子高生のアンナ・ファリスの中身が入れ替わってしまう「ホット・チック」('02)は、元のロブのキャラクターに可愛げがなかったから、いくらその後に彼が女子高生の言動で笑いを取っても、いまいち爽快な気持ちになれなかった(…と記憶している。うろ覚え気味)。ロブ(の外観)には親しみが持てず、アンナ(の外観)には中身はあのおっさんでしょ、と思ってしまう。私の場合「入れ替わり」ものは、どのキャラクター、どの役者にもそれなりに好感を持てないと楽しめない。
しかし、この映画の主人公マイクは、妻の言い分を信じるならパートナーとしては最悪だけど(彼いわく「20年間不機嫌だった」そうだけど、そんなのイヤすぎる!)、変身後のザック・エフロンはありあまる爽やかさでそのもやもやを打ち消してしまう。むしろ「中身はおっさん」と思うことで可愛らしく感じられる。昔にも書いたけど、「おじさんの心を持つ少年」って理想かもしれない(笑)
冒頭の上半身裸の姿からバスケプレイ、ちょこっと披露されるダンスなど、ザックの見せ場がいっぱい。加えて「入れ替わり」に付きものの、失言やギャップが引き起こす騒動の際に見せるちょっと情けない感じがとてもはまってる。女にビンタされるのも似合う(その理由が、私からしたら全然分からないんだけど…笑/「男にビンタされるのが似合う女優」が出てきたら…そういうことを多くの人が感じられるようになれば、そりゃあいい時代だ)
「17歳」になってしまったマイクの親代わりとなるのは、高校以来の親友ネッド(トーマス・レノン)。「おれならあの頃になんて絶対戻りたくない」「お前はおれをかばってくれたから、助けてやるよ」。「オタク」であることを活かして金持ちになった彼の豪邸やセンスが、ベタながら可笑しい。ライトセイバーで戦うシーンと、ダースベイダー風にワインを味わうシーンが笑える。
真っ暗闇の豪雨の中、カーラジオが乱れ、橋の欄干の上に老人が…というシーンには「素晴らしき哉、人生!」を思い出した。まあ、あんな深刻にはならないけど(笑)
劇場内には37歳より17歳に近い人が多いようだったけど、37にして(たとえ外見がカッコよくても)ハイスクールに突入するシーンなどは、それなりの年のほうが楽しめるかもしれない。
(09/05/17・新宿ピカデリー)
夏時間の庭 (2008/フランス/監督オリヴィエ・アサイヤス)
オルセー美術館20周年を機に制作された作品。パリ郊外を舞台に、母の遺産である数多くの美術品を整理する兄弟らの姿を描く。
 75歳のエレーヌ(エディット・スコブ)は、ボブカットの髪に白いブラウス、フレアのロングスカート。予告編で見ただけじゃ、いかにも「品行方正」な「母親」というイメージを受けるけど、結構普通の女の人だ。経済学者の長男が「おれの著作に反対するやつがいるんだ、ラジオのパーソナリティで…」という話をすると、「彼は知的で声のいい人よね〜」などという合いの手を入れ、結局息子は妻に対し「興味もないのに本を読みたいなんて言われると腹が立つ」とグチる(その後しばらくしての二人のキスシーンが素敵だ)。
75歳のエレーヌ(エディット・スコブ)は、ボブカットの髪に白いブラウス、フレアのロングスカート。予告編で見ただけじゃ、いかにも「品行方正」な「母親」というイメージを受けるけど、結構普通の女の人だ。経済学者の長男が「おれの著作に反対するやつがいるんだ、ラジオのパーソナリティで…」という話をすると、「彼は知的で声のいい人よね〜」などという合いの手を入れ、結局息子は妻に対し「興味もないのに本を読みたいなんて言われると腹が立つ」とグチる(その後しばらくしての二人のキスシーンが素敵だ)。
作中では主に男たちが彼女について語る。「暖房器具屋の妻なんかじゃイヤだったんだろう」「親父を見下してたんだ、死んだ次の日には姓を戻してる」。彼女が画家の叔父と愛し合っていたことがほのめかされる。ジュリエット・ビノシュは彼等に対し、「聖女だと思ってればいいじゃない?」と冗談めかして言う。
…なんて、私はそういうことばかり面白がってしまうけど、映画の主役はエレーヌでも、クレジットのトップであるジュリエット・ビノシュ演じる長女でもない。パリ郊外の自然と家、美術品、そこを訪れる人々のあいまった姿だ。
終盤、美術品を寄贈したオルセー美術館を訪ねた長男は、ガイドツアーの客に素通りされる机の展示を見て「動物園みたいだ」と嘆く。また女中のエロイーズは、鑑定作業中の家に持参した花を、それと知らず高価な美術品に活け「(エレーヌは)花のない花瓶は寂しいとおっしゃいました」と言う。
自然光で撮られた映像は、ほぼ「中にいる」人物の視点で、視界の広がるラストシーンを除き、この家がどんな場所に建っているのか、どういう外観なのか、といった説明的なカットはない。美術館級の家具の数々も、生活の一部として捉えられる。
遺産をめぐる兄弟の話し合いが何度も出てくる。一人っ子の私にとって、ああいう話をする相手がいることは羨ましい。私の受け継ぐものは、この作品に出てくる美術品とは大違いだけど、いずれは全て、責任を持って何とかしなければならない。処分に躊躇するとしたら、押入れの奥の掛け軸より、毎日遣った量産品のダイニングテーブルかもしれないなあ、などと思った。
昨年「PARIS」であらためてジュリエット・ビノシュを好きになったので、彼女目当てでもあったんだけど、今回も良かった。ジャージー生地の上着やジーンズ姿で白いカバンを肩から提げ、ニューヨークを拠点に忙しく働くプロダクトデザイナー(「タカシマヤ」のセリフが聴ける・笑)。母親と二人の時間を持て余したようにため息をついたり、机に突っ伏しそうになってお茶を飲んだりする姿が印象的だ。
ちなみに彼女の恋人役として、なぜかカイル・イーストウッドが出演していた。
作中では、「上海の工場で技術監督をしている」次男の口を借りて、安価な人件費で商品を大量生産すること(関連映画→「女工哀歌」感想)、ひいてはファストファッションに疑問を呈するようなことも示される。
前にも書いたけど、フランス映画ではいつもパンを手づかみしてるけど、今回はパウンドケーキのみならずキッシュも素手で運ばれてた(笑)手がべたべたしないのかな?
「あなたにこれは合わないかしら、モダンなものが好きだから」
「作品は良いか悪いか。時代なんて関係ないわ」
(09/05/16・銀座テアトルシネマ)
天使と悪魔 (2009/アメリカ/監督ロン・ハワード)
ダン・ブラウン原作による、ロン・ハワード監督&トム・ハンクス主演「ダ・ヴィンチ・コード」に続く第2作。教皇選挙の最中のヴァチカン・ローマを舞台に、宗教象徴学者ラングドン教授が枢機卿誘拐事件の謎を追う。
予告編で見たユアン・マクレガーの「いい人そうだけど腹に一物ある感じ」がはまってたので、楽しみにしていたら、実際、彼の映画といっていい内容だった。でも、もっと面白いシーンがあってもよかったんじゃない?と思ってしまうけど…。
教皇空位の際の代理権限を持つユアンが、非公開書庫への入室を要請したラングドン教授に対し、ただ「あなたは神を信じていますか?」とだけ問う場面でのやりとりが、後で振り返るととても面白い。
作中「○○する力は私にある」「○○する力はあなたにはない」などというセリフがしょっちゅう出てくるので、当たり前ながら、宗教界であれ何であれ、人は権力にこだわるものなんだなあと思った。
作中何度か「集団」が見られる。教皇選挙の結果を待ちわびる教徒たち、爆弾が仕掛けられたというニュースに(なぜか?)現場に集まってくる市民たち。映画にこういう集団が出てくると「携帯電話で写真を撮っている人」の有無が気になるけど、今回は見つけられなかった。
更に、教皇選挙の進展を追う各国のマスコミの姿(それぞれ自国の枢機卿が選ばれる見込み…と喋ってるのが可笑しい)が挿入されるんだけど、なぜあんなに頻繁に登場するのか分からなかった。原作だと何か意味があるのかな?
(09/05/15・新宿ピカデリー)
ウォーロード/男たちの誓い (2007/香港-中国/監督ピーター・チャン)
「中国の昔の話」ということしか知らず、金城武を観に行った。「レッドクリフ」では吹き替えられていた彼自身の声が聴けるのが嬉しい。語り手として、全編ナレーションもあり。
 太平天国の乱の最中の中国。部隊を全滅に追いやられた朝廷軍の将軍パン(ジェット・リー)は、盗賊のリーダー・アルフ(アンディ・ラウ)と弟分ウーヤン(金城武)に、仲間や村を守りたいなら官軍の兵士となるべきと説く。三人は義兄弟の契り「投名状」を結び、太平軍を次々と討伐していく。
太平天国の乱の最中の中国。部隊を全滅に追いやられた朝廷軍の将軍パン(ジェット・リー)は、盗賊のリーダー・アルフ(アンディ・ラウ)と弟分ウーヤン(金城武)に、仲間や村を守りたいなら官軍の兵士となるべきと説く。三人は義兄弟の契り「投名状」を結び、太平軍を次々と討伐していく。
作中「『善』のための死もある」というセリフが出てくるけど、何らかの目的のためには死も必要だ、ということを(その是非でなくテーマ自体を)、ここまで分かりやすく前面に押し出してる映画は珍しいと思った。
三人が手を組んで初の戦いはあっけなく勝利するくので、強いんだな〜この調子でアクションが続くのかな?と思っていたら、大きな戦闘シーンは数回のみで、後半は人間関係に焦点が当てられる。
ジェット・リー演じるパン将軍は、自分の理想を政治的に果たすため、二人と契りを結び、朝廷に頭を下げ、涙を流しながら捕虜を殺す。一方アンディ・ラウ演じるアルフは、学は無いが仲間を大事にする「村のリーダー」だ。作中では二人のぶつかり合いが大きなドラマとなる。
金城武のウーヤンは、現実的なパンと義理人情派のアルフの二人に挟まれた、中立的な立場。年若く一途なおぼこ風で、「死体から取ってきた」という十字架のペンダントを、「何だか分らないけどキレイだろ?」とプレゼントする場面が可愛い。
その彼が、戦場ではない所においては、最も多く人を殺す。「投名状」のために通行人を捉えて斬り、軍の規律を守るために見せしめの処刑を行い、邪魔な女の息の根を止め、最後に投名状を果たす。そうした際の、これまでの出演作では見られなかった表情や演技が新鮮だ。
ベタなことを言うようだけど、「女を殺す」場面では、どうせ死ぬならああいう眺め(金城武の顔を下から見上げたアングル)を目にしてからがいいなと思った。
ジェット・リーは始終「唇の乾いたグッチ裕三」にしか見えず。でも三人とも男前すぎるより、冷静に観られるからよかった。
また、蘇州城の太平軍のリーダーが「レッドクリフ」時の中村獅童に似ていたので、中国ではああいうキャラクターはああいう顔なのかなと思った。
(09/05/12・新宿ミラノ1)
チェイサー (2008/韓国/監督ナ・ホンジン)
「映画は映画だ」(感想)の際に流れた予告編に興味を持って観に行った。上映後にエレベーターで一緒になったおばさま二人が「もうほんとに!警察は!」とぷりぷりしてたので、映画としてとても成功してると思う(笑)
元刑事のジュンホ(キム・ユンソク…「ヨコヅナ マドンナ」(感想)の父親)が経営するデリヘルから、女性らが姿を消していた。目をつけて追った客のヨンミン(ハ・ジョンウ)は、二人して連行された先で殺人を自白。警察は当該地区の連続殺人事件との関連を確信し捜査を行うが、証拠が出ない。「最後の一人は生きてる」との言葉に、ジュンホは町を駈ける。
起こっていることを手際よく示すオープニングがいい。ちょっとイーストウッドの「ミスティック・リバー」を思い出した。
また、韓国ってああいうやり方なんだ〜(女側が自分の車を出すとか、ホテルに入るのにあんな路上・縦列駐車しなきゃいけないとか。日本でもそういう場合があるのかな?)というのが単純に面白くもあった。私も何度も知らない人の車に乗ったけど、客観的に見るとおそろしいことだ。
その後は、映画の面白い要素を全て味わうことができる(ただし「かっこいい男」は除く・笑)
ジュンホとヨンミンは作中早々に顔を合わせ、最後の最後まで、肉体的に何度もぶつかり合う。どのアクションシーンもリアルで痛い。
一方、(私の偏見からすると)いかにも韓国らしい「上の者にはへこへこするが、出来る限り好き勝手する」というたくましさが現れた、コミカルな場面も多い。あらすじからは想像できないだろうけど、劇場では何度も笑いが起きていた。例えば二人の初対面における一波乱の後ジュンホが戻ってみると、近所の住民が、二台の車で通行止めになってしまった路上ででわいわいやっている住民たち(勝手に車に乗り込みハンドルを握ってる者も・笑)や、意見の相違から殴り合いを始める警察署員たち。他に、ジュンホにこき使われる舎弟の情けなさやボケぶりも可笑しい。暴力シーンについても、他のデリヘル経営者を訪ねた際のジュンホの一撃には爆笑してしまった。
さらには「最後の一人」であるミジンの幼い娘がジュンホに同行することになり、センチメンタルな雰囲気も醸し出される。
ヨンミンの尋問のために呼ばれた心理学者?のじいさんの嫌らしいこと。「常識的」な人間との接触により、それが通用しない犯人の怖さが浮き彫りになる、というのは映画によくあるパターンだけど、そうならない。全ての人間(というか「男」たち)は普通っぽく、そうでもなく、賢くもあり、間抜けでもある。
作中描かれる警察の無能ぶりは、かなり大げさだ。「血じゃないか…?」「キムチの汁だろう」というやりとりなんて、冗談でもなきゃ怖すぎる(笑)
(09/05/07・シネマスクエアとうきゅう)
ある公爵夫人の生涯 (2008/イギリスフランスイタリア/監督ソウル・ディブ)
18世紀のイギリスを舞台に、ジョージアナ・スペンサー(キーラ・ナイトレイ)が名門貴族のデヴォンシャー公爵(レイフ・ファインズ)に嫁いでからの数年間を描いた物語。
キーラ・ナイトレイの顔のアップが多く、しかも同じような表情ばかりなものだから、いわゆる「ゲシュタルト崩壊」を起こしたように、次第に何を見てるのか分からなくなってきた。あらためて、私にとって人の顔って、実際に見たり触れたりしないのであれば、他との対比により意味が出てくるものなんだなと思った。
(ちなみに「同じような…」というのはキーラの演技がどうだからというわけではなく、そういう物語、そういう映画なんだと思う)
背景や衣装は、観ていて本当に楽しかった。
建築物については、豪奢な公爵家もだけど、ジョージアナが愛人の子を産むために訪れた「田舎」の素敵に古い家が印象に残った。向かうまでの道のりの田舎っぷりもすごい。
建物じゃないけど、公爵家の使用人たちも味わい深い。「自動ドア」は良かった。主人が通る際、こちら側の使用人が杖をどんっとやると、向こう側の使用人たちがドアを開ける(他の映画でも見られるのかな?気付いたことない)。
衣装については、初夜の際にジョージアナが「女は衣服で自分を表現するのです」と言うので、どんな格好で自己表現するのかな?と考えながら観たけど、よく分からなかった。全体的に、ヴィクトリア時代のものより「現実的」な感じを受けた。チャールズの応援で演説に参加した際の、制服っぽい紺色のドレスが好み。
陳腐なことを言うようだけど、昔は女の結婚を「永久就職」などと仕事になぞらえたものだけど、まさにその通りだなと思った。初めて足を踏み入れる職場(公爵家の玄関ホール、階段の冷たさ!)、初めてのお役目(政党員たちの会議)…
レイフ・ファインズ演じる公爵は無表情だ。どういう親の元に生まれ、どんな成長をしてきたのだろう?と考えてしまった。魅力のないことこの上ない人間だけど(魅力なんて必要ないんだろうけど)「自分の考える愛し方で…」というのは、論理的でよく分かる。
ジョージアナが愛するチャールズを演じるドミニク・クーパーは、どうにも顔付きが受け入れられないんだけど、二人の関係がああいう結果になるなら、むしろそれでよかった。(観てるこっちが)未練が残らずに済むから(笑)
ジョージアナと彼が久しぶりに顔を合わせて会話を交わすシーンには、作中唯一、胸が痛くなった。
「あれは喜劇ですわ」
「私には悲劇に思えます」
入場の際にすれちがったおばさま二人が「あの、赤ちゃんを追いかけて走ってくとこ、泣いちゃったわね〜」と語っていたので、そういうシーンがあるのかと構えていたけど、無かった。何だったんだろう?
(09/05/01・テアトルタイムズスクエア)
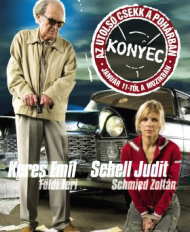 予告編やチラシからイメージするより、ずいぶんハードボイルドな映画だった(逆に言うなら、日本の予告編は、うまく切り取って「ほのぼの感」を出してるなと感心した・笑/画像はハンガリー本国のポスター)
予告編やチラシからイメージするより、ずいぶんハードボイルドな映画だった(逆に言うなら、日本の予告編は、うまく切り取って「ほのぼの感」を出してるなと感心した・笑/画像はハンガリー本国のポスター) 猿投の領主と部下の霊が現代に蘇り、400年前に潰えた築城の夢を果たそうとする。とあるヒントから導き出されたその材料は、段ボール。領主の熱意に心打たれた町民らの手で計画が進むが、同地に工場誘致をもくろむ行政側は、城を壊そうとたくらむ。
猿投の領主と部下の霊が現代に蘇り、400年前に潰えた築城の夢を果たそうとする。とあるヒントから導き出されたその材料は、段ボール。領主の熱意に心打たれた町民らの手で計画が進むが、同地に工場誘致をもくろむ行政側は、城を壊そうとたくらむ。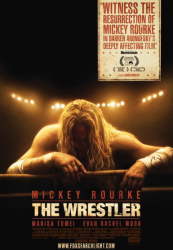 冒頭から胸がぐっとしめつけられるようで、中盤、ランディがキャシディ(マリサ・トメイ)に「息子にあげてくれ」と、冒頭に目を引いたあるものをプレゼントする場面で、涙がこぼれてしまった。
冒頭から胸がぐっとしめつけられるようで、中盤、ランディがキャシディ(マリサ・トメイ)に「息子にあげてくれ」と、冒頭に目を引いたあるものをプレゼントする場面で、涙がこぼれてしまった。 起伏やクライマックスはなく、走馬灯のように人生の出来事が描かれる。場面が切り替わると何年、何十年も経っており、生活形態が変化した理由がセリフで説明されるので唐突な感じも受けるけど、エピソードに沿って挿入されるサガン自身の文章が心地良い。
起伏やクライマックスはなく、走馬灯のように人生の出来事が描かれる。場面が切り替わると何年、何十年も経っており、生活形態が変化した理由がセリフで説明されるので唐突な感じも受けるけど、エピソードに沿って挿入されるサガン自身の文章が心地良い。 ベルサイユ宮殿の森に暮らす、多くのホームレスたち。ある日辿り着いた親子が、ダミアン(ギョーム・ドパルデュー)の小屋で一夜を過ごすが、母親は仕事を求めて姿を消した。仕方なく彼は、残された息子エンゾの面倒を見ることに。
ベルサイユ宮殿の森に暮らす、多くのホームレスたち。ある日辿り着いた親子が、ダミアン(ギョーム・ドパルデュー)の小屋で一夜を過ごすが、母親は仕事を求めて姿を消した。仕方なく彼は、残された息子エンゾの面倒を見ることに。 37歳のマイク(マシュー・ペリー)は、妻に家を追い出され、子どもたちに無視され、職場では認められず、人生どんづまり。バスケ部のスターだった17歳の頃を懐かしんでいると、不思議な力により肉体だけが若返ってしまう(ザック・エフロンが演じる)。そこで全てをやり直すべく、高校に編入することに。
37歳のマイク(マシュー・ペリー)は、妻に家を追い出され、子どもたちに無視され、職場では認められず、人生どんづまり。バスケ部のスターだった17歳の頃を懐かしんでいると、不思議な力により肉体だけが若返ってしまう(ザック・エフロンが演じる)。そこで全てをやり直すべく、高校に編入することに。 75歳のエレーヌ(エディット・スコブ)は、ボブカットの髪に白いブラウス、フレアのロングスカート。予告編で見ただけじゃ、いかにも「品行方正」な「母親」というイメージを受けるけど、結構普通の女の人だ。経済学者の長男が「おれの著作に反対するやつがいるんだ、ラジオのパーソナリティで…」という話をすると、「彼は知的で声のいい人よね〜」などという合いの手を入れ、結局息子は妻に対し「興味もないのに本を読みたいなんて言われると腹が立つ」とグチる(その後しばらくしての二人のキスシーンが素敵だ)。
75歳のエレーヌ(エディット・スコブ)は、ボブカットの髪に白いブラウス、フレアのロングスカート。予告編で見ただけじゃ、いかにも「品行方正」な「母親」というイメージを受けるけど、結構普通の女の人だ。経済学者の長男が「おれの著作に反対するやつがいるんだ、ラジオのパーソナリティで…」という話をすると、「彼は知的で声のいい人よね〜」などという合いの手を入れ、結局息子は妻に対し「興味もないのに本を読みたいなんて言われると腹が立つ」とグチる(その後しばらくしての二人のキスシーンが素敵だ)。 太平天国の乱の最中の中国。部隊を全滅に追いやられた朝廷軍の将軍パン(ジェット・リー)は、盗賊のリーダー・アルフ(アンディ・ラウ)と弟分ウーヤン(金城武)に、仲間や村を守りたいなら官軍の兵士となるべきと説く。三人は義兄弟の契り「投名状」を結び、太平軍を次々と討伐していく。
太平天国の乱の最中の中国。部隊を全滅に追いやられた朝廷軍の将軍パン(ジェット・リー)は、盗賊のリーダー・アルフ(アンディ・ラウ)と弟分ウーヤン(金城武)に、仲間や村を守りたいなら官軍の兵士となるべきと説く。三人は義兄弟の契り「投名状」を結び、太平軍を次々と討伐していく。