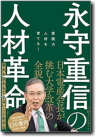
| 「永守重信の人材革命」 人材がいない!このままでは日本はダメになる 日経クロストレンド編集部 編 日経BP 刊 |
●日本電産を28歳で創業し、世界一の総合モーターメーカーに成長させた会長兼CEO(最高経営責任者)の永守重信氏。●優秀な技術を持つが経営不振に陥った企業を次々に買収し、再建させていった手腕の裏には、氏の持つ経営哲学、生きる哲学があります。
●「危機ほど楽しいものはない」「一番ダメなのは、チャレンジしないこと」「悪いことは、それをきっかけに業務全体を改革できるチャンスでもある」。●氏の言葉から、「諦めないで目的達成への強い意志を持ったアグレッシブな人材」が求められることが分かります。
■本書は、大学改革を追った書籍であると同時に、永守氏の組織論、人材育成論を学べる書籍です。■そして、カリスマ経営者の人間像に迫った書籍でもあります。■会社という組織の中で自分がどう動き、人を動かすために何をすべきか。そして、これから世界と戦っていくうえで必要な人材とは何か、若者にどう接すべきかといった視点でもビジネスパーソンに役立つと考えています。
■これからの日本で、いや世界で戦っていくためには、既存の概念は役に立たなくなっていることを永守氏は示し続けています。本書が、世界で戦い、勝つためのヒントに少しでもなれば幸いです。
 ■永守氏は、社員に必要な要素として、3つの「P」が重要であると説く。日本電産の2020年4月の新入社員向けビデオメッセージでこう語っている。■「昨今のグローバル競争は非常に厳しい。特に中国企業の技術力・競争力が向上し、真っ向勝負の状態だ。皆さんには3つのP(Proactive、Professional、Productive)が必ず必要になってくる。 日本人はとかく積極性がなく、自分から言葉を発しないが、それではとても戦っていけない。 指示を待つのではなく、自ら考えて行動すること(Proactive)。そのため、自分の専門をはっきりさせ、それを磨くこと(Professional)。そして、生産性を上げること(Productive)。 積極的に前にでて、生産性を上げ、専門性を磨くプロフェッショナルな人間になることが極めて重要である」
■永守氏は、社員に必要な要素として、3つの「P」が重要であると説く。日本電産の2020年4月の新入社員向けビデオメッセージでこう語っている。■「昨今のグローバル競争は非常に厳しい。特に中国企業の技術力・競争力が向上し、真っ向勝負の状態だ。皆さんには3つのP(Proactive、Professional、Productive)が必ず必要になってくる。 日本人はとかく積極性がなく、自分から言葉を発しないが、それではとても戦っていけない。 指示を待つのではなく、自ら考えて行動すること(Proactive)。そのため、自分の専門をはっきりさせ、それを磨くこと(Professional)。そして、生産性を上げること(Productive)。 積極的に前にでて、生産性を上げ、専門性を磨くプロフェッショナルな人間になることが極めて重要である」■その中でも、ベースとなっているのが、一つ目のP(Proactive)、自ら考えて行動することだ。かつて永守氏は、去ってほしい社員のタイプを著書『奇跡の人材育成法』(PHP研究所)の中でこう述べている。
・知恵の出ない社員・言われなければできない社員・すぐ他人の力に頼る社員・すぐ責任転嫁をする社員・やる気旺盛でない社員・すぐ不平不満を言う社員・よく休みよく遅れる社員
■どれも、自身で考え行動しようとする姿勢や、熱意を軸にした項目である。
■永守氏は、自身の経験則から、「IQなどによる能力的な差は、どんなに頭が良くても普通の人のせいぜい5倍ほど。一方、EQの高い社員とやる気のない社員を比べると、仕事で100倍以上の差が生まれることがある」と語る。■学校のテストや受験はIQが高いほうが有利だが、社会の中で競争を勝ち抜くためには、まさにこのEQが重要になると、永守氏は50年近くにわたる人材育成の経験から結論づける。
■冒頭で紹介した新入社員向けビデオメッセージでは、永守氏はこう続けている。「EQを伸ばすこと、一生懸命に働き、努力することが人生を大きく変えていくことを理解してほしい」。■リーダーに関しても、永守氏はEQの重要性を強く指摘する。「誰しも人を使えないといけない。組織というのは階段を上っていくもの。いくら頭が良くても、人を使えなければ上には立てない。従業員1万人の会社でも社長は1人。平社員であれば頭がいい人間が勝つ分野もあるけれど、上がっていけば頭は関係ない。IQで経営はできません」。こう断言する。
■永守氏はEQの高い人材を探し出し、そして育て上げてきた。IQ偏重の世の中において、EQ視点で実践力のある人材を探すのは極めて難しい。そこで永守氏は、さまざまな採用試験を考案し、試してきた。「心の中に種火を持っていて、自分で自分のやる気に火を付けられる人」を探すためにだ。
■前述のように、永守氏は1973年に社員3人と自宅の納屋で日本電産の創業を果たす。翌74年からは新卒採用をスタートするが、無名企業に人が集まるわけもなく大苦戦。その後、少しずつ実績が出るとともに採用試験に人が来るようにはなったものの、成績のいい、いわゆる優秀な人材は大手にばかり行ってしまう。集まるのは一般的に見ると二流、三流の人材ばかりだった。■だが、永守氏はここで逆転の発想をする。「大手に勝つためには、成績順に採用するような同じことをしていてはダメだ。やっていないことをしよう」と。従来にはない採用方法を生み出し、原石を発見しようとした。
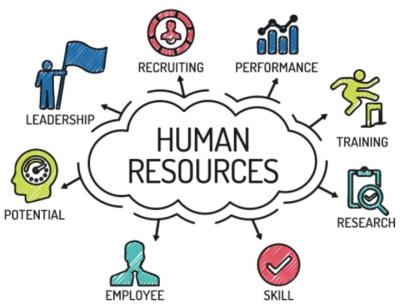
■76年度の新卒採用で実施したのが「大声試験」だ。1つの文章を、応募してきた学生に順に読んでもらい、声の大きい人から採用するというもの。「世の中を見ても、声の小さい、こそこそしゃべっている人で成功している人はいない。EQが高い人は自信を持っていて声が大きい」。仕事ができる人は声が大きいという、永守氏のビジネスにおける経験則から、自信があるかどうかなどを注意深く観察しようとしたのだ。
■続いて78年に実施したのが、「早飯試験」。のちに、この方法が最も成功したと永守氏は語る。応募してきた160人から面接で70人に絞り、何も知らせずに用意した弁当を食べてもらう。弁当は、しっかりかまないと飲み込めないおかずをたっぷりと詰めた特注品。永守氏や社員が実際に食べ、その結果から想定した時間以内に食べ終わった33人を無条件で採用した。
■その他にも、「先んずれば人を制す」と、試験会場に早く到着した人から順に採用する試験や、足が遅くても休まない人を採る「マラソン試験」など、ユニークな採用試験を実施したこともあった。これらは創業期の、まさにわらにもすがる思いでいい人材を採ろうと試行錯誤をした時期のことで、今ではここまでとがった採用は行っていない。だが、学校の成績や筆記試験ではなく、EQの高い人材を見極めていくスタイルは今なお健在だ。
■永守氏は、採用試験の際には成績は見ないものの、その後の会社での実績との比較は行っている。例えば、大声試験や早飯試験など、成績を一切加味せずに採用した社員の成績表を金庫にしまっていたが、数年後に開封して社内の成績と比較したところ、学業の成績は全く無関係なことが分かってきたという。さらに、最も成功したと語る早飯試験の合格者は、その後に社内で大活躍し、大幹部になった。
■日本電産には、今ではいわゆる一流大学の学生が入社するようになっているが、「2000年ごろから採用した新卒社員について、仕事の成果と卒業大学の相関関係を調べてみると、一流大学卒でも三流大学卒でも10年ほど経つと何も変わらないことが分かった」。三流大学出身者のほうが、成果を出していることも珍しくなかったという。
「自ら考え、もがく」 実践力を鍛える方法とは
■「EQは筋肉と一緒で、鍛えればどんどん伸ばせる」と永守氏は指摘する。その代わり、放っておくとまた元に戻る。だから、ずっと鍛え続けなければいけないという。■では、社会で能力を発揮するために必要なこのEQや実践力をどう伸ばしていくのか。重要なのは、「とにかく考えさせること」だ。永守氏は日本電産で、社員に徹底して考えさせる。権限を委譲し、仕事を部下に任せることを意識的に行う。
■そして、失敗することよりも、チャレンジしないことが問題であると説く。京都先端科学大学でも、詰め込みではない「自分で考えて行動する」ことを徹底的にカリキュラムに落とし込む。「90分、座学をやっていても仕方がない。半分以上を実践かアクティブラーニングなどにすべき」と、永守氏は語る。
「人間力」と「雑談力」を磨き、世界へ
■EQと同じく、永守氏が創業時からこだわるのが、「人間力」と「雑談力」だ。「欧米人は日本人と食事をするのを嫌がる。日本人は料理を黙って食べるだけで、話を楽しむことができないから」と永守氏は語る。■実社会において、ただ黙々と自分の仕事だけをこなして完結する機会は極めてまれ。コミュニケーションができない人間は、周囲と協調してチームとして何かを成し遂げることができないのはもちろん、周囲からの意見を聞けず、自身が成長をすることも難しくなる。当然、人の上に立つリーダーにもなれないというのだ。■永守氏は、特に管理職はこの2つの力を磨くべきだと言う。
■当然、人間力にはマナーや礼儀作法なども含まれる。日本電産では、新入社員研修にマナー講習を組み込んでいる。これだけなら、その他の企業でも行っていることだが、日本電産は、その後に段階的に実施する階層別の研修でも必ずマナー講習を実施する。内容も通り一遍の単純なものではない。名刺の受け渡しや電話応対の仕方といった定番かつ基本のビジネスマナーに加え、冠婚葬祭の知識や所作から、日常生活を送っていくうえで必要な礼儀作法まで幅広い。
■M&Aによって傘下に入った企業を再建する際、一般的な企業の多くは、「年齢が高いから」「能力が低いから」などという理由で人員の整理をしがちだが、永守氏は、「怠け者には辞めてもらう」というスタイルを取る。まさに、意識こそが重要であるという証明だろう。■特にトップの地位に就く者やチームを率いる人材には、極めて高い意識を持つことを永守氏は要求する。チームのトップの意識が変わることが、組織全体を変える大きな起爆剤となるからだ。「ヒツジばかりの組織の中に、1匹のオオカミを隊長として入れる。そうすると皆がオオカミに近いヒツジになるんですよ。1人のトップを入れ替えるだけで組織は劇的に変わる」(永守氏)。