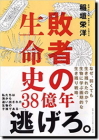
| 「 敗者の生命史38億年 」 なぜ、弱くても生き残れたのか? 生命に学ぶ画期的な生き残り戦略 稲垣 栄洋 著 PHP研究所 刊 |
●「弱肉強食」と言われるこの世界、本当に残るのは強者なのか?それとも強者のために脇に追いやられながらも、工夫を凝らして生き延びた敗者なのか?そして、どの様にして生き延びてきたのか?●強者しか生き残れないなら、どうして多種多様な生き物がいるのか?
●「生き残っている生き物はすべて、オンリー1であり、ナンバー1でもある」と言う本書では、生命史をもとに、時代を生き抜く我々が、どの様にして生き残り、生き抜けば良いかのヒントを示してくれます。

■ゼロから生み出された一が、十や百になるために必要なことは何であろう。その鍵となるものこそが、「エラー」である。生命は、単純なコピーの繰り返しである。しかし、ただ几帳面にコピーをしているだけでは、何の変化もない。ひたすら繰り返されるコピーには、しばしばコピーミスが起こる。このミスの繰り返しによって、生命はさまざまな変化を可能にしてきたのだ。■しかし、このエラーによる変化が生かされるには、長い年月が必要となった。どうしてこんな単純な仕組みが、三十八億年もの間、続けられてきたのだろう。そして、どうして、こんな単純な仕組みによって、さまざまな生物が進化を遂げたのだろう。
■エラーは、エラーでしかない。しかし、生命はエラーを繰り返してきた。そして、あるとき、そのエラーがまったく新しい価値を生み出していく。生命の進化は、この繰り返しなのである。■エラーをする生命に価値があるのか、ないのか。そんなことはわからない。しかし、ただ一つ言えることは、生命が三十八億年間の歴史の中で、襲い来る過酷な環境を乗り越えて、生命のリレーをつないできたのは、生命がエラーをする存在だったからということである。■エラーに価値があるのか、ないのか。少なくとも生命の末裔である私たちにとってもまた、「エラー」が重要な意味を持つことは生命の歴史が証明しているであろう。■生き抜いてきた生命の歴史には、真実がある。本書ではその真実から、現代を生き抜く知恵を学んでいこうと思う。
■ヒット曲「世界に一つだけの花」では「ナンバー1にならなくても、もともと特別なオンリー1なのだからそれでいい」という内容の歌詞がある。この有名なフレーズに対しては、二つの意見がある。■一つは、この歌詞のとおり、オンリー1が大切という意見である。競争に勝つことがすべてではない。ナンバー1でなければいけないということはない。私たち一人ひとりは特別な個性ある存在なのだから、オンリー1で良いのではないか、という意見である。
■これに対して反対意見もある。世の中は競争社会である。オンリー1で良いなどという甘いことを言っていれば生き残れない。やはりナンバー1を目指すべきだ、という意見である。■オンリー1で良いのか、それともナンバー1を目指すべきか。あなたは、どちらの考えに賛同されるだろうか?生命の三十八億年の歴史は、この歌詞に対して明確な答えを持っている。
すべての生物がナンバー1である
■ナンバー1しか生きられない。これが自然界の鉄則である。ゾウリムシを使った実験では、一つの水槽に入れた二種類のゾウリムシは、どちらかが滅びるまで、競い合い、争い合う。そして、勝者が生き残り、敗者は滅びゆくのである。■しかし、不思議なことがある。ナンバー1しか生き残れないとすれば、地球にはただ一種の生き物しか存在しないことになる。しかし、自然界を見渡せば、さまざまな生き物たちが暮らしている。■ナンバー1しか生きられない自然界で、どのようにして多くの生物が共存しているのだろうか?
■ゾウリムシの別の実験では、二種類のゾウリムシが共存する結果となった。それは、一種のゾウリムシが水槽の上で暮らしながら大腸菌を餌にしているのに対して、もう一種のゾウリムシは、水槽の底の方にいて、酵母菌を餌にしていたのだ。つまり、一つは水槽の上のナンバー1であり、もう一つは水槽の下のナンバー1だったのである。■このように、ナンバー1を分け合うことができれば、共存を果たすことができるのである。■このナンバー1になれる場所をニッチと言った。ニッチはその生物だけの場所である。つまり、オンリー1の場所だ。このようにすべての生物は、オンリー1であり、ナンバー1でもあるのである。■地球のどこかにニッチを見出すことができた生物は生き残り、ニッチを見つけることができなかった生物は滅んでいった。自然界はニッチをめぐる争いなのである。
ニッチは小さい方が良い
■それでは、どのようにすれば、ニッチを見出すことができるだろうか。ナンバー1になるには、どうしたら良いのだろうか。たとえば、野球でナンバー1になることを考えてみよう。世界でナンバー1になるのは並大抵ではない。それでは、日本に限定してみよう。高校野球で日本一になることは、世界一よりは易しいかも知れないが、それでも実現できるのは一握りの選手だけである。それならば、都道府県でナンバー1はどうだろう。それが無理ならば市町村でナンバー1、それも無理なら、学区でナンバー1でもいい。
■このように、条件を小さく細かく区切っていけば、ナンバー1になるチャンスが生まれてくるのである。マーケティングなどではニッチ市場というと、すき間にある小さなマーケットを意味する。生物の世界では、ニッチにはすき間という意味はない。ニッチは大きくても良いのだ。■しかし、大きいニッチを維持することは難しいから、すべての生物が小さなニッチを守っている。こうしてニッチを細分化して、分け合っているのである。■ナンバー1になる方法はたくさんある。だからこそ、地球上にはこれだけ多くの生物が存在しているのである。
「争う」より「ずらす」
■ニッチを確保したとしても、永遠にナンバー1であり続けるわけではない。すべての生物が生息範囲を広げようとしているから、ニッチが重なるときもある。あるいは、新たな生物がニッチを侵してくるかも知れない。■一つのニッチには、一つの生き物しか生存することができない。そこでは、さぞかし激しい競争や争いが繰り広げられることだろうと思うが、必ずしもそうではない。■生物は、負けたら終わりだ。絶対に負けられない戦いがあるとすれば、できれば「戦たくない」というのが本音だ。■しかも、勝者は生き残ると言っても、戦いが激しければ勝者にもダメージはある。あるいは、戦いにばかりエネルギーを費やしていると、環境の変化など降りかかる逆境を克服するエネルギーまで奪われてしまう。■そのため、できる限り「戦わない」というのが、生物の戦略の一つになる。とはいえ、大切なニッチを譲り渡して逃げてばかりもいられない。どこかで、ナンバー1でなければ、生き残ることはできないのだ。

■そこで生物は、自分のニッチを軸足にして、近い環境や条件でナンバー1になる場所を探していく。つまり、「ずらす」のである。この「ずらす戦略」はニッチシフトと呼ばれている。■ずらし方は、さまざまである。ゾウリムシの例のように、水槽の上の方と、水槽の底の方というように、場所をずらすという方法もある。もちろん、同じ場所にさまざまな生物が共存して棲むこともある。■アフリカのサバンナではシマウマは草原の草を食べて、キリンは高い木の葉を食べている。このように同じ場所でもエサをずらすという方法もある。あるいは、昼に活動するものと夜に活動するものというように、時間をずらすという方法もある。植物や昆虫であれば、季節をずらすという方法もあるだろう。
■このように条件のいずれかをずらすことで、すべての生物はナンバー1になれるオンリー1の場所を見出しているのである。そしてニッチをずらし分け合いながら生物は進化を遂げてきたのだ。もちろん、このニッチという考え方は、生物種単位での生き残りの話であって、個体それぞれの戦略ではない。しかし、私たち人間社会の生存戦略にとっても示唆に富む話ではないだろうか。
多様性が大切
■こうして、自然界は多種多様な生物たちで埋め尽くされている。しかし、不思議である。■すべての生物は共通の祖先となる単細胞生物から進化をした。そうだとすれば、その一種がそのまま進化を遂げて、地球上を一種の生物が占有していても良さそうなものである。共通の祖先を持つにも関わらず、子孫となった生物は互いに競い合い、あろうことか食べたり食べられたりしている。兄弟姉妹が骨肉の争いを繰り広げているようなものだ。■地球にはさまざまな環境がある。また、環境は常に変化していく。この地球でどのように生きていけば良いのか? その答えは一つではない。そして、何が正解なのかもわからない。■そうだとすれば、多くのオプションを用意しておいた方が良い。 だから、多様なオプションを試すように、生物は共通の祖先から、分かれ続けてきたのだ。
■私たち人類は七〇億人もいるが、似ている人はいても、同じ顔の人はいない。同じ性格、同じ能力の人もいない。同じ遺伝子型は存在しないのだ。もっとも、一つの卵から生まれた一卵性双生児は、同じ遺伝子型を持つ。しかし、人は環境によって性格や能力が変化するように作られている。そのため、双子であっても、まったく同じ人格とはならない。すべての人は、オンリー1の存在なのだ。
「ふつう」という幻想
■人間の脳は、複雑につながるこの世の中を、ありのまま理解することはできない。そのため、区別して単純化していくのである。そして、多様であることは、理解しにくいから、「できるだけ揃えたい」と脳は考える。■生物は多様であるから、本来、野菜はすべて形や大きさがバラバラである。しかし、それでは収穫作業も大変だし、箱詰めもできない。陳列するのも苦労だし、値段もそれぞれにはつけられない。そのため、人間は野菜という生物を、できるだけ揃えようとするのだ。■人間も、一人一人の顔が違うように、それぞれ個性ある存在である。しかし、それでは理解が難しいので、同じ教科書で、同じ授業をする。そして、テストや成績をつけて順番に並べる。こうして、整理することで、人間の脳ははじめて理解することができる。
 ■多様であったり、複雑であったりしてほしくないのだ。そんな人間は、好んで使う言葉に「ふつう」がある。「ふつうの人」と言うが、それはどんな人なのだろう。■生物の世界は、「違うこと」に価値を見出している。だからこそ、同じ顔の人が絶対に存在しないような多様な世界を作り出しているのである。一つ一つが、すべて違う存在なのだから、「ふつうなもの」も「平均的なもの」もありえない。■もちろん、私たちは人間だから、多様なものを単純化して、平均化したり、順位をつけたりして理解するしかない。■しかし、それは私たち人間の脳のために便宜的に行っているだけで、本当は、もっと多様で豊かな世界が広がっているということを忘れてはいけないだろう。
■多様であったり、複雑であったりしてほしくないのだ。そんな人間は、好んで使う言葉に「ふつう」がある。「ふつうの人」と言うが、それはどんな人なのだろう。■生物の世界は、「違うこと」に価値を見出している。だからこそ、同じ顔の人が絶対に存在しないような多様な世界を作り出しているのである。一つ一つが、すべて違う存在なのだから、「ふつうなもの」も「平均的なもの」もありえない。■もちろん、私たちは人間だから、多様なものを単純化して、平均化したり、順位をつけたりして理解するしかない。■しかし、それは私たち人間の脳のために便宜的に行っているだけで、本当は、もっと多様で豊かな世界が広がっているということを忘れてはいけないだろう。■このときに生命をつないだのが、地中奥深くに追いやられていた原始的な生命であったと考えられている。こうして命をつないだ生命に訪れた次の危機が、地球の表面全体が凍結してしまうような大氷河期である。■この時期には、地球の気温がマイナス50度にまで下がった、全球凍結によって、地球上の生命の多くは滅びてしまった。しかし、このとき生命のリレーをつないだのが、深海や地中深くに追いやられていた生命だったのである。■こうして地球に異変が起こり、生命の絶滅の危機が訪れるたびに、命をつないだのは、繁栄していた生命ではなく、僻地に追いやられていた生命だったのである。

■強い生き物は、弱い生き物をバリバリと食べていった。強い防御力を持つものは、固い殼や鋭いトゲで身を守った。その一方で、身を守る術もなく、逃げ回ることしかできなかった弱い生物がある。その弱い生き物は、体の中に脊索と呼ばれる筋を発達させて、天敵から逃れるために早く泳ぐ方法を身につけた。これが魚類の祖先となるのである。■やがて、脊索を発達させた魚類の中にも、強い種類が現れる。すると弱い魚たちは、汽水域に追いやられていった。そしてより弱い者は川へと追いやられ、さらに弱い者は、川上流へと追いやられていく。こうして止むにやまれず小さな川や水たまりに追いやられたものが、やがて両生類の祖先となるのである。
■巨大な恐竜が闊歩していた時代、人類の祖先はネズミのような小さな哺乳類であった。私たちの祖先は、恐竜の目を逃れるために、夜になって恐竜が寝静まると、餌を探しに動き回る夜行性の生活をしていたのである。常に恐竜の捕食の脅威にさらされていた小さな哺乳類は、聴覚や嗅覚などの感覚器官と、それを司る脳を発達させて、敏速な運動能力を手に入れた。■大地の敵を逃れて、樹上に逃れた哺乳類は、やがてサルヘと進化を遂げた。そして、豊かな森が乾燥化し、草原となっていく中で、森を奪われたサルは、天敵から身を守るために、二足歩行をするようになり、身を守るために道具や火を手にするようになった。
■人類の中でネアンデルタール人に能力で劣ったホモ・サピエンスは、集団を作り、技術と知恵を共有した。生物の歴史を振り返れば、生き延びてきたのは、弱きものたちであった。そして、常に新しい時代を作ってきたのは、時代の敗者であった。そして、敗者たちが逆境を乗り越え、雌伏の時を耐え抜いて、大逆転劇を演じ続けてきたのである。まさに、「捲土重来」である。■逃げ回りながら、追いやられながら、私たちの祖先は生き延びた。そして、どんなに細くとも命をつないできた。私たちはそんなたくましい敗者たちの子孫なのである。
■あなたのDNAの中には、生命の歴史が刻まれている。そして、私たちは生を手に入れると同時に、やがて来る死を背負うことになる。死は、生命が進化の過程で手に入れたものだ。■振り返ってみよう。単細胞生物は、細胞分裂を繰り返していくだけであった。彼らに死はない。しかし、やがて、単細胞生物は仲間と遺伝子を交換しながら細胞分裂をするようになった。新たに生まれた細胞は、元の細胞と同じではない。元の細胞はこの世からなくなり、新たな細胞が再生される。まさにスクラップアンドビルドである。こうして、再生し変化し続けることで、生命は永遠となる道を選んだのだ。■しかし、彼らは滅んでしまったわけではない。細胞分裂によって遺伝子は確実に受け継がれていく。元の細胞はなくなっても、確実に新たな細胞が遺伝子を引き継いでいく。そこには、死という終わりは見られない。
■私たち人間も、基本は単細胞生物と変わらない。たとえ私たちの体は滅びたとしても、たった一つの細胞が、私たちの遺伝子を確実に引き継ぐ。それが、女性にとっては一個の卵細胞であり、男性にとっては一個の精細胞である。■母親の体の中で細胞分裂によって生まれた卵細胞と父親の体の中で細胞分裂によって生まれた精細胞によって新たな一個の受精卵が生まれる。こうして、私たちの遺伝子は受け継がれていくのだ。これは単細胞生物たちが命をつないできたのと何ら変わらない。私たちもこうして、祖先から細胞分裂して遺伝子を引き継いできた。■もう三十八億年も、私たちは生き続けてきたのだ。私たちは永遠なのである。