映画メモ 2009年3・4月
(劇場・レンタル鑑賞の記録、お気に入り作品の紹介など。はてなダイアリーからの抜書です)
トワイライト〜初恋〜 / スラムドッグ$ミリオネア / ベティの小さな秘密 / いとしい人 / グラン・トリノ / チャーリー・バートレットの男子トイレ相談室 / フロスト×ニクソン / マーリー 世界一おバカな犬が教えてくれたこと / ヒストリーボーイズ / ベッドタイム・ストーリー / 映画は映画だ / パッセンジャーズ / ダウト〜あるカトリック学校で〜 / レールズ&タイズ / ヤッターマン / チェンジリング
トワイライト〜初恋〜 (2008/アメリカ/監督キャサリン・ハードウィック)
「僕の全てが、君を誘う罠…」
 面白すぎてびっくりした。今年観た中で一番かも…
面白すぎてびっくりした。今年観た中で一番かも…
昔離れた父親と再び暮らすため、明るいアリゾナから暗く寂れたワシントン州の町に越してきたベラ。べちょべちょの地面、どでかいクルマ、おおざっぱな食事…最初は彼女のように「こんなとこ絶対いや!」と思ってたのが、最後には全てが輝いて見える。
吸血鬼の彼と人間の彼女の恋物語。ストーリーもキャラクターも、コンパクトに色んな要素がつまっており、画面や音や小道具もぴったりはまってて、観ていてとても楽しい。
「自分の(意図的に得たわけではない、生来の)特性が王子様を惹きつける」「王子様が愛による自制心でもって本能?を抑える」というような「設定」は、私は嫌いだけど、この映画は、観てる間、そうしたことに目をつぶっていられる。そういう作品って貴重だ。
オープニングは主人公ベラの独白。何をすっとんきょうなこと言ってるんだと思っていたら、終盤、このナレーションは意外にところに繋がり、快感を得られる。
ラストもいい。これは続編がある!とわくわくさせられたところに、画面いっぱいに広がる、モノクロの「妄想」場面とタイトルロゴ。俗っぽいきらめきに胸が躍る。
色んなタイプの「男」が出てくるのも楽しい。吸血鬼一家をはじめ、冷たい血とはほど遠いタイプの、ネルシャツにジーンズの父親(私の叔父に顔が似てた。とてもいいキャラクター)、エキゾチックでしっかり者の幼馴染(恋人にするなら断然彼)、愛くるしいけど色気とは程遠い同級生。
そうした盛沢山の要素の中、馬鹿馬鹿しい設定や、若い二人の交わす唐突で稚拙なセリフのやりとりが、却って面白く感じられる。ちなみに「太陽にあたると肌が…」のくだりでは、全裸だと股間はどうなるのか気になってしょうがなかった(笑)
しみじみ思ったのは、「女のコ」…「女」は、緩急つけられると性的に盛り上がるってこと。セックスだって、一番分かりやすい盛り上げ方は、のろのろいくか突然いくかだ。
スーパーマンはロイスを抱いてベランダから夜空へ上っていくし、スパイダーマンはニューヨークの雑踏の中から二人きりの隠れ場に飛んでいく。そしてこの映画のエドワードは、ベラを背中に、湿地の森林のてっぺんに駆け上がる。吊り橋理論じゃないけど、「急」な移動は体と心を揺らがせる。
「緩」のほうは、勿論あの初めてのキス…ベタだけどどきどきしてしまう。
エドワードとベラが知り合ったばかりの校内でのシーンでは、やたら顔やその近くのぶれたようなアップが多いのも、得体の知れない相手と接近するどきどき感を高めていた。
吸血鬼一家の暮らす建物はとてもすてき。エドワードの部屋の窓が開け放たれてるのが何ともいえずいい。「月の光」で踊った後、二人はそこから濡れた森へ飛び出す。
じめじめした町らしい、窓の外から聴こえる雨の音や虫の声、ベラの雑貨ぽいファッション(プロムの際のアクセサリーの使い方とか)なども良かった。
同居人は、ラスト近くの二人の姿に「スターウォーズ エピソード2」の結婚式のシーンを思い出したそう。
エドワード役のロバート・パティンソンは、松山ケンイチみたいなタイプだなと思った。写真と予告編では、魅力を感じるどころか薄気味悪かったけど、映像に触れると惹き付けられる。たまに見せる笑顔も可愛かった。
(09/04/24・新宿ピカデリー)
スラムドッグ$ミリオネア (2008/イギリス/監督ダニー・ボイル)
・事前にH.I.S.のオフィシャルツアーの宣伝が流れたけど、あの映画を観てインドを訪ねたいと思う人は、何を観たいだろう?ともかく駅はすてきだった。
・正直言ってダニー・ボイルの映画は苦手だ。理由は説明できず、好みじゃないとしか言いようがない。でも面白いかも、と思って観た(いつもそう)。その結果、面白かったけど、心動かされるということはなかった。理由は分からない。
・主人公ジャマールを尋問する警官が、ロブ・シュナイダーに見えてしょうがなかった。
・ジャマールがラティカを探しに行く場面で、インドの売春街を捉えたドキュメンタリー「未来を写した子どもたち」を思い出した。
・ギャングとなったお兄ちゃんが、苦い別離の後に再会した弟に「もうお前を離さないぞ」などと言うシーンでは、先日試写会で観た「グラン・トリノ」を思い出した。モン族のタオ君が、わるい従姉にしつこく仲間入りを勧められるくだり。ああいうのってアジアっぽい感覚なんだろうか?
・上記のシーンで二人が会うのは、かつて暮らしたスラムの跡に建設中の、高層ビルの中だ。時代が変わる時、弱く貧しい者がまず追い立てられる。しかし人は、自分の居場所を求める。
・作中「クイズ・ミリオネア」について、ラティカは「別の人生を夢見るために観る」と言い、彼女を囲っているギャングのボスは「こんなものは観ない」と言う。ジャマールが最後の質問に臨む回において、国中の至る所で皆(ボスのような人はいないけど)がテレビに張り付く場面は楽しい。私もこの番組の日本版を数回観たことがあるけど、どういう気持ちだったろう?あまり感慨はなかったように思う。
・主人公と兄、ラティカは幼少時・少年期・青年期とそれぞれ3人の役者によって演じられる。幼少時は兄弟の区別が付かず困った。幼いラティカ役の子は、気の強そうな面白い顔立ちだったけど、大人になるとそうでもなくなっている。意図じゃないんだろうけど、色々あって、ああいう顔つきになったんだと思うとしっくりくる。
・ラストシーンでラティカが身に着けているスカーフやその色には、何か意味があるんだろうか?
(09/04/18・バルト9)
ベティの小さな秘密 (2006/フランス/監督ジャン・ピエール・アメリス)
フランスの田舎町。10歳のベティは、元ピアニストのママと、精神病院の院長のパパ、「一番の友達」のお姉ちゃんと暮らしている。しかしお姉ちゃんは寄宿制の学校に入学、ママは家を出ようとしており、パパはいらいら。
パパに「嘘をつかれた」ベティは、病院から逃げた青年イヴォンを納屋にかくまうことで「小さな秘密」を持つ。
冒頭のベティの様子からは、どことなく「ちぐはぐ」な印象を受ける。周囲の皆を愛しているが、うまくいかない。後に自分で言うように「不器用」なのかもしれない。お姉ちゃんは居なくなってしまうし(お化け屋敷で、ベティを降り返りもせず逃げてしまうのがフランス映画ってかんじで良い・笑)、ママは町へ出かけてばかりだし、パパは忙しくて一緒にごはんが食べられない。それでも「大丈夫、何でもないわ」。自転車を漕ぐ足の速さに、彼女の心が表れているようだ。
ベティは、飼っているウサギや保健所行きを控えた犬などに対し、しきりに「私がついてるわ」と言う。病院から逃げ出してきたイヴァンに対してもだ。大人同士のやりとりなら、私がもしそんなこと言われたら、「守り欲」のために一緒にいるなんてやなこったと思ってしまうけど(と言いつつ結果的には守られてばかりだけど)、彼女を見ていると、単純に、生きる者・生に対する執着って、いいものだなと思わせられる。
ベティはイヴァンをかくまう納屋に「リビング」や「寝室」をこしらえ(このささやかなシーンが楽しい)、セーターを着せてあげたり、ものを食べさせてあげたりとあれこれ世話を焼く。それに応える彼は動物のようだ。
作中もう一人出てくる「男」は、新学期にやってきた転校生。顔にアザがある彼について、ベティは「クラスで話かけるのは私だけなの」と語るが、彼は彼女を騙し、皆の前で笑い者にする。彼にとっては、そうすることが皆の仲間になる唯一の手段だったのかもしれないし、看護師の息子として「院長の娘」に複雑な気持ちを抱いていたのかもしれない。しんみりするくだりだけど、同時に、体に障害がある(ベティはそう感じている)男が女を手玉に取るというのは、セクシャルな感じがして、どきどきさせられる。
イヴォンと犬のナッツを連れて森の中で一夜を明かした後、ベティは熱いコーヒーを用意する。チューブから入れたのは…練乳じゃなくてコーヒーフレッシュのようなものかな?美味しそうじゃないけど、陽の光の下で誰かと一緒なら、わるくない。
(09/04/17)
いとしい人 (2007/アメリカ/監督ヘレン・ハント)
ヘレン・ハントの脚本・監督・主演による作品。とても面白かった。
 39歳の教員エイプリル(ヘレン・ハント)は出産を切に望んでいるが、夫のベン(マシュー・ブロデリック)に別れを告げられる。時期を同じくして養母が亡くなると、トークショーのホストとして有名なバーニス(ベット・ミドラー)が実の母親だと接近してくる。混乱しつつも、妻に去られた父兄のフランク(コリン・ファース)と親しくなるが、妊娠が発覚し…
39歳の教員エイプリル(ヘレン・ハント)は出産を切に望んでいるが、夫のベン(マシュー・ブロデリック)に別れを告げられる。時期を同じくして養母が亡くなると、トークショーのホストとして有名なバーニス(ベット・ミドラー)が実の母親だと接近してくる。混乱しつつも、妻に去られた父兄のフランク(コリン・ファース)と親しくなるが、妊娠が発覚し…
あることに執着する様をコメディタッチで描くというのは、そのこと(この作品では妊娠・出産)をカジュアルに扱ってると感じられるから、まずそれが好みだ。何でももっと気楽になればいいと思ってるから。子どもが欲しいと思ったことのない私も楽しく観られる。周囲の子どもたちとの、わざとらしいエピソードや場面がほとんどないのもいい。
そして、観ていて楽しいのはキャストの面々。
ヘレン・ハントはアンニュイな感じの垂れ目がキュート。もしあれが男の顔なら、ベッドの中でまぶたや法令線をのばして遊びたい。
冒頭の夫との話合いの様子など、彼女の真面目で頑固な性格を表していて笑えるけど、彼女が頑として「血のつながった子ども」にこだわるのは、もともとの性分に加えて生育歴のためなのだ。
それからベット・ミドラー。ロマンチックだけど実際的で、迷惑だけど憎めない。ペタ靴でさっさと歩くヘレンを、高いヒールの彼女がよちよち追いかけるという「いかにも」なシーンが二度あり、それだけでも楽しい上に、どちらの顛末も面白い。「送ってくれる?…今の店まで」/「心の中ではひざまずいてるわ」(いつか使ってみたいセリフ・笑)「…」「しょうがないわね!」→上の画像(本国のポスター)
シャツと下着だけの姿には、「メイクアップ・ハリウッド」で読んだエピソードを思い出した。
(「フォー・ザ・ボーイズ」の撮影中、軍服の上着に素脚とハイヒールという衣装が気に入らずごねていた彼女に、著者であるカオリ・ナラ・ターナーがボディメイクアップをほどこしたところ、気に入られ仲良くなったという話。この映画じゃそういうのは使わなかったろうけど、大丈夫だったのかな?)
男たちのキャラクターははっきりいってしょぼいけど、役者は豪華。
今や「フツオ」みたくなってるマシュー演じる夫のベンは、病室でもキャップを脱がない、ジャージとスニーカーの男。それでも久々に会えば、新鮮に感じて食指が動くのが笑える。寂しんぼうキャラですぐ恋人もできたんだろう。
コリン演じるフランクは…登場時くたびれ具合にびっくりしたけど(子どもを抱えて妻に去られた役なので、それでいいんだけど・笑)…最初は訳の分からないやつだけど、少し親しくなってみれば、分かりやすく可愛い男。「you move me」/「家族で薬をもらいに行こう」「…一緒に行かないの?」意図してるのかどうなのか、こういう、すっと心に入り込んでくる男っている。
エイプリルは、自分の意見をはっきりと述べ、相手に「どう思う?」「どう感じる?」と聞いて会話を進める。
新たな人間関係に揉まれた後、「神に裏切られてきた」彼女が、これまでとは違った心でお祈りをするシーンにはじんとしてしまった。
女優さんの初監督作ということで、昨年公開されたジュリー・デルピー脚本・監督・主演「パリ、恋人たちの2日間」を思い出した(感想)。
「パリ〜」の方が会話に重きが置かれてるけど、「この先どうなるか分からない」、でも今は好きだから一緒にいたい、という結論に達するところは同じだ。ただ「いとしい人」のエイプリルは、執拗なくらい将来の危うさを主張し、ほぼ無理やり、フランクにもそのことを認めさせる。これまで「裏切られてきた」と感じてきた彼女の身を守る術に思えて、ほろっとした。
「彼女を許したいの、でも・・・」
「何か買ってもらえよ」
(これはなかなかいいアドバイス!その後こうなる↓)
「償ってほしいの、あなたじゃなく私のために」
(09/04/15・角川シネマ新宿)
グラン・トリノ (2008/アメリカ/監督クリント・イーストウッド)
(09/04/09・よみうりホール試写会)
チャーリー・バートレットの男子トイレ相談室 (2008/アメリカ/監督ジョン・ポール)
金持ちの息子で成績優秀なチャーリー(アントン・イェルチン)の願望は、学校の人気者になること。問題行動と放校の末にとある公立学校に行きついた彼は、生徒たちへのカウンセリング業と薬の転売を始め、校内のカリスマとなる。
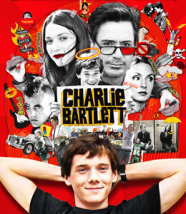 邦題からイメージするほどトイレにこもってるわけじゃないけど、チャーリーが皆と話すのがトイレの個室越しというのがいい。聴聞室のようでもあるし、「フェリスはある朝突然に」のマシュー・ブロデリックのように、こちらに向かって語りかけてくるわけじゃないけど、個室の中から「こっちのほう」を見ながら自分のことを話すというスタイル。
邦題からイメージするほどトイレにこもってるわけじゃないけど、チャーリーが皆と話すのがトイレの個室越しというのがいい。聴聞室のようでもあるし、「フェリスはある朝突然に」のマシュー・ブロデリックのように、こちらに向かって語りかけてくるわけじゃないけど、個室の中から「こっちのほう」を見ながら自分のことを話すというスタイル。
チャーリーが自分をいじめた相手を「友達」として取り込む際、事前に鏡の前で彼へのセリフを練習するシーンが印象的だ。彼にとっては内容の真偽じゃなく、自分の話ぶりが与える印象とその効果が重要なのだ。でもカウンセリングを行ううち、チャーリーと生徒たちとのやりとりは自然なかんじになってくる。彼自身の心もほぐれてきているのが分かる。
鏡といえば、男子トイレには申し訳程度の横長の鏡が掛かってるけど、使う者はいない。作中唯一それをのぞきこむのは、チャーリーと仲良くなったスーザンだけだ。
お嬢様育ちのチャーリーの母親は、音楽やテニスに興じて日々を過ごし、息子のことを愛している。チャーリーと一緒に「塀の中」の夫に会いに行く際、始めは黒いトップスと柄のスカートだったのが、終盤では全身ピンクのワンピースを身に着けている。私ならああいう服は、自分の気持ちが揺るぎなく晴れて、同伴者とうまくいってるときにしか選ばないだろう。
公立学校の校長であるネイサン(ロバート・ダウニーJr.)は「どうせなら平教員のままのほうがよかった」と愚痴りながら、酒を飲みラジコンボートで遊ぶ。
ラストで、クビになった彼をチャーリーが訪ねる。
「ぼくはstupid kidだ」
「…なんて言ったんだ?」
「ぼくはただの子どもだ」
「そう、お前は子どもなんだ!」
若者と場を同じくする仕事に就き「大人」として働いているとき、「責任」は持たず皆に影響を与えるチャーリーのような人間が現れたら苛々することだろう。子どもなんだからしょうがない、と思うしかない。
それから、学校の女の子たちのルックスが女優っぽくなく自然なのが目を引いた(ああいう学校なんだから当然だけど)。そう感じたのは、昨年観た「英国王給仕人に乾杯!」以来(これは違う意味で…胸をいじってなくて、よく昔っぽい人を集めた&見せたなあと感心した)
「今から外出禁止よ」
「どれくらい?」
「そうねえ…普通はどのくらい?」
「24時間かな」
「じゃあ、逮捕されたんだから30時間ね」
(09/04/08・ヒューマントラストシネマ文化村通り)
フロスト×ニクソン (2008/アメリカ/監督ロン・ハワード)
ウォーターゲート事件から3年、辞任し沈黙を守るリチャード・ニクソン(フランク・ランジェラ)に対し、英国人のテレビ司会者デビッド・フロスト(マイケル・シーン)がインタビューを申し込む。政界進出をもくろむニクソンと、全米進出を目指すフロスト。「スポットライトが当たるのは片方だけ、敗者には荒野のみ…」
予告編からはフロストとニクソンの「一騎打ち」という印象を受けたけど、映画はインタビューの場やその内容にばかり重きを置いているわけではない。まず二人は当然ながら、背後にブレーンを抱えているから、男…というかおじさんのいっぱい出てくる類の映画と言ってよい。資金繰りに奔走するフロスト自身を含め、描写はさらっとしてるけど、各々が自らの目的のために行動する様が楽しい。
また、作中の当の二人がこだわっていても、映画自体は「勝つか負けるか」を重々しく扱わない。その軽いかんじがいい。
インタビューの後日、ニクソンを訪ねたフロストが「パーティを楽しめることは幸せだ」…から続くセリフを言われるシーンに少し驚いた。観ながらずっと感じてたことだったから。上に書いたように、この映画ではインタビューでのやりとりはさほど大きな意味合いを持たないし、私にはフロストがインタビュアーとして優れているのかよく分からず、これは、人好きがすることを(我知らず)武器に頑張った、負けず嫌いの「tv-show guy」が勝つ話だなあと思っていたからだ。
(しかし作中のニクソンは「勝ち負けに関わらず、目的を持つことこそが人生を豊かにする」という考えの持ち主なのだから、負けたところで不幸には見えない)
ちなみに冒頭、機内でフロストが知り合ったキャロラインは「あなたは才能もないのに売れてるって話よ」と口にする。何気なく出たのか、反応を見たのか、いずれにせよ彼女は彼の才能や知名度ではなく、そのチャームに惹かれて行動を共にしていたように感じられ、そこのところが良かった。
フロストは、オリヴァー・プラット演じるジャーナリストやサム・ロックウェル演じるノンフィクション作家などと即席チームを組む。「a few freind」と誕生日を祝いたい、と言って去るシーンが可愛い。また、欧米の映画からいつも感じることだけど、「好き嫌い」や「なあなあ」に依らない付き合いが見ていて気持ちいい。
ケヴィン・ベーコン演じるニクソンの側近ブレナンの忠犬ぶりには(性的な意味で)ぐっときた。インタビューの後、彼の暮らしには何か変化があったんだろうか?
インタビュー前に彼とフロストが「言葉の定義」についてやりとりするシーンは、実際的な内容で面白い。交わされた「契約書」の内容を知りたいものだ。
この作品は、テレビ用のインタビュー(の撮影場面)を映画で描いているわけだけど、作中ふと、そのインタビューの単純な視聴者になることもあった。初日の、抽象的で一般的なニクソンの語りには眠気を覚えた。また、カンボジア問題の追及のために用意された映像に付けられた音楽は、陳腐でばかばかしく感じられた。既成のものを使ったのか、視聴者を意識したのか、「テレビは全てを矮小化してしまう」と理解しているジョン…テレビ側の人間であるフロスト達がああいうのを使うというのは、ちょっと面白い。
唯一の女性キャラクターであるキャロラインがらみで、とくに興味ぶかいシーンがなかったのは残念。靴を履くのが嫌いらしいところと、初めてニクソン邸を訪ねた際、窓からかつてのファーストレディを目にするところは面白かった。
彼女はフロストが生涯でおそらく一番必死になった時期に遭遇したのだから、そうそう、忙しい男に接するときってこういうふうだよなあ、というのを期待したけど、そういうシーンも無かった(私は忙しい男の人とは付き合わないけど…笑)
それにしても、もし日本なら、これから大統領(首相)に会いに行くんだけど来る?という誘いって、功を奏さないよなあ…(だって会いたいなんて、思わないじゃん?笑)
(09/04/01・新宿武蔵野館)
マーリー 世界一おバカな犬が教えてくれたこと (2008/アメリカ/監督デヴィッド・フランケル)
フロリダで新婚生活を送るジョン(オーウェン・ウィルソン)とジェニー(ジェニファー・アニストン)は、子育ての前にとラブラドールレトリバーを飼い始める。なぜか破格の値段だった子犬は「マーリー」と名付けられるが、犬のプロも投げ出すほどの行儀の悪さ。二人は苦労しながらも仕事や育児に精を出す。
 映画の始まりと終わりが好きな人の声というのはいいものだ。オーウェンが新聞記者の役なんて…と思ってたけど、子犬(といっても既に結構でかい)を迎えに行き、車に乗せて帰る姿に「オーウェンと犬!オーウェンと犬!」と興奮。彼の手によるコラムに合わせた「犬と、振り回されるオーウェン」の軽快なシーンが楽しい。
映画の始まりと終わりが好きな人の声というのはいいものだ。オーウェンが新聞記者の役なんて…と思ってたけど、子犬(といっても既に結構でかい)を迎えに行き、車に乗せて帰る姿に「オーウェンと犬!オーウェンと犬!」と興奮。彼の手によるコラムに合わせた「犬と、振り回されるオーウェン」の軽快なシーンが楽しい。
観賞後に同居人が「よく分からないところもあった」と言ってたから、犬を飼ったことがある人の方がより楽しめるのかもしれない。でもここに描かれているのは、あるカップルが「若く輝いていたころ」から妊娠・出産、子と犬に振り回される日々を経て、家庭を作り上げていく姿。オーウェンもジェニファーも、少しくたびれた感はあるけど、演技もなかなかで、チャーミングだった。
マーリーはバカなことをして、たまに飼い主の慰めとなり、やがて死んでいくだけだ。ジョンは自分の手に回ってこない仕事に憧れ、ジェニーは過去に立てた人生の計画を遂行しようとするが、日々の暮らしの中、人の思いやその関係は変わってゆく。そこにはただのバカ犬の存在もある。
(以下はほとんど、昔うちで飼ってた犬の話)
私が子どもの頃に飼っていた犬も、かなりのバカ犬だった(でも世界一の美男犬で、今でも夢に出てくる)。田舎だから庭に鎖で繋いでおけば済んだので良かった。犬小屋に貼りつけた自分の名前(の木片)を食べてしまうし、公園に連れて行くと物を食べている人めがけて突進するし、散歩中に突然引っ張られた祖父は肩を脱臼した。
マーリーはフロリダとフィラデルフィア、海と雪とを経験する。海に入るシーンでは、うちの犬が初めて泳いだ日を思い出し、雪の日に遊ぶシーンには、そうそう、うちの犬は白いと思ってても、雪の中だと茶色くて全然目立つんだよなあ、などと思い出した。
その後に上京した私は彼の死に際を知らない。でも帰省するたびに目立つ老いには心を痛めていたので、マーリーに死の兆候が現れ始めた頃からは何度も目頭を熱くした。新居の階段をのろのろとしか上れない足取り。子どもたちをバスまで迎えに行く際の、今にもくずおれそうな脚。どこを見ているのか分からない目。オーウェンが獣医に「うちの犬は普通じゃないから…」と言うシーンにも、ベタだな〜と思いつつ泣いてしまった。
マーリーを埋める際、ジェニファーが「さよなら、セールわんこ」と言うのが印象的だ。バカさって、環境の影響も勿論あるけど、生来のものも大いにあるなと思った。
(09/03/27・ユナイテッドシネマとしまえん)
ヒストリーボーイズ (2006/イギリス-アメリカ/監督ニコラス・ハイトナー)
2006年のトニー賞で6部門を受賞した舞台の映画化で、8人の男子高校生が名門大学を目指す話。
 男子・イギリス・80年代…というだけで楽しいけど、観ているうちに教員の方に心動かされた。
男子・イギリス・80年代…というだけで楽しいけど、観ているうちに教員の方に心動かされた。
イメージばかりで何がなんだか分かっていない軍人タイプの校長が作った進学組を担当するのは、「寂しいホモエロおやじ」の文学教師ヘクター(リチャード・グリフィス)、ハリウッドでリメイクされたらキャシー・ベイツが演じるであろう歴史教師のドロシー、そして即戦力として雇われた、優男エリート風の臨時教師アーウィン。舞台の映画化だからか、先生・生徒いずれについても、学校外での日常や背景にはほとんど触れられないのが硬派で好み。
上記3人の指導風景からは、「世の中なんでもアリ」だなんて甘っちょろい(あるいは通過すべき)姿勢であり、顔を合わせたばかりの相手に対しても自分の意見を強硬に主張できるほど足元を固めておくことが、教員の最低限の資質かもしれないと思わされる。生徒はとにかく何かをやらなきゃならない、そのためには足場が必要なのだ。
校長の適当さのせいもあり、3人はまとまりのないまま、全く違う方針で授業を進める。一堂に揃った面接指導のときのぐちゃぐちゃさが可笑しい。
「イギリスの名門大学の受験」ってどんなものか知らないけど、作中アーウィンが行うトレーニングは論文作成が主だ。「覚えておけばいつか分かる」と詩を暗記させ、映画や歌などの要素を授業に取り入れるヘクターに対し、「オックスフォード出」の彼のモットーは「知識を総動員して…『隠し玉』を使って、他人とは違うことを主張しろ」。
ホロコーストについて(歴史の授業で扱えるか否か)議論する場面でのアーウィンの指導や、ヘクターのある行動がそのままにされるという内容はどうなのか?と思うけど、こういうこともある、という話なんだろう。
この作品で描かれるのは、人と人とのやりとり、そこから生まれるものだ。授業の途中、生徒主導で関係ないことに盛り上がったり、教師の側が感情をぶちまけたり、一対一での会話が進むにつれて空気が変化したり。
日本のテレビドラマのように受験勉強の過程を分かりやすくドラマチックに描いてはいないので、受験当日は普段と同じようにやってくる。大学を訪れて「お城みたいだ、うちの親に見せたい」と言うのが可愛い(彼等の家庭は労働者階級)。昔のマット・ディモン風のオッジ(スポーツばかりの自称「単純バカ」)が面接を受ける部屋のすごいこと。
自称「ユダヤ人でチビだから最悪」のポズナーは、社交的でどこにいても目立つデイキン(ドミニク・クーパー…どうしても「フルハウス」のおいちゃんを思い出してしまう)に思いを寄せており、一分一秒それを隠そうとしない。ちなみに彼だけでなく、ヘクターもアーウィンもゲイだけど(対象が細かく違うかもしれないけど)、作品にはいわゆる「ゲイ映画」の雰囲気はない。たまたまそういう人たち(そういうことをオモテに出す人たち)が集まってるのかなあ、という感じだ。
またポズナーがダイキンに「ご褒美」に抱擁してもらうシーンを見て、全ての人間の色恋がこんなふうだったらどんなかなあと思った。誰もが簡単に迫れて、簡単に拒否できたら、どんなに楽だろう。社会的には有り得ないだろうけど(笑)
ところで、映画で有名な「ノーマンズ・ランド」という言葉は、ああいうときにも使うのかあ。80年代の(今ではちょっと古い)言い回しなのかな?ちなみにフィクションではよくああいうシーンがあるけど、なぜあんなことが出来るのか、私には理解できない…
(09/03/24)
ベッドタイム・ストーリー (2008/アメリカ/監督アダム・シャンクマン)
アダムが車中で「Rock Me Amadeus」を歌うシーンが最高(字幕版で観たかいがあった!…そして、ファルコがもういないことを思って哀しくなった)
 ホテルの設備係・スキーター(アダム・サンドラー)は、かつてオーナーだった父親(ジョナサン・プライス)から夢を引き継ぎ地道に働いているが、出世は困難。
ホテルの設備係・スキーター(アダム・サンドラー)は、かつてオーナーだった父親(ジョナサン・プライス)から夢を引き継ぎ地道に働いているが、出世は困難。
ある日、姉の子どもたちに語って聞かせたおやすみ前の物語が現実となった。驚きつつもそれを成功に繋げようと試みるが…
想像してたよりずっと面白かった。予告編はダメすぎる!この映画はまず設定が面白いのに、あれじゃあ勘違いしちゃう。でも端的に印象づけるのは難しいから、しょうがないか。
私は「エージェント・ゾーハン」のように「アダムがいるだけで笑える」ものが好きだから、彼のキャラクターよりも設定やストーリー、脇役の面白さが目立つ映画はつい勿体なく思ってしまう。勿論それでもじゅうぶんだけど。友人役の偽ジョニー・デップみたいなラッセル・ブランド(ディズニー映画で役名が「ミッキー」・笑)、ライバル役のガイ・ピアース(クレジット見るまで誰だか分からなかった!)のつなぎ+少し浮いてるヘルメット姿、正しい役柄で出演してるロブ・シュナイダーも良い(笑)
アダムの「プレゼン」シーンがとにかく面白くて、劇場であれだけ長時間続けて笑ったのは久し振り。単純な笑いのパワーってすごい。比べる意味ないかもしれないけど、ベン・スティラーが「トロピック・サンダー」でシンプル・ジャックを演ったのより、こっちの方が断然好み(笑)
冒頭の過去シーンから正反対の性格であることが分かるスターキーと姉(コートニー・コックス)とが、ラストでは理解を深めるのがいい。
また、この映画の大きな魅力は、舞台がホテルであること。スキーターいわく「家庭的な雰囲気がいいなら家に居ればいい、ホテルとは非日常を提供する場所」。子どもたちを連れ出す「キャンプ」が魅力的だ。ディズニー映画ってことで、ディズニーホテル(私は泊まったことないけど)のコンセプトを思ったりして。
ハッピー・マディソンの映画は、カラフルで、悪い人が出てこないというイメージがあるから、ディズニーとは相性がいいのかもしれない。
でもって「観終わった後にマシュマロが食べたくなる映画」でもある。ハンガーで焼いて。帰りにコンビニに寄ったけど、置いてなかったのでかなり欲求不満に…
(09/03/22・新宿ピカデリー)
映画は映画だ (2008/韓国/監督チャン・フン)
キュートで楽しい映画。韓国映画には疎いので、チャン・フン監督始め出演者も誰も知らない(原案はキム・ギドク)。劇場で見た予告編に惹かれて観に行った。
韓国の「主役型」の俳優さんは、恵まれた身体を更に鍛えて美しく(二の腕や胸が素晴らしい)、動きもきれいだなあと感心した。
 アクション映画で人気を博す俳優のスタ(カン・ジファン)と、かつて役者を目指していたヤクザのガンペ(ソ・ジソブ)。激しやすい性格のため相手役を見つけられないスタは、たまたま知り合ったガンペに共演を依頼する。
アクション映画で人気を博す俳優のスタ(カン・ジファン)と、かつて役者を目指していたヤクザのガンペ(ソ・ジソブ)。激しやすい性格のため相手役を見つけられないスタは、たまたま知り合ったガンペに共演を依頼する。
冒頭、町中のファミリー向け風の映画館から出てきたガンペは、すぐさまタクシーに乗り込み、手下が待つ車へ向かう。私なら映画の後は、誰かと一緒でも一人でも、歩いたりお茶したりして余韻を味わいたいけど、多忙な人は大変だ。
後日、人気俳優のスタが同じ店にいると知った彼は個室を訪ねる。「ヤクザ『なのに』映画好き」という要素をコメディ調に扱う映画は幾つかあるけど(「ゲット・ショーティ」など)、この映画ではその部分の描写はあっさりしたもの。だから余計、手下に「映画を撮ろう」と命じて遊ぶシーンが可愛らしく映る。
サインをもらっておきながら「演技とは、苦労してないヤツが真似をすることだ」と言い放つガンペ。観客である私からすると「それを言っちゃあおしまい」に過ぎない言葉だけど、自分の演技のリアリティに疑問を抱いていたスタは、彼のことが忘れられなくなる。
スタが求める「演技のリアリティ」とは、主にアクションの真実味のことだ。「本気で喧嘩すること」という条件をスタに飲ませたガンペは、ヒロインに対し本気のように襲いかかり(といっても自分の衣服は着けてたから、何をしてたのかよく分からない…)撮影を中断させてしまう。「本気の殴り合い」と「本気のレイプ」はどう違うんだろう(もちろんこの場合、相手役の了承を得ていないという問題があるけど、得たらレイプにならない)。「本気の殴り合い」は他のジャンルの映画なら、何に相当するんだろう。結局のところ、演技というのはどこか滑稽で、また当事者の心身を削るものだと思った。
幾度かのアクションシーン(アクション「撮影」シーン)の最中、なぜか先月観た「その男ヴァン・ダム」の冒頭の長回しシーン(これもまた「撮影」シーンだ)を思い出した。あれは見るからに「見世物」で、楽しかった。
ストーリーは、映画の撮影と、二人の身辺に起こる事件とが同時進行で進む。映画を通じての関わり合いが、彼等の私生活における言動に影響を及ぼす。そのことが必ずしも、彼等の「元の世界」的には、良い結果をもたらさないのが面白い。
ソ・ジソブ演じるヤクザは、寡黙ながら手下からの信頼は篤い。地味な一人暮らしの描写と、ベッドでマグロっぽいところが、いかにもというかんじでぐっときた。
カン・ジファン演じる俳優は、何かを口にしているシーンが多く(チョコレートやクラッカー?など)、実際の彼も同じようなんじゃないかと想像してしまった。また彼が恋人をカフェに呼び出すシーンは、「自分が変われば、世界の自分への接し方も変わる」というよい見本で、心動かされる。
ヒロイン役の女優さんは、格好がちょっと80年代ぽくて可愛い。とくに登場時のワンピースが好き。ある場面で、私が中高生の頃(90年前後)「フィッシュボーン」と呼んでた髪型をしてたのにはびっくりした。
作中の映画監督(江川達也〜マイケル・ムーア似)は、始めこそおどおどしているものの、結構身軽な動作で演技にケチを付けたり、作品のためならヤクザにくってかかったりと、憎めないキャラクター。
行く先々でチャミスルとそのグラスが何度も出てきたのも楽しかった。うちも近所の酒屋で買いだめして、行き付けの韓国料理屋さんのママに分けてもらったグラスで飲んでるから。
(09/03/17・シネマスクエアとうきゅう)
パッセンジャーズ (2008/アメリカ/監督ロドリゴ・ガルシア)
クレア(アン・ハサウェイ)は、飛行機事故で生き残った5名のセラピーを依頼され、仕事に取り掛かる。しかし周囲に尾行者らしい人影が現れ、生存者は一人ずつ姿を消してゆく。
(以下ネタばれに近いことを書いてます)
劇場から出る際、ポスターの「その真相を追ってはいけない」というコピーに違和感を覚えた。「追わなきゃだめ」なんじゃないの…?
予告編から私が連想してたのは、ウィリアム・アイリッシュの「階下で待ってて」。仕事中の恋人がビルから出てこないまま忽然と消えてしまうという似ても似つかないストーリーで、最後に読んだのは10数年前だけど、なぜかふと思い出した。もやの中の敵と一人で戦う、というイメージかな?
実際はいわゆるサスペンスではなく、言うなれば「癒し映画」だった。でも「癒し」が得意でない私も、主人公が真実を知るまでの、地に足ついてない感じを味わうのが楽しかった。夢だと気付いていながら目が覚めない、そんな感じ。
観た後に抱いた大きな疑問は、ここで描かれているのが、クレアのみが認識している世界なのか、それとも「中途」の数名が同じように認識している世界なのか、ということだ。エリック(パトリック・ウィルソン)が全裸で登場したり、ハイテンションに迫ってきたりするのは、彼に性的魅力を感じた彼女の意識が作り上げた姿だと思うんだけど、それならば他の数名はどんな彼を見ていたのか?もっともどんな映画であれ「誰にとっての世界か」ということを考えたらキリがないし、現実でも皆が認識する世界が同じものであるか否かは解釈が難しいところだから、何とも言えない、あるいは逆に、何とでも言えるけど。
私の「夢」の中に出てくる彼が、私と同じ「夢」を見ることはないけれど、恋愛などの感情や体験が交差することにより、共通の「夢」を見ることもあるかもしれない。そう考えると面白い。
主人公の役どころは、今の女優さんならアン・ハサウェイにしか出来ないなあと思った。心身ともに健康で聡明だけど、ちょっと気のつかない感じ(同行者いわく「あんなセラピスト、いらいらするから絶対やだ」笑)。「プリティ・プリンセス」以降の劇場公開作は全部観てるけど、これが一番しっくりくるかも…少なくとも「ゲット スマート」よりはまってる。作中の、常に黒(に近い色)のトップス+パンツという服装、同じく黒を基調とした、無機質だけど自然な感じの部屋は、とても感じがいい。
パトリック・ウィルソンも結構かっこよかった(…と思ったのは初めて・笑)裸や下着姿、バイクに乗るなど見所も多い。一番チャーミングなのはラストの事故シーンかな?これは意味深いことかも。
久々に見たダイアン・ウィーストに口をゆがめたクレア・デュバル、犬なども良かった。
同行者の感想は「落語みたいなオチだな」。ちなみに私の隣のおじさんも、同行者の隣のおじさんもスースー寝ていた。上に書いたように終盤までは本当にもたもたしてるので(それがこの映画の味だと思うけど)、眠くなるのも分かる。
(09/03/14・TOHOシネマズみゆき座)
ダウト〜あるカトリック学校で〜 (2008/アメリカ/監督ジョン・パトリック・シャンリィ)
60年代のニューヨーク・ブロンクス、カトリック系の教会学校。保守的で厳格な校長のシスター・アロイシス(メリル・ストリープ)は、自由な雰囲気で人気を博すフリン神父(フィリップ・シーモア・ホフマン)が、転校してきたばかりの黒人少年と「不適切な関係」にあるのではないかと疑い、彼を追放しようと行動を起こす。
 教会・学校内部と、シスターが足を伸ばすほんの近所が舞台だから、まず「閉じられた世界」の話として面白い。冒頭、説教の準備を手伝う男の子の姿も新鮮だし(女の子はやらないのかなと思ったけど、後に幾つかのシーンでああ、これは60年代の話なんだと気付かされる)、シスターたちの起き抜けや食事の様子なども、きれいな映像で撮られている。
教会・学校内部と、シスターが足を伸ばすほんの近所が舞台だから、まず「閉じられた世界」の話として面白い。冒頭、説教の準備を手伝う男の子の姿も新鮮だし(女の子はやらないのかなと思ったけど、後に幾つかのシーンでああ、これは60年代の話なんだと気付かされる)、シスターたちの起き抜けや食事の様子なども、きれいな映像で撮られている。
校長と神父の板挟みになる新米教師のシスター・ジェイムズ(エイミー・アダムス)は、素直で快活で、見ていて気持ちのいい人物だけど、登校指導のときから(もっと言うなら登場時から)先生としてはダメそうで、案の定、授業もひどい。放課後、彼女の教室を訪れた校長との「きちんと生徒を管理できてるの?私の所に送られてくる子が少ないけど」「自分で何とかしようと思ってるんです」(中略)「『ボールペン』が落ちてるわ」「私は禁止してます」(このセリフで彼女の性格が分かる。頑張り屋だが物事を深くは考えないようだ)などというやりとりが「(学校の)お仕事」的に面白い。その後の「どの教皇だっていい」理由も可笑しい。
校長が神父を呼び付け、件の少年を受け持つジェイムズ含む3人が校長室で対峙するシーンはやはり見もの。女であるシスター(校長)がいくら頑張っても、神父より地位は下。もともと一触即発の状態だったのが、「疑惑」により爆発する。上座の自分の椅子に座られた彼女は、神父を責め、席を取り戻す。
「悪者より知恵を働かせるのが自分の仕事」「神から離れても任務を遂行すべき」という考えの校長、お酒もたばこも大好きで生徒の色恋も応援するフリン神父、「子どもが大好き」なシスター・ジェイムズ、個性は三者三様で、学校には色んなオトナが必要だよなあ、と改めて思わされた。
メリル演じる校長は、登場時、黒い帽子で顔が見えない。でも彼女だと知ってるせいか否か?たたずまいだけで彼女、しかもどういう役柄の彼女なのか分かる。
彼女は厳格なだけでなく、年長のシスターが施設に送られないよう庇ったり、激昂するジェイムズが思わず肩の力を抜いてしまうようななだめ方をしたりと、面白味も備えた人間だ。ああいう人物に近付いて、自分へのある種の愛…執着を持たせられたら、性的に快感を得られるだろうなあと思った。そういう観方をしていると、彼女が何度か見せる惑いやラストシーンには、がっかりさせられる(笑)
フリン神父とシスター・ジェイムズ、校長とドナルド少年の母親、それぞれのやりとりから、この社会で「愛」と呼ばれるものは何なのだろうと考えた。当人同士の外に出たとき、それは問題となる。「哀れみから?」という校長の言葉も印象的だ。
ちなみに作中一番エロティックなのは、校内でドナルド少年が神父様を見つめる表情。それを受けてから部屋に入っていくフィリップ・シーモア・ホフマンのやり方も、デブなのに!憎らしいほどいやらしかった。
(09/03/12・TOHOシネマズシャンテ)
レールズ&タイズ (2007/アメリカ/監督アリソン・イーストウッド)
レンタル店に最新作として並んでいたもの。ジャケに「あの才能ある監督の娘、アリソン・イーストウッドの初監督作!」(語呂がわるい)とあるから、ついイーストウッド映画と比べながら観てしまった。
鉄道運転士のトム(ケヴィン・ベーコン)と末期がんに侵された妻のメーガン(マーシャ・ゲイ・ハーデン)のもとに、トムの列車で無理心中を計り亡くなった母親の息子がやってくるお話。音楽はカイル・イーストウッドが担当。
最後に「いつまでも一緒だよ」なんてセリフが出てくるんだから、イーストウッド映画とは全然違う世界だ。でも冒頭、特急列車を運転するケヴィン・ベーコンが仲間に「この仕事も先細りなんだから、身の振り方を考えないと」なんて言われるあたり、しかしケヴィン自身は「俺には鉄道しかない」なんて言うあたり、消えゆくものを描いた物語ということで、パパの映画と通じるところがあるかも。もっとも(作中の)特急列車が「消えゆくもの」とはあまり思えないんだけど。
そもそも、だいぶ老けたケヴィンのたたずまい自体もイーストウッドに似てるような気がした。妻に話しかけるときのちょっともじもじした感じとか。
私の大好きな鉄道模型も出てくる…んだけど、残念なことにあまり魅力的には撮られていない。監督は列車が好きじゃないのかな…?(笑)ケヴィンは鉄道に執着してる(と口で言ってる)わりにはそうした描写はとくにないし、彼と少年とのつながりも深くは描かれず、色んな点であっさりした作品だった。でも話の展開が早いのは、観易くて良かった。
(09/03/10)
ヤッターマン (2009/日本/監督三池崇史)
深田恭子の「よいしょ、よいしょ」という掛け声が耳に残って離れない…。
アニメの映画化(って、あまり他を知らないけど)として、かなり面白いと思った。
74年生まれの私は、小学校にあがる前に「ヤッターマン」の本放送を観た(もしくは少し後に再放送を観た)世代。懐かしさにひたってるとその感情を洗い流される、の繰り返しで、それが気持ちよかった。勝手に走り出す感じのオープニングも最高。
原作通りドクロストーンの争奪戦を描きながら、後半はドロンジョ様(深田恭子)の色恋問題に発展。目と目で…のガンちゃん(櫻井翔)とドロンジョ様に嫉妬するアイちゃんの姿に、「お子様は恋愛できない」「だから大人にあこがれる」ものだった昔の漫画を思い出し、懐かしさを覚えた(昔書いた気がするけど、「ガラスの仮面」の速水さんとマヤの関係に、今読むと違和感を覚えるのもこのためだと思う)。
もっとも同行者の記憶によると、原作ではドロンジョ様はガンちゃんを子ども扱いしてたようなので、オトナの女の心を射止めた今回は男の方の恋愛年齢は引き下げられたようで良かった(笑)
ドロンジョ様以外は原作に沿って集めたというかんじのキャスティングなので、「すごい演技」は観られない。阿部サダヲが苦手な私には、後半の嫌がらせは利いた。1号役の櫻井翔は、もうちょっとセクシーに撮れないものかな?と思ったけど(だって男キャラは彼一人みたいなもんなんだから・笑)、キャラクターにぴったりはまっていた。2号役の女優さんは、あのキャスケットが似合わないように感じたから、もうちょっと違う形ならいいのにと思った。
深田恭子が好きな私は、彼女が出るから観に行ったんだけど、「私の心を盗んだ、だから…」のセリフには心が震わされた!私とさほど運動神経変わらなさそうなのに、あのヒールで歩いたり蹴ったり出来るのに驚き(笑)
もっとも子どもの頃は、ドロンジョ様は40くらいだと思っていた…というか、子どもの頃は人を見ても性別や年齢なんて考えたことなかったけど、今にして思えばもっと年上だと思っていた…ので、キャスティングにはびっくりさせられたけど、ともかく彼女は良かった。最後に眼鏡を外したのは、(アニメとは違う)ドロンジョ様の魔法が溶けちゃったようで残念。
アニメならではの物事(実際アニメに登場したか否か知らないけど、巨大寿司とか)をそのまま表現してるのも面白く、そういえばヤッターワンに片手でつかまるあの乗り方に憧れてたなあ、と思い出した。その後、軽トラの荷台に乗ったり、台車で運んでもらったりして欲求を満たしたっけ。
映画になっても語呂上「今週の〜」は外せないから、最後が予告なんだなあ、と思った。
(09/03/07・新宿ピカデリー)
チェンジリング (2008/アメリカ/監督クリント・イーストウッド)
最後のテロップが、とても心に染みた。
何と言ったら分からない、またしても「こういうことがあったよ」という映画だった。イーストウッドなんだから当たり前じゃん、と思いつつ、とても嬉しい。
1920年代のロサンゼルスの街並、忙しい職場の様子、不意に訪れるホラー、市民の怒り(これがあっさりしてるのがいい!)、少年の話を聞く警官のタバコから落ちる灰、同時進行する聴聞会と裁判、ある「悪人」の死、その後に主人公の身に起きる出来事…全てがしっくりきている。
印象的だったのは、聴聞会の日に、クリスティン(アンジェリーナ・ジョリー)を迎えに来た牧師(ジョン・マルコヴィッチ)と彼女がやりとりするシーン。窓辺に立つクリスティンに、牧師は「息子さんも、あなたが新たな一歩を踏み出すことを願っていますよ」「違う世で息子さんに会ったとき、あなたが心を尽くして自分を探してくれたことを知りますよ」などと慰撫するが、彼女はそれを受け入れない。しかし反抗するわけでも冷淡にするわけでもなく、ただ自分の立場と思いを口にして、二人で部屋を出るのだ。その関係、空気に優しいものを感じて、イーストウッドらしいなと思った。
予告編の段階では、今作のアンジェリーナ・ジョリーはぎすぎすして気味が悪いなと思ってたけど、入魂の演技に惹き付けられた。特に聴聞会に出席するあたりから後は見せ場だらけ。頬をひくつかせるなんて、意識的にできるものなの?(笑)
警察の面々や精神病院のスタッフなども皆ぴったりはまっていた。
取り上げられている連続誘拐事件において、実際には性的暴行もあったようだけど、作中ではそうした描写はされない。またクリスティンについても、セックス的なものは一切描かれない(実際の行為という意味でなく)。彼女はストイックな聖女のようだ。
冒頭に流れる、母子の平穏な暮らし。クリスティンは息子のために生きている。それがあんなふうに事件に巻き込まれ、彼女自身が変化し、「生涯息子を探し続け」て死んでゆく…映画に描かれたより、その後の彼女の人生に興味が湧いた。
(09/03/01・TOHOシネマズ六本木ヒルズ)
 面白すぎてびっくりした。今年観た中で一番かも…
面白すぎてびっくりした。今年観た中で一番かも… 39歳の教員エイプリル(ヘレン・ハント)は出産を切に望んでいるが、夫のベン(マシュー・ブロデリック)に別れを告げられる。時期を同じくして養母が亡くなると、トークショーのホストとして有名なバーニス(ベット・ミドラー)が実の母親だと接近してくる。混乱しつつも、妻に去られた父兄のフランク(コリン・ファース)と親しくなるが、妊娠が発覚し…
39歳の教員エイプリル(ヘレン・ハント)は出産を切に望んでいるが、夫のベン(マシュー・ブロデリック)に別れを告げられる。時期を同じくして養母が亡くなると、トークショーのホストとして有名なバーニス(ベット・ミドラー)が実の母親だと接近してくる。混乱しつつも、妻に去られた父兄のフランク(コリン・ファース)と親しくなるが、妊娠が発覚し…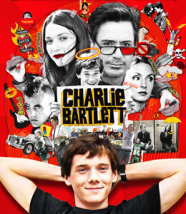 邦題からイメージするほどトイレにこもってるわけじゃないけど、チャーリーが皆と話すのがトイレの個室越しというのがいい。聴聞室のようでもあるし、「フェリスはある朝突然に」のマシュー・ブロデリックのように、こちらに向かって語りかけてくるわけじゃないけど、個室の中から「こっちのほう」を見ながら自分のことを話すというスタイル。
邦題からイメージするほどトイレにこもってるわけじゃないけど、チャーリーが皆と話すのがトイレの個室越しというのがいい。聴聞室のようでもあるし、「フェリスはある朝突然に」のマシュー・ブロデリックのように、こちらに向かって語りかけてくるわけじゃないけど、個室の中から「こっちのほう」を見ながら自分のことを話すというスタイル。 映画の始まりと終わりが好きな人の声というのはいいものだ。オーウェンが新聞記者の役なんて…と思ってたけど、子犬(といっても既に結構でかい)を迎えに行き、車に乗せて帰る姿に「オーウェンと犬!オーウェンと犬!」と興奮。彼の手によるコラムに合わせた「犬と、振り回されるオーウェン」の軽快なシーンが楽しい。
映画の始まりと終わりが好きな人の声というのはいいものだ。オーウェンが新聞記者の役なんて…と思ってたけど、子犬(といっても既に結構でかい)を迎えに行き、車に乗せて帰る姿に「オーウェンと犬!オーウェンと犬!」と興奮。彼の手によるコラムに合わせた「犬と、振り回されるオーウェン」の軽快なシーンが楽しい。 男子・イギリス・80年代…というだけで楽しいけど、観ているうちに教員の方に心動かされた。
男子・イギリス・80年代…というだけで楽しいけど、観ているうちに教員の方に心動かされた。 ホテルの設備係・スキーター(アダム・サンドラー)は、かつてオーナーだった父親(ジョナサン・プライス)から夢を引き継ぎ地道に働いているが、出世は困難。
ホテルの設備係・スキーター(アダム・サンドラー)は、かつてオーナーだった父親(ジョナサン・プライス)から夢を引き継ぎ地道に働いているが、出世は困難。 アクション映画で人気を博す俳優のスタ(カン・ジファン)と、かつて役者を目指していたヤクザのガンペ(ソ・ジソブ)。激しやすい性格のため相手役を見つけられないスタは、たまたま知り合ったガンペに共演を依頼する。
アクション映画で人気を博す俳優のスタ(カン・ジファン)と、かつて役者を目指していたヤクザのガンペ(ソ・ジソブ)。激しやすい性格のため相手役を見つけられないスタは、たまたま知り合ったガンペに共演を依頼する。 教会・学校内部と、シスターが足を伸ばすほんの近所が舞台だから、まず「閉じられた世界」の話として面白い。冒頭、説教の準備を手伝う男の子の姿も新鮮だし(女の子はやらないのかなと思ったけど、後に幾つかのシーンでああ、これは60年代の話なんだと気付かされる)、シスターたちの起き抜けや食事の様子なども、きれいな映像で撮られている。
教会・学校内部と、シスターが足を伸ばすほんの近所が舞台だから、まず「閉じられた世界」の話として面白い。冒頭、説教の準備を手伝う男の子の姿も新鮮だし(女の子はやらないのかなと思ったけど、後に幾つかのシーンでああ、これは60年代の話なんだと気付かされる)、シスターたちの起き抜けや食事の様子なども、きれいな映像で撮られている。